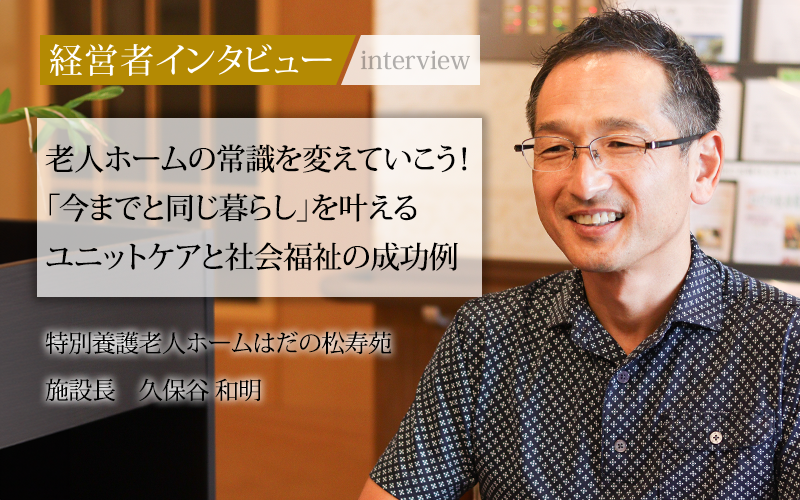
寿徳会は、1981年に神奈川県秦野市で設立された社会福祉法人だ。社会福祉の精神のもと、2つの知的障害者支援施設をはじめ、障害者就労支援施設「ハッピーラボ」、特別養護老人ホーム「はだの松寿苑」、学童保育「Colors」を運営している。寿徳会の理事長を父親に持ち、はだの松寿苑の施設長を担う久保谷和明氏に、事業の特徴や大切にしている思いについて聞いた。
「地域密着と社会貢献」をテーマに複数の支援施設を運営

ーーまずは、ご経歴についてお話しいただけますか。
久保谷和明:
学生時代はゴルフに打ち込んでいました。その後はゴルフ場に所属してプロを目指していましたが、27歳の頃、社会福祉法人寿徳会の理事長をしている父から「2005年に老人ホームをオープンするから手伝え」と声がかかり、準備から携わる形で介護業界に入りました。
寿徳会に入職してから3年ほどは入居やデイサービス、ショートステイなど現場の仕事を経験しました。副施設長を8年間務めたのち、2021年に施設長に就任した次第です。
ーー事業内容についてお聞かせください。
久保谷和明:
社会貢献を志す父の方針で、特別養護老人ホーム・障害者支援施設・学童保育を運営しています。はだの松寿苑はユニットリーダー研修実地研修施設として、国が進めるユニットケア推進のために周辺施設から年間70人程と多くのユニットリーダーを受け入れています。また、都内の学校と連携し、弊社の老人ホームを介護実務者研修の教室として、地域の施設職員が都心部まで通学することなく身近で取得できるようにしました。これも地域貢献と考えています。
ものづくりを通した障害者の就労支援にも力を入れています。地域のイベントに積極的に出店するほか、店舗と工場を兼ねた「ハッピーラボ 幸せ餃子」も開設しました。同施設には、近隣の方々がおいしい餃子を買いにいらっしゃいます。学童施設も「エリア内に学童がない」というお困りの声を受けて設立し、今では60名を超える子供たちが利用しています。
一人ひとりの意向を聴く「ユニットケア」との出会い――老人ホームの改革

ーー事業立ち上げにあたり、苦労したエピソードを教えてください。
久保谷和明:
法人では初めての老人ホームを開設するにあたり、既存施設や病院、飲食関係など、いろいろな業種から社員が集まりました。オープン当初は法人理念すらあることを忘れ職員同士、仕事のやり方や価値観の違いから各部署が連携できず、組織がまとまらない時期は本当に大変でした。1年間に40人入職しても40人が退職したほどです。
私も介護業界での経験が少なく、現状を改善するために会議を行っても中・長期的なビジョンを描けずにいました。転機となったのは、日本ユニットケア推進センターで行われたリーダー研修実地研修施設になるための勉強会に参加したことです。そこで、入居者一人ひとりの意向や好みを叶える「ユニットケア(個別ケア)」の意義を知り、大きな衝撃を受けました。
ユニットケアは、介護の質が上がる取り組みとして国も推進していますが、当時係長だった私は「職員が定着せず落ち着かない現状で職員に負担をかけることは、実際に難しいだろう」と思いました。しかし、ユニットリーダー研修を受講修了した職員から「(ユニットケアを知った上で)このまま実行しない施設で働くことはできない」と言われ、彼の強い覚悟を感じたのです。そこで、当時の施設長にその職員と2人で説得し、一部の部署だけで取り組みをスタートしました。
ーーどのようにユニットケアを導入したのですか?
久保谷和明:
しばらくは試行錯誤を繰り返しましたが、ユニットケア会議にリーダー以上30名の職員を参画させ、ユニットリーダー研修実地研修施設に30人ほどの職員が体験研修をしたことで、取り組みが加速しました。ユニットケア最大のメリットは「その人らしい暮らしを継続することで、入居者様が安心して暮らせること」です。
一般的な老人ホームは「みんなでいっしょに」というスタイルなので、今までの生活をその施設の日課に合わせることで、ストレスを感じる人もいます。また、包丁や電気ポットなど、始めから危険と判断されるものを遠ざけ、生活感のない空間で暮らすことになります。
私たちは入居者様から生活リズムと意向を聞き取り、職員間で統一したケアができるように日課表(24シート)を活用する仕組みをつくりました。入居者様が以前と変わりなく暮らせるように、居住空間の入居者様の手の届くところに家具や家電を置いたところ、職員も「楽しく仕事ができる」と良い評価をされました。
ーー職員の皆さんにも変化があったのですね。
久保谷和明:
「大変だから」と言って退職する人もいましたが、「私たちの仕事は誰のためにあるのか」という介護の根幹を考えると改革は必須でした。時間はかかりましたが、法人理念を浸透させ方針を掲げたことで職員がまとまりました。そして、自分たちのケアが入居者様に喜ばれることでモチベーションアップに繋がったと思います。結果的に、職員の定着率はここ3年間の平均で94%(離職率6%)となっています。
ケアを受ける人と職員の「心」を大切に――主体性を育む必要性

ーー大切にされてきた考えをうかがえますか。
久保谷和明:
ケアを受ける方やご家族に「この施設を選んでよかった」と言ってもらえる以上の喜びはありません。信頼関係を重視することはもちろんですが、専門性を高めるために、介護福祉士を始め、リハビリスタッフや管理栄養士、看護師の人員を厚くした体制を保っています。
「私たちはその人を心で受け、その人に心で応え、常に研鑽を積み、資質の向上を図りつつ、地域社会福祉を創造します」という法人理念も大切です。理念を理解した職員たちが、同じ方向を見ていることは弊社の強みだと言えます。その上で、職員の意見を聞く機会を設け年数回、私から理念研修など行う際は、経営・運営の状況(良い点・悪い点)を隠すことなく全て伝えることで職員が協力してくれます。
リーダーは「偉い人」ではなく、スタッフが安心して元気に働けるように努めるべき人物だと考えています。職員の中で「どうせ施設は変わらない」といった諦念が生まれないように、気になる点を指摘し合える環境づくりに留意しています。
ーー今後の展望をお聞かせください。
久保谷和明:
地域に必要とされながらも、事業存続が難しい施設から相談を受けるケースが増えてきました。今後、チャンスがあれば私たちのノウハウを活かし、社会福祉に貢献したいと考えています。
寄り添ったケアをしたいという職員が集まった一方で、主体性のある人を増やしていく必要性も感じています。取り組みの一つとして、職員が提案、実行できるよう研修体制や人事考課による育成の機会を設けています。今後も、職員みんながやりがいを持って、安心して働ける職場づくりを追求していけば、末永く健全な形で経営・運営を続けられると考えています。
編集後記
これまで老人ホームに対して「食事や散歩の時間が決まっている」と画一的なイメージを持っていただけに、ユニットケアがもたらすメリットに大きな感銘を受けた。「個人の心に寄り添うケア」は、高齢者が増加していく社会が目指すべき理想の介護ではないだろうか。取材で得られた「個人の生活がそこにある」という視点も、今日から人間関係のあらゆるシーンに取り入れて大事にしたいものだ。
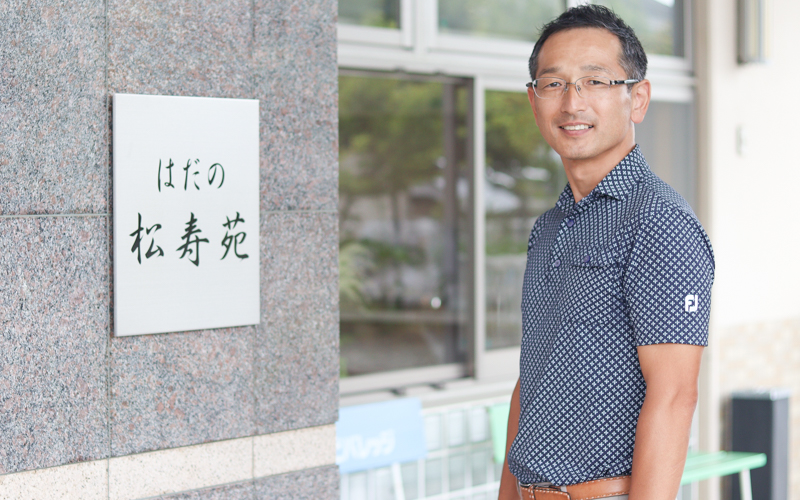
久保谷和明/1976年、神奈川県生まれ。2004年に社会福祉法人寿徳会に入職。2005年、特別養護老人ホーム「はだの松寿苑」にオープニングスタッフとして配属。2021年、施設長に就任。特別養護老人ホームはだの松寿苑の施設長として、現在は事業の拡大にも注力している。














