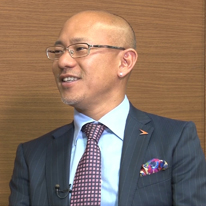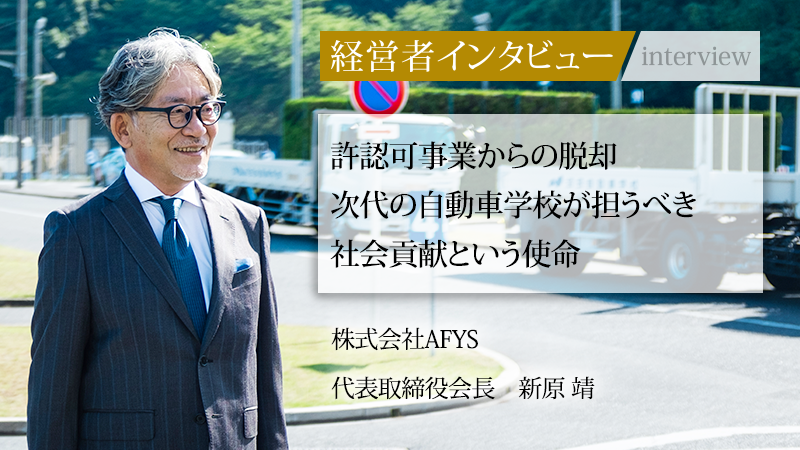
広島県を拠点に自動車学校を運営する株式会社AFYS。「All For Your Satisfaction 我々は全ての人(お客様、社員、地域社会)の満足のために存在する」という理念を社名にしている。同社は、自動車学校の役割は単に運転免許取得のための訓練を提供することに留まらず、「交通安全を通じて地域社会に貢献すること」こそが社会的な使命であると定義する。
かつて業績悪化から苦渋のリストラを決断した経験を持つ代表取締役会長の新原靖氏。利益追求の限界を知った挫折の底でつかんだのは、企業の存在意義そのものを問う経営哲学であった。社会インフラとして、すべての人の安全な暮らしを支える「地域の交通安全センター」へ。AFYSが描く未来像と、新原氏の情熱に迫る。
経営者としての土台を築いた修行時代と、かけがえのない仲間たち
ーー会長のこれまでのご経歴についてお聞かせください。
新原靖:
創業者である父の会社を継ぐことは私にとって自然な道でした。業界での経験を積むため、トヨタ自動車が100%出資する「中部日本自動車学校」に入社しました。そこは、全国から私のような境遇の自動車学校の跡継ぎたちが集まり、将来経営者となるために実務を学ぶ場所でした。
学校での寮生活を通じて、全国から集まった仲間たちとの繋がりを深めました。若い頃は同年代の友人という側面が強かったですが、それぞれが経営の道を歩むようになってからは、経営の悩みをぶつけ合い、情報を交換し合うかけがえのない存在です。長期研修のOBは当時50人ほどでしたが、今では150人以上に増え、このネットワークは経営者としての私にとって大きな財産となっています。
ーー家業に戻られた当初は、会社に対してどのような印象を持たれましたか。
新原靖:
正直なところ、最先端の教育プログラムを持つ学校から戻ってきた私には、家業のやり方が少し古臭く感じられました。若さもあって自分のアイデアを当時の社長である父に次々とぶつけましたが、ことごとく跳ね返される日々でした。しかし、転機が訪れました。入社2年目にしてオートバイ専門の新校設立を任されたのです。いざ自分でやってみると当然理想通りにはいきません。労使問題などにも直面する中で経営の難しさを痛感しました。自分の考えがいかに視野が狭かったかに気づかされた、非常に貴重な経験でした。
業績追求の果ての挫折と、理念経営への劇的な転換
ーー社長就任後は、どのような改革に取り組まれたのですか。
新原靖:
かつて自動車学校業界は、景気に左右されない安定した事業だと言われていました。しかし、私が社長に就任した頃には少子化が始まり、全国的に入校生の数が減り始めたのです。
そんな業界全体への逆風の中、わが社が運営する学校には以前と殆ど変わらない数のお客様に入校していただいていました。当時、自動車学校に営業部門があること自体が珍しかった時代に、私は他社に先駆けて営業部隊を組織しました。そして「お客様を何人入校させたら、これだけ賞与を上乗せする」というように、社員に対して明確なインセンティブを与え、徹底して目標を数値化する経営に舵を切ったのです。いわば、電卓を片手に業績を追求するような経営スタイルでした。
この改革は功を奏し、売上も利益も順調に伸長。少子化という大きな流れに逆行して、会社は成長を続けました。
ーー順調だった経営に、どのような転機が訪れたのでしょうか。
新原靖:
少子化の更なる加速です。それまでの成功体験を過信し、高コスト体質のまま経営を続けた結果、業績が著しく悪化。ついには営業赤字寸前にまで追い込まれました。そして、朝礼で社員に「リストラをします」と伝えざるを得ない状況に陥りました。最終的には希望退職者を募りましたが、誰も手を挙げず、社員一人ひとりと面談し「辞めてほしい」と頭を下げる事態になりました。自分の力不足で社員を辞めさせなければならない。経営者として、これほどつらいことはありません。
ーーその苦しい経験から、どのような気づきを得られましたか。
新原靖:
自身の力不足がもたらした事態に深く落ち込み、「何のためにこの会社を経営しているのか」と自問自答する中で、ようやくたどり着いた答えがありました。それは、「自動車学校は交通安全を通じて社会に貢献するのが本来の仕事だ」という、企業の存在意義そのものです。それまでの私は、利益の追求ばかり考え、まさに電卓片手に経営していたのです。
この気づきを得て、社員たちに「卒業後も事故を起こさないドライバーを育てる、そういう会社にしたい」と伝えました。営業の成績に対するインセンティブ報酬の話をしていた頃とは明らかに違い、社員の目が生き生きと輝いていました。この経験から、会社の基本理念である「交通安全で世の中に貢献する」ことを真剣に追いかけるべきだと確信しました。企業の経営は、利益の追求と社会的な使命の実現という、二本のレールの上を走るべきなのです。
社会的インフラとして地域を支える 自動車学校の未来像

ーー会長が考える、自動車学校が担うべき役割とは何でしょうか。
新原靖:
「交通安全を通して地域社会に貢献すること」、この一言に尽きると考えています。交通安全をビジネスとして扱えるのは、私たち自動車学校くらいではないでしょうか。だからこそ、単なる免許取得の場であってはならない。私は、自動車学校が「地域の交通安全センター」としての役割を担い、インフラとして社会に貢献するべきだと考えています。「このままではいけない」という強い危機感が我々を突き動かしています。
ーー「地域の交通安全センター」として、具体的にどのような展望をお持ちですか。
新原靖:
まずは、社会問題化している高齢者の危険運転に対応するための講習や、今後ますます増えるであろう外国人ドライバーへの対応です。こうした社会の問題に能動的に対処していくことは、社会的インフラとしての私たちの責務です。
私達の挑戦はそこに留まりません。顕在化している課題に対処するだけでなく、免許をすでに持っている全国8000万人のドライバーに対して、地域の交通安全を向上するためにどのようなサービスを提供できるかを考えなければなりません。たとえば、企業の従業員向けに定期的な安全講習を実施するなど、企業と連携した取り組みも考えられます。免許を取得した後も、あらゆる交通安全に関する課題を解決するための頼れる存在であり続ける。すべての人の交通安全に寄り添うこと、それが私たちが目指す未来です。
ーー最後に、今後の事業を推進する上での課題についてお聞かせください。
新原靖:
やはり人材です。まず、理念を次世代に引き継ぎ、会社を育てていくための経営幹部の育成は大きな課題です。そして、現場を担う従業員の採用と定着も大きな課題です。特に、私たちの仕事の中でも指導員の業務は教習車という閉鎖された空間での業務が多いため、経験の長い他の従業員の業務の見学を通じて育成することが非常に難しいです。これを補うため、OJT(On-the-Job Training、実務を通じた研修)などを通じた育成方法の確立に力を注いでいます。
また、DXはお客様との接点を強化し、業務を効率化するための協力なツールです。業界全体としてDXが進んでいない現状がありますが、積極的な導入のための戦略を立案する必要があります。これらの課題にひとつひとつ向き合いながら、理念の実現に向けて進んでいきたいと考えています。
編集後記
利益追求の先にあった挫折。その絶望の淵から、新原会長は「交通安全で世の中に貢献する」という、企業の社会的存在意義そのものを見出した。自動車学校を、単なる許認可事業から、地域に不可欠な「交通安全センター」という社会的インフラへと昇華させようとする強い意志は、業界全体の未来を切り拓く可能性を秘めている。会長の言葉の端々から、自社の発展だけでなく、地域社会の安全な未来を心から願う、経営者の熱い思いが伝わってきた。AFYSの挑戦は、これからも地域を明るく照らし続けるだろう。

新原靖/1959年12月20日、東京都生まれ。日本大学生産工学部中退後、1984年に株式会社トヨタ名古屋教育センター 中部日本自動車学校へ入社。1986年、有限会社沼田自動車学校入社。1999年、株式会社AFYSに改組し、同社代表取締役社長就任。2010年、同社代表取締役会長に就任。一般社団法人広島県指定自動車学校協会会長、一般社団法人全日本指定自動車学校協会連合会 副会長も務める。