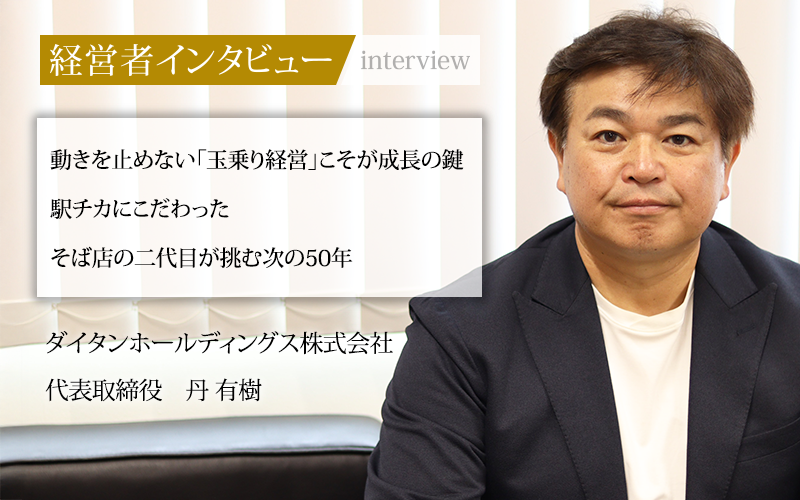
首都圏の駅前を中心に展開する立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」。その運営を担うダイタンホールディングス株式会社は、立地の強みを活かしてこれまでに100店舗以上を展開してきた。同社の舵を取るのは、テニスの世界から経営の道へ転向した異色のキャリアを持つ、二代目代表取締役の丹有樹氏だ。丹社長は現場の裁量を重んじながら、次の50年を見据えた既存の枠にとらわれない挑戦に取り組んでいる。その挑戦とはどのようなものか。丹社長に、ダイタンホールディングスのこれまでの歩みとこれからの展望を聞いた。
「やんちゃ」な社風に敬意を払って組織の前進に取り組む
ーーまず、丹社長の経歴をお聞かせください。
丹有樹:
ダイタンホールディングスは、もともと私の父が創業した会社です。ただ私は、大学卒業後すぐに家業に入ることはせず、得意だったテニスを活かしてプロテニス業界に進みました。それからしばらくは、テニスのコーチをしながら選手として大会に参加。テニスに関わる中で、自分の限界や可能性と向き合う日々を過ごしました。
テニスの現場で学んだのは、理屈だけでは勝てないということです。テニスを通して体で覚えた、瞬間的な判断や直感の重要性は、現在の経営判断の軸にも通じるものがあります。数字や理論を踏まえつつも、自身の直感を大切にする。この論理と直感のバランスが、今の私の意思決定の中核を成しています。
その後、株式会社プロテニス日本の設立に携わった経験を経て、2004年にダイタンホールディングスに入社しました。弊社の業務はテニスとはまったく異なるフィールドですが、「だからこそ自分にしか果たせない役割がある」と考え、経営の実務に本格的に関わり始めました。
現在は社長として、新規事業や海外展開などに取り組む一方で、「継いだものを次世代へつなぐこと」を自分の使命と捉えています。数百億円の企業にするという野心よりも、文化と土台を大切にし、安定させながらも変化を続ける。これまで培われてきた会社の文化を尊重して経営と向き合っています。
ーー貴社に入社してからどのようなことに、取り組まれましたか?
丹有樹:
既存の枠組みにとらわれない挑戦をしようと考え、新業態となるつけそばブランドを立ち上げました。この「そば屋がラーメンに寄せる」というあえての逆張りは、保守的な業界に一石を投じるものだったと思います。
このとき、逆張りにチャレンジしたのは、弊社が長年培ってきた“やんちゃな会社”という社風を守る意図も込められていました。弊社の現場には、店長一人ひとりが個性と熱意を武器に現場を動かすという、良い意味で会社に縛られない雰囲気があります。組織が大きくなってもこの気質が希薄化しないように、私自身があえてやんちゃな挑戦をする背中を見せようと思ったのです。社内に「自由にやっていいんだ」というメッセージを伝えることで、昔から続く現場の熱量を繋いでいく。その姿勢こそが、次世代に社風をつなげることになると信じています。
店舗を駅前にある「日常のメディア」へ。立地と発信力が生む飲食以外の価値とは

ーー貴社独自の強みを教えてください。
丹有樹:
弊社最大の強みは、駅前という立地を活かした“見せる飲食店”であることです。駅前に店を構えることは、ただ人を集めやすいだけでなく、日々の暮らしの中で多くの人の目に触れ続ける「日常のメディア」としての機能を果たしています。
この特徴を活かし、私たちは地方自治体と連携した取り組みも積極的に実施。たとえば、徳島県産のかき揚げや沖縄のもずくを使ったご当地メニューを期間限定で展開し、首都圏の店舗でその魅力を伝えてきました。こうした施策は話題づくりにもなりますし、地域貢献にもつながっています。
さらに、各店舗のスタッフが自らの裁量で動けることも、弊社の大きな強みです。現場に判断を委ねることで、メニューや内装に自然と個性がにじみ出てきます。地域のお客様の声をもとに工夫したり、自発的に新しい取り組みを始めたりと、日々のちょっとした変化を積み上げていくことで、店舗ごとのユニークな雰囲気が自然と醸し出されているようです。
「玉乗り経営」で進化する富士そば。海外・新業態・承継で描く次の50年
ーー今後の注力テーマをお聞かせください。
丹有樹:
まずは、全国の行政と連携しながらメディアとしての一面を引き続き強化していきたいです。富士そばの店舗には、1日で約5万5000人もの客が訪れます。さらに、店舗の前を通る人の数も考えたら、その数はもはや計り知れません。この可能性を十分に引き出すことが、次の成長の要になるのではないでしょうか。
また、外貨を稼ぐ飲食という視点から、海外展開への挑戦も検討しています。少子高齢化が進む日本では、従来のやり方だけではいずれ成長が頭打ちになるのが見えている。これまで一都三県にエリアを絞り、都市型モデルで展開してきましたが、それだけに依存していては未来が描けません。だからこそ、今のうちからリスクを取ってでも、新たなフィールドに踏み出す準備を整えています。
この挑戦は、あるセミナーで「無謀でも世界に出ていく経営者がいなくては、日本は弱くなる」という言葉を聞いて、背中を押されて海外進出を決めました。食文化の違いという大きな壁はあるものの、「そば」という日本文化の可能性を信じて、海外で受け入れてもらえる方法を模索しているところです。
こうした取り組みの根底にあるのが、私の考える「玉乗り経営」という姿勢です。止まればバランスを崩してしまう玉乗りのように、動き続けることでしか真の安定は得られません。だからこそ、海外展開も新業態も、事業を安定させるために動き続けながら挑戦するつもりです。
ーー今後、貴社をどのように成長させたいとお考えですか?
丹有樹:
新しい柱として、異なる業態・異なる顧客層を狙ったブランドを育て、「富士そば」の枠を超えた価値を提供できる体制を確立していきたいと考えています。
その一環として、新会社「ダイタンクリエイト」の立ち上げによる新ブランドの開発や、70年以上の歴史を持つ老舗ラーメン店「春木屋」の事業承継などが挙げられます。こうした多角的な展開によって、持続可能な成長戦略を描くと同時に、飲食業界が抱える継承問題にも向き合っていきたいと思っています。
もちろん、「富士そば」の伝統を守ることも大切ですが、それ以上にまずは会社が続いていくことが何より重要です。だからこそ、自社ブランドにこだわらず、価値ある店や文化をしっかりと引き継ぎ、育てていくことにも力を注いでいくつもりです。
今後もさまざまな方とのご縁を大切にしながら、多様な人とブランドの力を掛け合わせ、地に足のついた事業展開で、次の50年をかたちづくっていきたいと考えています。
編集後記
ダイタンホールディングスの立地戦略や現場主義、そして「玉乗り経営」という考え方は、変化を内包しながら安定を築いていくための実践知に満ちている。今後の海外進出や他業態への展開を通じて、新たな顧客層との接点をつくり、ブランド価値をさらに昇華させていくだろう。ダイタンホールディングスの“やんちゃな挑戦”は「そば」という文化を超えて、拡大していくのかもしれない。

丹有樹/1974年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学卒業後、テニスコーチをしながら日本のテニスツアーに参戦。その後、株式会社プロテニス日本の設立メンバーとして参画。2004年、「名代 富士そば」を運営するダイタングループに入社し、2015年に代表取締役に就任。














