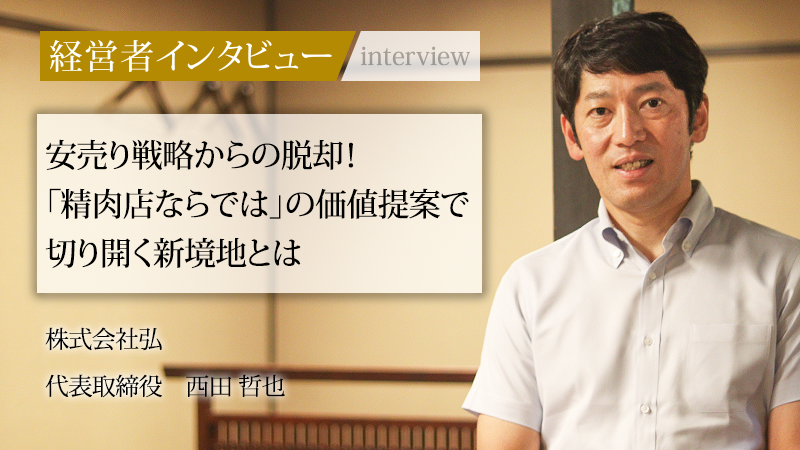
京都で人気を博す「京の焼肉処 弘」。その礎を築いた代表取締役・西田哲也氏は、実家の精肉店で肉の目利きを究めた人物である。最高の肉を知る「プロ」でありながら、飲食経営は「素人」。そのギャップが開業後の大きな壁として立ちはだかった。
安さだけではお客様に響かず苦戦した1年から、「精肉店ならではの価値提案」へと舵を切ったメニュー改革が、最初のターニングポイントとなる。さらに、会社存続を揺るがしたBSE問題の渦中で社員に支えられた経験は、「幸せ創造企業」という揺るぎない理念を育んだ。逆境を乗り越え、独自の強みを磨き続ける同社の軌跡に迫る。
肉のプロが越えた壁、失敗から見いだした価値提案
ーーご実家が精肉店とのことですが、どのような経緯で焼肉店として独立されたのでしょうか。
西田哲也:
物心ついた頃から家業を手伝っていたので、将来は家業に関連した事業をしたいと自然に考えていました。私は次男ということもあり、大学卒業後は一度就職することも考えましたが、さまざまな会社を見るうちに、組織に属するよりも早く自分で事業を立ち上げたいという思いが強くなったのです。大学卒業と同時に父が京都食肉市場の役員になったこともあり、まずは実家の精肉店に入り、兄と二人で店を切り盛りすることに。そこで7年間働く中で、自分の肉に関する知識や技術を最も活かせるのは飲食業ではないか、と考えたのが独立のきっかけです。
ーー精肉店でのご経験を活かして開業された焼肉店ですが、当初はいかがでしたか。
西田哲也:
肉のことは分かっていても、飲食店経営に関しては全くの素人でした。最初の1年ほどは本当にお客様が来ず、これは失敗したかと思いましたね。当時の私は「他の焼肉店は品質の劣る肉をこんなに高く売っている。うちの肉が一番だ」と、肉の質と安さにしか目が向いていませんでした。しかし、お客様にとっては肉の質はもちろん、サイドメニューやサービス、空間を含めたトータルな体験に価値を感じるという視点が抜け落ちていたのです。そのため、お客様からは「肉はいいけどな」と言いながら帰られるような有様でした。
ーー客足が伸びない苦しい1年間を、どのようにして乗り越えられたのでしょうか。
西田哲也:
肉を売ることと、お店で食事の時間を提供することは全く違うのだと痛感し、全てを一から学び直すことにしました。お客様が来ない暇な時間を使って、とにかくいろいろな飲食店に食べに行って研究したり、自分でタレやスープなどのサイドメニューをつくっては試食したりを繰り返したのです。この1年間で、飲食店経営のノウハウを必死にインプットしたことで、少しずつですが状況を好転させることができました。
事業の飛躍を導いた3つのターニングポイント
ーー開業当初の苦戦を、どのようにして乗り越えられたのでしょうか。
西田哲也:
「肉のプロが提案する焼肉店」という原点に立ち返り、メニューを全面的に見直したことが転機になりました。当初は他店の価格を意識して「安さ」を売りにしようとしましたが、それではお客様に響きませんでした。そこで、「精肉店の自分が一番おいしい食べ方を知っているのだから、それを提案しよう」と考え方を変えたのです。たとえば、それまで焼肉には不向きとされていたモモの赤身もカットを工夫し、サーロインは焼肉として最もおいしく味わえるよう、あえて分厚くカットして提供するなど、部位ごとの特徴を最大限に活かしたメニューを開発しました。これが「あそこの焼肉は他とは違う」という口コミにつながり、店の人気を確立する転機となりました。
ーー事業を拡大される中で、最大の危機はどのようなことでしたか。
西田哲也:
2001年に2号店を出した直後、BSE(牛海綿状脳症)問題が発生しました。連日、牛肉の危険性が報道され、1号店の売上は半分になり、会社は存続の危機に陥りました。返済のプレッシャーで精神的に追い詰められ、どうしていいか分からずにいた私を支えてくれたのが社員たちでした。
彼らは自発的にチラシをつくって駅前で配ってくれたり、不安なはずなのに休日にまで店に出てきてくれたりしたのです。私は彼らに「大丈夫だ」とすら言えず、逆に励まされる始末でした。このとき、もし会社が持ち直したら、絶対に社員に「この会社に残ってよかった」と思ってもらえる会社にしようと固く誓いました。それが、現在の経営理念である「幸せ創造企業」の原点です。
ーーBSE問題という大きな危機を乗り越えられましたが、その他に事業の壁となった出来事はありましたか。
西田哲也:
3店舗目と4店舗目を同じ年に出店した際、現場がかなり疲弊してしまいました。早朝から深夜までの長時間労働で社員に大きな負担がかかり、離職者が続出してしまったのです。このままでは組織が崩壊すると感じ、出店を一時的にストップしました。
そして、セントラルキッチンを設立し、各店舗で行っていた仕込みなどを集約することで、現場の負担を軽減する体制を整えました。まずは社員が無理なく働ける環境を整えてから、次のステップに進むべきだと。2005年に一度立ち止まって足元を固められたことが、結果的に持続的な成長につながったと思います。
「一頭買い」を核とする、精肉店ならではの価値提案

ーー貴社の事業の核となる強みについてお聞かせください。
西田哲也:
兄が目利きをして和牛を一頭買いしていることです。これにより、高品質な肉を安定的に、かつ中間マージンなしで安く仕入れることが可能になっています。また、生産者や牛の血統、ランクまで自分たちで吟味して買い付けられるため、提供したい品質を自在にコントロールできる点も大きなメリットですね。
ーー貴社の強みである「一頭買い」は、具体的にどのような価値提案につながっているのでしょうか。
西田哲也:
一頭買いで仕入れた牛のあらゆる部位を、それぞれの特徴が最も活きるカットや調理法で味わっていただく。それが私たちの価値提案の根幹です。単にカルビやロースといった定番メニューを並べるのではなく、「ヒレの厚切り」や「カタロースの一枚切り」、あるいはスリットを入れて食べやすくしたモモ肉など、精肉店だからこそ知っている食べ方でお客様に肉本来のおいしさを提案しています。他店ではなかなか味わえない特別なメニューがあることが、私たちの提供する価値だと考えています。
ーー最後に、今後の事業展望についてお聞かせください。
西田哲也:
まずは、京都市内で20店舗体制を築き、京都でナンバーワンのブランドを確立することが第一の目標です。店舗を拡大する目的は、経営理念である「幸せ創造」の実現にあります。会社として成長し、社員が目指せるポストを増やすことで、彼らが将来に希望を持って働ける会社にしたいのです。そのための基盤が20店舗体制だと考えています。その基盤を固めた先には海外展開なども見据えていますが、実現には「自分がやりたい」と手を挙げてくれる人材の育成が不可欠です。まずはこの目標の中で、次の時代を担う人材を育てていきたいと思っています。
編集後記
「肉のプロ」が「経営のプロ」へと変貌を遂げる過程は、まさに逆境と学びの連続であった。今回の取材で浮き彫りになったのは、「失敗」を真正面から受け止め、それを次なる一手へとつなげる西田氏のしなやかな強さだ。肉の質への過信という最初の壁を、顧客目線での価値創造で乗り越え、BSEという外部要因の危機を、社員との絆という内部の強さに昇華させた。そして、急拡大の痛みを、持続可能な組織づくりへの投資へと転換する。全てのターニングポイントに共通するのは、困難の中にこそ成長の種を見いだすという経営哲学だろう。同社の歩みは、専門性という強みに溺れることなく、常に学び、変化し続けることの重要性を教えてくれた。

西田哲也/1968年2月生まれ。摂南大学を卒業後、精肉店弘に入社する。1997年、株式会社弘を設立し、「京の焼肉処 弘 千本三条本店」をオープン。代表取締役に就任し、現在に至る。














