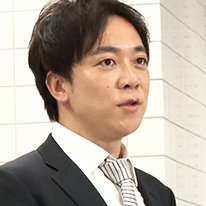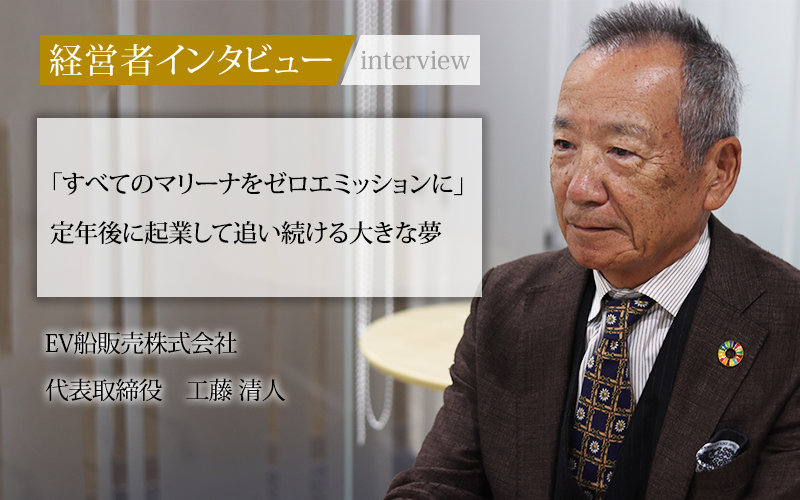
日本は2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言しており、船舶の分野でも政府は2028年までにゼロエミッション船(※)の商業運航を目指して取り組みを進めている。実際にEV船の開発や事業化に取り組む企業も増えており、EV船販売株式会社もその一つだ。2017年の創業以来、純粋に電気だけで動く「ピュアEV」の船の開発や販売を手がけてきた。
代表取締役の工藤清人氏はヤマハ発動機株式会社で船舶の営業を中心に定年まで勤め上げたのち、海洋系大学の研究員を経て起業したという。汲めども尽きないそのエネルギーの源がどこにあるのか、探ってみた。
(※)ゼロエミッション船:運航時に温室効果ガス(GHG)を排出しない、または排出量を実質的にゼロにする船舶のこと
マリン事業全般のノウハウや海洋系大学での研究経験を活かして起業
ーー定年前までのお話をお聞かせいただけますか。
工藤清人:
私は海洋系の東京商船大学(現:東京海洋大学)を6年半かけて卒業したのですが、船に乗るのは自分には合わないなと思って、最初は商社に入社しました。働き始めて1年半ほど経ったころ、大学時代の指導教官から「ヤマハ発動機の求人があるから行かないか」と声がかかりました。声がかかる前に結婚した妻が、偶然にも、ヤマハ発動機の本社近くの浜松市出身だったので、ご縁を感じ、転職を決めました。
最初は九州、次に本社、それから東京、仙台、名古屋、本社と異動を繰り返して、九州では漁船の営業・責任者、本社ではヨット、水上オートバイの普及、プレジャー製品の販売・企画、その後子会社の社長を経験しマリン事業全般に携わることができました。最後は丸の内の東京事務所で、国土交通省や海上保安庁などとやりとりする窓口を担当して定年を迎えました。ヤマハ発動機では、多様な業務に携わることができ面白い経験を積めた、幸せな会社員生活だったと思います。
ーー定年後、会社を設立されるまでの経緯を教えてください。
工藤清人:
定年退職してから1年半ほど経ったころ、母校の大学より3隻目のEV推進船をつくるので、「研究員にならないか」と声をかけていただきました。その後、65歳までの3年間大学の研究員として、EV船製造のとりまとめなどをしていました。
研究は楽しかったのですが、私はそれまで営業をやってきたので、研究だけをする生活に物足りなさを感じていました。そこで、EV船関連で大学に出入りする企業の方々に声をかけ2017年に今の会社を立ち上げました。
ーー起業に際し、どんな思いをお持ちでしたか。
工藤清人:
私がこの会社をつくった際、抱いていた思いの一つは将来の可能性です。一時期、EV自動車に対して世の中の注目が非常に集まった時期がありましたが、そのときに、「この流れと同じように、船舶業界にもEVの波が絶対来る」と確信していました。もう一つは、マリーナや漁港すべてで「ゼロエミッション」を実施したいという思いです。脱炭素の動きは陸上の世界に限った話ではなく、海の世界でも考えなければならない問題だと考えていました。
「マリーナや漁港でゼロエミッションを実現したい」という夢を追求

ーー起業されてから、大変だったことをお伺いできますか。
工藤清人:
起業当時は、東京オリンピックと大阪・関西万博のタイミングでビジネスや世の中の大きなうねりがくると思っていたので、そのタイミングを狙って会社をつくりました。ところが新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生してしまい、打撃を受けました。当初はEV船の部品として、安川電機のモーターを納めてもらえるはずだったのですが、それができなくなってしまったのです。
そこで、ドイツのトルキード(Torqeedo)社と組むべく弊社の取締役が奔走し、モーターやリチウムイオンバッテリー、制御システムを構築しているアッセンブリー企業と提携できました。その結果、「EV船外機搭載Estrela」&19t型EV観光交通船を建造することができました。ただ、東芝や安川電機の製品であれば、国の定める検査に通っていますが、トルキード社の製品だと一から全部検査を受けなければいけません。これが大変で、すべて終わるまで3年を要しました。
それでも「ゼロエミッションマリーナ設立」という目的があったので、2021年には堺にある「旧堺港のクリエイションマリーナ」で、ゼロエミッションMの実証実験を実施。太陽光発電システムで自前の電気を作り、蓄電池より非接触の装置を通じて自動化EV船へ電気を送り船を走らせるシステムを構築しました。まだコロナ禍の中でしたが、官民250数名の方にお越しいただき、大好評を得ることができました。
これまでは「ゼロエミッション」を目指してピュアEVのみでやってきたのですが、実はお客さまからはハイブリッドのご要望があり、ハイブリッド船の開発を始めています。来年(2026年)8月にはハイブリッド船が完成、それから実証実験を行い、2027年春には国内外で販売を始める予定です。
ーー貴社の強みは何だとお考えですか。
工藤清人:
私はヤマハ発動機時代にマリン事業を担当していたので、それがビジネスの軸になり、非常に助けになっています。今でもヤマハや大学のときに築いたネットワークを活かしながらビジネスをしていて、国との交渉ごとをする際も、先方はみなさん以前からの知り合いですので、そこが私のいちばんの強みかもしれません。
3年後に新会社を設立し、これまでの経験やノウハウを若手に託したい
ーー今後の新たな展開について、方針をお聞かせください。
工藤清人:
3年後を目処に、現在の会社とは別に若手中心の会社を設立し、特に海外、とりわけ東南アジアへの展開、その後はアメリカ本土進出を考えています。たとえば、タイでは観光船の需要が非常に高まっています。ベトナムのある州からは具体的な案件で「一緒にやろう」という話をいただいています。弊社のノウハウを活かせるプロジェクトなので、推進するつもりです。
そのために、若い人材を集めることと、資金を3億円拠出してくれる投資家を見つけること。それが今一番の私の目標で、そのための企画書ももうじきできあがるところです。
ーー新会社では、どんな方を求めていらっしゃいますか。
工藤清人:
遊び心のある人、そして目標を持って、夢を実現したいという人を募集しています。私は今、ヤマハ発動機でのマリン事業の経験やノウハウを活かして仕事をしていますが、それを新会社の若い人たちにすべて教えたい。そして、彼らにはそれをコアとしてさらにグローバルに伸びていってほしい、それが私の夢ですね。
編集後記
ビジネスパーソンとしてひとつの企業で定年まで勤め上げ、その経験を活かして新たな事業を立ち上げた工藤社長。それを実現させたのは、もちろんそれまでに積み上げてきた知見や人脈によるところが大きいだろうが、一方で大きな夢を持ち続け、いつからでも新しいことに挑戦できるベンチャーマインドがあるからともいえる。工藤社長のキャリアパスは、これからますます高齢化が進む日本社会における理想形のひとつかもしれない。

工藤清人/1949年、熊本市生まれ。東京商船大学(現・東京海洋大学)卒業。商社を経てヤマハ発動機株式会社に入社、30数年勤め上げる。定年退職後、出身大学で次世代プロジェクトチーム(電動システム・水素燃料電池等開発)の研究員として3年間勤務。また一般財団法人電池推進船普及研究財団を設立し、専務理事となる。2017年、EV船販売株式会社を設立。ゼロエミッション社会の実現を目指している。