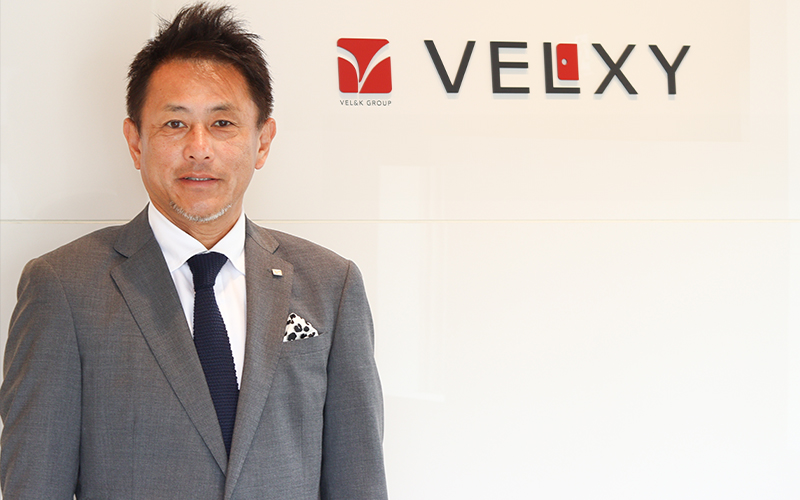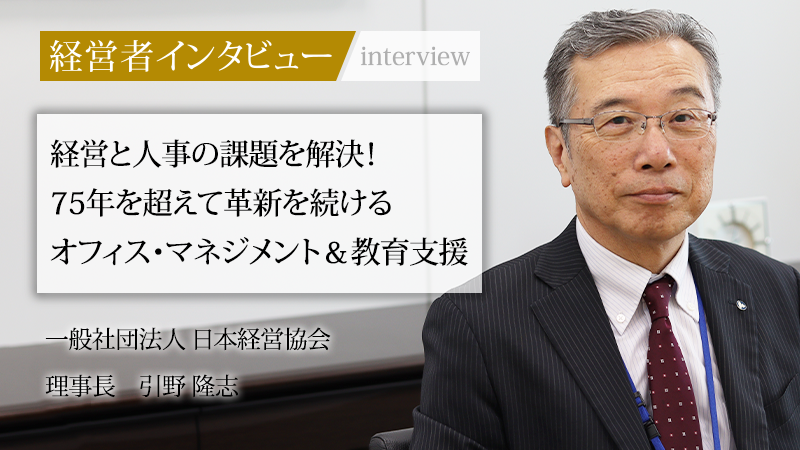
1949年に創立された日本経営協会は、国内における経営の近代化と事務の効率化を目指し、啓発活動を続けてきた一般社団法人だ。事業の核となるのは、企業・行政・自治体向けの展示会やセミナーの開催と、人材開発の支援サービスである。理事長を務める引野隆志氏に、これまでの経歴や事業の変遷と強み、今後の展望をうかがった。
民間企業を経て社団法人へ、社内DXの先駆者として活躍
ーーご経歴をお話しいただけますか。
引野隆志:
大学を卒業後、5年ほど広告代理店に勤めたのち、産業機器を扱う工業会に転職しました。広告代理店では創造力や発想力、工業会では実務的なスキルを身につけられたと思います。その後、知人からアドバイスを受けて弊社の新人採用に応募し、ご縁をいただきました。
さまざまな展示会を主催する団体ということで、広告代理店時代のような、大きな事業にもう一度挑戦してみたいという思いもあったといえます。
ーー民間企業と社団法人で、風土の違いはありましたか?
引野隆志:
ありました。広告代理店は社内ルールに柔軟性があり、自由にチャレンジできる風土でしたね。工業会は小さな組織だったので、役員や上司の判断のもと、規則に従って業務を遂行する環境でした。
どちらの世界も見たうえで、日本経営協会はその中間にあたる組織だと感じています。社団法人といっても株式会社に近く、自分たちで事業を成長させ、収益を上げていく経営形態です。
ーー貴社での印象的なご経験もうかがえますか。
引野隆志:
印象に残っている経験といえば、パソコンによる業務の効率化です。実務にパソコンを活用するという点で、先駆け的な活動をしてきたと思います。私が入社した1988年は、パソコンが普及し始めた時代です。
事務業務の生産性向上につながるとして、展示会でもOA機器を紹介するようになり、担当者として知識を身につける必要がありました。その中で私は、展示会の受付業務と帳票管理、招待券やDMの作成業務などをパソコンで効率化したのです。
インターネット回線を協会内に完備し、サーバーを立ち上げ、地域本部と企業をつなぐ全国的なインフラを整備するなど、IT化の領域で力を発揮できました。また、その流れで「2000年問題」(※)に対処し、システムの更新業務もやり切ったことが、のちの評価につながったのではないでしょうか。
(※)2000年問題:西暦カウントの処理上、2000年以降はコンピューターシステムが誤動作する可能性があるとされた問題。
コンベンション事業とオーダーメイドの教育支援が柱

ーー現在の事業内容を教えてください。
引野隆志:
事業の柱は、展示会・カンファレンスを主催するコンベンション事業と、人材育成を課題とする民間企業・自治体向けの研修・コンサルティング事業です。その他、付随事業としてeラーニングの提供、事務スキルや経営学の検定試験を実施しています。
弊社はもともと、戦後の復興期にあたる1949年に「日本事務能率協会」として創立されました。欧米のオフィスを参考に、日本企業にもファイリングのスキルを浸透させて、事務能力を向上させることが創立当時の目的です。そのためには理念の発信に加えて、ツールの存在を知ってもらう必要があるとし、事務用品を紹介する展示会事業を始めたのです。
時代と共に展示会の需要は変化し、近年は医療団体、自治体向けの総合フェアが伸びています。特に病院関係の展示会は、日本病院会との共催で育ててきたもので、業界内の課題にマッチする内容をお届けしています。
ーー研修・コンサルティング事業における強みをお聞かせください。
引野隆志:
中堅企業を中心に、大手企業から自治体まで、いろいろなお客様とかかわってきたことが一つの強みです。その豊富な経験を生かし、主催・受託を問わず幅広い分野で、人材育成に関する教育プログラムや研修ツールを提供しています。
古くからお付き合いのある会員様には、「真面目で堅実なイメージと安心感がある」「質の高い研修がそろっている」といった評価もいただいています。
教育関係では、さまざまな切り口で開催している公開講座(セミナー)も好評です。弊会はお客様の課題や要望をうかがったうえで、専門性のある講師を招き、資料や研修プログラムを制作しています。画一的ではない、オーダーメイドのセミナーは他の企業や団体との大きな違いでしょう。
「事業」を軸に地域が連携する新たな組織づくり
ーー2023年に理事長に就任されました。その後の取り組みをお話しいただけますか?
引野隆志:
コロナ禍で展示会が開催できず、過去最大級のダメージを受けた状況での引き継ぎでした。従来の経営では完全回復は難しいと考え、2025年4月から大きな組織改革を進めています。
この改革により、弊会は地域本部制ではなく、事業部制の組織へと変わります。これまで地域ごとの本部に任せていた各種事業に、横のつながりを持たせて、全国で連携していく取り組みです。事務処理のフローも変わるため、DX推進プロジェクトも立ち上げて、同時に進めていきます。
外部のITツールを組織全体に浸透させれば、社内システムを逐一開発する必要はなく、本来やるべき業務にリソースを割けるようになるでしょう。もちろん、内部にもいろいろな意見があるので、自身の考えをより伝えて、組織改革への意識を高めていかなくてはいけません。
ーー今後の展望をお聞かせください。
引野隆志:
事業部制を強化していくにあたって、営業部門の若手育成に力を入れています。より戦略的にお客様をサポートできるように、経営・マネジメントや人材育成に関する学習意欲を高めて、人材のチャレンジを後押しする組織づくりをしていきたいです。
新しい試みとしてスタートした、会員向けWebサービスも充実させる方針です。経営者の方々へのインタビュー動画をはじめ、さまざまな発信を通して会員数の増加を目指します。
編集後記
民間企業と社団法人という、組織風土の異なる職場を経験してきた引野氏。歴史ある団体に双方の長所を取り入れることで、柔軟性のあるビジネスと組織への帰属意識を伸ばしているのが、最新の「日本経営協会」だといえる。現在行っている組織改革により、どのように変わるのか。今後の活動から目が離せない。
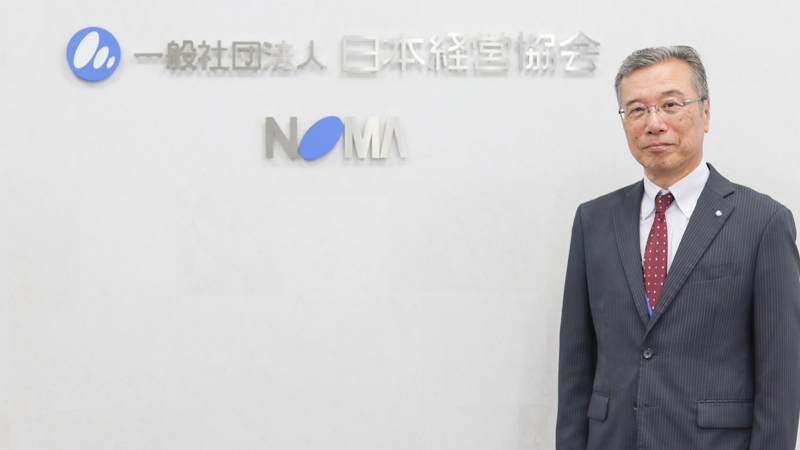
引野隆志/1957年生まれ。1980年、中央大学文学部文学科英文学専攻を卒業。広告代理店、産業機器工業会を経て、1988年に一般社団法人日本経営協会に入職。展示会、セミナー、講師派遣、情報システムなどの主力事業に携わる。2023年、理事長に就任。