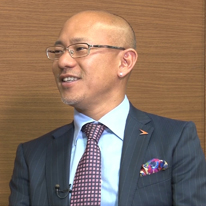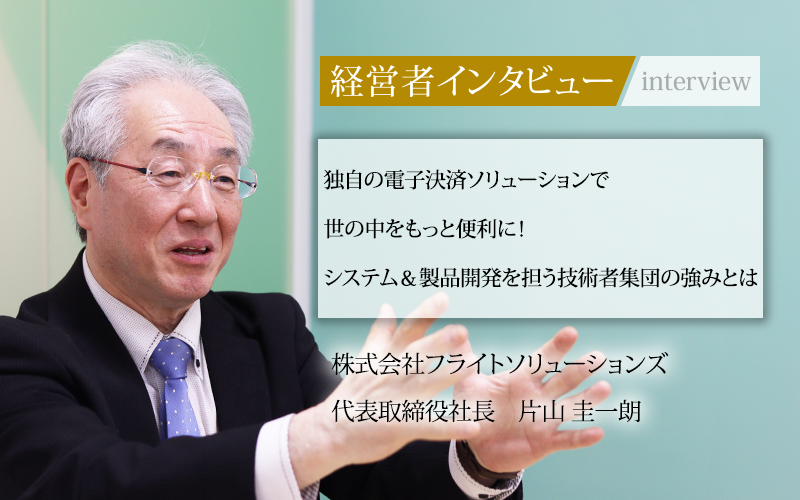
株式会社フライトソリューションズは、決済システムを中心とした製品開発事業とシステム開発事業を展開する企業だ。iPadを使ったクレジットカード決済システム「Payment Meister(ペイメント・マイスター)」は高いシェアを誇り、多数の大手事業者との取引を有している。今回、代表取締役社長の片山圭一朗氏に、システム開発と製品開発を展開することで得られるメリットや今後の事業展開などについて、話をうかがった。
急な事業撤退で取り残された顧客を守るため起業
ーー大学在学中に、ベンチャー企業の立ち上げに参画した経緯をお聞かせください。
片山圭一朗:
大学4年生のとき、マイコン(マイクロコンピューター)クラブサークルの先輩方が、有名なIT企業の中心メンバーとして立ち上げを行っていたことなどから、90%以上の学生は大手メーカー等に就職し、残りの10%はベンチャー企業への就職や自分たちでベンチャー企業を立ち上げる状況でした。私は、当時留年していた先輩方からコンピュータグラフィックス(CG)のシステムを開発する会社の起業に誘われ、開発責任者として参画したのが始まりでした。
参画後は、開発を加速するため日本の大手家電メーカーの中央研究所のメンバーなどを50人ほどスカウトして体制を整え、すぐに日本初のコンピューターグラフィックス(CG)のシステムを開発しました。さまざまな分野に販売し、2年目には売上高10億円を達成しました。
ーーそこから独立した経緯を教えていただけますか。
片山圭一朗:
CG事業のベンチャーを立ち上げる際、証券系の大手ベンチャーキャピタルが私たちの技術に価値を感じ、資本金を全額出資してくださいました。起業後すぐに売上高10億円を達成したのですが、彼らは「10億円が100億円に伸びることはあっても、1000億円までにはなり得ない」と考えたようです。また、「今後経済が停滞した際に、CGはあれば美しいけれど必需品ではないので予算カットの対象になる」という判断もあり、「CGをやめて、別の分野で今ある技術を活かした方が良い」との経営判断になり、CG事業から撤退することが決まりました。
CGシステム開発のために集めた50人の技術者に対し、その後も継続的に活躍できる転職先を斡旋することが私の前職での最後の仕事となりました。それをやり遂げた後、そのまま自分だけ会社に残るという選択肢は私の中になく、用意された副社長の座を辞退し退職しました。
ただ、CGシステムをご利用いただいているお客様を放置するわけにはいきません。そこで、前の会社のお客様の保守サポートを引き継ぐ形で今の会社を設立しました。この時期は、まさに波乱の連続でしたね。
経営の安定化のため画像解析サービスへ転換
ーー起業当時の状況と、起業後の事業の変遷をお聞かせください。
片山圭一朗:
創業当時は3~4人の社員でスタートし、当初は映像制作に関わるどんな開発でも請けてがむしゃらに進んでいましたが、前職の会社が判断した「CGはあれば美しいけれど、必需品ではないので予算カットの対象になる」という説にも一理あると考えました。そこで考えたのが、同じ映像処理の技術を活用した医療の診断装置や工業用の画像検査装置など景気に左右されない「無くてはならない必需品」でした。
たとえば、自動車の塗装時に塗りムラや傷がないかをカメラで撮影した映像から判断する技術の開発です。さらに、日本医科大学と共同でゴーグル型カメラでめまいを訴える患者の目の振動周期を計測し、脳や三半規管系、心療など、どこに問題があるのかを切り分ける診断装置を開発しました。これは医療機器の認定も取得し販売していました。
また、当時のパソコンの処理能力では映像の解析が困難だったため、画像解析を高速に行うために、画像解析・画像処理に特化した日本で最初のUNIXワークステーションを開発し、画像解析専用として販売をしました。
インターネットの普及とデジタル放送の開始で起死回生

ーー貴社の転換点についてお聞かせください。
片山圭一朗:
業績は順調に伸びていましたが、バブル経済の崩壊に伴い、状況が一変。取引先の設備投資の動きがピタッと止まり、収益は大幅に減少し、会社は再び縮小していくことになりました。気づけば自分一人の会社として細々と事業を続けていましたね。
そうした中、大きな転機となったのが、インターネットの隆盛です。1995年、まだ家庭にインターネット環境が普及していない時代に、コーヒー1杯でパソコンを使ってネットサーフィンができるというインターネットカフェが日本のあちこちでスタートしたのです。
私の大学の卒業研究が当時発明されたばかりのイーサネットの構築だったことから、インターネットカフェの設計の依頼が一気に舞い込み、大きな売上を立てることができました。
また、1996年には衛星放送のパーフェクTV!(現在のスカパー)が始まった際には、映像技術に強い点が評価され、大手メーカー経由でデジタル映像技術の開発を提供することになったのです。さらに、「スカイパーフェクTV!」への切り替えに伴うシステム統合にも関わりました。
売上高3億円を達成し、1999年に再び社員を雇えるようになりました。2000年はBSデジタル放送、2004年には地上デジタル放送、2006年にはワンセグ放送がスタートし、それらの仕事を数多く手がけ、その結果、上場も果たすこともできました。
ーー2002年に「フライトシステムコンサルティング(現:フライトソリューションズ)」へ社名を変更したのはなぜですか?
片山圭一朗:
当時、プログラム開発を仙台の会社に委託していたのですが、その会社と経営統合して2年で上場することを目標に社名を変更しました。東京は営業とコンサルティングの拠点、仙台はプログラム製造の拠点として、製販一体化を目指したのです。今振り返っても、これは正しい判断でした。合併していなかったら、上場もできていなかったと思います。
事業安定のため、自社製品の開発に着手
ーーその後の事業の流れをお聞かせください。
片山圭一朗:
2009年当時、弊社はシステム開発(SI事業)の完全なる一本足打法の経営スタイルでした。リーマンショックによりほとんどの大手企業がIT投資、開発投資を一斉に凍結したことから、システム開発の売上が急速に縮小してしまったのです。加えて、それまで大手SI事業会社が見向きもしなかったような金額の小さな入札にも参入してくるようになり、採算割れに近い金額でしか受注できない状況となり危機感を持つようになりました。
そうした中、以前からお付き合いの深かったApple本社の幹部の方から、iPhoneを用いたクレジットカード決済ソリューションの製品化に関して、当社の技術であれば実現できると後押しをいただきました。そして、世界最初のiPhoneによるクレジットカード決済をリリースしたSquare社から1か月遅れで、2010年9月に日本で初めてiPhoneに専用のジャケットを装着して決済するソリューションをリリースしました。これが製品事業の第一歩です。
ーー決済システム事業は開始当初から順調だったのでしょうか。
片山圭一朗:
事業を始めてからしばらくは苦難の連続でしたね。まず、新しいiPhoneモデルが発売されると外形(サイズ)が変わってしまい、ジャケット型の決済装置の形も合わなくなってしまうという課題がありました。
そして何より大きかったのは、当時iPhoneは売れていましたが、99%個人消費であり、法人にはまったく入っていませんでした。日本企業の場合、すべてのIT機器に関して「取扱規定」を制定しないと導入が難しいという日本固有の課題があったのです。
2010年当時、大手企業各社には「パソコン取扱規定」や「携帯電話取扱規定」が存在しましたが、iPhoneは携帯電話とは比べ物にならないパソコン並みの高機能です。一方でパソコンより手軽に持ち運べるし、その分紛失もしやすいものということもあり、各社の情報システム部門はスマートフォンの扱いに苦慮していました。
しかし2012年にiPadが発売されたころから、携帯キャリアをはじめIT各社がスマートフォンの取り扱い規定策定の支援サービスを始めたことで、企業への導入が徐々に広がっていきました。
システム開発と製品開発の二軸で事業を運営するメリット

ーー現在の貴社の事業内容をお聞かせください。
片山圭一朗:
弊社の主力商品は、クレジット決済端末兼マイナンバーカード公式読み取り端末の「Incredist Premium (インクレディスト プレミアム)」シリーズです。

iPad上での決済アプリケーション「Payment Meister(ペイメント・マイスター)」と組み合わせることでタブレット決済が可能になります。また、据置型決済端末の「Incredist Trinity(インクレディストトリニティ)」などバリエーションもあります。ICチップ付きのクレジットカード、NFC対応のクレジットカードのほか、Apple Payや日本独自の電子マネーにも対応しています。
弊社の決済システムを導入するメリットは、弊社がiPadの決済ソリューションを日本国内でいち早く展開していることです。アプリケーションとの連携やIncredist シリーズをはじめとする決済端末も自社で開発・販売を行っているため、お客様にはSDKでの提供が可能となります。そのため、基幹システムとデータ連携が柔軟に対応でき、大手企業・上場企業に対してほぼ独壇場での展開をしています。
さらに、今後は自社の決済センターを持つことで、対面・非対面の決済の融合などお客様のニーズに合った幅広い決済サービスを提供してまいります。

さらに、同じ端末を利用してマイナンバーカードで本人確認を行う「myVerifist(マイベリフィスト)」も提供。マイナンバーカードをかざすだけで電子署名や署名検証、本人確認ができ、厳格な本人確認の「公的個人認証」が実現できます。
また、市販のAndroid端末を活用した新しい決済ソリューション「Tapion(タピオン)」も開発し、専用タブレットの「Tapionタブレット」も製品化しています。当初は初期コストを抑えたい小・中規模事業者に向けて開発したのですが、実際には訪問販売系の企業様やファストフード様など、大手企業様からの引合いを多数いただいているサービスです。
ーー貴社の強みを教えていただけますか。
片山圭一朗:
弊社の強みは、システム開発で培ったスキルを活かした製品開発と、自社製品の優位性です。私たちはシステム開発と製品開発の2事業を展開していますが、システム開発では金融や物流、デジタル放送など、さまざまな分野で顧客のニーズに合わせた開発を行うことで、エンジニアのスキルアップにつながっています。そして、このシステム開発で技術を培ったエンジニアが製品開発に携わることで、高品質な製品を生み出すというサイクルが出来上がっています。
もう一つの強みが、自社で開発・運用するフライト決済センターが対面決済とECサイトなどの非対面決済の両方に対応している点です。どちらか一方に特化している企業はありますが、1社で両方に対応しているのは弊社だけではないでしょうか。この強みを活かしたサービスを提供し、より便利な社会の構築に貢献できると考えています。
スキル向上に余念がない技術者が集まった組織
ーー組織の特徴や社風について教えてください。
片山圭一朗:
私がCTO(最高技術責任者)を兼ねていることもあり、技術の好きな人が多い会社で、CFO(最高財務責任者)も含め社員の9割以上が技術者か元技術者です。AIによる自動プログラミングなど最新技術を導入するなど、常に新しい技術を取り入れ、挑戦できることが弊社の特徴ですね。
また、社員の特徴としては、若手社員が自主的に勉強会を開催し、自ら社内研修を企画するなど、自主性のある人が多いです。勉強会は社員のスキル向上につながることを前提に、就業時間内の開催を許可しています。
社内の雰囲気は、コンパクトな組織なため事業部間の交流が盛んで、役職ではなく名前で呼び合うなど、風通しが良い職場だと思います。私は新入社員を含め全社員から「片山さん」と呼ばれています。
ーー片山社長が社員の方々と接する機会は多いですか。
片山圭一朗:
私の執務室はガラス扉で中の様子が見えるようになっており、電話をしているとき以外は誰でも入って来られるようにしています。3年ほど前まで私もプログラムを書いていて技術的なアドバイスもできるので、社員も相談しやすいようですね。
採用面接と新人教育に力を入れ、人材のミスマッチを防止
ーー採用についてはいかがですか。
片山圭一朗:
弊社は新卒採用に力を入れています。最終面接は私を含め役員全員が参加し、特に技術を磨き続ける情熱があるかを重点的にチェックしています。
常に技術改革が行われる職場ですが、入社1年目から新製品開発を任されるなど、裁量権の大きな仕事ができるのが弊社で働く魅力の1つです。そのため、技術者としてスキルアップしたいという方には成長できる環境が整っています。
ーー新入社員教育の取り組みを教えてください。
片山圭一朗:
入社から3ヶ月間は外部の研修所で、他社の新入社員と一緒にシステム開発の基礎を学び、その後の1ヶ月間は、CTO補佐官と若手メンバーで社内研修を実施します。昨年の研修では、仮想的に新製品の企画・開発を行いました。「大学生向けのマイナンバーを活用したサービスを考える」というテーマに対して、マイナンバーで出席確認ができるサービスを提案してくれたチームがあり、実用性の高い企画が研修の段階で生まれることもあります。
この研修を通して、事業部の全マネジャーが参加する週に一度の報告会で、一人ひとりの適性を見極めた人員配置を行うことで、職場のミスマッチの防止につながっています。
将来仲間になる人・起業を目指している方々へのメッセージ
ーー今後の展望をお聞かせください。
片山圭一朗:
弊社の製品を世の中に普及させ、キャッシュレス化の推進に貢献したいですね。そのために、今後は、病院を受診する際に2回目以降の支払いを自動化するなど、決済サービスの機能をさらに拡充していく予定です。また、Android端末を使用した決済システム「タピオン」の普及拡大も目指しています。
世の中の役に立つシステムを提供するために、今後も新しい技術を積極的に取り入れ、開発効率を上げていこうと考えています。
ーー最後に貴社への入社を希望している方や、起業を考えている方へメッセージをお願いします。
片山圭一朗:
みなさんには「技術で社会を変える」、そんな強い想いを持ってほしいですね。技術者は研究者ではなく製品を生み出すイノベーターなので、「新しい技術で世の中をもっと便利に、人々の生活をより豊かにする」といった高い志を持つことがイノベーションの糧になります。起業するにしてもこうした気概がないと、その会社は労働力を集めただけの人材会社になってしまいます。
また、プライベートでもさまざまなことに挑戦し、視野を広げるのもおすすめしたいです。私自身、会社経営をしながら27歳までアルペンスキーをしており、全日本社会人選手権の出場経験もあります。また、ジャズのレーベルを立ち上げ、5枚のアルバムを出しています。このように、仕事だけに固執せずさまざまな場所で経験を積み、人間性を磨いていってください。
編集後記
参画したばかりの会社の事業撤退が決まり、顧客を守りたいという想いに駆られて経営者の道を歩み始め、一人社長となってから再起し上場を果たすなど、激動の人生を歩んできた片山社長。自分の力ではままならない窮地に追い込まれた当時のエピソードも、ユーモアを交えながら常に明るく話す姿が印象的だった。株式会社フライトソリューションズはこれからも日々技術力の向上に努め、まだ世の中にない、新たなサービスを提供していくことだろう。

片山圭一朗/1962年、東京生まれ。1984年国立電気通信大学を卒業後、大学発ベンチャーに開発責任者として参画し、日本最初のコンピューターグラフィックマシンの開発に従事。1988年前身となる株式会社フライト(現:株式会社フライトソリューションズ)を創業、代表取締役社長に就任。2004年東証マザーズ(現:東証スタンダード)への上場を果たし、現在も代表取締役社長兼CTOとして技術開発に携わる。