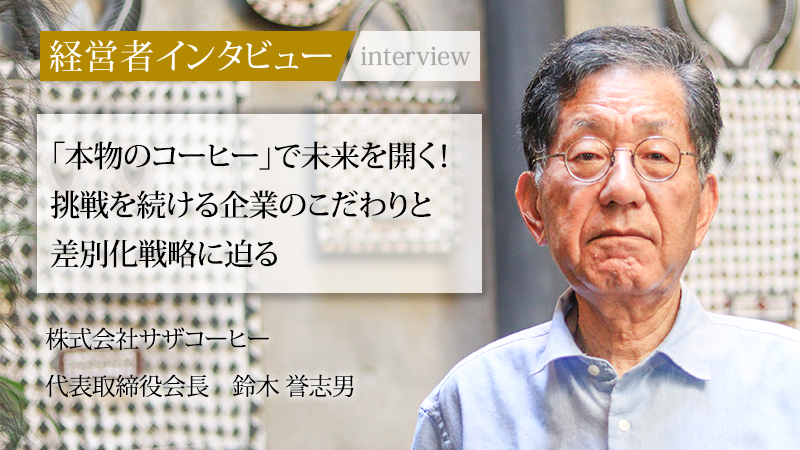
茨城県ひたちなか市に本店を構え、独自の哲学でコーヒー業界に新風を吹き込む株式会社サザコーヒー。「1杯5万円」の最高級コーヒーの販売や、地域の歴史と連携した「頭で飲むコーヒー」の開発など、他のコーヒーチェーンとは一線を画すユニークな戦略で知られる。映画館の経営危機から偶然始まったコーヒー事業を、いかにして誰も真似できない個性的なブランドへと育て上げたのか。創業者である代表取締役会長の鈴木誉志男氏に、これまでの歩みと差別化戦略の真髄、そして未来への展望を聞いた。
映画館の閉館から始まった、コーヒーを巡る冒険
ーーコーヒー事業を始められたきっかけは何ですか?
鈴木誉志男:
私はもともと映画館の息子で、大学卒業後は東宝で映画の宣伝などをしていました。しかし地元に戻った頃、東京オリンピック後にカラーテレビが普及し、映画館の経営が立ち行かなくなったのです。その時にコーヒー店を始めました。
ーー創業当時はどのような状況でしたか?
鈴木誉志男:
コーヒーに関しての知識がないまま事業を始めたため、創業から3年目に1人で中南米の農園を旅しました。最初は月に20〜30キロの豆しか使わない、まさに手探りのスタートでした。
夢中でやっていると面白いもので、苦労は感じませんでしたが、今思えば、朝7時から夜11時まで働く無茶苦茶な仕事ぶりでしたね。何より、映画館が立ち行かなくなる中で、子どもの頃からお世話になった従業員たちに退職金を払うため、一生懸命働いたというのが最初の原動力です。
世界基準と探究心で見いだした「本物のコーヒー」
ーー良いコーヒー豆を見極める上で、大切にしていることは何ですか。
鈴木誉志男:
一つは味で追いかけること。もう一つは、環境です。おいしいお米が昼夜の寒暖差が激しい場所で育つように、コーヒーも植物としてのストレスがかかる環境でこそ、良い遺伝子を残そうとしておいしくなります。私は、収穫量が多い品種ではなく、そうした環境で育った本当においしいコーヒーが採れる品種を追いかけたいのです。
ーー貴社が目指す「おいしいコーヒー」は、どのような基準で評価されているのですか。
鈴木誉志男:
スペシャルティコーヒー協会が定めた世界基準です。これは感性ではなく、科学的な理屈に基づいています。アロマ、フレーバー、後味、コク、酸味など10項目で点数をつけ、その合計点が最も高いものが最高のコーヒーと定義される。私たちはこの世界基準でトップクラスのものを目指し、生産国で開かれる品評会で点数の高いものを買い付けるよう努めています。
ーー高品質を支えているのは、どのような要素でしょうか。
鈴木誉志男:
良い豆を買い、上手に焙煎し、高い技術で淹れる。この3つが基本です。特に抽出技術には自信があり、弊社の社員はバリスタの全国大会で優勝、世界大会で2位という実績も持っています。しかし、私たちの品質を本当に支えているのは、会社全体のチームワークです。なぜこのコーヒーがおいしいのか、その価値をお客様にご理解いただく努力を続け、それに応えて購入してくださるお客様との信頼関係があってこそ、私たちの取り組みは成り立つのです。
「脳足りん」な差別化戦略で常識を打ち破る

ーー貴社の差別化戦略について、具体的な事例があればお聞かせください。
鈴木誉志男:
私たちは、他社が手がけないようなことにも挑戦します。その象徴が、現在世界で最も高価な「ゲイシャ」というコーヒーです。通常のニューヨーク国際相場取引所のコーヒーが、1ポンド3〜4ドルのところ、私たちは5,000ドルもするコーヒーを10年間も買い続けています。業界では「サザコーヒーは少し脳が足りん」と言われていますよ。
ーー1杯5万円にもなるコーヒーを、なぜ買い続けるのですか?
鈴木誉志男:
もちろん、それで儲かっているわけではありません。これは一つの話題性であり、差別化です。このコーヒーは5〜6キロといったごく少量しか存在しないため、店舗数が多い大手企業では全店で扱うことができず、買うことができません。だからこそ、私たちが「世界で一番高いコーヒーを持っている」という事実がブランドになる。この「脳足りん」と言われる部分こそが、私たちのコーヒーの特徴なのです。
歴史や物語を紡ぐ、味覚と「頭」で味わうコーヒー
ーー商品のコンセプトとして、味以外に大切にされていることはありますか。
鈴木誉志男:
私たちは、味覚だけでなく「頭で飲む」コーヒー、つまりその背景にある物語や歴史も一緒に楽しむという飲み方を提案しています。たとえば茨城大学、筑波大学、千葉大学、東洋大学など、さまざまな大学と連携してコーヒーを開発しました。また、茨城県の歴史にちなんで、徳川慶喜公やその弟君、咸臨丸の航海長といった人物にまつわる徳川将軍のコーヒー、日本史に登場する、幕末の人々が飲んだコーヒーもつくっています。水戸黄門様がコーヒーを飲んでいたという史実も掘り起こしているところです。
ーー「頭で飲むコーヒー」で何を目指していますか?
鈴木誉志男:
コーヒーを茨城県の新しい観光品にしたい、という思いがあります。お土産といえばお菓子が定番ですが、そこに歴史や物語のあるコーヒーという選択肢を加えたい。これは新しい試みです。幸い、大学と連携した商品は学生や同窓生の方々に買っていただいており、売上の一部を学校に寄付させていただくという、少し変わった形で地域にも貢献しています。
次代へつなぐ哲学、サザコーヒーが描く未来図
ーー事業承継についてはどのようにお考えですか?
鈴木誉志男:
会社の永続的な発展のためには、事業承継が極めて重要です。そのためには、後継者である社長が自身のビジョンに基づき、主体的に挑戦できる環境を整えることが肝要だと考えています。私自身も創業者として事業を展開してきた経験から、次代の経営には過度な干渉をせず、その自主性を尊重するよう心がけています。代替わりしても挑戦を続けられる会社であるためには、私が息子を見守ることが良いことなのだろうと思っています。
ーー新商品開発や今後の展望についてお聞かせください。
鈴木誉志男:
新商品開発は、大手にはできない、小さい会社だからこそできることを追求します。良いコーヒーは、実は小規模な農園で少量しか採れないことが多いのです。弊社では、社長自ら海外の生産者を訪ね、そうした希少な豆を直接仕入れています。現場に行かなければ分からないことを見つけ出し、スピーディーに商品化していく。これが私たちの強みです。海外展開については、現在、台湾の百貨店で商品を展開しており、今後も茨城県が推進する海外展開の動きと連携しながら、アジア圏での販売を強化していきたいですね。
編集後記
映画館の経営難をきっかけに、偶然始まったコーヒー事業。創業者である鈴木誉志男氏は、以来50年以上にわたり、常に常識にとらわれない独自の道を歩んできた。「1杯5万円のコーヒー」や「頭で飲むコーヒー」という奇想天外な戦略は、単なる話題づくりではない。それは、大資本と同じ土俵で戦うことを避け、自社の価値を最大化するための、計算され尽くした生存戦略である。その根底には、大手と同じことはしないという、創業者としての強い意志と遊び心が感じられる。「他社が手がけないことに挑戦する」という哲学は、次の世代に着実に受け継がれ、サザコーヒーの新たな物語を紡いでいくだろう。

鈴木誉志男/1942年生まれ。1969年株式会社サザコーヒーを創業。1992年勝田信用組合理事長、2002年ひたちなか観光協会会長、2012年ひたちなか商工会議所会頭、現在名誉会頭、サザコーヒー会長、日本コーヒー文化学会副会長を歴任。














