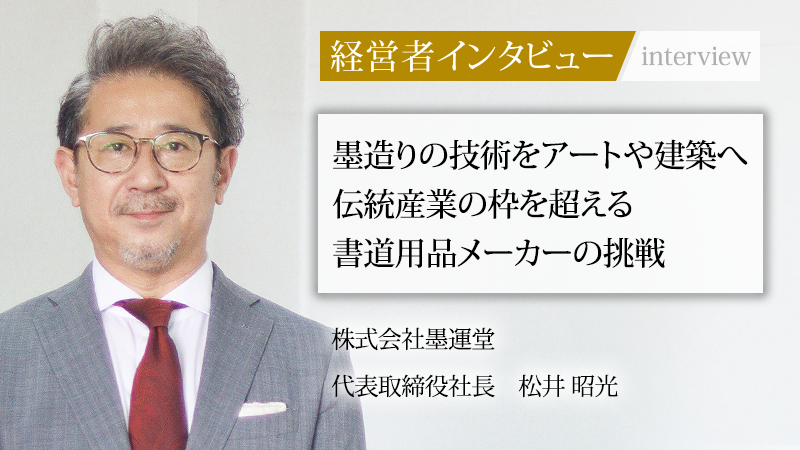
固形の墨と液体の墨液、双方を製造する国内でも数少ない書道用品メーカー、株式会社墨運堂。100年以上の歴史を誇る同社は、伝統を継承しつつ新たな分野にも挑戦を続ける。書道の枠を超え、建築資材や福祉用品といった領域にも進出している。その舵取りを担うのが、代表取締役社長の松井昭光氏だ。日本経済新聞社のグループ会社である日本経済社で10年間勤務した後、家業へ転身。広告業界で培った視点を武器に、大胆な組織改革を断行してきた。斜陽産業と言われる業界で「なくてはならない存在」を目指す、その情熱と未来への展望に迫る。
「売れるもの」を見抜く視点。広告業界で培った経営の礎
ーー社長の社会人として最初のキャリアについてお聞かせください。
松井昭光:
大学時代に広告会社でアルバイトをしていた経験から、その世界に魅力を感じており、卒業後も広告業界で働きたいという気持ちがずっとありました。当時、弊社には親兄弟が多くいたので、特に自分が継がなければという意識はあまりなく、親からも「無理にとは言わないが、いずれ戻ってきてくれたら嬉しい」という程度にしか話されていませんでした。そのため、まずは自分の希望を叶えようと広告会社を探す中で、日本経済新聞社のグループ会社にご縁をいただき、入社いたしました。
ーーその広告業界でのご経験は、現在の経営にどのように活かされていますか。
松井昭光:
日経グループだったため、情報に対して非常に敏感でなければならない環境でした。ビジネス寄りの案件が多く、広く視野を持たなければならなかった経験は今に活きています。特に後半は通販広告を長く担当し、物事の見方が大きく変わりました。
広告で売れなければ掲載料が入らない仕組みだったので、どうすれば売れるのか、人の行動に繋がるのかを常に考えるようになりました。そのプロセスを通じて、物に対する多角的な見方が養われたと感じています。
100年企業のアナログ文化と対峙 事業承継と改革への道
ーー広告業界で培った視点を持って家業に戻られた際、どのようなギャップやご苦労がありましたか。
松井昭光:
家業なのである種の覚悟はありましたが、もどかしさは強く感じました。社会人として10年も働くと、ひと通りの仕事はできるという自負がありました。しかし、製造業のことは何も知らず、得意先からは「何も知らない若造が来た」という目で見られる。そのジレンマは大きかったです。
また、会社の何もかもがアナログ。最新のシステムを使うのが当たり前だった前の会社とは雲泥の差でした。そのため、非効率に感じる部分も多く、慣れるまでの1年間は我慢しました。そして、がむしゃらに営業で全国を回り、業界について勉強しました。
ーー社長に就任された経緯についてお聞かせください。
松井昭光:
先代の父が「元気な内に社長交代したい」というタイミングと、私自身「親が元気なうちに事業承継を済ませたい」という思いもありました。父が会長として残ってくれたおかげで、銀行や各種団体への引き継ぎもスムーズに進みました。2015年に社長に就任しましたが、本当の意味で事業承継が完了したのは2022年頃です。
ーー社長に就任されて、まず何から着手されたのでしょうか。
松井昭光:
まず、組織をフラットにしたいと考えました。以前は人数の割に役職や部署が多く、情報伝達に時間がかかったり、特定の仕事が属人化したりする問題があったのです。そこで部署を営業・製造・管理の3つに集約し、管理職の世代交代を進め、社内の風通しを良くしました。
この組織改革は、品質向上の取り組みにもつながっています。これまで見過ごされてきた無駄な部分、たとえば過剰な在庫や不要な製造工程なども見えるようになり、全社で改善に取り組むことでコストカットを実現できました。今後は、新しい機械設備やシステムも導入し、さらなる品質向上を目指します。
あわせて、広報に対する考え方も大きく変えました。先代はメディア等にはあまり出ませんでしたが、われわれの世代は会社のことを知っていただく良い機会だと捉え、SNSの活用や学校見学の受け入れ、講演会など、広報PR活動にも積極的に取り組んでいます。
書道の技術を核に、建築から海外まで。墨運堂の事業展開

ーー改めて、貴社の事業内容について教えてください。
松井昭光:
書道用品の製造卸が主事業ですが、それだけでは会社の規模を維持していくのが難しいのが現状です。そこで、弊社の軸足である「墨造り」の技術やノウハウを応用して、他の分野の製品を開発しています。たとえば、木造建築で使う墨液や漆喰に混ぜる墨、木の剪定口に塗る癒合剤などです。その他にも、ホームセンターや金物屋に並ぶような建築・園芸用品も手掛けています。
ーー海外展開の取り組みについて、お聞かせください。
松井昭光:
筆を持つ文化圏、主に中国や台湾、韓国といったアジア圏を中心に展開しています。もともと墨は中国から伝来しましたが、今では「日本製の品質が非常に良い」と評価を得ています。弊社はかなり早い段階から中国市場に進出しており、現地の代理店と組んで市場開拓や商品開発を進めてきました。この業界は特に人間関係が重要です。そのため、物以上に代理店との信頼関係を強化することを大切にし、中国や韓国でのシェアを広げていく考えです。
ーー多様な製品を開発する上で、特に大切にされていることは何でしょうか。
松井昭光:
「安心・安全・安定」という3つのキーワードが、長く使っていただける商品づくりの根底にあります。近年は大学との共同研究やアーティストによる監修を重視しています。つくり手だけでなく、研究者や利用者の視点を取り入れることで、現代のニーズに合った製品開発を目指しています。
それに加え、SNSなどを通じてさまざまなジャンルの人との繋がりも大切にしています。日本酒のラベルやお店の暖簾では、筆文字が使われることがあります。そこでアーティストの方々と連携し、日常の場で弊社の製品を使ってもらうことが、効果的なブランディングに繋がると考えています。
伝統と革新の両輪で描く、「なくてはならない存在」への道

ーー最後に、今後5年、10年先を見据えた長期的な展望をお聞かせください。
松井昭光:
最終的な目標は、この業界で「なくてはならない存在」、つまり唯一無二の存在にならなければならないと考えています。業界規模は縮小していくかもしれませんが、その中で生き残る会社になることが重要です。そのためには、高い商品開発力と、全国に啓蒙活動を続ける体制づくりが不可欠です。
弊社が事業を続けなければ、書道家の方々が作品をつくれなくなってしまいます。その使命感を常に意識し、伝統と革新の両輪で会社を前に進めていきたいですね。
編集後記
100年以上の歴史を持つ同社は、「書道」という文化を未来へ繋ぐ使命感を胸に、伝統を守りながらも大胆な変革を遂げている。その根底には、ユーザーの声に耳を傾け、社会の変化に敏感であろうとする、広告業界で培われた確かな視点があった。「なくてはならない存在」を目指す同社の真摯な挑戦から、今後も目が離せない。

松井昭光/1971年奈良県生まれ、関西学院大学卒。大学卒業後、株式会社日本経済社へ入社。2003年に家業である株式会社墨運堂へ入社。本社、福岡営業所、東京店で勤務の後、2015年に同社代表取締役社長に就任。現在は奈良製墨組合の理事長、全国書道用品生産連盟の支部長も務める。また、地域のさまざまな団体にも所属し、地域社会への奉仕活動にも注力している。














