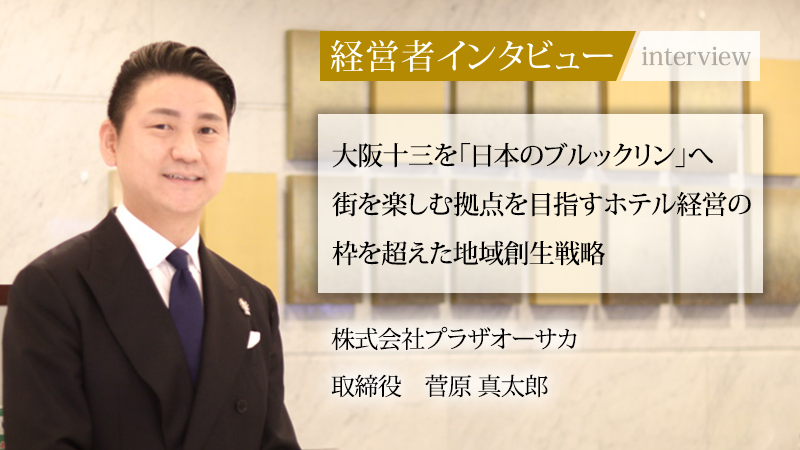
大阪・十三のランドマークとして知られる「ホテルプラザオーサカ」。同社を率いる取締役の菅原真太郎氏は、一度は家業を継がず、銀行員の道を選んだ。しかし、多くの経営者との出会いを経てその決意は変わった。神戸のホテルでの下積み時代に知ったサービス業の真の喜びを胸に、父から継いだホテルの改革に着手。現在は、ホテル経営の枠を超え、街全体の価値を高める壮大な挑戦を見据えている。菅原氏を動かす情熱の原点と、そのビジョンに迫る。
経営者との出会いが導いた家業を継ぐという決意
ーー貴社に入社されるまでのご経歴についてお聞かせください。
菅原真太郎:
「ホテルプラザオーサカ」は祖父が創業者で、父が跡を継いでいました。しかし、私自身に家業を継ぐ意識は全くありませんでした。私が大学生だった2010年頃、大阪の観光業は今ほど盛り上がっていませんでした。そのため、ホテルの業績も芳しくなかったのです。父からも「ホテルに戻らずに、就職して頑張ればよい」と言われていたため、他の学生と同じように就職活動をして、三井住友銀行に入社しました。
銀行の道を選んだのは、「さまざまな経営者の方とお会いしてみたい」という思いがあったからです。銀行の法人営業なら、若くてもその機会を得られるのではないかと考えました。
銀行では多くの経営者の方々とお会いしました。その中で、皆さんがご自身の会社や社員、ビジョンを非常に大切にされている姿に感銘を受けました。その頃から「祖父が創業し、父が継いでいるこのホテルに自分が関わらないのは違うのではないか」と思い始めました。
当時、ホテルの業績が芳しくなかったので、父には家業を継ぐことを大反対されました。しかし私は、勝手に辞表を提出し、退職後に報告しました。
サービスの本質を知った下積み時代の「感動体験」
ーー銀行退職後、すぐに貴社に入社されたのでしょうか。
菅原真太郎:
自分自身で宿泊業の現場をしっかり学んでから戻りたい、という思いがありました。その時、ご縁があって神戸ベイシェラトンホテルで修業することになったのです。最初に配属されたのは、バイキングレストランのホールサービス部門でした。当時私は25歳でしたが、大学生のアルバイトの方々に頭を下げ、皿洗いや掃除から始めました。サービス業のアルバイト経験もなかったので、銀行員時代のプライドは打ち砕かれました。
そこから仕事は一通りできるようになったものの、その根幹にある面白さはまだ分かっていませんでした。そんなある日、転機が訪れました。レストランにいらっしゃった老夫婦と娘さんグループの会話に耳を傾けると、お客様が「私、今日誕生日なの」と話していたのです。そこで食後の飲み物の注文を受けた際に、ラテアートで「Happy Birthday」と描いてお出ししました。すると、とても喜んでくださいました。そのお客様は翌日、お友達を連れてきてくださり、私のファンになってくれたのです。この時に、サービス業の本質を理解しました。
それまでは、注文されたものをただ出す「オペレーション」をこなすだけでした。しかしお客様をよく観察すると、そこにはたくさんのヒントが隠されていることに気づいたのです。お客様が口に出す要望以上のもの、つまり付加価値を提供することで初めて感動が生まれる。この一連の流れに気づいてから、仕事がとても楽しくなりました。
ーー貴社に入社されてから、どんな取り組みをされましたか。
菅原真太郎:
当時、ホテルには実質的な企画広報部がなく、販促物も古いままでした。そこでシェラトンでの経験を活かし、販促チラシのつくり直しから着手しました。ホームページのリニューアル、SNSの活用まで、一つひとつ全てやり直していきました。
独自の強みは圧倒的なスケールと地域とのつながり

ーー改めて、「ホテルプラザオーサカ」の特徴や強みについて教えてください。
菅原真太郎:
最大の強みは、そのスケールメリットです。客室数が650室と非常に大きなキャパシティを誇ります。さらに宴会場やレストランも充実しており、お客様のあらゆるニーズに応えやすい環境です。また、シティホテルでありながら、地域の皆様との繋がりが非常に深いのも特徴だと考えています。
ーー現在、どのような取り組みに注力されていますか。
菅原真太郎:
近年、レストラン事業、特にインバウンドのお客様をターゲットにした和牛の鉄板焼レストランに力を入れています。このレストランは、旅行の口コミサイト「トリップアドバイザー」で、大阪のレストラン部門1位を獲得したこともあります。今後はこの成功事例を他のレストランにも共有し、付加価値向上を目指します。具体的には、和食レストランでハラル認証を活かし、イスラム教徒の方向けに本格的なコースを提供する計画を立てています。

ーー採用・人材についてはどのようにお考えですか?
菅原真太郎:
外国人材の採用と、生産性を高めて給与水準を上げていくこと。この両輪で進める必要があると考えています。現在35名の外国人スタッフが働いています。彼らは母国を離れて日本で働くという強い意志と熱意があり、非常に優秀です。今後、ますますインバウンドのお客様が増えることが予想されます。語学が堪能な彼らが活躍できるチャンスも増えるでしょう。将来的には経営幹部や役員にも登用し、彼らが「日本で働いて良かった」と思えるよう、給与や役職でしっかりと応えていきたいです。
宿泊業界の未来を拓くホテルから始まる街づくり

ーー今後の展望についてお聞かせください。
菅原真太郎:
大阪・十三という街は、梅田から近いのに「治安が悪い」といったネガティブなイメージが根強くあります。しかし、この街にはディープな大阪らしさや魅力的な飲食店、独自の文化もあります。そこで現在は、地元の方々と協力し、十三を「目指して来る街」にするプロジェクトを進めています。
目標は、十三を「日本のブルックリン」のようにブランディングすることです。かつて治安が悪いとされたブルックリンは、アートや文化の力でオシャレな街に生まれ変わりました。そのように、十三もブランディングしたいと考えています。その中心的な取り組みが「淀壁(よどかべ)」というウォールアートプロジェクトです。街の壁にアートを描き、街全体をギャラリーのようにしています。加えて、十三ならではのナイトカルチャーやグルメを掛け合わせます。これにより、世界中の人々が「十三に行きたい」と目指して訪れる街にしたいです。
ただ、完全に海外向けにつくり変えるわけではありません。十三ならではのローカルな雰囲気や大阪らしい“泥臭さ”は残したいと考えています。そして、本物の日本の文化や人々との交流を楽しめる街づくりを目指します。十三という街の中心に「ホテルプラザオーサカ」があり、十三を目的として泊まりに来てくださったお客様が、街を周遊して楽しむ。そんな街のブランディングに貢献できたら嬉しいです。
編集後記
銀行員からホテルマンへ。その異色の経歴は、決して平坦な道のりではなかった。しかし、多様な経営者との出会い、サービス業の現場で知った「感動」の価値そのすべてが、今の菅原氏を形づくっている。ホテル単体の成長に留まらず、地域全体を巻き込んで「十三」という街の価値を高めようとする挑戦は、宿泊業界の新たなモデルケースとなるだろう。

菅原真太郎/1988年兵庫県生まれ。ニューヨーク州立大学バッファロー校への一年間の留学を経て、2010年に甲南大学を卒業。株式会社三井住友銀行で約3年間の法人営業を経験し、その後は神戸ベイシェラトンホテルでの勤務を経て、2016年に株式会社プラザオーサカに戻り、取締役に就任。現在は、宿泊業界団体の全旅連青年部の役員や宿泊業技能試験センターの理事としても活動している。














