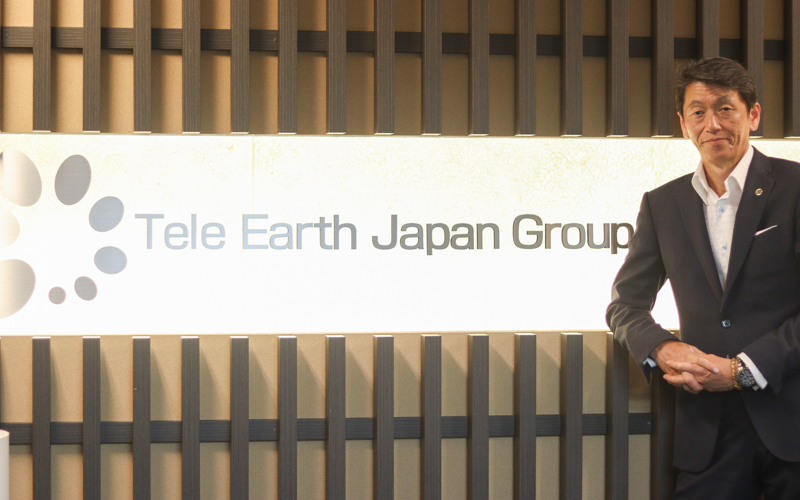北海道の地で創業し、今や全国にその名を知られる味付きジンギスカンのパイオニア「松尾ジンギスカン」。同店を運営する株式会社マツオは秘伝のタレを武器に、レストラン運営と食品製造・販売の二つの顔を持つ独自の強みを確立している。父の急逝により、20代で予期せず家業に戻った代表取締役の松尾吉洋氏。伝統を守り抜く一方で、「停滞は後退」との信念から、大胆な事業のスクラップ&ビルドやリブランディングを実行した。近年ではM&Aやフランチャイズ事業にも乗り出し、人気フットウェアブランド「スケッチャーズ」のフランチャイズ運営を手がけるなど、その挑戦はとどまることを知らない。「三方よし」の精神を胸に、老舗の暖簾を背負いながら次なる成長を目指す同氏に、その軌跡と未来への展望を聞いた。
予期せぬ事業承継と経営の原点
ーー社会人としてのキャリアはどのようにスタートされたのでしょうか。
松尾吉洋:
大学卒業後、弊社に入社しました。父とは当初、「私が30歳になるまでは東京で社会人経験を積み、将来的に家業を継ぐ」というイメージを共有していました。しかし、父が50歳で急逝。当時会長だった祖父から「大学を卒業したら帰ってこい」と言われました。いずれ自分が継ぐ覚悟はしていましたが、想定よりも早いタイミングで家業へ入ることになりました。
入社後は、会社の原点である羊肉の加工処理などを行う工場からキャリアをスタートさせました。肉のトリミングや、社内でも数人しか携われない秘伝のタレの調合など、自社のサービスの根幹を学びました。その後は祖父の一声で回転寿司事業をゼロから立ち上げたり、観光客向けの大型施設でレストラン運営から土産品の販売、旅行代理店への営業まで担当したりと、さまざまな現場を経験しました。最後に札幌初の直営店立ち上げを担い、ようやくジンギスカン事業の最前線に戻ってきた、という経緯です。
ーー多岐にわたる現場経験は、現在の経営にどう活きていますか。
松尾吉洋:
同族企業の跡継ぎということで、「『直系のボンボンか』と言われるのだけは避けたい」という強い思いがありました。だからこそ、「誰よりも働いてようやく周りと同じスタートラインに立てる」と自覚し、入社以来ずっと走り続けてきました。会社の全部門を現場の第一線で経験できたことは、今の私の大きな財産です。それぞれの現場が抱える課題や可能性を肌で理解しているからこそ、自信を持って経営の舵取りができています。
伝統を未来へ繋ぐための大胆な事業再構築

ーー社長就任後、どのような改革から着手されたのでしょうか。
松尾吉洋:
主に「リブランディング」「事業のスクラップ&ビルド」「働き方改革」の三つです。特に苦労したのは、時代の変化に合わなくなっていた大型観光施設事業からの撤退という決断でした。従業員の雇用をどう守るかという重責を背負いながら、事業譲渡や撤退を推進しました。この痛みを伴う事業の「スクラップ」があったからこそ、本業であるジンギスカン事業に経営資源を集中させ、ブランドを再構築する「ビルド」が可能になりました。
ーー経営者として大切にされている理念についてお聞かせください。
松尾吉洋:
創業者である祖父が自然と実践していた「三方よし」の精神です。祖父は三方よしという言葉は使っていませんが、常々、「金を追うな。お客様に喜んでもらえれば、利益は後からついてくる」と話していました。買い手、世間、そして売り手である私たちも幸せになる。この考え方が経営の根幹にあります。
また、祖父は「謝恩」、つまり感謝の思いを取引先やお客様に還元することを非常に大切にしていました。その精神を今も引き継いでいます。
ーー地域や次世代に対して、どのような取り組みをされていますか。
松尾吉洋:
「ジンギスカンは観光客が食べるもの」というイメージになってしまっては本末転倒です。あくまで地元、北海道で愛され続けなければ、全国、そして世界には通用しないと考えています。その思いから、創業の地である滝川市近郊の小中学校へ、毎年7月末に約1トンのジンギスカンを給食として無償提供しています。子どもたちに「松尾ジンギスカンの給食を食べたら夏休み」と感じてもらう。記憶に残る食文化としてこの味を次の世代へ継承していくことが、私たちの使命です。

羊肉の可能性を信じ目指す100億円企業への道筋

ーー貴社の事業における最大の強みは何だとお考えですか。
松尾吉洋:
創業以来の「秘伝のタレ」で味付けされたジンギスカンであることはもちろんですが、ビジネスモデルとしては「レストランチェーン」と「食品メーカー」という二つの軸を持つ点も強みです。レストランで私たちの味を知っていただき、ご家庭でパッケージ商品を楽しんでいただく。あるいはその逆のパターンもあります。
この両輪経営のおかげで、コロナ禍でレストラン事業が苦しい時期も、巣ごもり需要で食品メーカーとしての売上が伸び、会社全体を支えることができました。これは非常に大きな強みです。
ーー伝統の味を守りつつ、生産面ではどのような革新に取り組んでいますか。
松尾吉洋:
味の根幹に関わる部分は、今も頑なに手作業を守っています。たとえば、肉の脂や筋を手作業で丁寧に取り除くトリミング作業などです。その一方で、それ以外の工程では生産性向上のためのDXや機械化を積極的に推進しています。変わらぬ味を安全安心で、かつ持続的に提供し続けるためには、守るべき伝統と、攻めるべき革新の両方が不可欠です。

ーー今後のビジョンについてお聞かせいただけますか。
松尾吉洋:
グループ全体で「10年後に売上100億円企業」を目指すことを宣言しています。その中核はもちろんジンギスカン事業です。羊肉はまだ日本の食卓では馴染みが薄いですが、大きなポテンシャルを秘めていると考えています。栄養価も高く、豚、鶏、牛に次ぐ「第4の食肉」になり得るからです。「ジンギスカンのマツオ」から「羊肉といえばマツオ」を目指し、そのおいしさと文化を日本全国に広めていきます。その上で、M&Aや新規事業といった多角化にも挑戦し、変化に強い経営基盤を築いていきます。
成長を加速させるための異業種参入と人材戦略

ーー直近では特にどのような取り組みに注力されていますか。
松尾吉洋:
今期から次世代のフットウェアブランド「スケッチャーズ」の小売事業に参入しました。「ジンギスカン屋がなぜ靴屋を?」と周囲には驚かれましたが、記録的な好スタートを切り、すでに2号店の計画も進んでいます。これも「停滞は後退」という信念に基づく挑戦の一つです。
また、ジンギスカン事業においても、これまであまり使われてこなかった羊のタンや中落ちカルビといった部位の商品化を進めています。常に新しい可能性を模索し、お客様を飽きさせない努力を続けています。
ーー今後の事業展開を見据え、どのような人材を求めていますか。
松尾吉洋:
大きく三つの分野で、私たちの挑戦を加速させてくれる仲間を求めています。一つは、伝統の味を未来へつなぐ「食品工場の管理責任者」。品質と生産性の両方を追求できる方です。二つ目は、国内外の店舗展開を牽引する「飲食店のマネジメント人材」。ジンギスカンに限らず、弊社の持つ多様なブランドを成長させてくれる方を歓迎します。そして三つ目は、まだ見ぬ市場を切り拓く「海外事業のノウハウを持つ人材」です。ジンギスカンというコンテンツにこだわらず、共に世界へ挑戦できる方と出会いたいと考えています。
編集後記
北海道の食文化を代表する老舗、マツオ。4代目である松尾氏の言葉からは、伝統への深い敬意と未来へつなぐ覚悟が伝わってくる。しかしその手法は、大胆な事業改革や異業種参入など決して保守的ではない。「停滞は後退」という哲学は、変化の時代を生き抜くための確固たる戦略だ。創業者から受け継ぐ「三方よし」の精神を根幹に、食文化の未来と関わる人の笑顔を見据える。老舗の新たな挑戦は、まだ始まったばかりである。

松尾吉洋/北海道滝川市生まれ。1999年早稲田大学卒業。同年に株式会社マツオに入社し2014年に代表取締役社長に就任。「松尾めん羊牧場」の開設をはじめ、「スケッチャーズ」FC事業の展開、また積極的にM&Aも実施。ジンギスカンの食文化普及に努め、地元の学校給食へ食材の無償提供を行うなど、地域貢献にも注力している。滝川スカイスポーツ振興協会会長、滝川少年野球連盟会長、たきかわ観光協会副会長などを務める。