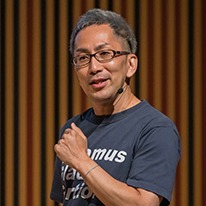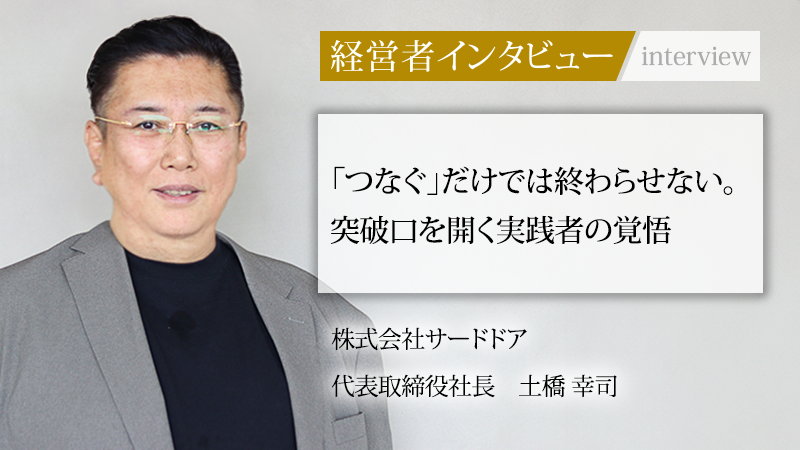
スタートアップの成長に欠かせないのは「信頼できる誰かと出会える場」だ。株式会社サードドア代表取締役社長の土橋幸司氏は、14年間にわたり、大手生命保険会社の中で起業家たちの挑戦に寄り添い続けてきた。誰もが相互に支え合える「他者貢献」の場として、マスターマインドビジネスコミュニティを創設。これまで継続してきた活動を本業として実践するため、2024年、60歳を迎える節目に法人化した。見えない扉の向こうに希望を見いだす、一人の経営者の言葉に耳を傾けた。
支援の限界と可能性に向き合い、仲間の力で扉を開く仕組みを構築
ーーこれまでのご経歴について、おうかがいできますか。
土橋幸司:
大学卒業後、第一生命保険に入社、幅広い業務を経験後、生保営業のあり方を変えたいとの思いから2010年に社内FA制度を利用して、直販営業部門に異動しました。コミュニティは士業の方々との協業から始まりましたが、徐々にスタートアップとの接点が増え、気がつけば14年間、常に起業家と向き合ってきました。彼らの情熱に突き動かされ、次第に自分の時間のほとんどをスタートアップ支援に費やすようになっていたのです。
具体的な役割は、起業家と大企業、投資家、行政などをつなぐ商談の仲介役でした。必要なリソースが明確になれば、最短距離で最適な人や機関を紹介し、数えきれないほどのマッチングを成立させました。しかし、活動を続けるうちに限界も感じ始めました。すべてのつながりを自分が仲介し続けるのは、物理的に困難です。私がいなくても、仲間同士が自然につながり、支え合える場所が必要だと痛感しました。
その思いが、現在のコミュニティ誕生のきっかけです。2011年にマスターマインドビジネスコミュニティを立ち上げました。以来、大企業からスタートアップ、専門家、行政まで、業界や立場を越えて多彩な人材が集い、信頼と共助の輪が広がり続けています。互いの知見を持ち寄り、補完し合うことで、一人では到達できない成果を生み出す。そのような「他者貢献」の場をつくることが、私の役割だと考えています。
ーー社名「サードドア」には、どんな想いが込められているのでしょうか。
土橋幸司:
この名は、アレックス・バナヤン氏の著書『サードドア』から取りました。人生には3つの扉があります。誰もが列をなす正面入口、特権階級用の裏口、そして、誰も教えてくれない「第三の通用口」です。私は、起業家がそのサードドアを見つけられるよう、伴走したいと考えています。足りないリソースやネットワークをつなぎ、彼らの行動の可能性を広げる存在でありたいです。
活動の根底には、「利他こそ、最も合理的な利己」という価値観があります。これは思想家ジャック・アタリの言葉ですが、私自身も深く共感しています。人に貢献できることが、自分の幸福にもつながる。この考えは、人が喜ぶ顔を見るのが好きだった母の影響が大きいのかもしれません。私にも母と同じ血が流れているんです。
仲間と支え合うエコシステムで起業家の挑戦に永続的な支援を

ーーコミュニティは現在、どのような形で運営されているのですか。
土橋幸司:
今では1,600名を超える起業家や専門家が参加するエコシステム(※1)に育ちました。活動の軸は、主に4つです。スタートアップと大企業などを結ぶ事業発表イベント、個別のビジネスマッチング、資金調達支援、そして専用のFacebookグループでの情報交換です。一度きりのご縁をつなぐだけでなく、継続的に交流できる仕組みを整えています。
イベント後の交流会では、私自身が極力お引き合わせを行い、質の高いマッチングを実現に努めています。商談の設定においては、お互いにとって利益がある関係になるストーリーを描くことを何よりも大切にしています。
また、社会学者のマーク・グラノヴェッターが提唱する「弱い紐帯の強さ」という理論があります。これは、普段接点のない人々が集まることでイノベーションが生まれるという考え方です。私たちのコミュニティでは、熱量の違いや参加姿勢の多様性もそのまま受け入れ、誰もが心地よく参加できる温かい空気感を大切にしています。
そして、メンバーに「セレンディピティ(偶発的な幸運)」をもたらすため、日々計画的に多動しています。個々の出会いを点ではなく線へ、そして面へと広げ、信頼の輪を強固にすることで、コミュニティ全体で社会に新たな価値を生み出し続けたいと考えています。
(※1)エコシステム:企業や個人同士がお互いに協力し、それぞれの業務やサービスを補う構造
ーーこれまでに、どのような成果がありましたか。
土橋幸司:
起業後、実稼働半年ほどでスタートアップのサービスをエンタープライズに導入6例、スタートアップ同士の協業4例、エンタープライズ同士の協業1例。東京都中小企業振興公社による事業可能性評価事業で連続21企業推薦採択、スタートアップのセカンダリー株式引受アレンジ等、明白な成果を形にすることが出来ています。
会社員時代に増して、マッチングの精度が上がっているのは、お引き合わせする両社の時間や機会を何よりも大切に考えているからです。起業して、自らが身に染みている現れだと思います。
ーー法人化にはどんな背景があったのでしょう。
土橋幸司:
実は、私自身もサードドアを見つける経験を経て、株式会社サードドアの設立に至りました。長年、無償でコミュニティ運営を続けてきたため、活動の有償化、そして法人化には大きなハードルがありました。
しかし、何十年ぶりに再会した友人が、私の活動に賛同し協賛を申し出てくれたのです。この後押しが、会社員としてのキャリアから一歩を踏み出し、起業を決断する大きなきっかけとなりました。
この経験は、私にとってまさに「見えない扉が突然、目の前に現れる」サードドアそのものでした。自分を信じて、まっすぐに進み続ける限り、必ずサードドアは見つかる。私自身の経験を通して今、確信しています。
スタートアップのその先へ 社会と未来を繋ぐ架け橋になる

ーー協業の呼びかけに込めた想いを聞かせてください。
土橋幸司:
人生のミッションとして、「社会課題解決の突破口を起業家と一緒に探し当てたい」と考えています。その中で、「仲間を増やし、共創社会を本気で実現したい」という思いが年々強まっています。これからも自分の持つ人脈や経験を惜しみなく還元し、志ある起業家のサードドアをともに探す支援者であり続けたい。そのような想いを込めています。
ーーこれから先、どのような未来を見据えていますか。
土橋幸司:
これまで以上に、思いを共有できる仲間と一緒に働きたいですね。年齢ではなく、情熱で仕事を続けていく。「生涯現役」を貫く覚悟で、今後もスタートアップの未来と社会の未来をつなぐハブとしてあり続けたいと思っています。
編集後記
取材を終えて印象に残ったのは、土橋氏の語る言葉が、すべて実体験に裏打ちされているということだ。「支援」という言葉に甘えず、利害を超えたつながりをどう設計するか。それに挑み続ける姿は、まさに利他の精神を体現し、「突破口を開く実践者」という表現がふさわしいだろう。

土橋幸司/福井県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。14年にわたりスタートアップへの商談支援を行い、社内論文制度最高賞、社長特別賞などを受賞。2011年にスタートアップ支援コミュニティを創設。2024年に株式会社サードドアを設立。東京都・三菱地所・WeWorkなどとの協業を経て、起業家と支援者をつなぐエコシステムの運営を本業化。特許庁「IP BASE AWARD」エコシステム部門グランプリほか受賞歴多数。現在上場企業グループ6社を含む18社の協賛を受け、コミュニティ運営を継続。