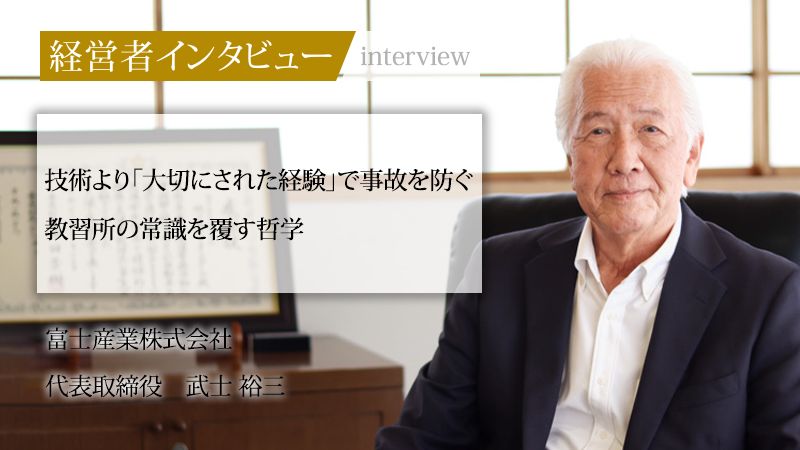
東京・足立区に根差す富士産業株式会社(竹の塚モータースクール)は、単なる運転技術の教育機関ではない。「人間力の育成」を通じて交通事故ゼロの社会を目指す教習所である。その根底には、生徒が「かけがえのない人間として大切に扱われた経験」こそが究極の安全運転マインドを育むという、確固たる信念が存在する。この哲学を築き上げたのが、30歳で労働争議の渦中にあった教習所のトップに就任するという経歴を持つ代表取締役、武士裕三氏だ。壮絶な経験から生まれた理念の軌跡に迫る。
「先生」から修羅場へ 未経験で乗り込んだ教習所の現実
ーーまずは、教習所に着任されるまでの経歴についてお聞かせください。
武士裕三:
大学時代に立教大学で初の少林寺拳法部を創設した経験が、すべての始まりです。そのご縁で、親会社である富士交通株式会社のタクシー乗務員にも拳法を教えることになり、学生ながら「先生」と呼ばれていました。卒業後はそのまま富士交通に入社し、30歳まで経理や配車を担当。さらに、当時会社が自費で対応していた重要な事故処理業務などにも携わりました。
ーーなぜ、教習所の管理者になられたのですか。
武士裕三:
当時、竹の塚モータースクールは労働争議が激しく、管理者が次々と辞めてしまう事態に陥っていました。管理者の不在は、卒業者の技能試験が免除される「指定自動車教習所」の指定取り消しに直結します。しかし、後任のなり手が見つかりません。最終的に「他に誰もいない」という理由で、30歳のとき、経験のない私に白羽の矢が立ったのです。
ーー着任当時の教習所は、どのような状況だったのでしょうか。
武士裕三:
所長として赴任してみると、コースのフェンスには赤い旗(※1)がずらりと並び、建物の中は窓がすべてアジテーション(※2)のビラで覆われて真っ暗です。掃除担当の従業員まで赤い鉢巻をしているのを見て、「大変なところに来てしまった」と実感したのを覚えています。そこから、組合との長い対話、というよりは「闘い」が始まりました。
(※1)赤い旗:社会主義・共産主義・労働運動の象徴
(※2)アジテーション:強い調子の文章や演説などによって人々の気持ちをあおり、ある行動を起こすようにしむけること
裁判の勝利と空虚感、経営者として「仲間」に目覚めた日
ーーどのようにして、その困難な状況を立て直していったのですか。
武士裕三:
教習所を閉鎖することも視野に入れ取締役に就任し、旧弊を打破して社員の意識改革を進めることから始めました。最大の争点は、組合が一切認めなかった人事評価に基づく賞与査定です。これを導入するために裁判となり、約1年続きました。最終的には、査定を1割で認めるという形で会社の主張が通り、事実上の勝利で終わりました。
しかし、この結果を素直に喜ぶことはできませんでした。意気消沈している社員たちの姿を見て、「何か違うな。彼らは組合員である前に、同じ会社で働く仲間ではないか」と感じたのです。そこで初めて、私は彼らを対立する相手としか見ていなかったのだと、心の底から反省しました。会社がどこを目指すのか、何を大切にするのかが示されない中で、彼らは大きな不安を抱えていたのでしょう。
その瞬間から、考え方が180度変わりました。「どうすれば社員が幸せに、誇りを持って仕事ができる会社になるか」と考えるようになったのです。教習所の仕事は、運転できなかった人を社会に貢献できるドライバーに育てる、大変意義のある仕事。この社会的価値を社員と共有し、共に目指すところから再出発しようと決意しました。
教習所は接客業 人間力を育む独自の幸福論
ーー「人間力経営」とは、具体的にどのようなものですか。
武士裕三:
「教習所は接客業であり、その最前線に立つ社員ができるだけ幸福であることが重要だ」と考えています。社員自身が幸せであることはもちろん、幸せそうな人に教わる方がお客様にとっても心地よいからです。そのために、職場の雰囲気づくりを何よりも大切にしています。
ーー職場の雰囲気づくりのために、特に徹底されていることはありますか。
武士裕三:
「人の悪口を絶対に言わない」ということです。悪口は会社の空気を悪くし、結局は自分自身が損をします。人には良い面と悪い面の両方がありますが、常に良い面に光を当てることで、人から学び、自分も成長できるのです。四季の美しいところだけを見れば一年中幸せでいられるように、物事の捉え方一つで世界は変わるのです。
「大切にされた記憶」で築く究極の安全マインド

ーー運転技術の指導以外でどのようなことを重視されていますか。
武士裕三:
教習所の最終的な目標は、卒業生が事故を起こさないことです。しかし、過去に苦い経験がありました。非常に優秀な成績で卒業した生徒が、死亡事故を起こしてしまったのです。このことから、知識や技術といった警察の完璧なカリキュラムだけでは事故を防げないと痛感しました。欠けていたのは、「安全運転をしよう」と心から思うマインドの問題だったのです。
このマインドは知識では育ちません。行動を変えるのは経験だけです。そこで私たちがたどり着いた結論は、教える側が身をもって示すことでした。つまり、生徒一人ひとりに「自分はこの教習所で、かけがえのない人間として大切に扱われた」という強い思いを持って卒業してもらえるようにしています。なぜなら、自分が大切にされた経験は、道路上の他の人も誰かにとって「かけがえのない存在」であるという想像力を育むからです。その実感こそが、他者を思いやる安全運転の本当の土台になると信じています。私たちの製品とは、目に見える物ではなく、生徒の心の中につくられる人間そのものなのです。
理念を文化に昇華させる仕組みづくり
ーー理念を浸透させるために、どのような制度を設けていますか。
武士裕三:
社員同士で毎月「感謝状」を贈り合う取り組みがあります。どんなささいなことでも感謝の気持ちを言葉にすると、日々の幸せに気づき、人を尊重する良い空気が生まれます。
また、人事評価ではお客様アンケートを最も重視しています。アンケートは「自分を映し出す鏡」だと位置づけています。私たちの仕事は、努力の量が評価されるものではありません。どれだけ一生懸命に教えたかではなく、生徒にどれだけ伝わり、吸収されたかという成果がすべてなのです。この評価方法によって、社員の意識は「教える」から「伝える」へと大きく変わりました。
ーー最後に、今後の展望についてお聞かせください。
武士裕三:
免許を取得する人が減っていく時代ですが、私たちの事業の根幹は変わりません。それは、手本となる社員一人ひとりの「人間力」です。私たちの仕事は、単に運転の知識や技術を教えるのではなく、生徒に安全運転のマインドを「感じてもらう」ことにあります。
そのために不可欠なのが、社員自身の人間的な魅力であり、心を磨き続ける姿勢です。この取り組みにゴールはありません。これまで築き上げてきた、人を思いやる文化をさらに突き詰め、深めていくことこそが、未来に対する私たちの答えであり、社会への貢献だと考えています。
編集後記
労働争議という「力」と「力」のぶつかり合いを経験した武士社長の語る「幸福」や「感謝」という言葉は、深く胸に響く。「大切にされた経験」を安全運転の礎に据えるという、一見、遠回りに思える発想は、人の心を動かす本質を的確に捉えている。これは単なる一教習所の物語ではない。あらゆる組織やリーダーが自らの在り方を問い直す、普遍的な示唆に富んだ経営哲学といえよう。同社の挑戦が示す未来に、大きな期待を寄せたい。

武士裕三/昭和23年東京都生まれ。立教大学社会学部卒、在学中に体育会少林寺拳法部を創部。昭和46年富士交通株式会社、富士産業株式会社取締役、平成8年に両社社長(竹の塚モータースクール設置者)に就任。平成14年千葉県君津モータースクール、平成15年群馬県高崎モータースクール設置者に就任。平成19年より12年間、東京指定自動車教習所協会の会長、並びに全日本指定自動車教習所協会連合会の副会長を歴任。














