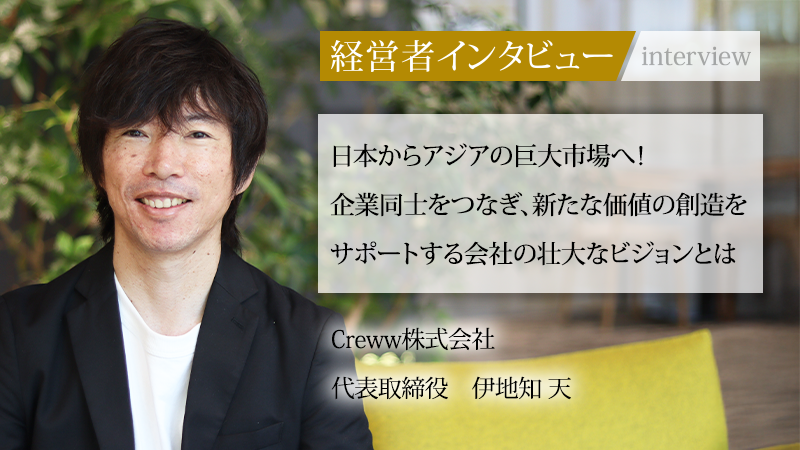
大手企業や中堅・中小企業が持つ経営資源と、スタートアップが持つ斬新なアイデアやテクノロジー。この両者を掛け合わせ、新たな価値を創造するオープンイノベーションを支援するプラットフォーム「Creww Growth」やスタートアップコミュニティ、オウンドメディア「PORT by Creww」などを運営するのが、Creww株式会社である。同社は、日本で「スタートアップ」という言葉がまだ浸透していなかった時代からその可能性に着目し、数多くの協業を実現してきたパイオニアだ。
代表取締役の伊地知天氏は、15歳で単身渡米し、海外で3度の起業を経験。2011年の東日本大震災を機に帰国し、日本の未来のために現在の事業を立ち上げた。彼の原動力とは何か。そして、日本から国境を越え、アジアと世界の壁を壊そうとする壮大なビジョンに迫る。
15歳で単身渡米。壮絶な原体験が育んだ起業家精神
ーー15歳で単身渡米を決意されたきっかけをお聞かせください。
伊地知天:
住んでいた家の隣に国連で働く方が引っ越してきたことが良い刺激となり、海外という広い世界へ目を向けるようになったのがきっかけです。当時、私が通っていた茨城県の高校で海外へ行く生徒はまずおらず、変わり者だったと思います。
実は、当時は英語が一番苦手な科目でした。そんな中、アメリカ政府が運営する交換留学プログラムを見つけ、100%落ちると思いながらも応募したところ、定員割れで参加できることになったのです。
渡航先はサウスカロライナ州の黒人が8割を占める地域で、アジア人は私一人という環境でした。シャワーは3分、食事は豆だけといった過酷なホームステイも経験しましたが、この1年間は人生で最も勉強し、精神的にも鍛えられ、結果的に少々のことではくじけない力が身についたと感じています。
ーー大学在学中に起業されたそうですが、どのような経緯だったのでしょうか。
伊地知天:
壮絶な留学の1年間に比べれば大学の勉強は要領をつかんでいたため、ある程度力を抜いてもこなせるほどで、時間に余裕が生まれました。私はお酒が飲めないのでパーティーなどには興味がなく、空いた時間でやりたいことを実現するために会社をつくったという経緯です。最初は、ロサンゼルスで出会った音楽業界の方々と日本の若者をつなぐ、短期の音楽留学などを手掛ける会社を立ち上げました。その後は、別の会社で言語の壁を越えるといって、当時では珍しかった翻訳のクラウドソーシングサービスを立ち上げ、越境のオンラインショッピングモール事業を行いました。
東日本大震災を機に帰国 人脈ゼロから事業を立ち上げた軌跡
ーー現在の事業を立ち上げた経緯についてお聞かせください。
伊地知天:
2011年の東日本大震災がきっかけです。当時、アメリカのニュースでは地震そのものよりもメルトダウンの報道が多く、周囲からは大反対されました。しかし、いてもたってもいられず、4月には日本へ戻りました。
その後、ボランティアで宮城県を訪れた際に「街は綺麗になっても、産業が撤退してしまえば復興はしない」という厳しい現実を目の当たりにしたのです。産業がなければ人は戻らず、街も発展しない。そこで、物資がない状況でも生み出せる産業は何かと考えたとき、場所の制約を受けにくいIT分野での起業、つまりスタートアップを増やすことが一つの答えではないかと思い至り、現在の事業を立ち上げたのです。
ーーその後、どのようにして事業を立ち上げたのですか。
伊地知天:
当時の日本のスタートアップエコシステム(※1)は非常に小さく、このままではいけないという強い問題意識がありました。そこで、事業に共感してくれる協力者を集めるために「アドバイザリーボード」(※2)という仕組みをつくったのです。最初は2名ほどしかいなかった日本の知人に声をかけると、「喜んで応援する」と、次々に人を紹介してくれました。まさに倍々ゲームのように仲間が広がり、事業をスタートさせることができました。
(※1)スタートアップエコシステム:新しいビジネスを創出するスタートアップ企業を支援するための産業生態系
(※2)アドバイザリーボード:経営におけるあらゆる課題に対する助言を目的に設置された諮問委員会
挑戦の先に変革は生まれる クライアントの成長を促す支援の真髄
ーー貴社の事業内容と独自の強みについて教えてください。
伊地知天:
弊社では、オープンイノベーション(※3)を支援するプラットフォームとして、「Creww Growth」やスタートアップコミュニティ、オウンドメディア「PORT by Creww」などのサービスを運営しています。これらを通じて、新規事業やデジタル化を目指す大手・中堅企業と、それを実現する技術やアイデアを持つスタートアップをつなぎ、スピーディーで効率的な価値創造をサポートすることが主な事業内容です。
(※3)オープンイノベーション:社内社外の垣根なくアイデアやノウハウ、技術を取り入れ、革新的な製品やサービス、新規事業、ビジネスモデルなど新たな価値を創出するイノベーション手法の一つ
ーー多くの協業実績を生み出せた秘訣は何でしょうか。
伊地知天:
ポイントは、良くも悪くもお客様の「御用聞き」にならなかったことだと考えています。クライアントが本当に求めているのは、一過性の新規事業ではありません。継続的にイノベーションが生まれる土壌をつくることなのです。そのためには、ただ寄り添うだけでなく、ときにはっきり伝える姿勢が重要になります。
ーー貴社の支援スタイルとして、「クライアントに『挑戦』を促す」とのことですが、具体的に教えていただけますか。
伊地知天:
これは色々ありますが、たとえば、小さいところで言えば、契約書ひとつとってもそうです。大企業が持つ既存の契約書のフォーマットは、スタートアップとの協業には適さないことが一昔前までは多々ありました。その際、弊社は安易に間に入るのではなく、大企業の担当者の方に、「これは前例のないことをやるための第一歩です。まずは社内の法務部と戦ってください」とあえて挑戦を促すのです。
自らの組織と向き合い、自分たちの手で「例外」をつくる経験をしてもらう。この最初の成功体験こそが、継続的にイノベーションを生み出す組織風土への変革を促し、その後のスタートアップとの連携を格段にスムーズにすると考えています。
困難を乗り越える秘訣は「人の力を借りる天才」であること
ーー数々の困難を乗り越える上で、大切にされている考え方があれば教えてください。
伊地知天:
困難を乗り越えられたのは、「周りに恵まれた」という一言に尽きます。以前、初期のアドバイザーの一人から「お前は人の力を借りる天才だな」と言われたことがあるのですが、これが全てかもしれません。
人の力を借りることを恥ずかしいと思わず、常に自然体でいること。誰かの前で強がったり、自分を良く見せたりする必要はありません。大変なときは「助けて」と正直に言えば、必ず周りが手を差し伸べてくれると信じています。
アジアと世界の架け橋へ。国境を越える壮大なビジョン

ーー今後の事業において、特に注力していきたいテーマは何ですか。
伊地知天:
弊社が創業した13年前、「スタートアップ」という言葉すら一般的ではありませんでした。そこからオープンイノベーションという流れをつくる一翼を担ってきた自負はあります。しかし、日本のスタートアップエコシステムが次のレベルへ行くためには、グローバル化が不可欠です。その先陣を切ることが、次なるミッションだと考えています。
技術的な課題はAI翻訳などの進化でほぼ解消されましたが、最大の課題はマインドセットにあります。海外の有名ブランドが技術を公募しても、応募しないアジア企業は少なくありません。「自分たちのことなど相手にされない」と思い込み、行動しないのです。この見えない壁を壊すことが最も重要です。
ーー今後、会社をどのような姿にしていきたいですか。
伊地知天:
5年以内に、アジア最大のイノベーションプラットフォームになることを目指しています。今、世界の企業がアクセスできるのは、ヨーロッパとアメリカという2つの市場だけです。人口でいえば世界の半分を占めるアジア市場を、私たちがアンロックする。世界の企業がアジアの優れた技術や才能を探すとき、誰もが最初に訪れる。そんな「架け橋」のような存在になりたいです。
編集後記
15歳で経験した壮絶な海外生活。2011年の東日本大震災を機に芽生えた「新たな産業やイノベーションが生まれるエコシステムを作りたい」「大企業とスタートアップの間にある壁を壊したい」という思いが、伊地知氏の起業家人生を貫く揺るぎない背骨となっている。その情熱は今、壮大な挑戦へと向かっている。日本のスタートアップと大企業、さらにはアジアと世界の巨大な壁を壊す挑戦だ。「人の力を借りる天才」。この言葉の裏には、格好つけず、自分の志を素直に語る誠実な姿勢がある。それこそが多くの協力者を惹きつけ、困難な道を切り拓く原動力なのだろう。同社の挑戦は、日本の未来を担う多くの挑戦者にとって、大きな希望となるに違いない。

伊地知天/1983年生まれ。15歳で単身渡米。2005年、21歳の時にカリフォルニア州立大学在学中に起業。アメリカで立ち上げた会社は2010年に米大手事業会社へ売却。2009年にフィリピンで創業した会社は創業3年で売却。大震災を機に日本に戻り、2012年にCreww株式会社を創業。現在は、スタートアップエコシステムやオープンイノベーションに関わる多くの組織やプロジェクトに参画している。














