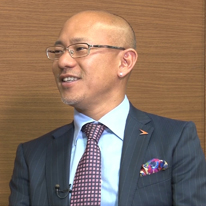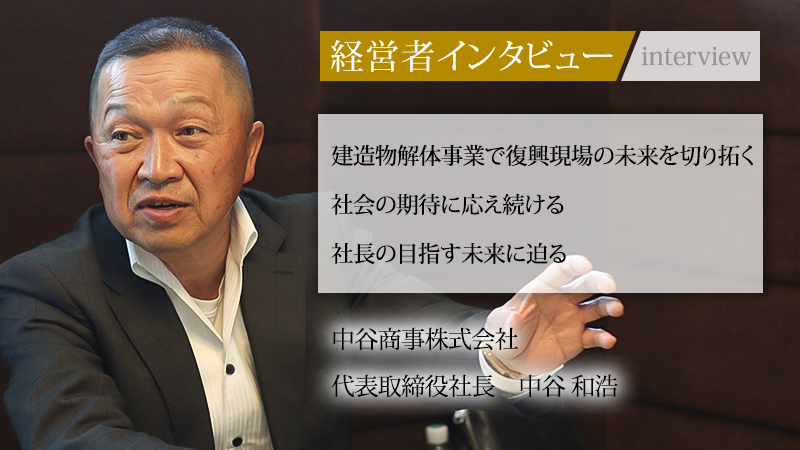
石川県金沢市に拠点を置き、建物の解体事業を手がける中谷商事株式会社。同社は、他社が敬遠するような困難な現場をあえて引き受ける独自の戦略で、地域に不可欠な存在として信頼を築いてきた。2024年の能登半島地震では、珠洲市の公費解体という重責を担い、復興の最前線で力を尽くしている。家出同然で上京し、ものづくりの世界で腕を磨いたのち家業に戻った経歴を持つ代表取締役社長の中谷和浩氏に、困難に挑み続ける原動力と事業の展望について話を聞いた。
家出から始まった道程 不屈の精神を育んだ日々
ーー社長のキャリアの原点についてお聞かせください。
中谷和浩:
実家が解体業を営んでいたので、幼い頃から後を継ぐのが当たり前だと思っていました。仕事終わりの社員たちと会社の風呂に一緒に入るのが楽しみで、家業は常に身近な存在でしたね。
しかし、私は家業よりも、そこで使われている巨大な機械を見るのが好きで、いつしかその機械をつくる仕事に就きたいという思いが強くなっていました。そんな夢を叶えるべく、大学への進学が決まっていたのですが、その道を断って町工場で働くことを決意します。親には「大学に行かないなら出ていけ」と猛反対されましたが、憧れの仕事に就きたい一心で家を飛び出し、埼玉県川口市の町工場で社会人としての第一歩を踏み出しました。
ーー前職の会社では、どのようなご経験をされたのでしょうか。
中谷和浩:
従業員5人ほどの少数精鋭の会社だったので、製造から修理まで、若いうちから責任ある仕事を任せてもらえました。トラックで関東一円を駆け回る毎日でしたが、3年ほどで仕事を全て覚えることができていたこともあり、そういう意味では仕事が自分に合っていたように思います。
機械についてあまりに詳しかったため、お客様が私の言葉を自社の社長以上に信用してくださるようになりました。それに目を付けた社長が、当時21歳だった私に営業も任せてくれるようになったのです。
当時はバブルの全盛期で、若手にも大きなチャンスが与えられる時代でした。1台8000万円の機械を5台売れば会社としては黒字になるところ、ある年には11台を販売する成果を上げることができました。
ーーその後、家業に戻ることになった経緯をお聞かせいただけますか。
中谷和浩:
前職の社長から「役員になってくれ」と頼まれたことがきっかけです。当時25歳だった私は、今後どうするべきかを実家に相談し、そこでもらったアドバイスが後押しとなって、故郷に戻ることを決意しました。
そうして1994年、26歳の時に中谷商事へ入社。しかし、入社後すぐに前職での経験が活かせるわけではありませんでした。というのも、当時の弊社はビルの解体が主な事業でしたが、石川県では仕事の絶対数が決まっているため「仕事は順番にしか回ってこない」というような環境で、既にそれぞれの仕事に対しての役割分担が確立されていたのです。そのため、私に与えられたのはトラックの運転手の仕事のみでした。
あらゆる業務に携わってきた前職とのギャップから、自分の力をどう活かせば良いか悩んだ時期もありましたね。しかし、この時の悔しさや現場での経験こそが、後の会社経営に活きる重要な土台となりました。
誰も行かぬ地へ 能登半島地震の復興を担う覚悟
ーー現在、特に注力されている事業についてお聞かせください。
中谷和浩:
能登半島地震で被災した珠洲市で、公費による建物の復興の解体のお手伝いをしています。これは国から委託された公共工事です。全部で8,000棟以上の建物の解体を責任を持って進めているところです。
ーー貴社が請け負うことになった経緯を教えてください。
中谷和浩:
地震直後、珠洲の壊滅的な状況を見て「一体誰が行くんだ」という話になったそうです。その際、解体協会の中で「中谷商事ならきっとやってくれる」という雰囲気になったと聞いています。
弊社は、以前から人が嫌がる仕事や難しい仕事を専門的に引き受けてきました。たとえば、山奥の鉄塔やダムの解体など、特殊な技術が求められる現場です。今回もその一環です。「困難な仕事でも、これまで担ってきた私たちがやるべきだ」と考え、覚悟を決めました。
震災復興にあたり、地元の銀行から融資を受け、まず3億円を借りて100人分のプレハブ宿舎を建設しました。被災して全財産を失ってもなお前を向く現地の方々を思えば、私たちの3億円の借金など大したことではありません。そんな思いでした。
ーーこれまでの経営で、印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
中谷和浩:
コロナ禍の時期に仕事が激減し、創業以来初めて6500万円の赤字を出した時期がありました。このままではいけないと考え、当時の売上高がないのに多額の資金を投じてテレビCMを打ちました。そして「地元の方々に中谷商事はまだ元気だぞ」というイメージを発信したのです。
また、若手が少ないという危機的状況を打開するため、野球部を設立しました。仲間と協力して目標に向かう野球部の選手のような人材が集まれば、会社は必ず良くなると考えたのです。結果として、若い人材が集まるようになりました。現在、社員35人のうち、野球部員8名を含め27歳以下の若手が12名在籍しています。

現在、どの業界においても人手不足が課題ですが、弊社は若い力がそろっています。彼らの活躍のおかげで、会社の未来が見えてきました。先日、プロ球団に劣らない設備を持つ室内練習場も完成したところです。
社員の夢が会社の夢に 石川県一そして日本一へ
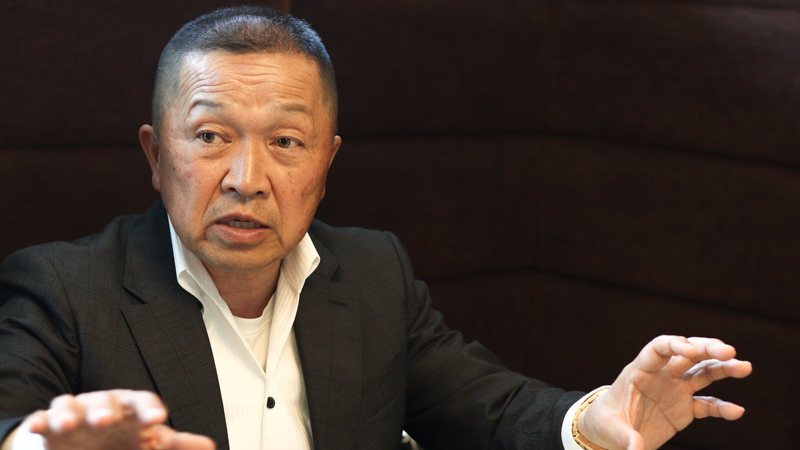
ーー社員の皆さんにはどのような思いをお持ちですか?
中谷和浩:
社員には「自分のために仕事をしてくれ」と常に言っています。人助けも、自分が満足できなければ続きません。自分が楽しくなるような、誰にも恥じない仕事をしてほしいです。また、「先輩の真似をしよう。先輩は真似されるようなことをしよう」とも伝えています。一日一つずつ学んでいけば、3年後にはプロ中のプロになれるはずです。
純利益が1億円を超えた年は、ボーナスとは別で、決算賞与として全社員に一律100万円を出すと約束しています。これは通常の賞与とは別のものです。今期は震災復興事業で売上が大きく伸びたため、新入社員から全員に支給する予定です。
ーー今後、会社をどのようにしていきたいですか?
中谷和浩:
会社を大きくすることよりも、今の若い子たちの夢を叶えてあげたいです。それが私の目標です。野球で日本一、仕事で石川県一、そしていずれは日本一になりたいと考えています。社員には「この会社に一生いるな。10年したらみんな社長になれるんだから」と言っています。弊社で仕事を覚えて独立し、良い車に乗って、良い家を建てる。そんな夢を叶えられる会社でありたいです。
編集後記
中谷氏が何度も口にした「人の嫌がることをやる」という言葉は、単なる逆張り戦略ではない。家出、挫折、そして家業での葛藤を経て掴んだ、揺るぎない生存戦略である。その覚悟は、未曽有の災害現場で先頭に立つ姿に表れている。驚異的なV字回復も、野球部設立という奇策も、全てはこの哲学に根差しているように思える。「自分のためにやれ」という言葉は、突き詰めれば自らの仕事に誇りを持ち、その喜びを追求せよというメッセージだろう。同社の未来は、社長の背中を見て育つ若者たちの双肩にかかっている。その飛躍が楽しみだ。

中谷和浩/1966年生まれ。石川県出身。星稜高校卒業後、埼玉県川口市の機械メーカーに就職し、製造から営業まで幅広く経験。1994年、中谷商事株式会社に入社。2012年、同社代表取締役社長に就任。「人の嫌がる仕事」をあえて引き受ける経営戦略と、野球部設立をはじめとするユニークな人材育成で事業を拡大。2024年の能登半島地震では、珠洲市の公費解体を一手に引き受け、復興の最前線で指揮を執る。