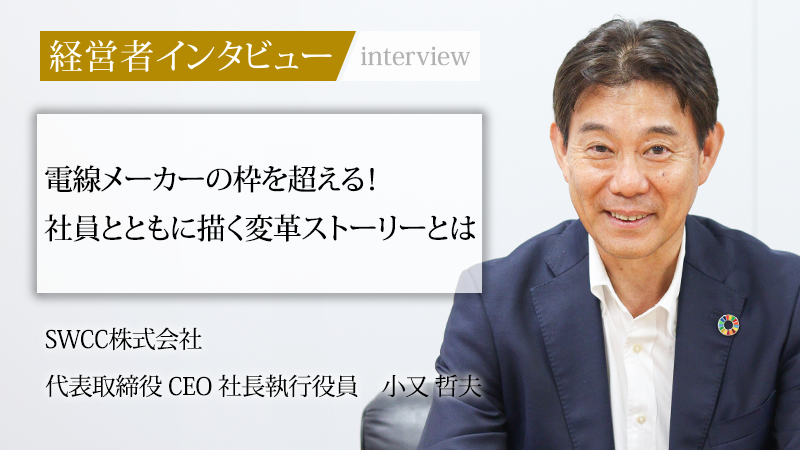
「昭和電線」から社名を変更し、社会インフラを支える総合メーカーとして新たな成長フェーズに突入したSWCC株式会社。電線事業で培った技術力を核としながら、M&Aにより通信・コンポーネンツ事業を強化し、エネルギー・インフラ事業と並ぶ第二の柱の育成を急ぐ。同社は社員一人ひとりの挑戦を促し、ソリューション提案型メーカーへの変革を目指している。危機的状況からの構造改革を支え、2025年4月に社長のバトンを受け継いだ小又哲夫氏に、その軌跡と未来への展望を聞いた。
すべての経験がつながり一社員から経営者へ
ーー社長のキャリアの原点についてお聞かせください。
小又哲夫:
1989年に昭和電線電纜株式会社(当時)に入社しました。入社当初は、主力である電線事業ではなく、コンピューターの黎明期に急成長していたワイヤーハーネス(※1)の部門に配属されました。電線に付加価値をつける加工事業で、まさに人が足りない状況でした。家に帰るのが日をまたぐことも珍しくないほど多忙でしたが、若手が多く、活気に満ちた職場環境でした。一生懸命であれば、失敗しても皆が助けてくれる。その社風を肌で感じたことが、私の原点になっていると感じます。
(※1)ワイヤーハーネス:自動車や電子機器の内部で、電力や信号を伝える複数の電線を束ねた部品のこと
ーーご経歴で、特に大きな転機となったのはどのような経験ですか。
小又哲夫:
30代半ばで経験した、中国での工場立ち上げです。2000年のITバブルで光ファイバー関連の受注が急増し、国内での生産が追いつかなくなりました。そこで自ら「中国に工場を出すべきだ」と提案したところ、「じゃあ君が行きなさい」と。約5年間、100人規模の会社の責任者として、技術や製造だけでなく、採算管理、人事、財務といった経営全般を経験しました。この経験は、私のキャリアにとって非常に大きな財産です。チャンスをくれた上司と会社に、大いに感謝しているし、私も次の世代にチャンスを与えていきたいと思える経験となった。
ーー中国での業務では、どんな気付きがありましたか。
小又哲夫:
苦労も多かったですが、最も衝撃的だったのは、従業員によるストライキです。ITバブルが弾けて仕事が激減し、歩合制だった給与が下がった後、少し仕事が増え始めたタイミングで起きました。生産が完全に止まってしまい、本当に困惑しました。
しかし、合弁先の中国人パートナーに助けられながら対話を重ね、何とか乗りきりました。この経験を通じて、ものづくりを支えてくれる人たちの存在の大きさと、彼らの声に真摯に向き合うことの重要性を痛感させられました。
そこから学んだのは、日本のやり方を一方的に押し付けない、ということです。「郷に入っては郷に従え」の精神で現地の文化や習慣を尊重する一方で、工場内のルールは国籍に関係なく、同じ会社で働く仲間として全員で守ってもらう。このメリハリをつけたことで、従業員との信頼関係を築けたと感じています。異なる文化の中で人を巻き込み、助けられながら仕事を進めるという姿勢は、この時に深く学びました。
事業と組織の壁を壊す 全社を貫く戦略家の視点
ーー日本に戻られてからの状況をおうかがいできますか。
小又哲夫:
帰国後は、ITバブル崩壊後の事業撤退や縮小といった、成長期とは逆の厳しい仕事も経験しました。そして2015年、本社の経営企画部門に異動したことが大きな節目となります。
それまでは主に通信事業に携わっていましたが、初めて全社的な経営戦略に携わる立場になりました。当時、経営企画部門が事業ごとに存在し、組織の壁になっていました。これを一つに統合することを提言し、実行に移したのです。これにより、部門間の交流が促進され、全社で一貫した戦略を迅速に展開できる体制が整いました。戦略部門の人員も効率化でき、大きな成果だったと考えています。
事業の立ち上げから拡大、そして撤退まで、一通りのサイクルを現場で経験してきたことが、現在大きく活きていると感じます。
ーーその後、ご自身の役割にはどのような変化がありましたか。
小又哲夫:
事業会社の経営企画を統合した実績から、親会社であるホールディングスの経営戦略も兼任することになりました。親会社と事業会社では、株主や投資家、現場(営業、技術、製造)など、それぞれ見る方向が異なり、戦略に温度差が生まれがちです。その二つの機能を一人の頭の中で考えることで、意思決定のスピードと一体感を格段に高められました。
この経験が、現在のホールディングス体制から事業会社制へ移行した今の組織の礎です。そして、私が役員、社長へと進む道筋になったと感じています。
「昭和電線」から「SWCC」へ 社員と創る未来の羅針盤

ーー改めて、貴社の事業と歴史についてご紹介いただけますか。
小又哲夫:
弊社は、昭和に生まれた総合電線メーカーとして、長年にわたり電力と通信という社会インフラを支えてきました。しかし、国内のインフラ整備が一巡し、需要が成熟期を迎える中で大きな転換期を迎えます。電力設備の老朽化に伴う更新需要や、再生可能エネルギーの普及という新たな潮流が生まれました。その一方で、電線を主力とする事業領域に留まっていては成長できないという危機感があったのです。
ーー貴社の代表的な製品について教えてください。
小又哲夫:
電力インフラ事業の戦略製品である電力接続部品「SICONEX®(サイコネックス)」が大きな柱です。これは、変電設備で使われる従来の陶器製碍子(※2)を、自社開発のプラスチック製に置き換えたものです。軽量でコンパクトなうえ、オイルやガスを使わない「完全乾式」のため、防災性に優れています。地震などで倒れても火災の危険がありません。何より、工期を約30%短縮できるため、人手不足に悩む建設業界にとって大きなソリューションとなっています。この分野で圧倒的なシェアを獲得できました。
(※2)碍子(がいし):電線と鉄塔など、電気を通すものと通さないものを絶縁するための部品
ーー社名を変更された背景には、どのような思いがあったのでしょうか。
小又哲夫:
電線という事業領域の枠を超え、社会課題の解決領域をさらに広げていくという強い決意の表れです。「SWCC」は、もともと製品に印字していたブランド名で、お客様にも広く認知されていました。この馴染み深いブランドを社名にすることで、付加価値の高いビジネスや全く新しい価値を創造する会社へと進化する。その姿勢を明確にしました。
社名変更と同時にパーパス(※3)の策定も行いました。パーパス策定は、社内の20代から50代までの多様なメンバーが集まり、半年かけてつくり上げました。一般的なパーパスより長いのですが、そこには理由があります。80年以上の歴史を振り返り、私たちが社会のために何をしてきたのか。そしてこれからどうあるべきか。その真剣な議論の結果が詰まっているのです。
ーーパーパスには、どのようなメッセージが込められていますか。
小又哲夫:
変化を恐れず、インフラや電線という既存の枠組みにとらわれない。そして、自分たちの品質を大切にしながら新しい価値創造へ「挑戦」し続ける。そういった思いが込められています。トップダウンではなく、社員が主体となって会社の羅針盤をつくったことに、大きな意味があると考えています。私たちが目指す「SWCCはソリューション提案型メーカーへ!」というビジョンは、まさにこのパーパスそのものです。
(※3)パーパス:企業の存在意義や社会における目的を指す言葉
V字回復に安住しない 独自技術とM&Aで切り拓く未来

ーー社長就任にあたり、大切にされていることはありますか。
小又哲夫:
前社長が推進した「Change & Growth」のスローガンの下、この7年間で会社の業績は劇的に改善しました。営業利益は約5倍になり、時価総額も2000億円を超えるなど、危機的な状況からV字回復を果たしています。「良い時に引き継いだ」と言われるプレッシャーの中で、私の使命は改革の精神を継続することです。そして、会社を確かな成長フェーズに乗せることだと考えています。過去の成功体験に安住せず、変化し続けることが不可欠です。
ーー情報通信分野や、M&Aによる相乗効果はいかがでしょうか。
小又哲夫:
通信分野では、データセンターで使われる「間欠固定型光ファイバテープ心線(e-Ribbon®)」(※4)が強みです。これは、非常に多くの光ファイバーを細いケーブルに高密度で収めることができる技術です。世界でも数社しか持っていない高度なもので、海外でも戦える製品だと期待しています。
また、2023年にM&Aを行った株式会社TOTOKU(旧・東京特殊電線株式会社)とのシナジーも大きな成長要因です。たとえば、EVのシートヒーターは両社の技術を合わせると世界で30%のシェアになります。さらに、半導体検査に不可欠な精密部品でも協業を進めています。
(※4)間欠固定型光ファイバテープ心線(e-Ribbon®):多数の光ファイバーをテープ状にまとめ、高密度にケーブルへ収納する技術
「るつぼ」から抜け出す進化を止めない挑戦
ーー今後に向けたビジョンをお聞かせください。
小又哲夫:
繰り返しになりますが、電線という事業領域の枠にとらわれず、事業領域の拡大を加速させます。これまでの昭和電線という固定観念を脱し、新しいものへと変わっていく。そして、日本国内だけでなく、海外での成長にも本格的に取り組みます。持続的な成長ができる会社へと進化させていく。それが私の役割です。
ーービジョンを実現するために、どのような取り組みをされる予定ですか。
小又哲夫:
弊社のコア技術は、金属、特に新しい合金線を開発する技術です。この強みをさらに伸ばすため、自社内にとどまらず、東北大学と共同で「高機能金属材料 共同研究部門」を設立しました。外部提携を通じて新しい製品を創出し、パーパスに掲げた新しいことを生み出していく挑戦を具体化していきます。
また、これまでの電力・通信インフラ市場に加え、モビリティや半導体を新たな成長領域と定め、営業活動を強化しています。重要なのは、お客様の困り事や潜在的なニーズを掘り起こすソリューション営業です。TOTOKUのM&Aで得た顧客基盤と弊社の営業基盤を活かし、互いの強みでクロスセル(※5)を促進します。これにより、新しい市場を切り拓いていきます。
(※5)クロスセル:既存の顧客に、関連する別の製品やサービスを提案・販売すること
改革から成長へ 進化したROIC経営
ーー貴社の経営の根幹についてお聞かせください。
小又哲夫:
弊社の構造改革の軸となってきたのが「ROIC(投下資本利益率)経営」です。ROICとは、投下した資本に対してどれだけ利益を生み出せたかを示す指標です。かつては「赤字でなければ良い」という風潮がありましたが、この厳しい指標を導入しました。これにより、稼ぐ力の低い事業は撤退・縮小するという事業構成の見直しを断行しました。その結果、筋肉質な経営体質へと転換できたのです。
これまでは「改革のためのROIC経営」でしたが、これからは「成長のためのROIC経営」へと一段階、高度化させていきます。経営の軸としてROICを据えながら、生み出したキャッシュフローを最大化する。そして、そのキャッシュを「成長投資」と「株主還元」にバランス良く配分し、さらなる成長へとつなげる。この好循環を力強く回していくことが、これからの弊社を支える根幹になると考えています。
編集後記
若手時代から中国での工場立ち上げ、事業撤退まで、あらゆる現場を経験してきた小又氏の言葉には、生々しい実感と重みがあった。電線という伝統的な事業の枠を自ら壊し、ソリューション提案型メーカーへと突き進む同社。その変革を支えるのは、社員が主体となってつくり上げたパーパスと、ROICという明確な経営哲学だ。同社が次に生み出す未来に、大いに期待したい。

小又哲夫/芝浦工業大学工学部卒業。大学卒業後、昭和電線電纜株式会社(現・SWCC株式会社)入社。2018年、同社執行役員に就任。以降、常務執行役員、COO副社長執行役員などを歴任し、2025年、代表取締役 CEO 社長執行役員に就任。














