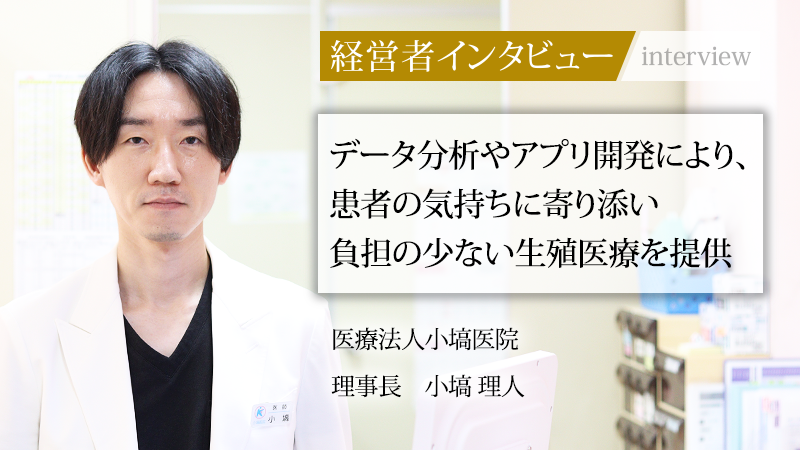
日本の少子化は深刻さを増し、2024年の日本の合計特殊出生率は1.15と過去最低を更新した。要因はさまざま考えられるが、晩婚化による妊娠率の低下も見逃せない要因の一つである。茨城県小美玉市の小塙医院は、長年婦人科・産婦人科として地域の医療に貢献してきた。2023年に3代目理事長に就任した小塙理人氏は、最新のエビデンスを追求した治療を提供する生殖医療のエキスパートだ。小塙理事長に、同院の治療方針や特徴について話を聞いた。
生命の根本であり社会課題の解決につながる生殖医療
ーー生殖医療の道を選んだ理由を教えてください。
小塙理人:
祖父と父が産婦人科医だったため、いずれ医院を継承するかもしれないという意識は若い頃からありました。さまざまな分野を見る中でも、生殖医療は医学の力で新しい生命の誕生に関われるという点に、命の原点に関わる尊さを強く感じ、生殖医療という分野に魅力を感じました。また、少子高齢化という日本社会が直面する大きな課題に対して、医療という立場から貢献できる可能性があることも、この道を志す大きな動機になりました。
晩婚化を背景に、体外受精や顕微授精、人工授精といった治療に取り組む患者さんが増えていると感じます。加えて、2022年4月から不妊治療が保険適用になったのを機に、これまで費用面でためらっていた若い方も含め、不妊治療に踏み出す方が増えました。
ーー2023年に理事長に就任された時は、どのような思いを抱いていたのでしょうか。
小塙理人:
2019年に小美玉市へ戻った際、まず感じたのは、私自身の幼少期と比べて明らかに子どもの数が減っているという現実でした。少子化は全国的な課題ですが、地元でその影響を肌で感じたことで、強い危機感を持つようになりました。県の少子化対策課や産婦人科医会の方々とも意見を交わす中で、地域として出生率を少しでも改善していく必要があると、より強く意識するようになりました。
また、地域医療の拠点として、「ここに来れば安心」と思っていただける存在になりたいという思いもありました。単に医療を提供するだけでなく、地域に根ざし、信頼されるクリニックであることを目指しています。
ーー座右の銘を教えてください。
小塙理人:
「初心忘れるべからず」という言葉を、今でも大切にしています。2019年、父ががんを患い、やむを得ずクリニックを約3か月間休診したことがありました。その間に「小塙医院は閉院したらしい」という噂が地域に広まり、私が勤務を開始して診療を再開した後も、患者さんの数は激減し、経営的にも非常に厳しい状況が続きました。
そのような中で、改めて地域に必要とされる存在であり続けるためには、信頼を取り戻す努力が不可欠だと痛感しました。ホームページを整備して診療情報を丁寧に発信したり、県の産婦人科医会や市民公開講座に積極的に参加したりと、地道な広報活動を重ね、クリニックの再開を少しずつ地域に知っていただけるよう努めました。
また、実力や実績がなければ患者さんに選ばれないという強い思いから、生殖医療に関する国内外のエビデンスをもとに知識と技術の習得に努めました。当院で過去に蓄積されたデータも自ら分析し、統計解析を活用してより効果的な医療の提供を目指しました。
データ解析の結果から、卵子を育てる調節卵巣刺激法や、胚培養の方法そのものを根本から見直しました。そして、より高い妊娠率・出生率が期待できる手法を導入した結果、診療再開当初は数人しかいなかった外来患者さんの数が、やがて50人、60人、70人と少しずつ増えていったのです。
なぜ自分は産婦人科になり、生殖医療に従事するようになったのか、そして継承時の苦労、支えてくださった方々への感謝を忘れないように、「初心忘れるべからず」という言葉を座右の銘として胸に刻んでいます。
患者の負担を減らしより効率的に妊娠へ導く胚凍結

ーークリニックで主に行っている治療と、特徴を教えてください。
小塙理人:
タイミング法、人工授精、体外受精といった不妊治療と、不正出血や下腹部痛、更年期障害などに対応する一般的な婦人科の治療に加え、将来の妊娠に備えてご自身の体を調べる「プレコンセプションケア」などを行っています。男性の不妊治療も対応しており、カップルで来院される方も増えています。
不妊治療では、一度の採卵でできるだけ妊娠率・出生率を上げることを意識しています。受精卵(胚)を凍結する技術を用いれば、1度の採卵で複数回の妊娠を目指せます。採卵時の年齢が受精卵の質に影響するため、若いうちに凍結した胚を用いて2人目、3人目のお子さんを授かることを推奨しています。これにより、身体的な負担が大きい採卵の回数を減らせることに加えて、当院では毎月、採卵・胚培養・胚移植の全データを綿密に分析し、結果を考察することで、医療の質を継続的に担保しています。再現性のある成果を生むためには、感覚ではなくデータに基づいた振り返りと改善の積み重ねが不可欠だと考えています。
ーー患者さんとのコミュニケーションで意識していることはありますか?
小塙理人:
私たち医療者の一言が、患者さんの治療への意欲や、その先の人生を左右することもあります。だからこそ、誠意をもって対話し、一人ひとりの患者さんと丁寧に向き合う姿勢を大切にしています。医療面だけでなく心情面にも目を配り、患者さんが今何を求めているのかを常に先回りして考え、寄り添うことを心がけています。
治療にかけられる予算や痛みの感じ方、これまでの妊娠・出産歴は人それぞれ異なります。治療方針を提案する際には、医学的な情報だけでなく、患者さんの生活背景や価値観も含めて総合的に判断し、「患者さん本位」であることを常に意識しています。
また、医師と患者さんのコミュニケーションを円滑にするアプリも開発しました。医療従事者にとっては、投薬の種類や量、タイミングなど医療上の判断をするためのツールになります。患者さんにとっては、ご自身の妊娠率を把握し、採卵するかしないかの検討するための一つの指標となるでしょう。
地域医療の拠点として患者の信頼に応え続ける
ーー小塙医院が患者さんに選ばれるのはなぜだとお考えですか?
小塙理人:
「治療について医師や看護師と話しやすい」という点も評価いただいているようです。治療段階ごとに選択肢を示して一緒に考えるなど、患者さんのニーズに合わせた医療が信頼につながっているのかもしれません。
また、「建物は歴史を感じるが、清潔に保たれている」というお声も多くいただきます。どこかノスタルジーを感じられる雰囲気は残しつつ、安心して通っていただけるよう清掃には特に力を入れています。
ーースタッフの皆さんはどのような姿勢で仕事に臨んでいるのですか?
小塙理人:
スタッフはみんな柔軟性が高く、新たな試みが数日で組織として機能できるように動いてくれています。「患者さんのために、もっとできることはありませんか?」と自発的に聞いてくれるスタッフが多く、私が目指す医療を体現してくれていることに大変感謝しています。
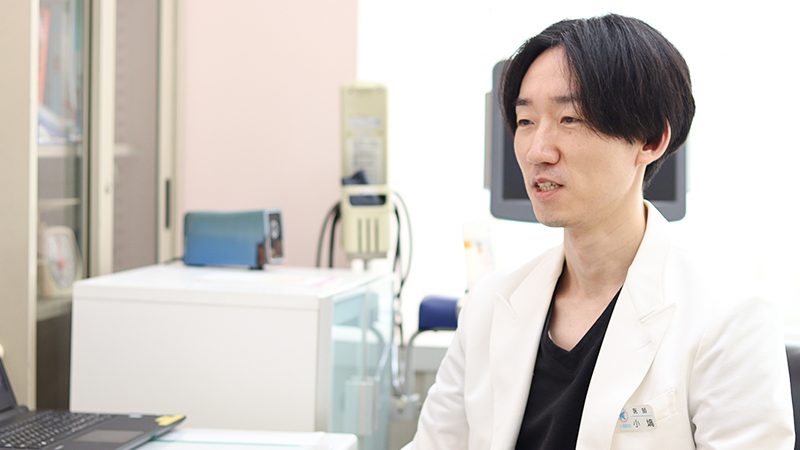
ーー今後の展望をお聞かせください。
小塙理人:
「婦人科で困ったら小塙医院に行こう」と思っていただけるよう、地域医療の拠点として、持続可能な施設や組織づくりをしていきたいです。海外の学会や論文を通じて、常に最先端の医療知識を吸収し、より効果的かつ効率的な治療法を模索・考察することで、茨城県のみならず、日本全体の出生率向上に貢献していきたいと考えています。将来的には、自身の研究論文が世界の生殖医療のエビデンスの一つとして活用されることも目指しています。
また、当院の近くには茨城空港があり、地域的に外国人の患者さんも一定数いらっしゃいます。今後さらにグローバルなニーズが高まることが予想されるため、スタッフの英語対応の強化や、海外の医療機関との連携も視野に入れています。地域に根ざしつつ、世界水準の医療を提供できる、そんなグローバルな医療施設を目指して取り組んでいきたいと考えています。
編集後記
日進月歩の勢いで進化する医療技術の中でも、生殖医療は繊細な分野だ。技術だけでなく患者とのコミュニケーションが結果を左右する可能性があるからだ。小塙氏は婦人科と不妊治療を専門としながらも、長年の実績にあぐらをかくことなく、常に技術を研鑽している。苦労を乗り越えた経験があるからこそ、初心を忘れず、常に真剣に患者と向き合い続けているのだろう。

小塙理人/千葉大学医学部卒業後、慶應義塾大学産婦人科に入局。都立大塚病院で初期研修、複数の基幹病院で産婦人科後期研修を経て、慶應義塾大学生殖生理研究室で生殖医療を学ぶ。2019年より小塙医院勤務、2023年より理事長に就任。














