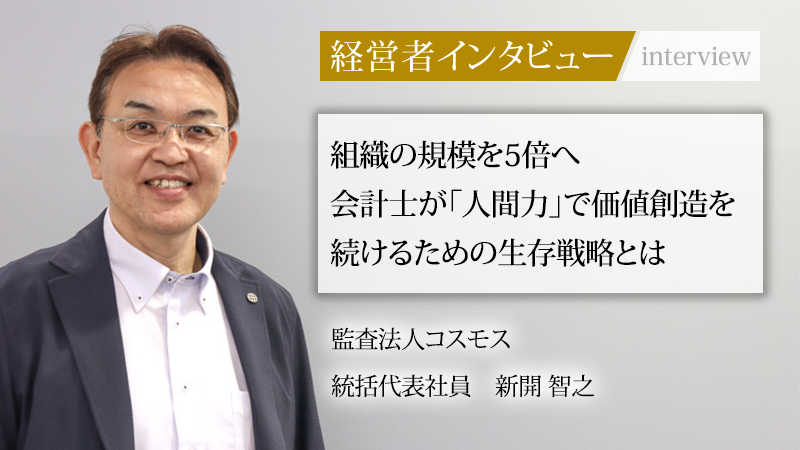
中小企業の価値向上を掲げ、独自の市場戦略で急成長を遂げる監査法人コスモス。同社を率いる統括代表社員の新開智之氏は、就任からわずか6年で組織規模を5倍に拡大させたという驚異的な実績を持つ。その原動力となったのが、多くの中小企業にとって新たな選択肢となる、東京プロマーケット(※1)への上場支援だ。パートナー就任時に抱いた起業家精神を胸に、会計士の新たな可能性を切り拓いてきた新開氏に、その軌跡と組織づくりの哲学を聞いた。
(※1)東京プロマーケット:東京証券取引所が運営している株式市場のひとつ。プライム市場やスタンダード市場など、東京証券取引所のほかの市場が一般の投資家向けの市場であるのに対し、東京プロマーケットはプロ投資家のみが株式の取引を行える。
キャリアの原点 就職氷河期とコスモスへの入所
ーー監査法人コスモスへ入所された経緯を教えてください。
新開智之:
大学は教育学部でしたが、公認会計士の道へ進むことを決め、2年間の勉強を経て1994年10月に二次試験に合格しました。しかし、当時は就職氷河期の真っ只中で、大手監査事務所への就職は叶いませんでした。
そんな中、当時設立6年目だった監査法人コスモスが私を受け入れてくれたのです。地元が愛知県だったため、名古屋の監査事務所で働きたいという思いもありました。専門学校からの情報を頼りにたどり着いたのがこの事務所です。
「自分で稼げ」の一言が転機に 起業家精神の覚醒
ーー代表社員にご就任されるまでで、特に印象的なご経験や学びは何ですか。
新開智之:
入所から10年、パートナー(※2)になる際に言われた言葉が大きな転機でした。「これからは自分の給料は自分で稼げ」「この事務所を発展させるも潰すも、あなたたち次第だ」。この一言を機に、会社にいながらも起業家のような精神、アントレプレナーシップを持つ意識が芽生えました。これが私の会計士人生の大きなターニングポイントになったと感じます。
公認会計士は経営の「歴史」は学びますが、経営の「仕方」は学びません。そこに課題を感じていた私は、自分で稼ぐチャンスを活かそうと考えました。そして、「企業の社会的責任」への関心から、環境ISO(※3)の資格を取得したのです。審査やコンサルティングを通じて欧米流のマネジメントシステム、つまり実践的な経営を学べたことが非常に大きな財産です。この経験が、私たちが支援すべきは中小企業であり、IPOという領域で支援するという現在の使命の礎となっています。
(※2)パートナー:監査法人に出資し、共同経営者として組織を運営する役職。株式会社でいう役員や株主のような立場であり、監査業務の最終責任者として、監査報告書への署名や、クライアントへのサービス提供、組織運営などを担う。
(※3)環境ISO:環境を保護した上で環境パフォーマンスの向上を目指す環境マネジメントシステムで、国際標準化機構(ISO)によって定められた国際認証規格。
「成長と貢献」が原動力 変化を恐れず理想を追求する哲学
ーー経営者として譲れない信念や、大切にされている価値観は何でしょうか。
新開智之:
根本にあるのは「誠実」「素直」「謙虚」であることです。物事の原理原則に対し素直であり、自分が何者かを知り謙虚でいる。そして何より、「このままでいい」と変化しない自分は許せません。人としても組織としても成長し続けなければ、専門家として社会の役には立てないという強い思いがあります。そこは譲れない信念です。
ーー「成長と貢献」という信念について、より詳しくお聞かせください。
新開智之:
ポケットにお金がなければ寄付はできません。しかし、尽きることのない井戸を持っていれば、いくらでも水を分け与えられます。この「持っている」状態が「成長している」ということです。自らが成長し、能力や価値という水で満たされ、それが溢れ出すことで、初めて社会に貢献できます。自身の能力を「湧き上がる井戸」のようにしていくことが、私と組織が目指す姿なのです。
就任後6年で組織規模5倍を実現した「人事制度」と「市場戦略」
ーー統括代表社員に就任されてから、どのような改革を進めてこられましたか。
新開智之:
私が統括代表になってからの6〜7年で、組織規模を5倍にしてきました。当時20名に満たなかった事務所は、今や100名を超えています。この成長を牽引したのは、明確な方針があったからです。それは、日本の99.7%を占める中小企業を、「東京プロマーケット」への上場支援を通じて価値ある存在にしていくというものです。この活動が、多くの中小企業の課題解決につながったことが大きな要因といえるでしょう。
ーー急成長を支えた組織的な取り組みの中で、特に重要な施策は何でしたか。
新開智之:
明確な人事考課制度の構築です。他法人では評価が曖昧になりがちだと聞きます。しかし私たちの事務所では、入所から10年でパートナーを目指せるキャリアパスを明確に示しています。合格者からパートナー、そして代表社員に至るまで詳細なステップを用意しました。これにより、能力を客観的に評価する仕組みを整え、誰もが納得してステップアップを目指せる環境をつくっています。
ーー急成長を遂げる上で、市場をどのように捉え、戦略を立てられたのですか。
新開智之:
監査事務所がこれだけの自己成長を遂げるのは非常に難しいことです。それを可能にしたのは、「どこに市場を創造するのか」という視点でした。私たちが着目した東京プロマーケットは、当時その価値を知る人がまだ少なかったのです。私たちはその価値にいち早く気づき、信用力を高めたいと願う中小企業にその価値を訴求できました。これが一番の成功要因だと分析しています。
AI活用と人間力で拓く未来 公認会計士の新たな価値創造へ

ーー事業をさらに拡大する上で、今後の課題は何だとお考えですか。
新開智之:
品質の向上は永遠の課題です。これにはAIの活用が鍵になると考えています。公認会計士はAIに取って代わられるのではなく、AIを使いこなす存在になるべきでしょう。AIにはできない「ホスピタリティ」「クリエイティビティ」「マネジメント」といった領域の能力を強化します。そして、AIにできることは任せて効率化を図るのです。そのためのリカレント教育(※4)も含め、AIの実装がこれからの課題となります。
(※4)リカレント教育:社会人になった後も、必要なタイミングで教育機関や社会人向け講座に戻り、学び直すこと。
ーー最後に、今後の幹部人材の育成についてお考えをお聞かせください。
新開智之:
幹部育成は、これからの最重要課題です。監査やIPOのスキルはもちろんですが、それ以上に「人間力」が求められます。マネジメントとは「人を介して仕事をする技術」です。このことを幹部メンバーにしっかりと伝え、その技術の習熟と能力開発をどう進めていくか。それが、私のこれからの課題だと認識しています。
編集後記
わずか6年で組織規模を5倍に拡大させた監査法人コスモス。その躍進は、新開氏の「成長と貢献」という揺るぎない信念に支えられていた。自らが「湧き上がる井戸」となり社会に貢献するという哲学は、起業家精神を胸に「東京プロマーケット」という未開拓市場を切り拓いてきた経験そのものに裏打ちされている。公認会計士は、安定だけを求める職業ではない。変化を恐れぬ挑戦で社会に新たな価値を創造できる仕事だと、同社の歩みは力強く示している。

新開智之/1968年、愛知県一宮市生まれ。1992年に岐阜大学教育学部を卒業後、公認会計士の道を志す。1994年、監査法人コスモスに入所。2007年に代表社員、2019年に統括代表社員に就任。中小企業支援、特に東京プロマーケットへの上場支援を強みとし、法人を急成長に導く。現在は太平洋工業株式会社、サン電子株式会社にて社外取締役監査等委員も務める。














