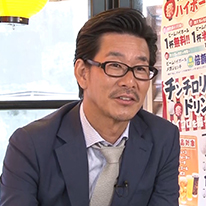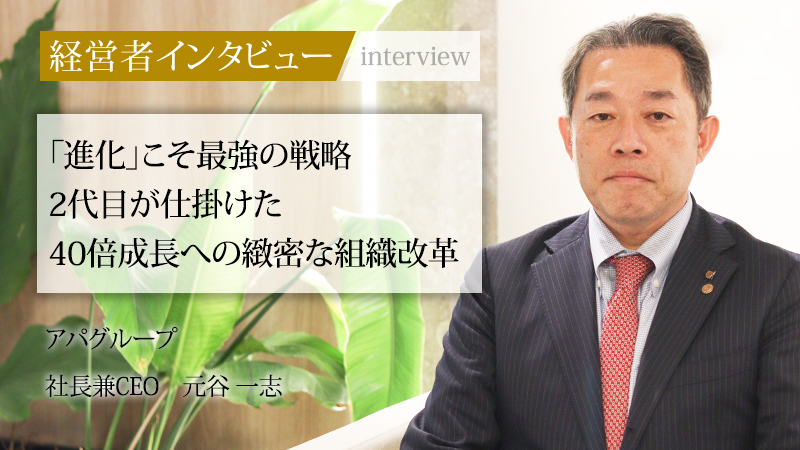
日本最大級のホテルネットワークを誇るアパグループ。その舵取りを担うのは、創業者である元谷外志雄氏を父に持つ、社長兼CEOの元谷一志氏だ。大学卒業後、金融の論理を学ぶべく銀行へ入行。その後、アパグループへ常務として入社すると、目覚ましい手腕を発揮する。当時18ホテル・3,500室だった事業規模を、13万室超へと約40倍にまで拡大させる立役者となった。創業家に生まれ、その巨大な看板を背負う2代目は、いかにして組織を変革し、次なるグローバル戦略を描いているのか。その軌跡と未来への展望に迫る。
「情報弱者になるな」創業家に叩き込まれた理不尽と帝王学
ーー創業者であるお父様との思い出のエピソードをお聞かせください。
元谷一志:
物心ついたときから「お前は二代目なのだから、継ぐことが義務付けられている」と呪文のように聞かされて育ちました。それに反発するというよりも、「そういうものなのだろう」と素直に受け止めていましたね。
父からは、まるで「巨人の星」の星一徹のような、厳しい教育を受けました。夜9時に寝たのに2時間後に叩き起こされ、「金沢で土地を買ったから今から見に行くぞ」と、当時住んでいた小松市から車で向かうこともありました。現地に着くと、「この土地の最終形が見えるか」と問われるのです。小学生の知見で「マンションが建てられるのですか?」などと尋ねるのですが、的外れなことを言うと「バカタレ!」と怒鳴られ、不動産の専門用語を交えながら解説が始まります。ある意味、子どもとしてではなく一人のビジネスパーソンとして扱われる、厳しい英才教育だったのだと思います。
また、両親からは「勉強なんかするな」と言われていました。父の持論は、「勉強とは答えがあるものだが、実業の世界に答えはない。答えがない中でどう考え、チャレンジするかが重要だ」というものです。勉強は情報のインプットとアウトプットの正確性を競うにすぎない。それよりも社会の仕組みに疑問を持ち、自分で調べて答えを導き出す社会勉強の方が重要だと教えられました。
さらに、「情報の感度が悪い奴はビジネスの感度が悪い」と小学生の頃から言われ、ビジネスの感度を上げるためには「東京都心で情報のシャワーを浴びろ」と。そのために「大学は4年間都心にいられるところに行け」とまで言われましたね。
ーーどのような経緯で、家業に入られることになったのでしょうか。
元谷一志:
大学4年生の就職活動のとき、父から「家業を継ぐ気があるのか」と問われました。そして、「もし継ぐ気がないのなら『法定遺留分を含め、財産をすべて放棄します』という書面にサインをすれば自由にしていい」と言われました。ある種の「踏み絵」ですよね。
そのとき、「ゼロから自分で起業しても100億円企業をつくるのが関の山だろう」と考えました。しかし、この家に生まれたからには1兆円の仕事をしたい。そのためには、今ある事業という「種」を大きくしていく手伝いをすることが最善だと判断し、家業に入ることを決意しました。
金融の論理を学ぶ 家業を継ぐための銀行員時代
ーー家業を継ぐと決められた上で、まずは銀行に入行された理由をお聞かせください。
元谷一志:
父も母も「金融が第一だ」という考えでした。企業にとってお金の流れは人間の血流と同じ。黒字でも倒産するし、赤字でも倒産しないこともある。企業の「貸し手の論理」と「借り手の論理」の両方を学ぶ必要がある。「身をもって学んでこい」と言われ、住友銀行(現・三井住友銀行)に入行しました。
銀行員時代、最初の2年間は新規の預金獲得や外国為替などを担当しました。その後、宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)の資格を持っていたこともあり、法人業務部の不動産チームに配属されました。そこでのミッションは、銀行が持つ不動産の有効活用です。たとえば、営業時間外の夜間の駐車場をコインパーキングとして活用したり、カフェ併設型のATMを導入したりと、収益性を高める取り組みを行いました。この経験を通じて、集客が周辺領域を潤すということを実感できましたね。
3,500室から40倍へ 2代目が見た課題と断行した現場改革

ーーアパグループへ入られてから、どのような役割を担われたのでしょうか。
元谷一志:
家業に入るといきなり常務に就任しました。当時の役員は会長と同世代の50代以上の方がほとんどで、20代は私一人でした。ホテル業界は未経験でしたから、若さを武器にしたユーザー目線で物事を考えていこうと常に心がけていました。
私が入社した頃は約18ホテル、3,500室規模でしたが、現在ではグループ全体で13万8,000室を超える規模となりました。この約40倍の成長に、いくばくかは貢献できたのではないかと考えています。
ーー入社後、組織に対してどのような課題を感じられましたか。
元谷一志:
役員たちが過去の成功体験に固執していたことです。「以前この方法で成功したから、これが正しい」という考えが根強く、時代の変化に対応できていませんでした。また、各ホテルの支配人たちは、ホスピタリティは素晴らしいものの、残念ながら数字への意識が十分ではありませんでした。売上や利益への意識が非常に弱かったのです。同業他社の動向にも関心が薄く、強い危機感を覚えました。
ーーその課題に対して、どのような改革を進められたのでしょうか。
元谷一志:
当時、主流になりつつあったインターネット予約にいち早く対応する必要があると考えました。そこでDX(※)という言葉が生まれる前から、インターネットを活用した経営・運営体制の構築を進めました。そして、支配人たちの意識改革のために、地区ごとの支配人が集まって話し合いをする「ブロック会議」を提唱しました。これにより、月間の売上見込みとGOP(Gross Operating Profit:営業総利益)といった収支を全支配人が意識する文化をつくりました。他社の強みや料金プランを徹底的に分析させ、数字にこだわる風土を醸成した結果、支配人たちのレベルは格段に上がりました。
(※)DX:デジタルトランスフォーメーション。デジタル技術を活用してビジネスを変革すること)
ーー収益性を高めるための具体的な施策はありましたか。
元谷一志:
コスト管理を徹底し、安売りではなく、客単価を上げて利益を最大化する意識を浸透させました。たとえば、「稼働率80%で単価7,000円」と「稼働率70%で単価8,000円」では、売上は同じです。しかし、後者の方が清掃コストなどがかからず、手元に残る利益は大きくなります。さらに、一度チェックアウトされた部屋を清掃し、その日のうちに再度販売する「デイユース」の考え方を取り入れ、RevPAR(販売可能な客室あたりの収益)を向上させる重要性を説きました。
「Even Better!」進化を止めないアパホテルの哲学
ーー貴社で大切にされていることはどのようなことですか。
元谷一志:
私が社長に就任してから「Even Better! APA HOTEL」をスローガンに掲げています。これは「良いものを、さらに良く」という意味です。同じサービスを提供し続けると顧客満足度は少しずつ下がってしまうという「限界効用逓減の法則」がありますが、私たちは常に進化することで、リピーターのお客様にも毎回新しい価値を提供したい。その考えのもと、「1ホテル1イノベーション」を標榜し、新しいホテルを開業するたびに、何か一つ新しい要素を加えるようにしています。
高機能・高品質・環境対応型というアパホテルの提唱する新都市型ホテルの基本コンセプトを守りながら、常に進化を続けることが競争力の源泉だと考えています。
ーー従業員に対する取り組みについてもお聞かせください。
元谷一志:
社員を大切にする「善循環」を生み出すことを重視しています。この13年間で合計8万1,000円のベースアップを実施したほか、役職に応じた人間ドックの提供や、全事業所への置き型社食の導入など福利厚生の充実にも努めてきました。結果として従業員満足度は向上し、離職率は低下。来年の新卒採用では、内定者の歩留まりも大きく改善したため予定より前倒しで終了するほどです。
選択と集中から多角化へ M&Aで描くグローバル戦略

ーー競争が激化するホテル業界で、今後の成長戦略をどのようにお考えですか。
元谷一志:
これまでの自社開発・運営に加え、M&Aも積極的に活用していきます。今年6月にはイシン・ホテルズ・グループを完全子会社化し、「the b」という新しいブランドが加わりました。これは大きな意味を持つ戦略です。たとえば、新宿エリアのようにアパホテルが集中している地域では、これ以上出店すると自社競合が起こる可能性があります。しかし、別のブランドを持つことで、それを防ぎながらエリア内のシェアをさらに高められます。
また、ブランドを使い分けることには、出店スピードの面でも大きなメリットがあります。土地取得から開業まで2年以上かかるアパホテルと異なり、賃貸方式の「the b」は出店スピードが速いという利点があります。
選択と集中だけでなく、ホテルの領域を広げていくフェーズに入ったと考えています。今後も、後継者問題を抱えるホテルチェーンなどをM&Aすることも検討しています。
ーー海外展開についてはいかがでしょうか。
元谷一志:
円安が進む中、資産ポートフォリオにおける海外比率を高めることは急務です。昨年、ワシントン州シアトルに、新都市型ホテルコンセプトを融合させた北米ブランド「COAST hotels byAPA」アメリカ第1号店をオープンしました。今後は北米での展開にさらに力を入れます。将来的には、日本と時差が少なく、経済的にも安定しているオーストラリアでの展開も視野に入れています。現在の海外比率は約4%程度とまだ低いですが、これを大幅に引き上げていく計画です。
「1 Guest, 1 Digital Concierge」が拓く未来
ーーDXの活用についてはどのような構想をお持ちですか。
元谷一志:
「1 Guest, 1 Digital Concierge」というキャッチコピーで、お客様一人ひとりにパーソナライズされた、痒いところに手が届くサービスをデジタルで提供していきたいと考えています。たとえば、予約情報からお客様の好みをAIが学習し、チェックイン時にはお部屋の温度が最適に設定されている。おすすめのレストラン情報がアプリに届く。そういった、よりスマートできめ細やかなおもてなしを、テクノロジーの力で実現していくことが目標です。これを多言語対応させることで、国籍を問わずすべてのお客様の満足度をさらに高めていきたいですね。
ーー最後に、今後の目標についてお聞かせください。
元谷一志:
現在進行中の中期5カ年計画「AIM5」は、売上高や利益目標を前倒しで達成しました。残るホテルネットワーク15万室という目標も達成の見込みです。完了次第、次の5カ年計画「新・AIM5」を始動させ、日本、北米、そしてオーストラリアも加えた環太平洋での展開を加速させたい。そして、全従業員の1%にあたる約50~70人を海外に派遣できる国際的な人材の育成体制を築き、現在世界19位のホテルチェーンという順位を、一つでも上げていきたいと思います。
編集後記
創業者である父から受けたという英才教育。その強烈な原体験は、元谷氏の中に「答えのない問いに挑み続ける」という経営者としての揺るぎない軸を形成した。銀行でマクロな視点を養い、家業に入ってからは20代の若さで旧弊を打破。その改革は、単なる精神論ではない。数字に基づいた緻密な戦略と、現場を歩き続ける地道な努力に裏打ちされているのだ。常に進化を求める「Even Better!」の哲学と「善循環」を生む組織づくりは、アパグループを新たな成長軌道に乗せた。環太平洋を見据えるその冷静な瞳の奥に、巨大な家業をさらなる高みへと導く情熱が宿る。同社の挑戦はこれからも続く。

元谷一志/1971年4⽉20⽇福井県⽣まれ。⽯川県出⾝。1990年、⽯川県⽴⾦沢⼆⽔⾼等学校卒業。1995年、学習院⼤学経済学部経営学科卒業後、株式会社住友銀⾏(現・株式会社三井住友銀行)に入行。5年間勤務した後、1999年11⽉、アパホテル株式会社常務取締役として⼊社し、2004年に専務取締役に就任。2012年5⽉にアパグループ株式会社代表取締役社長、グループ専務取締役最⾼財務責任者、グローバル事業本部⻑を歴任。2022年4⽉、アパグループ社⻑兼最⾼経営責任者(CEO)に就任し、現在に⾄る。