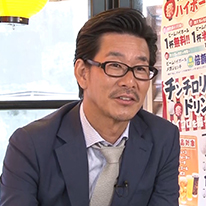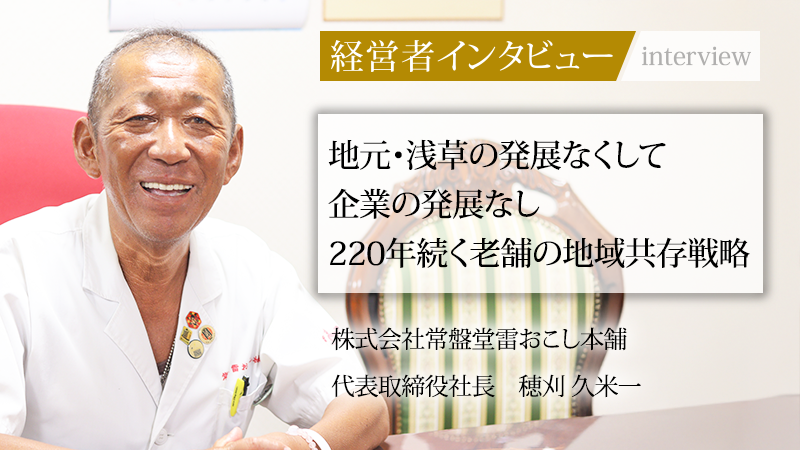
東京のシンボル・浅草に根を張り、220年以上の歴史を紡ぐ株式会社常盤堂雷おこし本舗。生まれも育ちも浅草という代表取締役社長の穂刈久米一氏は、偉大な父への反発から一度は外の世界を夢見た。しかしその道を絶たれ、予期せぬ形で老舗の舵取りを託される。就任直後に突きつけられたのは、72億円という巨額の負債。会社存続の危機という逆境から、いかにして事業を立て直し、伝統の暖簾を守り抜いたのか。父の背中を追いながら自身の信念を貫く穂刈氏の経営哲学と、浅草への深い愛情に迫る。
意に反した入社と予期せぬ事業承継
ーー貴社に入社された経緯をお聞かせください。
穂刈久米一:
実はホテルマンになりたいという思いがあり、就職活動をしていたのです。しかし、父から「お前には辛くなったら俺の会社に入れるという逃げ道がある。そんな甘えた社員を抱える社長がかわいそうだから、俺が雇ってやる」と言われ、外の世界で働く道を断たれました。結局、半ば強制的に入社し、そのまま工場へ配属となりました。
そこから4年間、ひたすら工場でおこしづくりを学びました。周りの友人たちがスーツを着て働く姿を羨ましく思うこともありましたが、今となっては、この時の経験が私の経営の礎となっています。もし私が外で修行をしていたら、父が急逝した際に、おこしのことも会社の内部事情も分からないまま社長になっていたでしょう。36歳で社長になるとは夢にも思っていませんでしたが、結果的には良かったのだと思っています。
72億円の負債から始まった事業再生の道のり
ーー社長に就任された当時、会社はどのような状況だったのでしょうか。
穂刈久米一:
父は高度経済成長期を駆け抜けた経営者で、借入金を元手に事業を拡大していく手法でした。しかし、私が社長に就任した平成8年はバブルが崩壊した直後。会社の蓋を開けてみると、72億円もの借入金があり、「この会社は潰れる」と血の気が引いたのを覚えています。従業員も400名おり、会社をどう守っていくか、そればかり考えていました。
ーーその危機的状況をどのように乗り越えられたのですか。
穂刈久米一:
まず、自分の目が届く範囲まで会社を小さくするしかないと考えました。「雷おこし」は東京の土産物なのだから、地方で売る必要はない、と。東京駅で買ったお土産が、大阪の駅でも売っていたらお客様はがっかりするはずです。そこで、全国の営業所を閉鎖し、3つあった工場も1つに集約しました。売上を伸ばすのではなく、固定経費を徹底的に削減するという後ろ向きなやり方でしたが、5年かけて会社を黒字化させることができました。
ーー事業縮小を進める上で、最も辛かったことは何でしたか。
穂刈久米一:
何よりも辛かったのは、社員を解雇することでした。会社のために一生懸命働いてくれた仲間たちに辞めてもらうのは、本当に断腸の思いでした。社員は会社の宝です。あの時の痛みは、今の私の経営における「人を大切にする」という信念につながっています。
「伝統は改革である」という経営哲学の実践

ーー経営に際し、大切にされている考え方はありますか。
穂刈久米一:
父から受け継いだ会社ですが、経営者になったからには自分の信じる道を遠慮なく進むべきだと考えています。実は、父が早くに他界したことで、思い切った改革ができたという側面もあります。私は、創業者の息子が社長に就任してから事業を立て直そうと事業縮小を計画しても、「俺が苦労してつくった店を閉めるな」と先代から反対されて立ち行かなくなった会社をたくさん見てきました。その点、私は誰にも反対されず、自分の責任で改革を実行できました。
ーー具体的にどのような改革をされたのでしょうか。
穂刈久米一:
たとえば、包装紙のデザインです。父は「老舗の顔を変えるな」と言っていましたが、私は雷門と共に歩んできたのだから、雷門をデザインに入れたかったのです。父の死後、すぐに包装紙と紙袋を雷門のデザインに変えました。時代が変わればお客様の好みも変わります。220年の歴史といっても、昔と今のお客様が同じものを食べているわけではありません。だから、味も時代に合わせて変えています。甘さを抑え、着色料をやめ、お米の風味を活かす。
伝統を守るとは、変えないことではなく、時代に合わせて変え続けること。「伝統は改革である」。これが私の信念です。
浅草の旦那衆との絆が生む地域との共存共栄
ーー地元・浅草との関わり方で、大切にされていることは何ですか。
穂刈久米一:
父から「地元の発展なくして企業の発展なし」と常々言われていました。浅草が魅力的な街になり、多くの人に来ていただいてこそ、私たちの商売は成り立ちます。ですから、浅草観光連盟などの地域の活動にも積極的に参加しています。ただ、父には「会社の仕事をおろそかにするな」とも言われていました。地域活動に没頭するあまり、自社の経営が見えなくなっては本末転倒です。そのバランスを常に意識しています。
浅草の旦那衆とのつながりも深く、みんな幼馴染です。子どもの頃は「くめちゃん」と呼ばれていましたが、今でもファーストネームに「ちゃん」付けで呼び合っています。みんなこの街に住み、商売をしている仲間だから、三社祭のようなお祭りも一体となって盛り上がる。この強いつながりが浅草の良さであり、強みとなっています。
ーー貴社にとって、浅草の雷門本店はどのような存在ですか。
穂刈久米一:
本店は私の宝箱です。土日には、私自身が店頭で実演販売をしているのですが、自分が心を込めてつくったおこしが、お客様の笑顔と共に目の前で確かな対価に変わっていく。その瞬間、「ああ、商売をしているな」という生の実感を得られます。この場所があるからこそ、私たちは商売を続けられる。私にとって、何よりも大切な場所です。
老舗経営者としての明確な引き際と覚悟
ーー今後の事業において、特に注力していきたいテーマは何でしょうか。
穂刈久米一:
一つは、時代に合わせた新商品の開発です。これまでに夏向けの「塩おこし」やお酒にも合う「チーズおこし」。若者にも好まれる「キャラメルアーモンド」などを次々と開発しました。社員のアイデアも積極的に取り入れ、今後も伝統を守りつつ常に時代のニーズに応えて行きたいと考えています。
そして、もう一つが人材の強化です。会社は社長一人では成り立ちません。つくる人、運ぶ人、売る人、それぞれのチームワークが不可欠です。最近は採用した社員がすぐに辞めてしまうことに寂しさを感じています。会社を縮小した時に断腸の思いで社員を解雇した経験があるからこそ、入社してくれたからには家族のように大切に育て、一緒に会社を盛り立てていきたいのです。
ーー未来に向けて、どのような展望をお持ちですか。
穂刈久米一:
私は、会社の社長とは駅伝のランナーだと思っています。今、襷(たすき)を持って走っているのが私です。絶対に倒れることなく、次の走者である専務の息子にこの襷を渡さなければなりません。私は2年後の67歳で引退すると決めています。それまでに会社をより良い状態にして、次の世代に渡す。それが老舗の社長である私の最後の任務だと考えています。
編集後記
父への反発、意に反した入社、そして巨額の負債。穂刈氏の経営者人生は、決して平坦な道のりではなかった。しかし、その言葉の節々から感じられたのは、逆境を乗り越えてきた者だけが持つ強さと、生まれ育った浅草への揺るぎない愛情だった。伝統の重みを背負いながらも、過去に固執せず未来を見据えるその姿勢は、事業承継に悩む多くの経営者にとって、確かな指針となるだろう。

穂刈久米一/1960年東京都浅草生まれ。1983年、学習院大学経済学部経済学科卒業後、株式会社常盤堂雷おこし本舗に入社。工場で4年間、雷おこしづくりの基礎を学ぶ。その後、浅草に戻り、販売の部署に異動。1990年同社代表取締役副社長、1996年同社代表取締役社長に就任。社長就任以来、今の時代に合わせて事業を縮小し、浅草中心の商売に。浅草の町の発展のため、各諸団体で汗を流している。