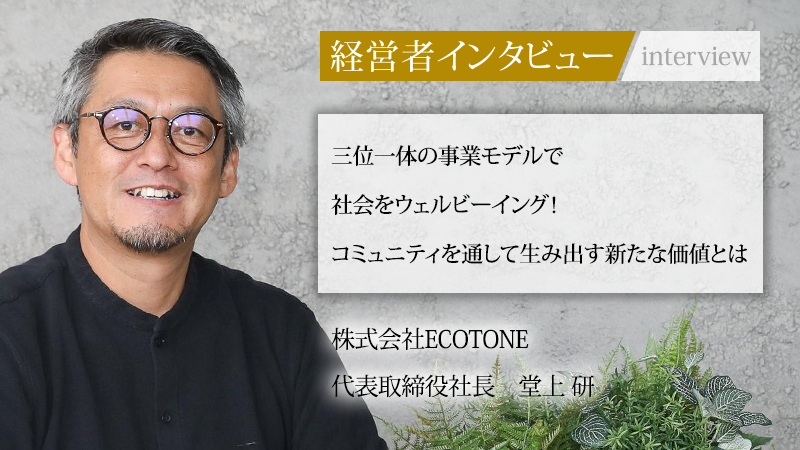
数々の国内大手企業の広告を手がけた博報堂での20年以上のキャリアを経て、社内起業家へと転身した人物がいる。株式会社ECOTONEの代表取締役社長、堂上研氏だ。同社は、心身と社会的な健康を意味するウェルビーイングを軸に、メディア運営・事業共創・コミュニティ運営を三位一体で展開する。大手広告会社の外に飛び出して、あえて「いばらの道」を選んだ理由とは。その軌跡と事業の強み、そして見据える未来について話を聞いた。
「評価」より「面白い」を追求する
ーー起業に至るまでのご経歴をお聞かせください。
堂上研:
大学卒業後、1999年に株式会社博報堂へ入社しました。もともとはアートに関心があり、3年ほどで退職してデザインの勉強をするつもりでした。希望していたクリエイティブ職ではなく営業に配属されましたが、CM制作やマーケティングなどの現場が面白く、気づけば10年以上が経っていました。
転機は、広告の仕事に一区切りついたと感じた時に訪れました。元々、「事業を自分でつくりたい」という思いが強く、10数年前に一度、退職と起業を決意しました。その際、博報堂の中で事業をつくる「社内で新規事業に挑戦していい」という機会を得たのです。しかし、最初のうちは失敗の連続でした。
ーー現在の事業モデルへはどのようにたどり着いたのでしょうか。
堂上研:
当初は、博報堂の広告やマーケティング事業領域からあえて離れたヘルスケアや教育といった、いわゆる飛び地の事業分野を考えていました。しかし、専門外の領域では結果が出ず、「餅は餅屋」だと痛感しました。そこで、私たちが持つ広告やマーケティング、メディア運営のノウハウといった博報堂のリソースを最大限に活かせる事業こそが、成功への近道だと気づきました。
博報堂という広告会社で、仕事を楽しみながら進めていくことを教えてくださった当時の役員がいます。「私たちの仕事は、社会に新しい価値を提供するクリエイティビティ」と声をかけてくださいました。その言葉に衝撃を受け、生活者に新しい価値を提供するこの仕事の面白さに目覚めたのです。実際、企業内起業の道を選んだのも、自身の評価のためではなく、自分が「面白い」と思えるかが大切だと思っています。社会をウェルビーイングにできるか。その軸が、現在の事業を立ち上げた原動力になっています。
メディアを起点に価値を循環させる三位一体の事業モデル

ーー貴社の事業内容と、強みについて教えてください。
堂上研:
弊社の事業は、主に3つの要素を三位一体で展開している点が最大の強みです。
1つ目は、メディア事業です。ウェルビーイングをテーマにしたメディア「Wellulu(ウェルル)」を運営しており、企業の人的資本経営やエンゲージメント向上のための記事のほか、経営者や企業のリーダーたちの人柄や、仕事の裏側にある“B面”に焦点を当てた対談記事などを掲載しています。検索エンジンで上位表示されるためのSEO対策を徹底することで広告に頼らない集客を実現し、設立からわずか2年で月間40万人が訪れるメディアへと大きく成長させました。
2つ目は、事業共創です。メディアで得たデータや知見を基に、企業と共に新しい事業を開発します。世の中には事業開発をしているチームがたくさんいるのですが、ウェルビーイングな顧客にどんな価値を提供するかが共創の中で動きます。衣食住などあらゆる産業が、ウェルビーイングトランスフォーメーションで、事業共創が進行中です。単なる情報発信やコンサルに留まらず、きちんとビジネスにまで実装させていく点が特徴です。
3つ目は、コミュニティ運営です。事業共創の過程で生まれたテーマを軸に、バーティカルにコミュニティを組成・運営しています。例えば、「睡眠上手になる会」といったコミュニティを立ち上げ、参加者が体験やデータを共有し、専門家から助言を受けられる場を提供します。このコミュニティでの発見を、また新たなメディアコンテンツや事業共創へとつなげていきます。
ーー貴社独自の価値観はどこにあるとお考えですか。
堂上研:
経営者を取材する際の視点に特徴があります。弊社では企業の業績や製品だけでなく、経営者の「B面」、つまりその方の人間性や思想、哲学、つまり「生き方」に深く切り込みます。ニコンの徳成社長にギターを持っていただいた記事は、その好例です。こうした人間味あふれるコンテンツは非常に評判が良く、企業の採用ページなどにも使っていただいております。
また、会社の成り立ちそのものも強みです。博報堂100%の子会社ではなく、あえて外部のエンジェル投資家や有識者を取締役として迎え入れています。会社自体を、公共のものであり、みんなで共創の中で育てていきたいと考えて外部資本を入れてもらいました。社名の「ECOTONE」は、生物学の言葉で、異なる生態系が接する移行帯を意味します。その名の通り、多様な知見や資本が交わることでイノベーションを生み出すオープンイノベーション(※1)を実践しているのです。
(※1)オープンイノベーション:企業が自社の経営資源だけでなく、外部の組織や機関の知識や技術も活用して新しい価値を創出する。
目指すは「社長輩出業」共創で拓くウェルビーイングの未来
ーー貴社が目指す、今後のビジョンについてお聞かせください。
堂上研:
企業間の共創ネットワークを拡大していきたいと考えています。働く、旅、睡眠、認知症予防、腸活、休養といったウェルビーイングに関する様々な領域でハブとなる企業と連携。そこからさらにネットワークを広げ、新しい事業を次々と共創していく計画です。
最終的に目指すのは、弊社をホールディングスのような役割とし、その傘下に何十もの事業会社が生まれている状態です。私たちは自らを「産業創出業」や「社長創出業」と位置づけています。事業をつくりたいという情熱を持つ人々を支援し、多くの経営者を世に送り出していきたいのです。
ーー一般的なベンチャーキャピタルとはどう異なるのでしょうか。
堂上研:
弊社は単にお金を出すだけの存在ではありません。お金はもちろん、人、アイデア、そして事業運営のノウハウまで提供し、事業の成功に深く関わるハンズオン(伴走)型の支援を行います。
ウェルビーイング市場は800兆円規模に成長するともいわれ、すべての産業が向かう大きな潮流だと確信しています。この巨大な市場で、私たちの共創ネットワークを通じて新しい価値を提供し続ける。それが、私たちが描く未来です。
編集後記
大手広告代理店での成功に安住せず、社内起業家へと挑戦した堂上氏。その原動力は「評価」ではなく「自分が面白いと思えるか」という純粋な探究心にあった。「つながりの中で、ひとりでも多くの人をウェルビーイングにする」という壮大なビジョンのもと、社会をウェルビーイングなものにしていく。ECOTONEという新たな「生態系」から、どのような革新が生まれるのか。今後の挑戦から目が離せない。

堂上研/1999年、国際基督教大学教養学部を卒業後、博報堂入社。主に、食品・飲料・保険・金融などの広告マーケティングプロデュースに従事した後、2012年には博報堂ビジネスアーツで、事業化クリエイティブのプロデュースを担当。2019年、「ミライの事業室」設立、室長代理・ビジネスデザインディレクターに就任。2024年、株式会社ECOTONEを設立し、代表取締役社長、Wellulu編集長に就任。














