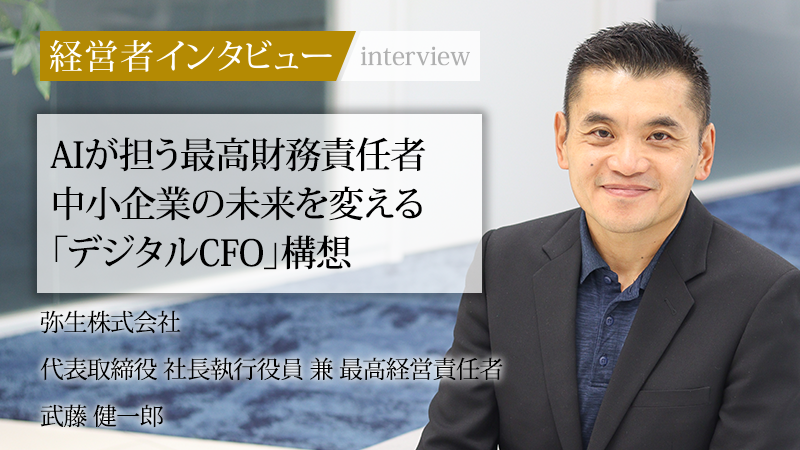
中小企業や個人事業者向けに会計ソフトを提供する弥生株式会社。ITエンジニアからコンサルタント、そしてGoogleでの事業責任者と、多彩なキャリアを歩んできた武藤健一郎氏が、2024年に同社のトップに就任した。Google時代に目の当たりにした、AIをめぐる企業の二極化。その課題意識を胸に、日本の大多数を占める中小企業の生産性向上という大きなテーマに挑む。武藤氏が目指すのは、会計業務の自動化の先にある「デジタルCFO」という未来像だ。新ミッションのもと、変革の道を歩み始めた同社の現在地と、その先のビジョンについて話を聞いた。
Google時代に見た企業の二極化 会計データに感じた変革の可能性
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせください。
武藤健一郎:
キャリアの最初はITエンジニアです。アンダーセンコンサルティング(現・アクセンチュア)でシステムの設計や構築に携わったのが始まりです。そこで論理的に物事を考えることを学び、自分よりはるかに優れたエンジニアがいるという事実にも直面しました。彼らと同じ土俵で戦うのは厳しいと感じ、MBA取得を経て経営コンサルの道へ進んだのです。
同時に、米国南部のチームで働いた経験は、多様性への理解を深める上で非常に影響を受けました。人種や文化の異なる人々がどう協働していくのか。20代でこのテーマに触れられたのは、人として大きく成長できる機会になったと感じます。
マッキンゼーには「Make your own McKinsey(自分のマッキンゼーを作れ)」という言葉があり、文字通り、自分がやりたいと思うプロジェクトを追求できる環境でした。エンジニアの経験を活かして主にテクノロジー関連企業のコンサルティングを手がけ、世界中を飛び回る刺激的な毎日を過ごしたのです。しかし、40歳という節目を迎え、コンサルタントとして10年間で培った論理思考や問題解決の手法を胸に、次のステージへ進むことを決意しました。
ーーその後入社されたGoogleでは、どのような課題意識を持たれたのでしょうか。
武藤健一郎:
Googleでは中小企業向けの広告営業を10年間担当しました。そこで、AIを使いこなす企業とそうでない企業の間に生まれる歴然とした差を目の当たりにしたのです。AIを巧みに使う企業は好循環に入り成長する一方、従来型の企業は悪循環に陥っていました。特にコロナ禍では、ロックダウンを経験したドイツ企業がデジタル化で大きく成長したのに対し、日本はその機会を逃してしまったと感じています。このままでは多くの中小企業が立ち行かなくなるという強い危機感を覚えました。
AIの活用が最も効果を発揮するのは、プロセスが定型化され、かつ良質で多様なデータが豊富な領域です。まさに会計業務がそれに当たります。そして、日本で最も多くの中小企業の会計データを持つのが弥生でした。この膨大なデータを活用すれば、中小企業の役に立つ本当に面白いAIがつくれるのではないか。そう考えたのが、弥生への入社を決めた理由です。
圧倒的な顧客基盤と独自の強み 中小企業に寄り添う事業の根幹

ーー貴社の事業内容と独自の強みについて教えてください。
武藤健一郎:
弊社は、主に小規模事業者向けの会計や給与計算のソフトウェアを開発・提供しています。強みは、製品が使いやすく導入しやすい価格帯であることと、全国の会計事務所や税理士事務所との強固なネットワークです。
新しい製品群である「Next」シリーズは、単なる会計業務のオンライン化に留まりません。クラウド上で各製品が連携し、データを繋ぐことで、中小企業の経営全体を支えるプラットフォームとなることを目指しています。AIによる資金繰り予測のような最新機能をいつでも利用でき、常に進化し続ける点が特徴です。
会計の未来像「デジタルCFO」構想 事業と組織の両輪で進める大変革
ーー5年後、10年後、会社はどのような姿を目指しますか。
武藤健一郎:
個人的には「中小企業のデジタルCFO」という立ち位置になれると良いと考えています。将来的には、会計のような定型業務はAIが担うのが当たり前になります。私たちは、事業者が本来の創造的な仕事に集中できる世界を実現します。そのための選択肢であり続けたいと考えています。そのために、使いやすい技術を追求し、お客さまと共にAIとの付き合い方を学んでいく必要があります。
今後は銀行系のサービスを拡充するなど、フィンテック分野へも進出します。たとえば、弊社の会計データを活用すれば、より良い条件の融資を提供できる可能性があります。このように、データとテクノロジーでお金にまつわる悩みを解決していく所存です。
ーー組織文化の変革に関してはどのような取り組みをされているのでしょうか。
武藤健一郎:
現在、プロセスよりも結果を重視する「パフォーマンス文化」への転換を進めています。単に「頑張った」ことではなく、生み出した「結果」で評価される、透明性の高い組織を目指しているのです。人の成長に欠かせないフィードバック文化を根付かせるべく、全社的な研修を実施しています。建設的な意見を交わしながら、新しいものを生み出す組織風土の醸成が目的です。
中小企業と共に描く成長の未来 日本に好循環を生むための決意
ーー貴社のミッションについておうかがいできます。
武藤健一郎:
弊社のミッションは「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」です。「事業コンシェルジュ構想」を掲げていた時期もありましたが、どこか受け身の姿勢を感じていました。AIの進化が速い時代、お客さまを待つのではなく、私たちから積極的に「〇〇しましょう」と提案し、共に変化していく。その強い意志を込めました。
ーー最後に、今後の事業拡大に向けた意気込みをお聞かせください。
武藤健一郎:
先述のミッションを実現するためには、より多くの中小企業の力になる必要があります。そのための分かりやすい指標として、私は社員に「お客さまの数を倍にしよう」と伝えています。これは単なる数値目標ではなく、その規模に対応できるシステムや仕組みを今から設計するための、未来志向の基準と言えます。この大きな目標を掲げ、私たちの挑戦で中小企業を元気にし、日本全体を盛り上げていくという決意です。
編集後記
ITエンジニア、経営コンサルタント、そしてGoogle。多様な世界で培われた論理的思考と、AIがもたらす未来への鋭い洞察。武藤氏が掲げる「デジタルCFO」構想は、中小企業のあり方そのものを変革する可能性を秘めている。受け身の「コンシェルジュ」から未来を指し示す「羅針盤」へ。弥生の挑戦は、変化の時代を生きるすべての事業者にとって、心強い道標となるだろう。

武藤健一郎/1972年、ブラジル・サンパウロ生まれ。1994年、アンダーセン コンサルティング株式会社(現・アクセンチュア株式会社)に入社。2001年、マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパンに入社。2012年からは、業務系ソフトウエアのカスタマーサポートなどを請け負うスタートアップ企業での日本支社長を経験。2014年、Google合同会社に執行役員として入社。2024年10月、弥生株式会社に入社し、代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者(CEO)就任。














