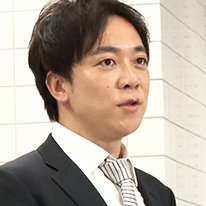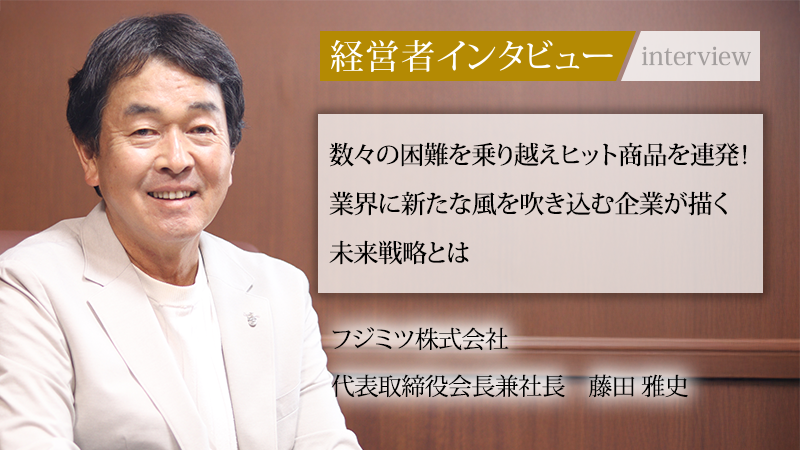
本社を山口県長門市に構え、138年の歴史を刻むフジミツ株式会社。地元で愛される伝統の練り製品づくりを守りながら、「チーズころん」や「おつまみかにかま」といった革新的な商品を次々と生み出し、業界に新風を吹き込んできた。その変革を牽引してきたのが、5代目社長の藤田雅史氏である。陸上自衛隊幹部候補生学校、アメリカ留学という経歴を持つ藤田氏が、先代である父との激しい対立を乗り越え、いかにして会社を変革してきたのか。山口から世界へ、失敗を恐れず挑戦を続ける経営者の情熱と、その視線の先にある未来に迫る。
波乱万丈の青年時代が、独自の経営観を育んだ
ーーこれまでのご経歴について教えてください。
藤田雅史:
私は1961年生まれで、三人兄弟の長男です。生まれた時から跡継ぎと見られて育ったため、子どもの頃は「とにかく田舎を出て東京の大学へ行きたい」と考えていました。中でも、東京水産大学(現:東京海洋大学)を志望していたのですが、高校2年生の時に文理を決める際、父から「経営感覚を学べ」と言われ、希望していた理系ではなく文系の経済学部に進路変更しました。
しかし、いくつか受けた大学は全て不合格に。そこで、他に受かりそうな大学を受験しようとしたところ、学校の先生が内申書を出してくれなかったのです。これは後で聞いた話ですが、母が「長男を東京へ行かせないでくれ。あの子は遊びほうけて家に帰らなくなるから」と心配して、高校の担任の先生に、合格しそうな東京の大学を受けさせないように頼んでいたそうです。そうした経緯もあり、地元の山口大学に進学。家業を継ぐことが決まっていたため卒業後の心配もなく、自分の人生に対する危機感が薄かった私は、大学時代も将来をあまり深く考えることなく過ごしていました。
そんな大学時代に、遊びに明け暮れていた私を見かねた父から「大学を出たら陸上自衛隊の幹部候補生学校へ行け」と突然命じられました。坊主頭にしなくてはならないし、自由もありません。最初は断ることばかり考えていましたが、後輩の女の子に当時公開された映画『愛と青春の旅だち』の話を聞きました。「先輩、リアル『愛と青春の旅だち』じゃないですか!かっこいい!」と言われ、その気になって入隊を決意したのです。
父としては、私にリーダーとしての資質を身につけさせたかったようですが、入隊時のパイロット適性検査の結果が良かったみたいで、希望していなかったヘリコプターのパイロットコースに進みました。しかし、そのことを知った母と祖母が「跡取り息子が事故にあったら大変だ」と大騒ぎになり、結局、1年半で退職することになりました。
ーー自衛隊を辞められた後はどのような経験をされましたか。
藤田雅史:
父から「将来は原料が海外から入るようになるから、英語を話せるようになって国際感覚を身につけてこい」と言われ、9ヶ月間アメリカのシアトルへ語学留学しました。大学時代、あれほど苦手だった英語を学ぶことになったのです。自分の人生で海外生活をするのはこの時だけだろうと考え、「今しかできないことをやろう」と思い、英語は苦手でしたがコミュニケーションには自信があったので「外国人の友達を一番多く持つ日本人になる」という目標を立て、日本人同士で固まるのをやめ、国籍を問わず外国人の友人と過ごすようにしました。
最初はつたない英語でしたが、気持ちを伝えようと懸命にコミュニケーションをとり続けた結果、次第に話せるようになりました。その努力が功を奏し、電話も普通にできるまでになり、学校も予定より早く卒業することができました。この時の経験が、後の私の考え方に大きな影響を与えています。

ーー貴社の歴史や成り立ちについてお聞かせください。
藤田雅史:
弊社は1887年に私の曽祖父の代から始まり、138年続いています。祖父の代までは、地元の魚を使った「焼き抜き蒲鉾」をつくる家内工業で、地域に根差した商売をしていました。
弊社にとって、父が会社を大きくしたいと考えたことが大きな転機でした。当時会社を仕切っていた父の叔父たちと意見が合わず、父は一度フジミツを離れ、職人二人を連れて別会社を立ち上げています。その会社が成長し、元のフジミツを吸収する形になったのです。
父は、北洋漁業で獲れるスケトウダラを使った「冷凍すり身」をいち早く導入して量産体制を築きました。また、営業部門をつくり、大阪の市場へ売り込みに行くなど、個人商店から会社組織へと成長させたのです。
「俺の目の黒いうちは」父との対立から生まれた大ヒット商品
ーー家業での最初の仕事は、どのようなものだったのでしょうか。
藤田雅史:
帰国したのは、25歳になった9月30日の夕方でした。父から突然「明日から10月になり、三隅工場はおでんで忙しくなる。工場長として行って、社員の残業を減らしてきなさい」と命じられました。あまりに突然で頭が真っ白になりましたね。もちろん経験はないので、最初は何も分からず、昼間はずっと商品の段ボールにテープを貼る毎日でした。
毎日、社員を帰宅させた後、当時の三隅工場の幹部社員の雑談を聞くのが「工場長」としての私の日課でした。しかし、仕事の段取りに関する会話はしているものの、残業を減らすための話が一切出ていないことに気づきました。現場には、その意識がなかったのです。
そこで、私が「残業を減らそう」と提案しても、最初は「無理だ」と相手にされませんでした。しかし、観察を続けるうちに特定の生産ラインがいつも遅れることが全体のボトルネックになっていると分かりました。そこで「そのラインだけ朝早く始めればいい」というごく当たり前の提案を実行したところ、全体の終業時間が2時間も早くなったのです。この成功体験が、改善活動の面白さに目覚めるきっかけでした。
ーーその後は、どのような仕事に取り組まれたのですか。
藤田雅史:
4年ほど工場で改善活動に取り組んだ後、会社の売上が落ち始めたのを機に、自ら志願して営業に移りました。当時、弊社の主力である板付きかまぼこのシェアは50%を超えていましたが、ちくわやさつま揚げは10%にも満たず、「かにかま」に至ってはゼロという状況でした。

そこで、シェアの低い分野で他社の売れ筋商品を参考に新商品を開発し、既存の販路で展開する戦略をとったところ、売上は再び伸び始めたのです。
本格的な商品開発を始めたのは30歳を過ぎてからです。特に「かにかま」は、父が「偽物だ。俺の目の黒いうちは絶対にやらせない」と猛反対していました。それでも諦めきれず、事業計画書を6回も書き直して提出し続けた結果、根負けした父から、最後は「お前はしつこい」の一言で許可が出ました。ただし、「どうせ売れないから、お前は関わるな。」という条件付きでした。もちろん私は関わる気満々でした。現在では「かにかま」は当社の売上の25%を占める主力商品になりました。
ーー代表商品である「チーズころん」は、どのようにして生まれたのでしょうか。
藤田雅史:
スナックで食べたおかきが歯にくっついた時、「表面がカリカリした、ちくわのような食感のおやつがあったら美味しいのでは」と思ったのが最初の発想です。これからの時代、女性に支持されるためには赤ワインに合う商品が必要だと考え、チーズを使用しました。「かまぼこでお菓子をつくる」というコンセプトで、あえてパッケージに「かまぼこ」の文字を入れなかったのは、業界の先駆けだったと思います。

しかし、この商品も「まがいものだ」「伝統あるかまぼこ屋のブランドを汚すな」と役員会で父から大反対されました。父との対立を通じて、交渉力が非常に鍛えられたと感じています。理論で勝っていても権力では負けてしまうため、銀行の役員や設計士など、第三者から父を説得してもらう方法を考えました。「自分が言っても通らないなら人を使う」ということを覚えた30代でしたね。
従業員の心に寄り添う「幸せ経営」の神髄
ーー採用において、特に大切にされていることは何ですか。
藤田雅史:
採用を成功させる鍵は、今働いてくれている従業員だと考えています。彼らが会社や仕事に満足してくれなければ、新しい人は入ってきません。特に田舎では口コミですぐに広まりますから、給与などの物質的な満足だけでなく、心に訴えかける企業ブランドをつくることが不可欠です。
そのための具体的な取り組みの一つが、弔電です。私が全ての従業員関係者の葬儀に参列することはできませんが、弔電は必ず送ります。その際、定型的な文章ではなく、必ずその方との思い出や家族への感謝を込めた、私自身の言葉でメッセージを作成します。
そうすると、葬儀屋さんまでが「フジミツの社長からの弔電は読んだ方がいいですよ」とご家族に勧めてくださるようになりました。実際に、司会の方が涙で声を詰まらせながら読んでくださったこともあります。悲しみの場でかけられた温かい言葉は、人の心に深く残ると信じています。周囲から「いい会社に入ったね」と言われることが、本人の誇りにもつながると考えています。
ーー従業員の皆さんの声を聞くために、具体的にどのようなことをされていますか。
藤田雅史:
役員には毎週現場に入るよう指示しています。そして、工場の幹部には「現場の暑さ対策は、涼しい部屋ではなく、その暑い現場で考えろ」と常に言っています。従業員の声を聞き、物理的な環境改善だけでなく「心のクールダウン」を促すことが大切なのです。また、ボウリング大会を企画するなど、私がアイデアを出してコミュニケーションの場をつくることもあります。
ーー近年、組織づくりにおいて新たに取り組まれていることはありますか。
藤田雅史:
6年前に「社長塾」を始めました。60歳を目前にして、それまでのワンマン経営では組織が育たないと気づいたのがきっかけです。業績が上がらないのを人のせいにしていましたが、自分が直接コミュニケーションをとってみると、私の考えが意外と伝わっていないと分かりました。そこで、部長以上の幹部を集め、私の経験を図や表で可視化して共有しています。私が60の手習いで伝え方を工夫することで、幹部たちが自ら現場の課題を見つけ、改善に取り組むようになりました。自分の考えを定型化して伝えるということを学んだ、陸上自衛隊幹部候補生学校での経験が大いに役に立っています。
失敗を恐れず山口から世界へ フジミツが描く未来図

ーーこれまでの海外展開では、どのような取り組みをされてきましたか。
藤田雅史:
アメリカ留学の成果の1つとして、「人に対する度胸」が身についたと思っています。外国人と話をすることに全く抵抗がありません。「どうせ相手も人間だ」と思えば、立場を超えて誰とでもフランクに話せます。そうやって人間関係を広げていくことが、商売にもプラスになると考えています。この考えを基に、練り製品の食文化が日本と近いアジア圏を中心に、韓国への輸出や、中国、ベトナムでの事業展開を進めてきました。
もちろん、成功体験ばかりではなく、失敗も数多くあります。中国での現地法人は今でこそ成功していますが、ベトナムでの事業は完全に失敗に終わりました。また、練り製品の健康イメージを向上させるために始めたオーガニック事業も、時代を先取りしすぎてうまくいきませんでした。
ーー今後の事業展開や成長戦略については、どのようにお考えですか。
藤田雅史:
M&Aに取り組んでいます。東京の経営者会で大企業の跡継ぎたちと交流する中で、彼らの経営スキームを学び、かまぼこ業界でも始めました。その際に心がけているのは、相手の会社のブランド、つまり「のれん」と技術、商品を必ず残すことです。伝統産業であるため、それを大事にしなければ従業員の方々も辞めてしまうからです。
また、これまでは商品を売ることばかり考えてきましたが、これからは「技術を売る」ことを検討しています。それは、単に美味しいものをつくる技術だけではありません。日本の製造業がこの30年間で培ってきた「コストダウン」のノウハウ、特に弊社がこの5年間で実践してきた工場改善の経験は、海外企業にとって大きな価値を持つはずです。このノウハウを提供し、コスト削減を実現した分の一部をロイヤリティとしていただく。そのために、去年から会社の定款に「コンサル業」の項目を加えました。
ーー今後の展望についてお聞かせください。
藤田雅史:
「今が当たり前と思ってはいけない」という意識を、従業員全員で共有できるように、これからも試行錯誤を続けていきます。私自身、60歳を過ぎてから「『やりたいこと』と『できること』は違う。時代を先駆けるだけでなく、時代に合わせることも必要だ」と気づきました。「社長塾」などを通じて、私の経験を共有し、会社全体で変化に対応できる組織づくりに力を注いでいきます。
ーー最後に、この記事の読者へのメッセージをお願いします。
藤田雅史:
物事に対する「気づき」が改善の第一歩です。私も、工場長になりたての頃、現場の何気ない会話の中に課題のヒントが隠されていることに気づき、そこから改善を始めました。「チーズころん」のような商品も、飲み屋でのお菓子の食感という、日常の些細な出来事が発想の源になっています。
便利なネット社会で情報は簡単に手に入ります。しかし、自分自身の目で見て、肌で感じて「なぜだろう」と考えることが重要です。その小さな気づきの積み重ねが、やがて大きな成果や自分だけの価値に繋がっていくのだと私は思います。
編集後記
「しつこい」と父に言わしめ、大ヒット商品を生み出した粘り強さ。国籍や立場を越え「どうせ相手も人間だ」と懐に飛び込むコミュニケーション能力。藤田氏の全ての行動原理は、自衛隊やアメリカ留学で培われた経験に裏打ちされていた。伝統ある企業の5代目でありながら、その姿は常に挑戦者そのものだ。特に、一通の弔電に心を込める「幸せ経営」の神髄に触れたとき、この会社の強さの根源を垣間見た気がした。失敗を恐れず、山口から世界へと挑み続ける同社の未来に期待したい。