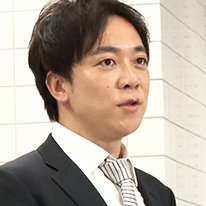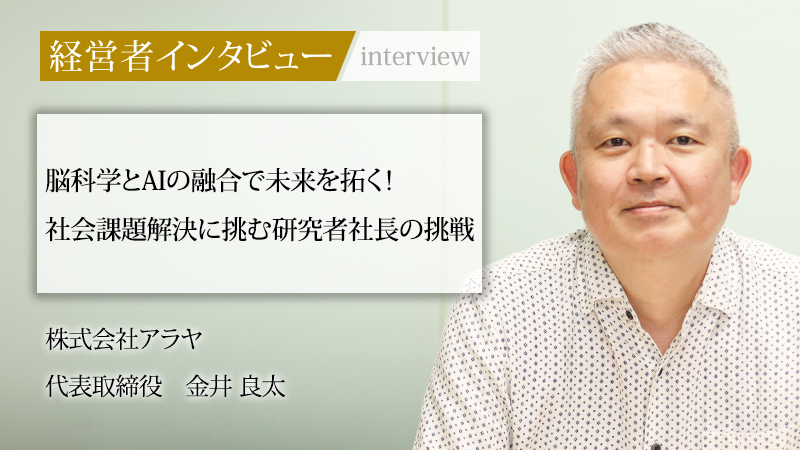
脳科学とAI(人工知能)を融合させた「ニューロAI」によって社会変革を推進する株式会社アラヤ。同社を率いる代表取締役の金井良太氏は、オランダ、アメリカ、イギリスと海外で研究キャリアを積んだ後に創業した経歴の持ち主である。脳の研究から始まった探求は、AIとの出合いによって新たな展開を見せ、現在では建設業界の革新から研究支援まで、多岐にわたる分野で独自のソリューションを提供している。今回、困難を乗り越える原動力となった研究への愛と事業への思いについて、詳しく話を聞いた。
研究者からの転身 起業への道
ーーまず、これまでの経歴を教えていただけますか。
金井良太:
オランダで博士号を取得した後、カリフォルニア工科大学に渡り、ポスドク(博士研究員)として研究を続けました。その後、イギリスのユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンに5年ほど在籍し、サセックス大学では教員として研究や授業を受け持った後、起業しました。
当時、脳のデータを大量に集めていて、データをもっと集めれば人間を深く理解できると考えていました。しかし、大学でのデータ収集には限界があったため、会社組織であればより多くのデータを集められるのではと考え、起業を決意したのです。個人的には「日本に住んでみたい」、「違うことに挑戦したい」という気持ちもありました。
もともと、どこかに就職するという選択肢は考えておらず、「いつか自分で会社を興すだろう」と思っていました。
ーー会社を立ち上げてから、AIの領域に進まれたきっかけは何だったのでしょうか。
金井良太:
当初は脳の研究を軸に事業を展開しようと考えていたのですが、ビジネスとして成立させるには困難でした。同じ頃、AIが一気に注目され始め、私自身が脳の分析にAIを活用していたことが転機となり、この領域に足を踏み入れたのです。
当初の目的とは異なる方向に進むことへの葛藤はありました。しかし、AIの世界は圧倒的な勢いで進化し、新しい技術も次々に登場してやれることが増えていく中で、私の興味も自然と広がっていきました。
AIのおかげで、たとえば、泳ぐマグロの数をAIで数えたり、車の運転支援技術や建設にも関わるようになったりするなど、AIを多分野に活用する企業へ成長を遂げました。明確な戦略があったというよりも、その時々の最善を選び取ってきた結果だと思います。
ーー起業や研究を続ける中で、苦労したことを教えてください。
金井良太:
正直に言うと、「この無限地獄から早く抜け出したい」と思うほどの苦労もありましたが、それでもやはり研究は面白いものです。AIの事業とは別に、私は今も意識の仕組みといった研究を続けています。
事業は、社会に必要とされて経済的な価値を生み出さなければ続きません。一方、研究はすぐには役立たないかもしれませんが、精神的な充足感を与えてくれます。この両方を行き来することが、私のバランスを保つ秘訣なのかもしれません。
多角的なAIソリューションで産業を革新

ーー改めて貴社の事業内容について教えていただけますか。
金井良太:
弊社には、3つの事業があります。
1つ目は中心となる先端AI開発事業です。自動車や金融、インフラなど幅広い業界のお客様に対して、ご要望に合わせて画像認識や生成AI、大規模言語モデルなどの技術を応用し、AIを開発しています。また、瞬時にさびを特定できる「さび検出AIモデル」のようなパッケージ化されたソリューションや、お客様と共に課題の掘り下げから解決まで伴走する、オーダーメイド型AI開発サービスも提供しています。
2つ目は建設事業です。橋やビルの建設計画を仮想空間で再現し、施工手順や安全性を事前に検証できます。この技術は、社内外への説明にも役立ちます。さらに、トンネル掘削やショベルカー(バックホー)の自動運転AIも開発し、建設業界が抱える人手不足や安全性の課題に取り組んでいます。
3つ目は研究支援事業です。脳波などの生体情報とAIの融合が弊社の強みであり、研究から開発まで一貫して対応できる体制が特徴です。安全運転時の脳活動を活用した製品開発支援や、研究プロセスを自動化して研究者がリサーチに専念できる環境を後押しする「Research DX」などを開発・提供しています。
脳×AIの独自性と「見えない価値」の追求
ーー貴社ならではの技術や取り組みはどのような点でしょうか。
金井良太:
弊社の大きな特徴は、脳とAIを融合させる分野に本格的に取り組んでいる点です。ドライバーの脳活動を可視化して安全運転支援に活かすプロジェクトなど、脳や生体情報を活用した研究支援に強みがあります。
国の「ムーンショット型研究開発制度」(※1)に採択された結果、通常のスタートアップでは難しい基礎研究にも着手できており、これが技術的な信頼性や独自性につながっています。
さらに、法人向けだけでなく個人向けの領域にも挑戦しており、AIを使った体験型エンターテインメントの開発も進行中です。AIをもっと身近で楽しいものとして届けていきたいと考えています。
(※1)ムーンショット型研究開発制度:日本発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発(ムーンショット)を推進する国の大型研究プログラム
ーー貴社が大切にしている価値観について教えてください。
金井良太:
お金に直結しないものは世の中では軽く見られがちです。しかし実際には、お金には換算できないものの、非常に大切なものもあります。だからこそ、そうした見えにくい価値と経済をうまくつなぎ直すことが必要だと考えています。
利益を生み出すことも大事にしていますが、それ以上に「大切な何かを育てる」ことを意識しています。もしお金よりも大事だと思えることがあるのなら、それを世の中に表現していける会社でありたいです。
弊社には、会社の利益に直結しなくても、社員が大事だと感じたことに挑戦できる「Visionary Lab」があります。また、アラヤで研究を続けている社員も少なくありません。
AIが当たり前になる未来への挑戦
ーー今後のビジョンについておうかがいできますか。
金井良太:
AIが当たり前に使われる未来を目指し、さまざまな業界の生産性向上に取り組んでいます。
建設事業では、全工程の自動化を目標に掲げ、将来的にはプログラムを書くだけで建物が完成するような世界を構想しています。宇宙建設などの挑戦も視野に入れ、建設業そのものを進化させたいと考えています。
研究支援事業では、「AIが研究する未来」を視野に入れています。AIによる仮説生成や論文執筆といった動きはすでに始まっています。これを脳科学分野にも応用し、次世代の研究者を支える基盤をつくっていきたいです。
最終的には、今の100倍の事業規模を目指しています。そのためには、技術だけでなく、社員の挑戦意欲や組織の柔軟性も重要です。私たちは技術を軸に社会の根本課題に挑む会社であり続けたい。自ら課題を見つけてリスクを取り、挑戦する。そのような文化を根付かせていきたいです。
編集後記
研究者出身の社長らしく、利益追求だけでなく「大切な何かを育てる」という哲学が印象的である。特に社員の挑戦を支援する「Visionary Lab」の取り組みは、技術系企業の理想的な文化を体現していると言えよう。建設の全工程自動化や宇宙建設への言及など、壮大なビジョンを語る一方で、現実的な事業展開も着実に進めている。研究者の理想と経営者の現実感を今後もどのように両立させ、どのように発展していくのか、今後の展開から目が離せない。

金井良太/1977年東京都生まれ。京都大学理学部卒業、オランダのユトレヒト大学で博士号を取得。2013年に株式会社アラヤを創業。サイエンスと経済の融合を掲げ、「ニューロAI」や画像認識など先端AI技術の研究開発、社会実装を推進。2020年より内閣府「ムーンショットプロジェクト」のプロジェクトマネージャーに就任。AIを活用したブレインマシンインターフェイスの開発を指揮する。