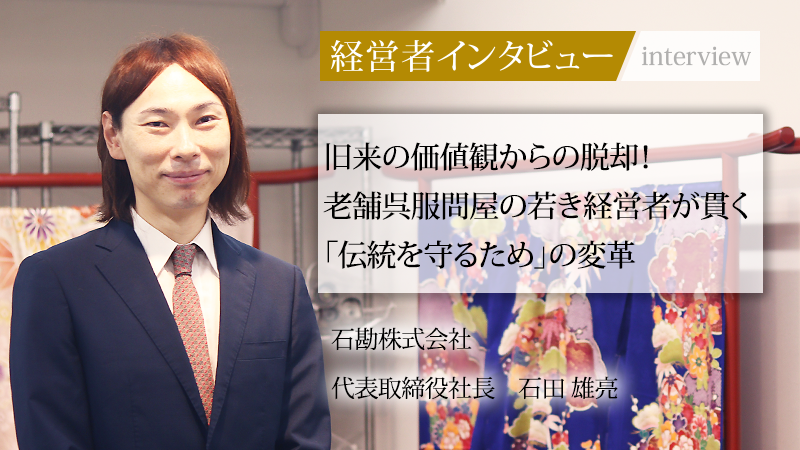
呉服の製造卸として京都に深く根を下ろす石勘株式会社。しかし、着物業界が構造的な転換期を迎える中、同社もまた存亡の危機に瀕していた。代表取締役社長の石田雄亮氏は、31歳という若さで、23億円もの巨額の負債を抱えた会社の経営を突如として託される。絶望的な状況から、規模の追求という旧来の価値観と決別し、事業の選択と集中、そして不動産事業という新たな収益基盤の確立によって会社を再建。伝統を守るために変わり続けることを選んだ若き経営者に、その壮絶な軌跡と未来への挑戦をうかがった。
家業を継ぐ覚悟なき修行時代、そして突如訪れた事業承継の現実
ーー当初から家業を継ぐ意識はあったのでしょうか。
石田雄亮:
いえ、幼い頃は家業を継ぐとは全く考えていませんでした。私は東京生まれで、父もすぐには家業に入らなかったため、実家が京都の着物屋だと知っていてもどこか他人事のように感じていました。ただ、大学卒業を意識する頃になると、いずれは自分がかかわるのだろうと漠然と考えるようになり、まずは修行のため大手の呉服問屋である株式会社ウライの門を叩きました。当時は着物の種類すら分からない、完全な素人からのスタートでしたね。
ウライさんでは2年余り、着物の基礎から催事販売までを叩き込んでいただきました。その後、一度石勘に戻りリサイクル着物を扱う部署を経験し、今度は取引先の小売企業へ3年間出向しました。この「問屋」と「小売」という川上と川下の両面から業界を俯瞰できた経験が、後の経営に大きく活きています。
ーーどのような経緯で社長に就任されたのですか?
石田雄亮:
本社に戻り営業担当として働いていた矢先、会社の経営が急速に悪化しました。銀行からも経営陣の一新を強く求められる事態となり、他に選択肢がない中で、31歳の時に社長を引き継ぐことになったのです。
売上至上主義との決別、負債23億からのサバイバル

ーー社長に就任された当時、会社はどのような経営状況だったのでしょうか。
石田雄亮:
まさに危機的、という言葉がふさわしい状況でした。当時の主力だった中国工場との契約が大きな足かせとなり、不良在庫が雪だるま式に膨らみ、赤字を垂れ流し続けていました。社長就任にあたり初めて決算書を隅々まで見て、会社の規模に全く見合わない巨額の借入金の存在を知った時は、本当に血の気が引きました。
ーーそこからどのように再建への一歩を踏み出されたのですか。
石田雄亮:
「ここまで来たら、今潰れるのも数年後に潰れるのも同じだ」と、ある意味で開き直りました。そして、会社を「潰さない」こと、ただそれだけを最優先事項に掲げたのです。社長就任後も営業活動を行い、新たな経営陣で大幅な意識改革を実行しました。
ーー大きな決断には、何かきっかけがあったのでしょうか。
石田雄亮:
5年ほど前、私と同じように厳しい状況で事業を承継した同世代の経営者仲間との出会いが大きな転機となりました。「会社が潰れたら元も子もない」と本音で語り合う中で、旧来の“売上こそ正義”という価値観の呪縛から解き放たれたのです。彼らがいなければ、売上規模ではなく、いかにして利益を生み出すかという本質的な視点に切り替えることはできなかったでしょう。
この覚悟のもと、父の代まで続いた「売上何十億」という規模を追求する経営を180度転換し、「売上は追わなくていい」と社内に宣言しました。利益なき拡大路線と決別し、損失を覚悟で不良在庫の処分を断行したのです。
ーー守りの改革と同時に、会社の土台を安定させるための攻めの一手はありましたか?
石田雄亮:
着物事業だけで収益を安定させるのは、市場環境を考えても極めて困難だと判断しました。そこで、全く別の収益の柱を立てることを決意します。幸い地価が上昇していたタイミングを捉え、保有していた東京の店舗を売却。その資金を元手に、この本社ビルを改装してテナントとして貸し出す不動産事業を開始し、何があっても会社が揺らがないための安定したキャッシュフローの基盤を築きました。
伝統と変革の狭間で探る、主力事業の新たな活路

ーー安定した収益基盤を築かれた上で、着物事業は現在どのように展開されているのでしょうか。
石田雄亮:
かつての中国工場への依存体制からは完全に脱却し、現在は自社に導入したインクジェット捺染機での着物製造が事業の核となっています。この最先端の機械を駆使し、主に振袖や訪問着などを製造して、全国の問屋や呉服店様へとお届けしています。
ーー他社にはない石勘ならではの強み、そして乗り越えるべき課題は何だとお考えですか?
石田雄亮:
自社で製造機能を持つことに加え、人通りの多い京都の中心地に拠点を構えている「立地」もまた、他にはない強みだと考えています。しかし、この場所で製造業だけを営んでいては採算が合わないのも事実です。この立地を最大限に活かし、製造業という枠組みにとらわれない新しい事業に挑戦できる可能性こそが、私たちの最大の強みであり、同時に取り組むべき最重要課題だと認識しています。
着物の枠を超えて未来を拓く、BtoC事業と新たな挑戦

ーー会社を立て直した後、次なる成長に向けた新たな挑戦があれば教えてください。
石田雄亮:
今年の春、カフェを併設した新店舗をオープンし、お客様と直接つながるBtoC事業へと舵を切りました。従来の製造卸だけでは限界があるという危機感に加え、大口取引先の倒産という出来事も、社内に変革への機運を生み出しました。さらに、着物の生地が持つ可能性を広げるため、ホテルのクッションを製作するなど、呉服業界以外の分野にも積極的に挑戦しています。
ーー新たにオープンされたカフェ併設の店舗にはどのような思いが込められているのでしょうか
石田雄亮:
一番は、着物が持つ「高価で敷居が高い」というイメージを払拭することです。この店では、お土産感覚で手に取れる1万円以下の羽織から、ご予算に合わせてご提案する「初めての一枚」まで、幅広い商品をご用意しました。お客様一人ひとりと丁寧に対話を重ね、着物の本当の魅力を知っていただくための「入り口」のような場所にしたいと考えています。
ーー伝統と挑戦を両立させる上で、どのような方々と共に未来をつくっていきたいですか?
石田雄亮:
伝統を守り継ぐ意志はもちろん大切ですが、それと同じくらい新しいことに挑戦する情熱を歓迎する社風でありたい。特にこの新店舗では、国内外から多様なお客様がいらっしゃいます。着物への興味はもちろん、たとえば語学力を活かしたい方など、これまで呉服業界にはなかったスキルや視点を持った方々と一緒に、新しい価値を創造していきたいですね。
ーー最後に、石勘株式会社が目指す未来の姿についてお聞かせください。
石田雄亮:
残念ながら、残念ながら、着物業界全体が今後右肩上がりに成長することは考えにくいでしょう。石勘の核である着物製造業は守り続けますが、その事業規模は時代の変化に合わせて柔軟に変えていく必要があります。長期的には、この新店舗を起点として、「シルク」という素材そのものの素晴らしさを、着物という形にとらわれずに世界へ伝え、もう一つの収益の柱として育てていきたい。規模の拡大ではなく、安定性を追求し、伝統を守るために変わり続ける。そんな会社を目指していきます。
編集後記
31歳で突如背負った23億円の負債。その重圧は想像を絶する。しかし、石田社長の言葉からにじみ出るのは悲壮感ではなく、厳しい現実を冷静に見据え、打つべき手を着実に打ってきたという静かな覚悟だ。伝統産業の継承には、旧来の価値観に固執しない、柔軟で多角的な経営戦略が不可欠である。石勘の力強い再建の歩みは、その事実を雄弁に物語っている。京都の街角に灯された新たな光が、着物文化を未来へとつなぐ希望となることを期待したい。

石田雄亮/1985年生まれ、同志社大学商学部卒業。呉服問屋、呉服催事販売の経験を経て、石勘株式会社に入社後、31歳で同社代表取締役社長に就任。2021年に株式会社ながもち屋代表取締役社長兼任。














