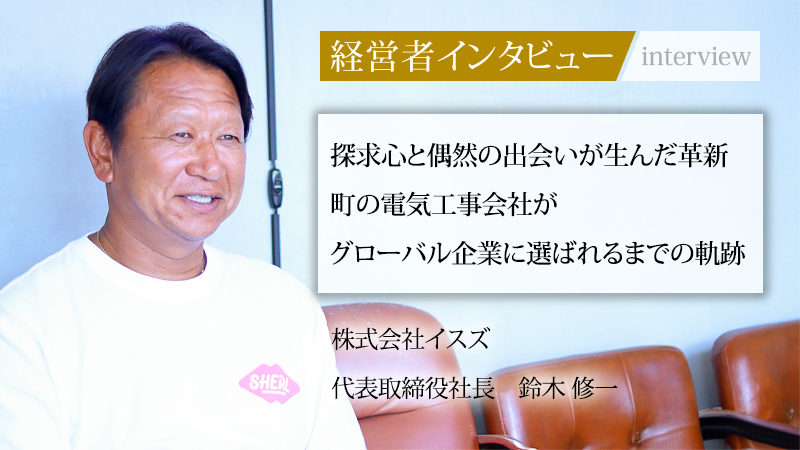
電気工事を基盤とし、神奈川県川崎市で創業以来の歴史を刻む株式会社イスズ。同社は今、太陽光発電や蓄電池といったエネルギーソリューション分野で培った知見を武器に、世界の最先端事業に挑んでいる。業界の常識にとらわれず、優れた技術を持つパートナーとの連携を重視し、新たな価値を創造し続ける。その経営手法は、多くの企業が学ぶべきヒントに満ちている。町の電気工事会社は、いかにして世界的な企業から選ばれる存在となったのか。代表取締役社長の鈴木修一氏にその軌跡と事業哲学を聞いた。
公共工事から太陽光事業への大きな転換
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせください。
鈴木修一:
父が創業した会社を継ぐことを見据え、家業とは別の電気工事会社で社会人としてのキャリアをスタートしました。1年半ほど現場で経験を積みましたが、その会社は途中で退職し、弊社へ入社したのは23歳の時です。
私が入社した当時、弊社は従業員が6人だけの小さな会社でした。事業内容も今ほど多岐にわたってはおらず、主に街灯に関する公共工事を入札で直接請け負う状況でした。
ーー入社後は、どのような役割を担われたのですか。
鈴木修一:
入社後は現場の作業から始めましたが、基本的には営業も兼務していました。当時は工事会社で、専任の営業担当もいなかったため、現会長である父が、営業の役割も担っている状況でした。私はその中で、将来性を見据えて太陽光などエネルギー関連事業の開拓に注力するようになります。
しかし、当時はまだ太陽光発電が社会に浸透していませんでした。昔ながらの訪問販売製品と同じように見られてしまうことも多々あり、本来の価値をご理解いただくのは、非常に難しい時代でした。
ーー事業拡大につながるターニングポイントはありましたか。
鈴木修一:
事業拡大の大きな転機は、オール電化が普及し始めたことです。この波に乗り、従来の工事請負だけでなく、メーカーから商品を仕入れて販売する事業を本格化させました。この戦略が功を奏し、売上は3億円から6億円、そして12億円へと倍々で成長を遂げます。当初の利益率は3%程度でした。しかし扱う量が増えるにつれてメーカーからの仕入れ価格も下がり、利益率が5%、7%と向上していきました。これにより、設計・調達・建設を一貫して担う事業者としての立ち位置を確立するに至ります。
しかし、このような急成長は当然良いことばかりではなく、売上が倍々で増えていく過程で、大量のクレームにも見舞われました。ただ、それもある程度は予測していたことです。そのため私自身が責任者として先頭に立ち、一件一件誠実に向き合いました。この経験は、お金だけの関係ではない取引先の重要性を教えてくれました。弊社の状況を深く理解してくださる、信頼できる会社とだけお付き合いすべきだと痛感しています。最終的に事業を支えるのは、人と人とのつながりだと考えています。
偶然の依頼から生まれた世界最先端のコンサルティング

ーー貴社の主力事業や、その強みについて教えてください。
鈴木修一:
現在は、太陽光発電や蓄電池に関する事業がメインです。これに建築工事が関連してくることもあり、お客様にはワンストップでサービスを提供できるのが強みです。お客様は法人が圧倒的に多く、上場企業などと直接契約を結んでいます。北海道や九州に発電所をつくりに行くこともあります。全国電気工事業工業組合連合会(通称・全日電工連)のネットワークを活用し、全国の仲間たちと協力しながら仕事を進めています。
ーー近年、新たに取り組まれていることはありますか。
鈴木修一:
最近ではデータセンターのコンサルティング事業を始めました。これは、本当に偶然の出会いから始まった事業です。エネルギー関連で電池開発などを手がけていたご縁で、ある方から「電気の申し込みを手伝ってほしい」と頼まれました。その案件が、偶然にもデータセンターでした。これまでに全く手がけたことのない、新しい挑戦です。
データセンターとは、サーバーや通信機器を設置・運用するための専用施設を指します。現代のデジタル社会に不可欠な存在です。特に、NVIDIA社製のGPU(※)に代表されるような高性能サーバーは、稼働に莫大な電力を消費します。そのため、広大な土地があっても電力確保が建設の大きな課題となります。
こうした課題を解決するため、弊社ではデータセンターを建設したい企業に代わって電力会社と交渉し、膨大な電力を確保するコンサルティング業務を手がけています。現在では、クライアントである世界的なトップ企業とも取引があります。これはまさに今、世界で最も活発に資金が動いている市場の一つであり、事業規模も非常に大きいのが特徴です。
(※)GPU:「Graphics Processing Unit(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)」の略称で、画像処理装置のこと。
業界イメージを刷新する異業種連携という独自戦略
ーー事業を展開する上で大切にされている考え方はありますか。
鈴木修一:
「面白いと思ったら挑戦する」というのが信条です。そして、仕事を取りにいくというよりは、根幹となる部分をしっかりと固めることを重視しています。誰でも売れるような商品は、結局は価格競争に陥ってしまいます。目先の利益を追求するのではなく、本質的な価値を提供し続けることが重要です。
ーー現在、力を入れている取り組みはありますか。
鈴木修一:
「堅い」「ダサい」といった業界イメージの払拭は大きな課題です。そこで若い人たちにも魅力を感じてもらうため、カルチャーの発信拠点としてコミュニティ広場「SHERL SHIN-YOKOHAMA」を運営しています。これは、フードコートやスケートボードパークなどを備えた複合施設で、多様な人々が自然と集う“街の公園”のような場所を目指しています。
ここで重視しているのは、単に施設を運営するだけでなく、異業種のトップランナーとの連携です。たとえば、ファッション業界を牽引するセレクトショップ「BEAMS」の現役役員の方や、俳優・アーティストの方々との協業もその一例となります。彼らの感性や影響力を活かし、従来の建設業界の枠に収まらない企画を創出。大手企業では真似のできないような面白い企画を通じて、新しい企業カルチャーを創造していく方針です。
ーー最後に、今後の展望についてお聞かせください。
鈴木修一:
私たちは、これからも先端事業を開発し続ける企業でありたいと考えています。その指針となるのが、企業ロゴにも掲げる「SHERL」というコンセプトです。「SHERL」とは、「Sustainability(持続可能性)」「Health(健康)」「Energy(エネルギー)」「Relationship(絆)」「Life(生活・人生)」という5つの単語の頭文字から成り、弊社の事業が目指すべき方向性を示す言葉です。
具体的には、現在取り組んでいるデータセンターや蓄電池の事業のように、5つの要素に関わる事業の根幹をしっかりと押さえることが最も重要です。社会にとって不可欠なこれらの分野で、常に新しい価値を提供し続けること。それが私たちの目指す未来です。
編集後記
町の電気工事会社が、なぜグローバルなデータセンター開発の最前線で戦えるのか。その答えは、鈴木氏の「面白いことをやる」という純粋な探求心と、自社のリソースに固執せず、最適なパートナーと柔軟に連携する卓越した戦略にあった。長年の経験で培った技術力という揺るぎない土台の上に、業界の垣根を越えたカルチャーを融合させ、新たな価値を創造し続ける株式会社イスズ。同社の挑戦は、伝統的な産業に身を置く多くのビジネスパーソンにとって、未来を切り拓くための大きなヒントとなるに違いない。

鈴木修一/1975年神奈川県生まれ、神奈川県立工業高校卒。電気工事会社に入社し、1年半の修業期間を経て1998年に株式会社イスズへ入社。2016年に同社代表取締役社長に就任。地域コミュニティの活性化や太陽光発電によるSDGsへの取り組みにも注力している。














