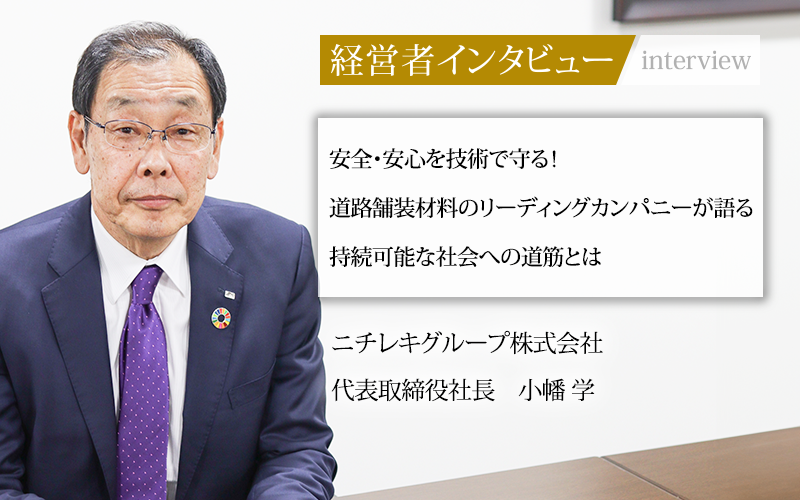
アスファルト乳剤や改質アスファルトにおいて国内トップレベルのシェアを誇り、環境に配慮した舗装技術で社会インフラを支えるニチレキグループ株式会社。同社は主に道路舗装の調査・診断から補修方法の設計・提案、材料の製造・販売から工事の施工・管理まで一貫したサービスを提供し、安全・安心な道路インフラを実現する技術開発に注力している。「種播き精神」という基本理念のもと、国内外の道づくりに挑む同社の代表取締役社長、小幡学氏に話をうかがった。
首都高の夜景に導かれ、土木技術者の道を選んだ
ーー貴社に入社した経緯を教えてください。
小幡学:
私はもともと医者を志し勉強に励んでいましたが、あるとき土木関係の仕事に就いていた父との子どものころの思い出が鮮明によみがえったのです。
私が小学生のころは、ちょうど首都高速道路が完成した時期で、父が「夜、高速道路にドライブに行ってみるか」と誘ってくれました。高速道路の上から見る景色は本当に美しかったのです。その景色を見て「道路づくりは楽しいかもしれない」と感じたことを思い出し、土木技術者の仕事を志望するようになりました。こうした経緯から、大学では舗装の研究室に所属し、卒業後は弊社に入社しました。
ーー入社後、特に印象に残っている経験をお聞かせください。
小幡学:
入社後、静岡営業所へ配属されたことが私の技術営業としての原点です。静岡県は東海道(国道1号線)や東名高速道路などが通る交通の要所であり、富士山があることから防災意識が高く、地震対策にも力を入れている地域でした。お客様から「災害時でも住民が避難できる強い道路が必要だ」という声を聞き、それに応える技術開発に取り組みました。今から40年以上前のことですが、この経験がなければ、材料開発や工法開発への情熱は生まれなかったでしょう。各地域の課題解決が私の仕事の原動力になったと感じています。
ーー技術開発ではどのようなことに一番苦労されましたか?
小幡学:
私が技術開発で最も苦労したのは、橋梁舗装の技術開発です。当時、橋の舗装は梅雨の時期に早期に破損するという問題を抱えていました。原因究明のため現場に入り、破損した箇所をすべて掘り起こして調査してみると、「剥離」と呼ばれる現象が起きており、水分の影響でアスファルトの強度が弱まっていることが分かったのです。
そこで、解決策として水分に強いアスファルトの開発と、水が溜まらないようにする排水システムの構築に取り組みました。たくさんの試作品をつくり、あらゆる条件下でテストを繰り返した結果、問題を解決する技術を開発でき、お客様に喜んでいただくことができました。この技術は現在、日本の橋梁舗装の多くに使われています。この技術開発がなければ、今日の弊社の発展はなかったかもしれませんね。
前社長の言葉を胸に、誰もが自由に活躍できる組織へ

ーー社長に就任されたときのお考えを教えてください。
小幡学:
2015年に社長に就任した際、前社長から「自由にやってくれ。それと、社員が自由に仕事をできるようにサポートしてほしい」という言葉をいただきました。私自身も、もともと奔放な性格なので、この言葉に強く共感したことを覚えています。「皆が自由に活動できる環境をつくります」と約束し、以来この言葉を経営の中心に据えてきました。
社長就任後は、特に社内のコミュニケーション環境の改善に注力しました。個室や仕切りなどを減らし、なるべく大部屋を使うようにして、大勢が同じ空間で働ける環境を整えたのです。そして、共通の課題に対して誰もが「それはまずいんじゃないか」「こうした方がいいんじゃないか」など、自由に意見交換できる雰囲気をつくっていきました。このような環境が定着したことで、会社全体の創造性も高まったと感じています。ときには若手社員の意見から新しい発想を得ることもあり、そんな風に自由に意見を出し合える環境こそが、私の目指す会社の姿なのです。
ーー組織づくりでは、どのようなことを大切にしていますか?
小幡学:
私は「スピード感」を非常に重視しています。以前は新しいアイデアが出ても実行するまでに時間がかかっていましたが、現在は「やってみよう」という姿勢を優先し、迅速に実行するよう促しています。失敗を恐れず、まずは試してみる姿勢を取ることで、組織全体の動きが格段に速くなりました。
また、マネジメントスタイルとしては、詳細な指示を出すのではなく、社員の自主性を尊重する姿勢を心がけています。社員から新たな提案があれば「それはいいね、やってみよう」と背中を押すことで、チャレンジ精神を育てています。統率がとれるかどうか最初は不安もありましたが、この姿勢のおかげで新しいアイデアを具現化しやすい組織風土を醸成することができました。
人々の暮らしを足元から支える、環境配慮に根差した事業展開
ーー貴社の主な事業内容を教えてください。
小幡学:
弊社は道路舗装のプロフェッショナル集団として、調査・診断から補修方法の設計・提案、材料の製造・販売から工事の施工・管理まで一貫したサービスを提供しています。弊社の仕事は縁の下の力持ちのようなもので、普段は意識されませんが、安全・安心な生活や経済を支える重要な役割を担っているのです。
事業の主な柱は2つあり、1つ目の柱はアスファルト乳剤や改質アスファルトといった舗装材料の開発・製造です。これは弊社の創業以来の中核事業で、国内トップレベルのシェアを誇っています。通常のアスファルトは高温で溶かしてから使いますが、アスファルト乳剤は、熱を加えず常温で施工できるため、カーボンニュートラルにも貢献できる環境配慮型の製品となっています。
2つ目の柱は、これらの技術を活かした工法開発と高品質な施工です。たとえば、環境に配慮した「スタビセメントRC工法」は、破損した舗装を現場で破砕して地震に強く強靭な舗装を再構築する工法で、産業廃棄物の削減と国土強靭化に貢献しています。既存の舗装をすべて撤去して新たに舗装する打ち替え工法と比較すると、工期の短縮も図れるため、交通渋滞による経済損失の軽減や、CO2排出量の抑制も同時に実現しています。
さらに、この2つの柱を支える事業として、舗装の調査・診断技術の提供があります。舗装は使用とともに劣化するため、定期的な点検が欠かせません。そこで、弊社では「smartロメンキャッチャーLY Jr.」を始めとした専用車両を使った高精度な点検や、東京大学および株式会社スマートシティ技術研究所と共同開発した「GLOCAL-EYEZ(グローカルアイズ)」というシステムを提供しています。
この「GLOCAL-EYEZ」というシステムは、スマートフォンがあれば、舗装のわだち掘れやひび割れなどを簡単に点検できるという画期的なものです。AI技術も活用しており、従来のシステムでは舗装の状態を解析する作業に1ヶ月ほど時間を要することが課題でしたが、わずか1時間程度で完了するようになりました。
基本理念に込められた思いが未来の道を切り拓く

ーー「種播き精神」という基本理念にはどのような思いが込められているのでしょうか?
小幡学:
「種播き精神」という基本理念は、創業者である池田英一が掲げた言葉で、「たとえ自分自身が収穫できなくても、次世代のために一生懸命種を播き、土壌を整えていく」という思いを表したものです。自分が収穫できるかどうかではなく、将来誰かの役に立つことを今始めよう、という考え方ですね。
私にとってこの基本理念は非常に重要で、自身の入社試験の面接では「この基本理念がなければ、私は面接に来ていません」と言ったほどです。当時の面接官は「生意気な奴だ」と思ったそうですが、私はこの言葉こそが本当の社会貢献だと心から感じました。
今でも弊社の朝礼では、社員が当番制でこの基本理念を唱和しています。この言葉は単なるスローガンではなく、私たち1人ひとりの行動指針となっているのです。
弊社の技術開発もこの基本理念に支えられています。道路舗装の技術開発は一朝一夕では成果が出ず、先ほど申し上げた橋の舗装技術も、多くの試行錯誤を経て完成しています。現在でこそ多くの人に評価されていますが、開発当初は成功するかどうか誰にも分かりませんでした。それでも研究を続けたのは、まさに「種播き精神」があったからです。この基本理念があるからこそ、短期的な成果にとらわれず、10年、20年先を見据えた技術開発に挑戦できる企業文化が育まれているのだと思います。
「モノ」と「ヒト」への投資で広がる、社会貢献の舞台
ーー未来の成長に向けて、どのような取り組みを行っていますか?
小幡学:
未来への投資は「モノ」と「ヒト」の両面から進めています。「モノ」の代表が茨城県つくばみらい市に建設中の「つくばビッグシップ」という環境配慮型生産・物流基地です。この名前は、土地の形が船に似ていることから名づけました。
約11万平米の広大な敷地に、舗装分野においては世界に類を見ない規模と機能を持つ拠点として、2026年度上期までには事務所棟や工場建屋等を竣工させ、2027年度には新しい工場の稼働開始を目指しています。これは単なる生産拠点ではなく、情報センターとしての機能も持たせ、舗装の点検データを集約・分析し、最適な手法を提案するための拠点としても運用していく予定です。
「ヒト」への投資としては、技術者の育成に力を入れており、技術者の博士号取得支援など教育制度を充実させるとともに、海外出身の方の積極的な採用も進めているところです。現在はインド、中国、台湾、マレーシアなど、さまざまな国籍の社員が活躍しており、彼らの多様な視点が新たな技術革新につながっていると感じています。
さらに、年齢に関わらず優れた人材を採用する方針もとっており、定年退職後も活躍できる場を提供しています。特に年齢を重ねたベテラン社員たちが持つ豊富な経験と知識は、若手社員にとって大きな学びとなります。このように多様な背景を持つ人材が集まり、自由に意見を出し合うことで、より革新的な技術開発が可能になると考えています。
ーー今後の展望についてお聞かせください。
小幡学:
私は、今後も道路の社会的役割は変わらないと確信しています。なぜなら、いくら技術が進化しても、人や物が移動するには安全な道路が不可欠だと考えているからです。
そんな中、特に注目しているのが、モビリティの変化です。電気自動車は従来の車両と比べて1.2〜1.5倍の重量があり、舗装への負担が大きくなります。さらに自動運転技術が進歩すると、車両は同じ位置を規則正しく走行するため、特定の箇所に負荷が集中することとなるでしょう。現在はカーボンニュートラルへの貢献として、環境配慮型の製品・工法の開発を強化していますが、こうしたモビリティの変化に耐えられる舗装の技術開発は急務だと考えています。
また、国内の道路インフラ整備を最優先としながらも、海外展開も積極的に進めています。すでに中国市場では現地企業と協力関係を構築しており、最近ではインドに合弁会社を設立しました。これからもさまざまな取り組みを通じて、世界中の人々が安心して道路を利用できるよう、取り組んでまいります。
編集後記
創業以来、現場の課題解決を軸に事業を展開してきた姿勢が印象的だった。「種播き精神」という基本理念を体現する自由闊達な企業風土は、同社の技術革新の原動力となっている。私たちの安全な移動を支える道路には、想像以上の技術と創意工夫が込められていることを知った。環境にも配慮しつつ、社会貢献を目指す同社の取り組みは、今後も安心できる社会を人々に提供してくれるに違いない。

小幡学/日本大学 理工学部 土木工学科卒業。大学卒業後、日瀝化学工業株式会社(現:ニチレキグループ株式会社)に入社。技術営業として静岡営業所長、中部支店長などを経て、執行役員東京エリアマネージャー、取締役常務執行役員 事業本部長などを歴任。2015年、同社代表取締役社長に就任。2022年、東北大学大学院 工学研究科 インフラ・マネジメント研究センターと共同で、同研究科に「インフラマネジメント“足すテナビリティ”共同研究部門」を開設し、特任教授に就任。














