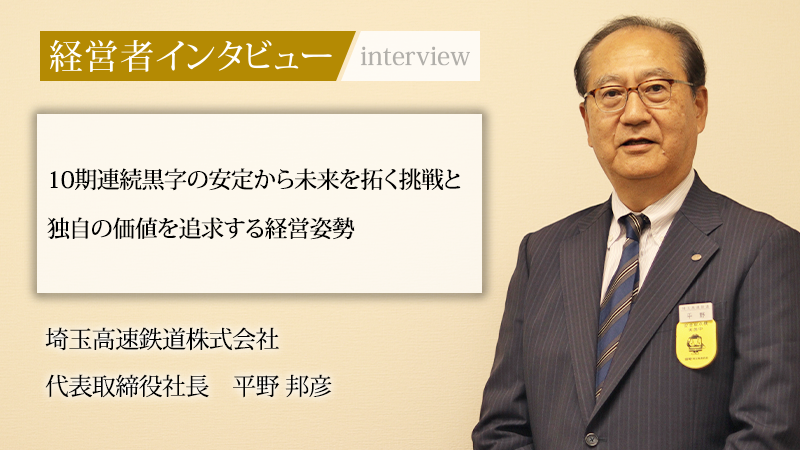
東京都心と埼玉県を結び、地域の足として重要な役割を担う埼玉高速鉄道株式会社。同社は、「埼玉スタジアム2002」へのアクセス路線でもあり、「SR」の愛称で地域に密着した強固な関係性を築く。2024年に代表取締役社長へ就任した平野邦彦氏は、土木技術者としてキャリアを始め、国鉄・JRで大型開発事業を歴任した多様な経験を持つ人物だ。社長就任後、社の変革期を牽引し、常に新しい可能性に挑み続ける平野氏に、その歩みや会社の現状と未来、そして次代を担う若者への思いを聞いた。
現場経験と金融の知見 2つの異なる世界で培った多角的な視点
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせいただけますか。
平野邦彦:
大学では土木を専攻しており、全国規模で社会の役に立つ鉄道の仕事に大きな魅力を感じ、技術者として国鉄に入社しました。当初は駅の工事の施工管理などを担当し、青函トンネルの建設にも携わりました。
その後、分割民営化により東日本旅客鉄道(JR東日本)になってからは、開発事業という新しい分野に移りました。民鉄各社が行っているような不動産開発をJR東日本としても本格化させる流れの中で、駅ビルなどの大規模な開発に長く携わったのです。その後は住宅事業やスポーツ施設の運営、東京駅商業施設「グランスタ」の活性化に向けた企画・運営を手がけるなど、さまざまな経験を積みました。
ーーキャリアにおける大きな転換点はありましたか。
平野邦彦:
JR東日本になってすぐ、信託銀行へ2年間出向した経験は非常に大きかったです。それまでヘルメットをかぶって現場監督をしていた私が、いきなり金融の最前線で働くことになりました。そこで初めて「民間のマインド」を肌で感じたのです。ユーザー目線で勝敗を分けるものは何か、マーケットをどう捉えるべきか。現場の技術者だった私にとって、この時に培われた民間の視点は、その後のキャリアの大きな財産となりました。
また、これまでに全く知らない組織へ一人で飛び込む経験を何度かしました。そうした環境でチームワークの大切さを知り、視点が変わり、物事を多角的に捉えられるようになります。担当する分野は違っても、結局は「物事をどうやってやり抜くか」という本質は同じです。それぞれの場所で得た多様な経験が、今の自分を形成していると考えています。
10期連続黒字からの再出発 独自の価値を追求する新たな挑戦
ーー社長就任当時、会社にどのような印象を持ちましたか。
平野邦彦:
2024年6月に私が就任したとき、2015年に事業再生ADRが成立し、その後会社は9期連続の黒字を達成しており、経営基盤は非常に安定していました(現在は10期連続の黒字を達成)。かつては経営が苦しい時代もあったと聞いています。そこから立て直した社員たちの安全・安定輸送や経費削減などの努力は素晴らしいものです。
一方で、その安定に甘んじることなく、社員のマインドをもう一段階引き上げる必要があると感じました。「もっと積極的に考え、さまざまなことに挑戦しなければ、未来はない」と考えたのです。
ーー社長として最初に取り組まれたことは何でしたか。
平野邦彦:
先述のとおり、経営基盤は安定していました。しかしその一方で、長きにわたる経営再生期間の経費節減により、事務所や駅の設備の老朽化が目につくようになったのです。そこでまず着手したのが、開業から25年近くが経過した諸設備の効率的な更新です。会社の足元を見つめ直すことから始めました。
また、弊社は他の大手民鉄各社と比べるとコンパクトな組織であり、新しい取り組みを行うための資金力やノウハウにも限りがあります。そこで、相互直通運転という強みを活かし、他の鉄道会社との連携も積極的に進めています。車両整備での協力や短期研修プログラムへの参加などを通じて、さまざまな知見を吸収しようと努めています。
加えて、今期からを「経営成長・発展期」と位置づけ、その実現のために組織を改革し、これまでなかった「企画部」や「地域共創課」を新設し、若手社員も抜擢しました。部署横断的なテーマ、地域の発展に資するテーマや長期的な経営課題に取り組む体制を整えたのです。
働き方や給与制度の見直しも含め、多角的に会社を変革し、社員がワクワクしながら働ける環境をつくることが、社員一人ひとりそして会社の成長につながると信じています。
ーー貴社を「SR」と表現されていますが、その背景についてお聞かせください。
平野邦彦:
SRは、そもそも埼玉高速鉄道の英語の略称ですが、「S」はSmall(小さい)、「R」はResponse(対応)だと私は捉えています。路線は14.6kmと短いですが、小さいからこそ意思決定が速く、小回りが利く。これが弊社の強みです。大手にはできない、弊社だからこそ提供できる独自の価値を追求し、きらりと光るような会社にしていきたいと考えています。
沿線地域との強固な信頼関係と実現を目指す未来の鉄道網

ーー貴社の強みや、地域との関わりについてお聞かせください。
平野邦彦:
弊社の強みは、沿線地域との関係性が非常に良好であることです。官民共同出資の第三セクターとして、地域に密着した取り組みを推進しており、高い安全性を維持している点は誇りです。この首都圏にある沿線は「都会田舎」とも言われ、都会に近い利便性と豊かな自然が共存する魅力的なエリアです。このポテンシャルを最大限に活かし、沿線をさらに活性化させていくことが大きなテーマです。
ーー今後の路線の延伸計画についておうかがいできますか。
平野邦彦:
浦和美園駅から岩槻駅までの7.2kmを結ぶ延伸計画は、地元の皆様の悲願です。これは、埼玉スタジアム駅と中間駅を含む計3駅を新設する計画で、現在、埼玉県、さいたま市、施工を担い保有する鉄道・運輸機構、そして弊社(鉄道事業者)という4者で事業化に向けた検討が本格的に進んでいます。採算性を示す費用便益比(B/C)も事業性が成立する水準にあり、実現への方向性は見えてきました。
この延伸が実現すれば、東武アーバンパークライン岩槻駅と接続されます。これにより、鉄道網の「ミッシングリンク(繋がりの欠如)」が解消されます。鉄道空白地域の解消や、災害時等の代替路線としての機能充実にもつながり、地域の利便性は飛躍的に向上するのです。
将来的には弊社線と直通運転している東京メトロ南北線が品川駅まで延伸され、リニア中央新幹線にもつながります。中間駅には、新しい街が生まれ、埼玉スタジアムへのアクセスも格段に向上するなど、延伸は計り知れない可能性を秘めているのです。
成長し続けるための普遍的な原則は「思い 学び 対話」
ーー今後の人材の採用や育成について、どのようにお考えですか。
平野邦彦:
過去に採用を絞っていた時期があり、人的な構成に課題があるのは事実で、特に鉄道を支える技術者の採用は急務です。また、社員一人ひとりのスキルをいかに伸ばしていくかも重要なテーマだと考えています。だからこそ、鉄道事業の根幹である安全を第一に考えつつも、現状に満足せず、前向きに新しいことに挑戦してくれる意欲のある人材を求めています。
ーー若者たちが活躍するために、最も重要なことは何だと思われますか。
平野邦彦:
「強い思いを持つこと」だと考えます。「これをやりたい」という強い思いがあれば、どんな困難も乗り越えられます。思いがあれば、どうすれば実現できるか試行錯誤する。たとえ失敗しても、それは未来への糧になります。
そして、分からないことは躊躇せずに聞くこと。学ぶ姿勢があれば、誰もが助けてくれます。上司や同僚とキャッチボールをするような対話は、信頼関係を築き、自身のネットワークを広げる上で非常に重要です。強い思いを持ち、学び、対話すること。そしてやり遂げる。人生は、その繰り返しなのだと思います。
編集後記
土木技術者から開発事業、そして経営のトップへ。平野氏の多様なキャリアは、物事を多角的に捉える「視点」の重要性を物語る。その経験に裏打ちされた言葉には、現状維持を良しとせず、常に新しい価値を求める強い意志がみなぎっていた。今期を「経営成長・発展期」と位置づけ、社内変革のアクセルを踏む同氏の目は、会社の未来、沿線の未来、さらには次代を担う若者たちの未来までも見据えている。その挑戦が、地域社会に新たな輝きをもたらす日は、そう遠くないだろう。

平野邦彦/1955年2月生まれ。1980年、日本国有鉄道に入社。1987年、分割民営化により、東日本旅客鉄道株式会社に入社。以降、横浜支社長、常務執行役員 総合企画本部副本部長などを歴任。同社では高輪ゲートウェイ駅や渋谷駅など、大型ターミナル周辺の大規模開発に多く携わる。その後、株式会社鉄道会館にて代表取締役社長、独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長代理に就任。2024年6月から埼玉高速鉄道株式会社代表取締役社長に就任。














