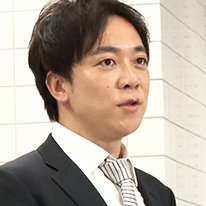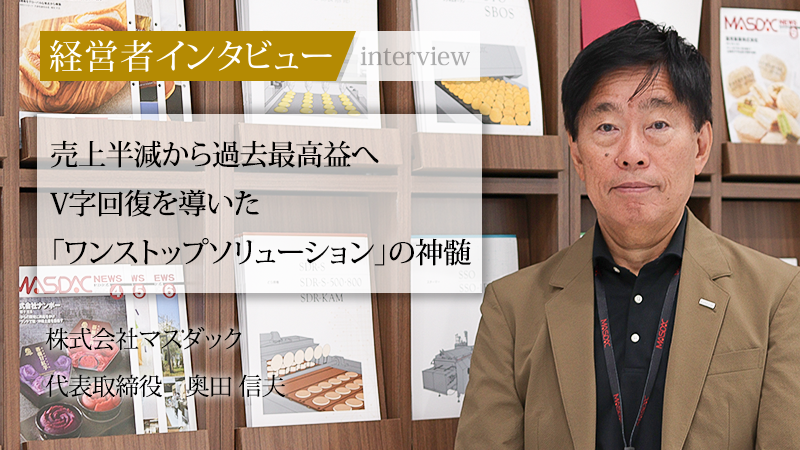
菓子の受託製造(OEM)と、その製造機械の開発・販売という2つの事業を両輪で展開する株式会社マスダック。株式会社グレープストーンが販売する「東京ばな奈(株式会社グレープストーンの登録商標)」をはじめ、数々のヒット商品の裏側を支えてきた同社は、菓子開発から設備開発、製造までを一貫して支援する「ワンストップソリューション」を最大の強みとする。コロナ禍で売上が半減する危機的状況の中、2020年に特別顧問として入社したのが、パナソニック株式会社で30年のキャリアを積んだ奥田信夫氏である。卓越した経営手腕で業績のV字回復を成し遂げ、会社を再び成長軌道に乗せた同氏に、事業の独自性から経営哲学、そして海外展開を見据えた未来図まで、その情熱の源泉を聞いた。
菓子と機械のプロ集団が生み出す独自の価値
ーー貴社は具体的にどのような事業を展開されているのでしょうか。
奥田信夫:
私たちは、大きく分けて2つの事業を展開しています。1つは、そのお菓子を安定して大量に生産するための「食品機械事業」。もう1つは、皆様がご存知のお菓子そのものをつくる「食品製造事業」です。
世の中には素晴らしいお菓子メーカーや、高性能な機械メーカーは数多くありますが、私たちのように、その両方を高い専門性を持って手掛けている企業は非常に稀です。この2つの事業を有機的に結びつけ、お客様をトータルでサポートできるのが私たちの最大の強みであり、これを「ワンストップソリューション」と呼んでいます。
たとえば、お客様の「こんなお菓子をつくりたい」という情熱やアイデアを起点に、私たちがレシピ開発からご一緒し、そのお菓子専用の製造機械を設計・開発し、最終的には私たちの工場で量産を引き受けることまで可能です。単なる機械メーカーでも、OEM工場でもない。「菓子と機械のプロフェッショナル集団」として、お客様の夢の実現をあらゆる角度から支援する。それがマスダックという会社です。
ーー「ワンストップソリューション」は、どのようなお考えや哲学から生まれたものなのでしょうか。
奥田信夫:
私たちは単なる「製造業者」ではなく、お客様の夢を共に実現する「パートナー」でありたいと常に考えています。なぜなら、私たちの事業の原点は機械ではなく、常にお客様の「こんなお菓子をつくりたい」という“情熱”にあるからです。その熱い思いに、私たちの技術力で応えたいのです。
「東京ばな奈」で言えば、メーカー・ブランドオーナーである株式会社グレープストーン様の「これまでにない東京土産をつくりたい」という強い思いがすべての始まりでした。企画段階から試作品づくりを何度も重ねて、実際のバナナのような曲がりのある形状が出来上がったというような苦労話が沢山あります。
しかし、考えてみてください。あの柔らかいスポンジケーキを美しいカーブ形状で、しかもクリームを注入しながら寸分の狂いもなく量産するのは、並大抵の技術ではありません。ですが、その「無理かもしれない」と思われる挑戦に、金型技術や製造ノウハウのすべてを注ぎ込んで応えることこそ、私たちの存在価値なのです。お客様の情熱と私たちの技術がまさしく一体となったからこそ、あの商品は世に出ることができた。
パートナー様からいただく「マスダックがいなければ生まれなかった」というお言葉は、私たちにとって最高の栄誉であり、この事業の根幹を象徴するものだと受け止めています。
V字回復を導いた経営哲学「強くて良い会社」とは

ーー奥田社長は、どのような経緯で社長に就任されたのでしょうか?
奥田信夫:
パナソニックでは一貫してBtoBの事業、特に電子部品をプリント基板に実装する機械の事業に携わっていました。その後、いくつかの企業を経験し、2020年10月にマスダックに入社しました。当時の増田社長(現会長)からは、「企業改革と経営人財育成」をミッションとして頂きました。マスダックはコロナ禍の影響を真正面から受け、業績が絶不調の時期でした。観光土産菓子の売上が蒸発し、それに伴い機械事業も落ち込み、売上はコロナ前の約130億円から半分以下の60億円台にまで減少。会社は赤字に陥っていました。
ーーその厳しい状況から、どのように会社を立て直されたのでしょうか。
奥田信夫:
就任後、すぐに全社的な経営改革プロジェクトを立ち上げました。改革は3つのステージに分けて進めました。第1ステージは「WM 2021 PJ(ホワイトマスダック2021)」。これは危機的な赤字状態から脱却し、必ず黒字を達成する(白字に戻す)という強い思いを込めたプロジェクトで、危機的状況からの脱出と経営の足腰の強化に全力を注ぎました。おかげさまで2021年には黒字化を達成できました。第2ステージは「GM 2025 PJ(グローイングマスダック2025)」として、成長戦略の策定と実行フェーズに移行しました。そして第3ステージとして、2023年には事業会社を統合し「M-1 PJ」体制を構築。これにより、機械事業と菓子事業のシナジーを最大化し、圧倒的な競争優位性を確立するための基盤を固めました。これらの改革を経て、2024年度には売上高、経常利益ともに過去最高を更新することができました。
ーー経営者として最も大切にされている価値観や哲学についてお聞かせください。
奥田信夫:
パナソニック時代の上司であり、当時のドメインカンパニー(社内分社)社長であったK氏から教わった「強くて良い会社をつくる」という言葉が、私の経営における最上位の価値観です。「良い会社」とは、社員やその家族、お客様はじめ関係お取引先様、株主様、社会といったすべてのステークホルダーにとってかけがえのない存在であり続けることです。そして、それを実現するためには、しっかりと収益を上げ、事業を継続させていく「強さ」が不可欠です。つまり、「良い会社」であるためには「強い会社」でなければならない。この考え方は、事業部のトップを任されていた頃から今まで、変わることなく私の根幹にあります。
お菓子業界の魅力とマスダックが持つ無限の可能性
ーー数ある企業の中から、当時苦境にあったマスダックへの参画を決意された理由は何だったのでしょうか。
奥田信夫:
お菓子が持つ力に魅了されたからです。おいしいお菓子を食べて怒り出す人は世界中どこにもいません。誰もが笑顔になる。こんなにも人を幸せにできる素晴らしい業界があるのかと、初めてマスダックという会社に触れたときに強く感じました。私がこれまで身を置いてきたエレクトロニクス産業は、どちらかと言うと、求める製品機能を実現させることが第一で、そこに笑顔が介在する余地はあまりありませんでした。しかし、お菓子業界は「笑顔と幸せをお届けする」という言葉がそのまま当てはまる。この業界のリーディングカンパニーであるマスダックが、コロナという一過性の要因で苦しんでいる。これは私にとって、非常に大きな挑戦の機会だと感じました。
ーーコロナ禍という逆風の中でも、会社の成長性を確信されていたのですね。
奥田信夫:
はい、間違いなく成長できると感じていました。コロナ禍によって、職人技に頼った手作業での生産体制が持つ衛生面でのリスクや、人手不足といった課題が一気に顕在化しました。つまり、“機械化・自動化”へのニーズは確実に高まります。そして、人間が生きていく上で“食”がなくなることは絶対にありません。“自動化”と“食”の交差点にマスダックはいる。ここに成長性がないわけがないのです。社員たちは未曽有の危機的状況に戸惑っている雰囲気でしたが、私はワクワクしていました。順風満帆な会社に私は呼ばれません。苦境にあるからこそ、私の経験が活かせると考えました。
会社の未来を創る「3P人材」と育成への情熱
ーー社長に就任後は、何から着手されたのでしょうか。
奥田信夫:
まず、現場の生の声を聞くことから始めました。トップが現状を正しく認識しなければ、正しい改革はできませんからね。そこで約2ヶ月かけて、50名の幹部・幹部候補と一人ひとり個別に対話する時間を作ったのです。
目的は2つありました。ひとつは、彼らが肌で感じている会社の課題や問題点を洗い出すこと。そしてもうひとつは、この会社の未来を託せるリーダーは誰か、その人物を見極めることでした。
私の信念として、「計画をつくる人間」と「実行する人間」は同じでなければなりません。そうでなければ本当の意味での当事者意識は生まれない。自らが立案に関わった計画だからこそ、人は「絶対にやり遂げよう」と本気になれる。ですから、まず改革の核となるチームを見つけることが、最初の仕事だったのです。
ーーリーダーとなる人材を見極める上で、どのような点を重視されていますか。
奥田信夫:
私がリーダーに求める資質は、シンプルに「3P」という言葉で整理しています。 1つ目のPは「Productive(生産的)」。常に物事を建設的に捉え、どうすれば前に進められるかを考えられる力。 2つ目のPは「Proactive(主体的)」。指示待ちではなく、自らが会社の課題を自分事として捉え、行動を起こせる力。 そして3つ目のPが「Professional(専門性)」です。「この分野なら誰にも負けない」と胸を張れる専門性を持っていてほしい。
そして、こうした3Pを兼ね備えた人材、あるいはそのポテンシャルを持つ人材をさらに引き上げていくことが、今の私の重要なミッションです。そのために現在、外部の専門家に伴走してもらって「経営人材育成塾」という次世代リーダー育成プログラムを走らせています。
「5-20-100の法則」というのがあるのですが、この次世代リーダー育成取組の目標は、まず全社員の5%にあたる「改革の先頭を走る人材」を育てること。強い意志と戦略実行力を持つリーダーが5%生まれれば、その熱はやがて20%に伝播し、会社全体を変える大きなうねりになる。私はそう確信しています。この塾から、未来のマスダックを担う人材を輩出することに全力を注いでいます。
「はじめに菓子ありき」の精神で世界市場へ挑む
ーー「ワンストップソリューション」という強みを活かし、今後どのような未来を描いていらっしゃいますか。
奥田信夫:
短期的には、2030年度に売上200億円超、2桁の経常利益率を達成することが目標です。その実現のために、3つの戦略骨格を明確にしています。1つ目は、菓子の周辺領域である一般食品にも事業を広げる「Food Manufacturing Service (FMS)」の推進。2つ目は、従来からの機械事業、食品製造事業に加えて、サービスのマネタイズを実現して、「機械・OEM・サービスの三位一体の事業ポートフォリオ」を実現すること。そして3つ目は、海外事業の拡大です。現在は売上の大半が国内ですが、将来的には海外比率を機械事業全体の40%まで高めていきたいと考えています。
ーー海外展開を成功させる上での鍵は何だとお考えですか。
奥田信夫:
“グローカル”、つまりグローバルな視点とローカルな視点の融合です。全体戦略は統一しつつも、現地の文化や嗜好に合わせたローカライズが不可欠です。たとえば、日本で評価の高いレシピをそのままベトナムに持っていっても「甘すぎる」と受け入れられない。現地の食文化を深く理解し、ベトナム人の味覚に合わせたレシピを開発することで、心から「おいしい」と感じてもらえるお菓子を提案することが成功の肝となります。私たちの強みは、この商品開発から支援できることです。まず“おいしいお菓子”でお客様の心を掴む。そこから機械の販売やOEM製造へとつなげていく。この流れは、海外市場でこそ大きな武器になると確信しています。
ーー最後に、本記事の読者であるビジネスパーソンや学生の皆さんにメッセージをお願いします。
奥田信夫:
私たちが何よりも大切にしている、創業者から受け継がれてきた「はじめに菓子ありき」という言葉があります。まさしく今回、お話ししたことすべてに通じるのですが、「こんなお菓子をつくりたい」「このお菓子で事業をしたい」というお客様の思いがなければ、私たちの機械事業もOEM事業も成り立ちません。すべては「お菓子」から始まるのです。この原点を、私たちはこれからも大切にしていきます。お菓子が好きな方、そして笑顔と幸せを届ける事業に興味がある方は、ぜひマスダックという会社に注目してください。皆さんの期待に、きっと応えられると思います。
編集後記
「はじめに菓子ありき」。この創業者の言葉は、株式会社マスダックの事業の本質を見事に捉えている。高度な製造技術やグローバルな事業戦略も、すべては「おいしいお菓子を届けたい」という純粋な思いから出発しているのだ。パナソニックで磨かれた経営手腕と、お菓子がもたらす笑顔への温かいまなざし。その両方を併せ持つ奥田社長のリーダーシップのもと、同社は国内市場での確固たる地位を築くだけでなく、世界の食文化に新たな彩りを加えていくに違いない。同社の今後の展開を、引き続き注視していきたい。

奥田信夫/1958年熊本県生まれ、九州大学卒。松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)に入社し、約30年FA・電子部品を中心にBtoB事業一筋で勤務。米系含む中堅企業3社で経営責任者を歴任後、コロナ禍真っ盛りの2020年10月に「マスダックの経営改革と経営人材育成」を使命に株式会社マスダックへ入社。2022年6月に同社代表取締役社長に就任。以来、成長戦略をハンズオンで牽引し4期連続増収増益を達成。さらなる事業成長へ挑戦中。