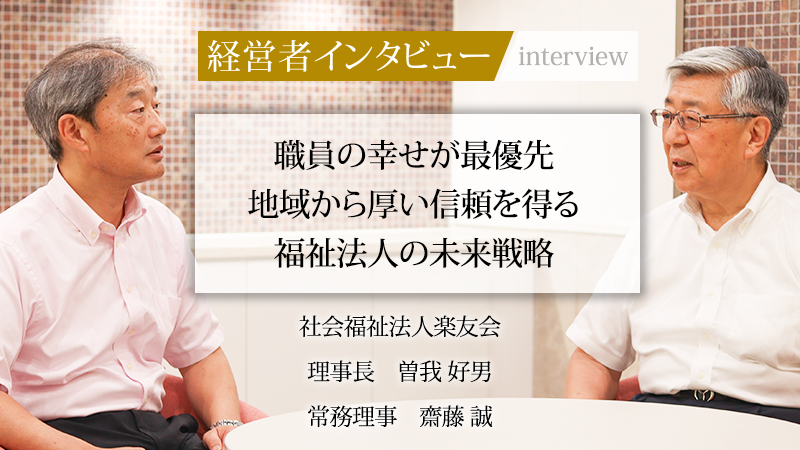
東京都多摩市に根差し、地域住民の暮らしを支える社会福祉法人楽友会。行政官として街づくりに貢献してきた理事長の曽我好男氏と、民間企業から福祉の世界へ転身した常務理事の齋藤誠氏。異なる経歴を持つ二人が率いる同法人の最大の財産は「人」である。地域からの厚い信頼と、職員一人ひとりが主役となる組織文化を育み、コロナ禍を乗り越えてきた。福祉の未来を見据え、職員の幸せを第一に考える情熱と、その取り組みの核心に迫る。
行政と民間 異なる道から福祉の世界へ
ーー曽我理事長のこれまでのご経歴についてお聞かせください。
曽我好男:
私は多摩市の職員として36年間勤務しました。キャリアの最初は福祉関係の部署でしたが、その後は財政や企画といった部門での経験が長かったです。部長職になってからは健康福祉部長として再び福祉の現場に戻り、最終的に総務部長を経験しました。定年退職後は大学で教鞭を執るなどした後、ご縁があって弊法人の理事長に2020年に就任した次第です。
行政、特に企画財政や総務での経験は、財務や中期計画の策定、人事制度を考える上で大いに役立っています。その一方で、公務員の世界とは異なる厳しさに触れることもありました。もちろん公務員の仕事が決して楽というわけではありません。しかし、こちらに来て、民間の法人が持つ特有の経営環境や給与体系の違いなどを実感しています。
ーー齋藤常務理事はどのようなきっかけで福祉の世界へ入られたのでしょうか。
齋藤誠:
当時の社会経済の大きな変化が、キャリアを見つめ直す一つの転機となりました。正直なところ、当初から福祉の道を強く志していたわけではありません。しかし、実際にこの業界へ足を踏み入れてみると、変えるべき古い体質がまだ残っていると感じました。そこから、一般企業での経験を活かして変革したいという思いが次第に強くなっていきました。
ーー楽友会に中途採用後1年で管理職に抜擢されましたが、特に意識されたことはありますか。
齋藤誠:
「発言すること」を常に意識してきました。当たり前だと思うことでも、それを言葉や文字にしてきちんと伝える。そうした姿勢で業務改善や組織づくりに積極的に関わってきたことが、早い段階で管理職への道を開き、今の立場につながっていると感じています。
楽友会らしさの源泉 地域からの信頼と職員が主役の文化

ーーお二人が考える、貴法人の最大の強みや「らしさ」とは何でしょうか。
曽我好男:
地域からの評判が良いこと、これに尽きると思います。「楽友会はいいね」という声を直接耳にする機会が少なくありません。これは、職員一人ひとりがご利用者に真摯に寄り添う姿勢が、地域全体に信頼として広がっている証です。私たちは、地域の福祉における総合的な相談窓口のような役割を担うことを目指しています。何か困りごとがあれば「楽友会に行けば何とかなる」と思っていただける、そんな頼れる存在でありたいと考えています。
齋藤誠:
弊法人の強みは間違いなく「人」です。先日、ご利用者のご家族から、本当に嬉しいお言葉をいただきました。「ここの職員は資質、マナー、笑顔、対応が抜きん出ている。いろんな施設を見てきたからこそ分かる」という内容です。これはマニュアル通りの研修だけで生まれるものではありません。職員たちが自ら考え、ご利用者のためにイベントなどを企画する「手づくり感」と、それを支える組織風土が私たちの「らしさ」です。
ーー若い人材が多く活躍されていますが、採用における工夫について教えてください。
齋藤誠:
新卒採用では、大学や専門学校等から実習生を積極的に受け入れています。さまざまな施設を見る中で目が肥えている学生さんたちに、実習を通して弊法人の雰囲気や働きがいを肌で感じてもらうのです。先輩の指導などを直接体験することで、「ここで働きたい」と魅力を感じて門を叩いてくれるケースが多く、長年かけて培ってきた育成の仕組みが採用に実を結びついています。
実際、ここ4年ほどで採用した新卒職員は一人も退職していません。もちろん、経験豊富なベテランも在籍しており、若い力とベテランの知見が融合していることも、私たちの大きな強みになっています。
コロナ禍を越えて DX推進と持続可能な働き方へ

ーーコロナ禍は、貴法人にどのような変化をもたらしましたか。
曽我好男:
職員の感染症に対する意識が格段に高まり、組織としての危機管理能力が向上しました。また、この経験を機にDXを一気に推進しました。補助金を活用して会議でのタブレット導入や受付システムの電子化、ペーパーレス化を進め、業務の効率化を図っています。
DXによって研修は集合型からリモートやウェブ形式に変わりました。その結果、移動時間がなくなり、職員は時間を有効に使えるようになったのです。また、施設長級や事務部門では万が一に備えてリモートワークができる体制を整備しました。これにより、長く続いたコロナ禍の中でリスクを低減させる成果を出すことができましたし、より柔軟で持続可能な働き方が可能になっています。
職員の幸せが原動力 「本当の福祉」で描く未来
ーー今後、どのような組織にしていきたいとお考えですか。
曽我好男:
まずは「人」を育てること。人材を「人財」に変えていくための環境整備が私の最大の使命です。同時に、施設の老朽化を見据えた計画も進めなければなりません。将来的には、自立支援と手厚い介護の中間を埋めるような、新しい事業の展開も視野に入れています。
齋藤誠:
私は「職員を幸せにする」ことを目標としています。職員が幸せでなければ、ご利用者を幸せにすることはできません。給与や働きがい、風土を含め、職員の幸福を追求し、次の世代の管理職を育てていく。私が「管理職は職員を見なさい」と常に伝えているのは、そのためです。
ーーどのような方と一緒に働きたいとお考えですか。
齋藤誠:
現場では、常に問題意識を持って「これでいいのか」と自ら考えられる方。事務職では、自分の担当業務だけでなく、周りと協力し合える、気が利く器用さを持った方が望ましいです。組織としてチームワークを大切にしているので、協調性のある方にきていただきたいと考えています。
ーー最後に、福祉の仕事に興味を持つ読者へメッセージをお願いします。
曽我好男:
福祉や介護の仕事に興味を持ち、「誰かを支えたい」という温かい気持ちをお持ちの方に、ぜひ私たちの仲間になっていただきたいです。私が考える「本当の福祉」とは、1から10まで全てをやってあげることではありません。ご本人ができることまで取り上げてしまうと、その方の生きがいや役割まで奪ってしまいます。できない部分を私たちが支え、ご本人が持つ力を引き出して差し上げることこそ、この仕事の醍醐味です。
入社後の研修体制は確立していますので、経験がなくても心配は要りません。安心してこの世界に飛び込んできてください。
齋藤誠:
福祉の仕事は、介護だけでなく児童や障害など多様な分野があります。人と関わるのが好きな方も、逆に少し苦手な方も、それぞれが輝ける場所が必ず見つかるはずです。弊法人のように、高齢福祉で実務と資格取得によって個々の職員が飛躍できる分野もあります。ぜひ広い視野でこの世界を見てほしいと思います。
編集後記
行政で培った俯瞰的な視点と、民間企業で磨かれた現場感覚。異なる強みを持つ二人のリーダーの下、楽友会は「人が主役」という信念を揺るぎない現実にしている。職員の幸せを追求する姿勢が、質の高いケアを生み、地域からの信頼につながる。この好循環こそが、同法人の最大の強みであろう。福祉業界の未来を担う「人財」が、この場所から数多く巣立っていくに違いない。
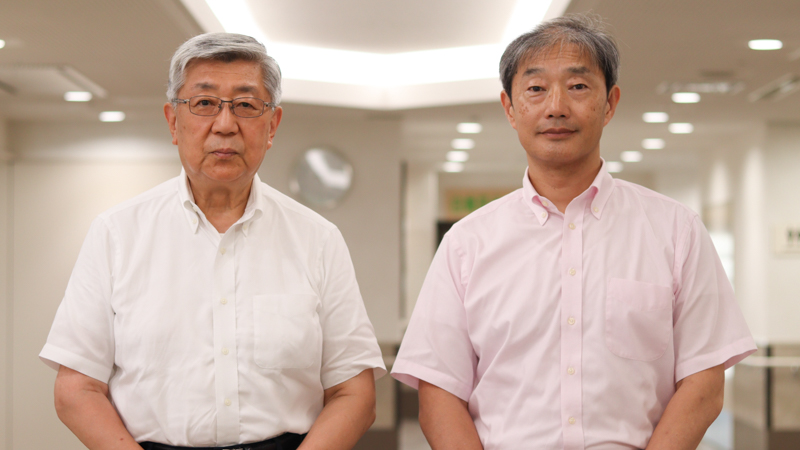
曽我好男/多摩市職員を36年在職し、健康福祉部長等を歴任。定年後、東京都市町村職員研修所及び中央大学講師を経て、2020年に社会福祉法人楽友会理事長に就任。現在、他法人の監事をはじめ行政問題に関する委員も務める。
齋藤誠/一般企業を経験し34歳で福祉業界へ転職。現在、社会福祉法人楽友会の常務理事として、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム施設長及び在宅部門を統括する傍ら、社会福祉系の大学で教鞭を執っている。














