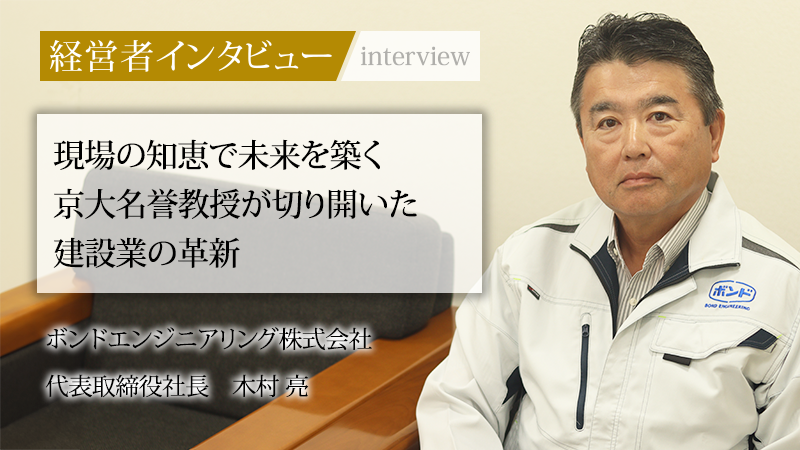
大阪に拠点を置くボンドエンジニアリング株式会社は、橋梁やトンネル、コンクリートや鋼構造物の維持管理や耐震補強を手がける企業だ。構造物の安全を保ち、人々の暮らしを守る事業を展開する同社の舵取りを担うのが代表取締役社長の木村亮氏だ。稀有な京都大学名誉教授から経営者への転身は、一体何を求めての決断だったのだろうか。大学教授として長年研究と人材育成に尽力し、現在は建設業界に新たな風を吹き込む木村氏のこれまでの歩みと、その思いに迫る。
キャリアの転換点とボンドエンジニアリングとの出会い
ーーご自身のキャリアの原点についてお聞かせください。
木村亮:
もともとは、普通の建設会社に入り、海外で仕事をしたいと考えていました。しかし、大学院への進学後、指導教授から「研究者にならないか」と声をかけていただき、お受けしたことがきっかけで、研究者の道に進みました。
博士号を取得し、その後は助教授を経て教授に就任し、16年ほど務めましたが、私は65歳という定年を待たずに大学を退職しました。なぜなら、もし定年を迎えてから一般企業に入ったとしても、顧問という立場でしかかかわれないのではないかと考えたからです。それならば、役員や経営者として、より深く経営に携わる方が面白いのではないかという気持ちがありました。また、これまでの研究者としての仕事は普通の人が想像できないほどハードでしたから、元気なうちに全く違う新しいことに挑戦してみたいという思いも強かったのです。
ーーその後、どのような経緯で社長に就任されたのでしょうか。
木村亮:
実は、弊社の親会社であるコニシ株式会社とは、15年ほど前からアドバイザーとしてかかわりがありました。そして7、8年前からは社外取締役も務めていました。その中で、弊社の事業内容を技術的な観点から深く知るにつれ、これから「メンテナンス」が重要になると確信するようになりました。新しい構造物を作るよりも、今あるものを長く安全に使う維持管理の分野に強い関心を抱いたのです。
私の専門は橋本体などの上部構造物の劣化が専門ではありません。しかし、大学で土木全般を研究していたため、弊社の事業内容は深く理解できました。NPOで培った現場での実践的な課題解決のノウハウも、この会社で活かせると考えました。こうした経緯から、より深く関わりたいという思いが強くなり、2年半前に入社いたしました。
NPO運営で培った経営感覚
ーーNPO法人ではどのような活動をされていたのでしょうか。
木村亮:
私は約20年ほど前から、「道普請人」というNPO法人の運営に携わっていました。そのNPOでは、途上国などで泥だらけになった道を、住民が最も簡単な技術で自力で直せるよう支援する活動を行っていました。
この活動は、職員を雇用し、資金を集め、事業を円滑に進めるといった、企業経営と何ら変わらない要素が求められました。この経験を通じて経営的な感覚を養うことができ、それが現在のボンドエンジニアリングの経営基盤になっていると考えています。
現場の知恵が未来を拓く 独自の技術開発への信念
ーー今後の会社づくりで、特に重視していきたいことは何ですか。
木村亮:
新卒やキャリア採用を強化し、若い人が入りやすい環境を整えたいと考えています。また、技術開発は難しいことを発明するのではなく、当たり前のことをちょっと工夫するだけで非常に面白いことが起こります。必ずしも最先端のAIや半導体のような難しい技術開発だけがイノベーションではありません。現場の目線から生まれた身近なアイデアが重要なのです。この維持管理の世界も、新しい技術は重要ですが、それ以上に現場で実際に作業している人が持つ経験や知恵、つまり日々の作業から生まれるノウハウこそが、真の価値を生み出す源泉だと考えています。
ーー今後どのようなところに可能性を感じ、取り組んでいきたいとお考えでしょうか。
木村亮:
現状、ドローンを活用した調査などもあるものの、調査のやり方にはまだまだ工夫の余地があると思っています。たとえば、コンクリートの壁面を這い上がり、打音検査をして劣化状況を診断するロボットなど、人が立ち入れない場所での調査を簡単に行う技術は、今後も開発できる可能性があります。また、過酷な労働環境の改善も重要です。たとえば、養生(ようじょう)の方法一つとっても、工夫次第でより効率的かつ安全な作業が実現できます。現場で働く人々が持つ知恵やノウハウを吸い上げ、それを新たな技術や仕組みとして世の中に広めていきたいと考えています。
社員と家族の幸せを追求する 建設業界の常識を覆す働き方改革

ーー経営者として、貴社をどのような会社に育てていきたいですか。
木村亮:
お客様に「ボンドエンジニアリングなら安心して任せられる」と厚い信頼をいただける会社を目指しています。安かろう悪かろうではなく、適正な対価をいただくことで、質の高い仕事を提供し、手戻りのない丁寧な施工を通して、信頼を積み重ねていきたいです。そのためには、社員はもちろん、協力会社の皆さんと共に成長できる関係を築くことが不可欠です。
ーー社長がキャリアを通じて大切にされている信念は何でしょうか。
木村亮:
経営者としての役割は、社員とその家族、そして協力会社の方々がきちんと生活し、豊かになることだと考えています。この土木の維持管理という仕事は、地震が来ても構造物が崩れないようにするなど、人々の暮らしを守り、豊かにする仕事です。私は、社員が「この会社で働いてよかった」と思える会社づくりを、皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思っています。また、大学時代から「教育」「研究」「社会貢献」の3つを高レベルでこなす人になりたいと考えていました。大学教授として研究者を育成し、研究者としては日本を代表するほどの成果をあげ、社会貢献としてはNPO法人を立ち上げました。今後は、この維持管理の仕事を通して、日本の発展に貢献していきたいと考えています。
編集後記
京都大学名誉教授という唯一無二の経歴を持つ木村氏。その言葉からは、研究者としての探究心、教育者としての人材育成への情熱、そして経営者としての社会への深い思いを感じ取ることができた。特に印象的だったのは、技術開発に対する「当たり前のことにちょっとした工夫を」という現場思考の言葉だ。これは、専門性の高い建設業界に限らず、あらゆるビジネスパーソンに示唆を与えるだろう。「社員とその家族の幸せを追求する」という氏の言葉通り、同社の取り組みは建設業界に新たな価値観を提示し、働き方の未来を切り開くと確信する。今後のさらなる飛躍に期待したい。

木村亮/1960年京都府生まれ、京都大学大学院工学研究科土木工学専攻修了。京都大学で助手、助教授、教授として研究・教育活動に38年間従事し、2023年に早期退職。京都大学博士(工学)、京都大学名誉教授。2023年にボンドエンジニアリング株式会社に入社、専務取締役を経て2025年4月に代表取締役社長に就任。構造物の耐震補強と維持管理、若手の人材育成に情熱を燃やす。NPO道普請人の理事長として、20年間世界の未舗装道路を住民と直す活動も実践。














