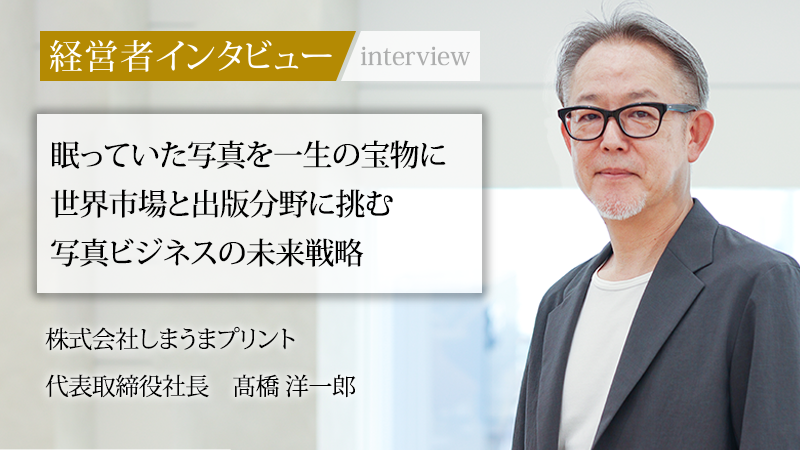
ネットプリント業界の常識を覆し、圧倒的な存在感を放つ株式会社しまうまプリント。「高品質、超低価格」を実現し、個人から法人まで幅広い支持を集める。同社の競争優位性は、企画から開発、生産までを自社で完結させる一貫した体制にある。音楽業界からITエンジニアへと転身し、モノづくりへの情熱を事業の核に据えてきたのが、代表取締役社長の髙橋洋一郎氏だ。そのユニークな経歴から生まれた経営哲学、他社を圧倒する強さの秘密、そして写真の価値を再定義し世界へ挑む壮大なビジョンに迫る。
音楽とITを経て辿り着いた「モノづくり」という事業の原点
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせください。
髙橋洋一郎:
学生時代にバンドをしていたこともあり、音楽に携わりたいという想いで楽器メーカーに就職。DTM機器など電子楽器に携わる中でコンピューターに触れ、その面白さに夢中になりました。プログラミングを独学で習得し、20代半ばでITエンジニアに転身したのです。そこからいくつかの会社を経て、共同創業者と共に弊社の前身となる会社を立ち上げました。
ーー貴社を創業したきっかけは何だったのでしょうか。
髙橋洋一郎:
エンジニアとして、手を動かして何かをつくり、お客様に価値を提供するということにやりがいを感じていました。弊社の事業は、お客様から注文を受けてから生産するという仕組みが根幹です。「生産を流せる受注の仕組み」をゼロからつくり上げたい。そのモノづくりへの強い想いが原点にあります。サービス開始の1年前から事業計画を練り、資金調達に奔走する日々でした。
ーー創業当時は、どのようなことに取り組んでいましたか。
髙橋洋一郎:
創業当初から約4年、鹿児島に単身赴任し、工場のスタッフとともに現場で業務を行っており、設備投資計画や資金調達、プリント資材搬入、ウェブサイトの更新、キャンペーンの施策、検索エンジン対策など幅広く担当しました。また、現場の改善を徹底しました。一例ですが、お客様の写真を取り違えないように、どうすればミスをなくし、効率を高められるのか。現場で考え、試行錯誤を繰り返す中で、自然と今のスタイルが確立されました。
業界の常識を覆した「1枚5円」の裏にある一貫体制

ーー貴社の事業の強みについて教えてください。
髙橋洋一郎:
街の写真店が1枚30〜40円だった時代に、弊社は「1枚5円」でプリントサービスを開始しました。企画から開発、生産、出荷までを自社で完結させる一貫体制です。鹿児島・熊本にある大規模なラボで、すべてを内製しています。
創業当初はマンションの一室から始めましたが、事業拡大に合わせて現在の日置市への工場移転と増設をしました。現在では受注から出荷までをほぼ自動化したラインが稼働しています。このワンストップの体制が、競争力の源泉です。他社には真似のできない高品質と低価格、スピーディーな納品を可能にしています。
ーープリント事業における顧客層についてお聞かせください。
髙橋洋一郎:
プリント事業は、年間でおよそ3億枚、フォトブックは200万冊以上を出荷しています。その内訳は、法人のお客様と個人のお客様がほぼ半々です。私たちは創業当初から法人向けと個人向けの両輪で事業を展開することを決めていました。法人向けの案件はコンペになることも少なくありません。しかし、品質と価格の両面で評価をいただき、ほとんどの案件で受注に至っています。この安定した基盤があることも、弊社の大きな強みと言えるでしょう。
ーー「しまうまプリント」というブランドについて、どのようなビジョンをお持ちですか。
髙橋洋一郎:
創業当初は、高品質・超低価格でサービスを提供することから始めました。もちろん、それは今も弊社の強みです。しかし近年は、安さだけではなく「魅力的な商品」をもう一つの軸として展開しています。安価な商品に加え、より画質の良い高価格帯のラインアップも整備。ギフトなど特別な需要にもお応えできるようになりました。「安くて早い」というイメージだけではありません。「大切な思い出を託せる高品質なブランド」として認知されるよう、進化を続けます。
デジタル時代に問い直す写真プリントの本質的価値

ーー貴社が事業を通じて実現したい世界観について教えていただけますか。
髙橋洋一郎:
スマートフォンが普及し、誰もが気軽に写真を撮る時代になりました。しかし、その多くはデジタルの世界で完結してしまいます。そんな中、私たちは改めて伝えたいと考えていることがあります。それは、写真を「モノ」として手に取ることの価値です。ふとした瞬間にアルバムを見返す楽しさや、誰かにギフトとして贈る喜び。そうした体験を通じて、人の想いや時間をつなぐ架け橋のような存在になりたいです。
ーー今後はどのような事業展開をお考えですか。
髙橋洋一郎:
年賀状の需要が減少するなど市場が変化する中で、次の一手は不可欠です。中でも私たちが特に期待しているのが、フォトブックを進化させた出版事業と新規事業です。出版事業では、クリエイターが在庫リスクなく受注生産で作品を販売できるプラットフォームとして『しまうまマルシェ』をリリースしました。同人誌や写真集・ZINEなどをつくりたい方を対象とし、弊社が生産から配送までを担うことで、クリエイターは創作活動に専念できます。この仕組みは創作の可能性を広げると信じており、今後の柱になる事業だと考えています。
加えて、新規事業の取り組みも進めています。現在は『しまうまプラス』というサービスを通じて、アクリルスタンドなどのアクリル商材を展開しています。秋にはステッカー商材を追加し、より幅広い層にご利用いただけるよう準備を進めているほか、年末の需要期に向けて写真入りカレンダーの展開も計画しています。これらを通じて、年賀状需要の減少を補いながら、新しい写真の楽しみ方をお客様に提案していきたいと考えています。
ーー海外市場への展開についてもお聞かせください。
髙橋洋一郎:
第一弾として台湾でサービスを開始しました。日本の工場から製品を空輸する形ですが、当初の予測を上回るほど好調です。弊社の強みである「高品質・低価格・スピード」は、特にアジア圏で受け入れられやすいと感じています。
今後はさらにエリアを広げ、需要が拡大すれば現地に工場を設立することも検討していきたいと考えています。工場運営やシステム開発のノウハウは確立済みです。そのため、どの国でも展開できる自信を持っています。
ーー事業を拡大していく上で、どのような人材を求めていますか。
髙橋洋一郎:
何よりもまず「写真に興味がある人」に来てほしいです。写真というツールを武器に、新しい価値を共に生み出す仲間を求めています。サービスやプロダクトを一緒に考えてくれる方を歓迎します。職種は企画職、デザイナー、エンジニアと幅広く募集しています。しかし共通して求めるのは、変化を楽しみ新しい価値を創造したいという情熱です。私たちのビジョンに共感し、共に挑戦してくれる方をお待ちしています。
編集後記
音楽への情熱を原点に、ITエンジニアとして培った技術と、創業者として貫いてきたモノづくりへのこだわり。髙橋氏のキャリアは、すべてが「しまうまプリント」という唯一無二のビジネスモデルに結実している。常に現場に身を置き、自ら手を動かし、改善を続ける。その真摯な姿勢こそが、同社を業界のトップランナーへと押し上げた原動力だろう。写真の価値が問われる時代。クリエイター支援や世界進出という挑戦でその価値を再定義しようとする同社の未来に注目だ。

髙橋洋一郎/1965年生まれ、東京都出身。2010年、しまうまプリントシステム株式会社(現・株式会社しまうまプリント)設立に携わり、2017年に代表取締役社長に就任。2020年に分社化し、株式会社しまうまプリント、株式会社しまうまプリントラボの両社の代表取締役社長に就任。「すべての想いを身近に 時をつなぐ会社になる」をミッションに、経営に注力しながら事業拡大を牽引している。














