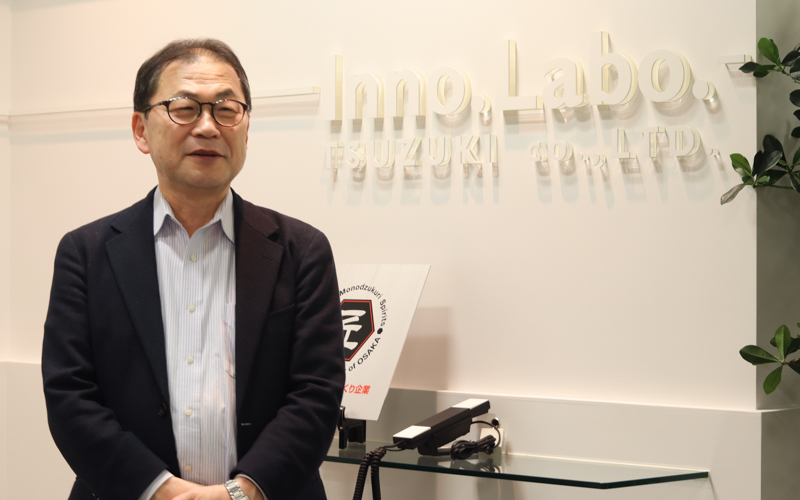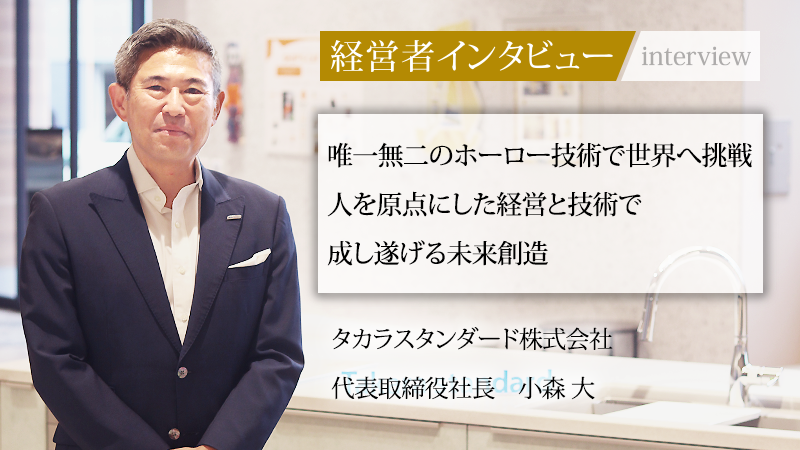
水まわり機器のリーディングカンパニーとして、日本の暮らしを支え続けるタカラスタンダード株式会社。独自の「高品位ホーロー」技術と、顧客に寄り添う全国規模の拠点網を強みとする。2024年4月、生え抜きの社員として同社の代表取締役社長に就任したのが小森大氏だ。若手時代の挑戦、地方の最前線で培った経験。そして本社の挫折を経てたどり着いた「五方よし」という経営哲学に至る軌跡は、まさに同社の歴史と未来を体現している。国内トップの座を盤石にし、海外へ、さらには宇宙へと広がる壮大なビジョンに迫る。
自身の裁量で道を拓いた若手時代の挑戦
ーー社会人としてのキャリアについておうかがいできますか。
小森大:
就職活動では金融業界とメーカーを志望していました。活動を続ける中で、もともと料理も好きだったことから住宅設備に興味があり、弊社の募集にたどり着き入社した経緯です。
入社当時から若手に仕事を任せる社風で、「この商圏は君に任せた」と、各自の裁量で挑戦させてくれる環境がありました。自分のアイデアや工夫をすぐに実践できたことは、若いうちからの多くの挑戦につながり、大きな財産となっています。当時は結果が求められる少し体育会系な雰囲気もありましたが、自分の工夫次第で成果が目に見えて変わっていく面白さを、肌で感じられる会社だと実感しました。結果として、弊社を選んで心から良かったと感じています。
ーーキャリアにおける転機についてお聞かせください。
小森大:
30代前半に、熊本県の天草に新設されたショールームの責任者として赴任したことが最初の転機です。上司がいない環境で、4人でスタートした組織を最終的に7人まで拡大させ、マネジメントから商品展示の工夫まで、自分の裁量で動かせたのです。全国的に見れば小さな拠点でしたが、ここでの経験を通じてマネジメントの面白さと難しさを学びました。
天草のような小さな市場は、どこで新築が建つかといった情報も掴みやすく、お客様との関係も築きやすい環境です。ビジネスの要点が凝縮された小規模なエリアで全てを任されたことは、経営の基礎を身につけるきっかけになり、私の視野を大きく広げてくれた貴重な経験となりました。
ーーチームで成果を出すために、どのような点に気を配っていますか。
小森大:
天草で3年勤務した後、次に赴任した岡山県の津山営業所は、競合メーカーの製造拠点がある土地でした。その企業の社員や関係者も多く住んでおり、完全に不利な環境です。そこで痛感したのが、チームとして成果を最大化させることの重要性でした。
私一人が1.5倍の力を出しても、組織全体への影響はわずかです。そこで、若手の教育やモチベーションアップに徹底的に力を入れました。まずは、メンバー一人ひとりをよく観察すること。毎日接していれば、表情の変化でその人の状態が分かります。その上で、困難な課題には一方的に指示するのではなく、山本五十六の言葉にある「やってみせ」の精神で、まず自分の背中を見せ、そして本人に任せてみる。できなければ、また一緒に行う。この繰り返しで、メンバーと共に成長していくことを常に心がけていました。
本社での挫折と経営哲学「五方よし」の発見
ーー業務を進めるうえで、壁にぶつかった経験はありますか。
小森大:
岡山支店長の後、本社の営業課長に就任したときのことです。販売促進や商品企画など会社の根幹に関わる部署で多くのことを学び、人脈も広がりました。しかし、当時の私にはまだその重責を担う覚悟が足りていなかったように思います。営業の最前線で数字を追いかけてきた人間が、急に支援する側のスタッフ部門に入り、「自分は何のためにここにいるのだろう」と戸惑いました。
経営陣や上層部に合わせて仕事を進めなければならない状況にも馴染むことができませんでした。経営陣は次世代の幹部候補として会社の仕組みを学ぶために本社での経験も積ませようと考えてくれていたと思うのですが、その思いに私の行動や成果が伴わず、結局3年で営業として再び現場に戻ることになります。これは私にとって大きな挫折となりました。
ーー苦しい時期をどのように乗り越えられたのでしょうか。
小森大:
営業の前線に戻ってからも、そこそこの成果は出せていましたが、振り返ると大きな成果とはいえない状態が続きました。そんな中、私の考え方を大きく変える二つの言葉に出会います。一つは、真心と相手への思いやりを指す、孔子の「忠恕(ちゅうじょ)の精神」(※1)。そしてもう一つが「五方よし」です。これは近江商人の「三方よし」を発展させた考え方で、第一に「社員とその家族」、第二に物流や施工などを担う「社外社員とその家族」、そして「顧客」「世間」「株主」と続く五者を大切にするという思想です。
この哲学を支店運営に取り入れてから、すべてが好転し始めました。退職者が減り、若手が生き生きと働き始めるなど、目に見えて変化が生まれました。150人ほどいた社員全員の顔と名前が一致するほど、社員との距離が近くなりました。組織の雰囲気が良くなることで社員の当事者意識が高まり、それが結果として業績を押し上げていきました。まず身内である社員を大切にすることが、巡り巡って全ての成功につながるのだと確信するに至りました。
(※1)忠恕(ちゅうじょ)の精神:、儒教の根本である「仁」(思いやり)の具体的な実践方法であり、自分の良心に忠実であること(忠)と相手の立場に立って物事を思いやること(恕)の両方を兼ね備えた精神。
社員とその家族のために下した社長就任の決断
ーーその後のキャリアにおいて、印象に残っているエピソードはありますか。
小森大:
埼玉支店で成果が出始めた頃、いわゆるヘッドハンティングの打診をいただいたことがあります。そのお話を冷静に検討する中で、改めてタカラスタンダードという会社を客観的に見つめ直す良い機会となったと感じています。これまでの自分のキャリアはもちろんのこと、この会社の将来性、良い点、改善すべき点、財務状況や他社にはない強みなどを、他社と徹底的に比較検討しました。
そして比較して見えたのは、弊社が持つ圧倒的な未来への可能性でした。改善すべき点は多々あるものの、この会社が一番未来を切り拓く力を秘めていると感じました。特に大きかったのが、他社には決して真似のできない「技術力」と、会社の保有する唯一無二のアセットです。
金属の強さとガラスの美しさを合わせ持ち、汚れや湿気、熱にも強い独自素材であるホーローは世界中でつくれます。しかし、その技術を応用してデザイン性の高いキッチンまでつくり上げるのは、世界で弊社だけです。この2つがあれば、これからどんなことにも挑戦できる。そう感じた時に、この会社で骨を埋める覚悟が決まりました。
ーー社長に就任されるにあたり、どのような心境でしたか。
小森大:
社長就任のお話をいただいたのは2年前です。そして「社員とその家族のため、そしてこの会社の未来のために社長をお受けします」と返事をしました。そこから1年間、自分が社長になった時にどうしていくか、さらに準備を進めてきました。
私が社長になる直前はコロナ禍の「巣ごもり需要」で業界全体が活気づき、供給責任を果たすことが最優先でした。しかし、その需要が落ち着いた今、未来を見据えて様々なことをアップデートしていく必要があります。社長としての私のミッションは「変革」を実行すること。時代に合わせ、先の未来をつくる変革を成し遂げることだと考えています。
他社が模倣不可能な「高品位ホーロー」の価値
ーー貴社事業の強みはどんなところでしょうか。
小森大:
弊社の強みは、やはり「高品位ホーロー」という唯一無二の素材です。かつては他社もホーロー製品を手がけていましたが、高いデザイン性が求められる時代になると、コストのかかる設備投資を敬遠して次々と撤退していきました。そんな中、弊社はホーローにこだわり続け、インクジェット技術などを駆使してデザイン性を高めることで、他社には模倣不可能な独自の価値を築き上げています。
そしてもう1つの強みが、分譲マンションのキッチンで約8割のシェアを獲得し、国内キッチン売り上げNo.1を誇るほどの強固な事業基盤です。それを支えるのが、全国160ヵ所のショールーム、消費地に近い15ヵ所の工場、10ヵ所の物流拠点です。この体制があるからこそ、大量生産・大量輸送から施工までを一貫して行い、お客様に最も近い場所で価値を提供できるのです。この業界では珍しく、メーカー希望小売価格と実売価格が大きくずれない正直な価格設定を貫いていることも、社員のプライドと会社のアイデンティティになっています。
宇宙も見据えた次の50年を支える新規事業の創出
ーー今後の展望についてお聞かせいただけますか。
小森大:
人口減少という大きな流れの中で、これまでのやり方だけでは未来はありません。だからこそ、人を中心に据えた「ウェルビーイング経営」(※2)を目指し、ビジネスの領域を「国内」「海外」「新規事業」という三本の柱で深掘りし、広げていく必要があります。
国内市場は縮小傾向と見られがちですが、私はそうは思っていません。世帯が減っても、水まわり機器はより高機能・高付加価値なものが求められるようになると考えています。その需要に応えるため、現在3番手のお風呂と洗面化粧台でトップを目指し、福岡の工場に約400億円を投資してシステムバスを生産する新棟を建設中です。
海外では、ホーローを武器に本格展開を進めます。「BtoBtoCビジネス」(※3)は現地の文化や商流の理解が必要で一足飛びにはいきませんが、一度基盤を築けばじわじわと着実に成長できます。現在の売上は約10億円ですが、これを2030年までに100億円規模まで拡大させる計画です。これからのタカラスタンダードをアップデートさせていくことが、私の最大の使命だと考えています。
(※2)ウェルビーイング経営:従業員の心身の健康や幸福を重視する経営手法。
(※3)BtoBtoCビジネス:企業が別の企業を通して、最終的に一般消費者に製品やサービスを提供するビジネスモデル。
ーーどのような新規事業を検討されていますか。
小森大:
今年1月に「ビジネスディベロップメント本部」を新設し、次の50年を支える新たな事業の創出に乗り出しました。注目しているのは、ホーローの原料である「フリット」(※4)の可能性です。「フリット」は熱による膨張がほとんどない特性を持ちます。義歯の加工性を良くしたり、電子基板の部材として使われたりするほか、スペースシャトル用の耐熱タイルなどへの応用も期待できます。さらに、月表面全体に広がる砂や粉状の土壌「レゴリス」のガラス片が原料になりうることから、将来の月面基地建設といった宇宙分野での活用も視野に入れ、様々な大学と連携して研究を進めています。
(※4)フリット:珪砂(けいしゃ)、長石(ちょうせき)、石灰などの天然原料や工業原料を高温で溶かし、急冷したガラス質の粉末。
国内トップから世界へつなぐ「全世界ホーロー化計画」

ーー最後に、社長としての今後の意気込みをお聞かせください。
小森大:
私の個人的な野心として「自分の理想のキッチンをつくる」という思いがあります。キッチンメーカーの社長として、そのプライドは常に持ち続けたいです。そして会社としては、国内で圧倒的ナンバーワンの地位を確立し、海外でも日系ブランドのトップに立ちたいと考えています。さらには「全世界ホーロー化計画」を成し遂げたいという壮大な野望も持っています。
弊社には、若手に任せる文化と、社員とその家族を第一に考える「五方よし」の社風があります。これまでの質実剛健な文化に、「ムーンショット」、つまり実現困難に思えるような壮大な発想で未来を考える新しい文化を掛け合わせ、私と思いを一つにしてくれる仲間たちと共に、未来のタカラスタンダードを創っていきたいです。
編集後記
地方の最前線で経営の神髄を学び、本社での挫折を経て「五方よし」という確固たる哲学を築いた小森氏。その核となるのは、どこまでも「人」を想う温かな視座だ。それは、他社が次々と手放したホーロー技術の可能性を信じ、磨き上げてきた企業の姿勢とも不思議と重なって見える。地に足を着けた思想と、誰もが見たことのない未来を見据える視点。一見、対極にあるこの二つをつなぎ合わせ、静かな情熱で未来への変革を語る姿に、次代を担うリーダーの確かな像を見た。

小森大/1970年11月19日生まれ、長崎県出身。1994年3月大分大学経済学部経営学科卒業後、タカラスタンダード株式会社に入社。岡山支店長、本社営業本部営業課長、埼玉支店長、東京支社長を経て、2020年4月同社執行役員、2023年4月常務執行役員、2023年6月取締役を歴任。2024年4月代表取締役社長に就任。