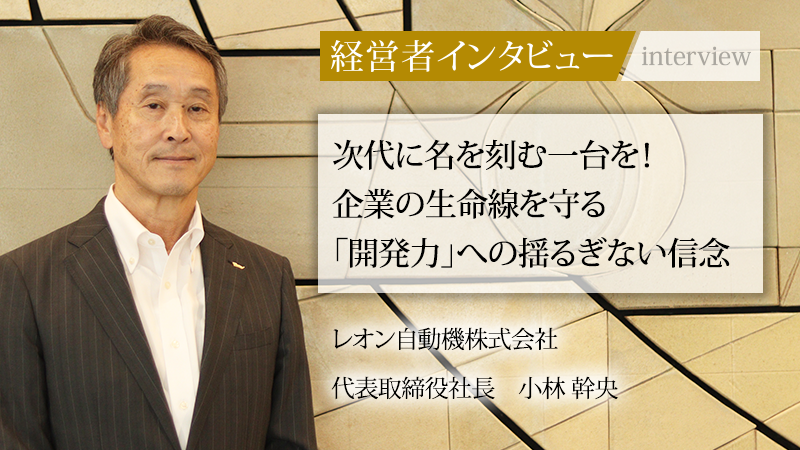
まんじゅうの餡を自動で包む「包あん機」を世界で初めて開発し、世界の食文化に革新をもたらしたレオン自動機株式会社。しかし、業界のトップランナーである同社は今、「大企業病」という成長の壁に直面している。この課題に立ち向かうのは、技術者として現場の最前線に立ち、子会社経営も経験した代表取締役社長の小林幹央氏だ。創業以来のDNAである「開発力」を武器に、組織の変革に挑む同社の現在地と未来への展望を追う。
海外での試練と経営者への転機 視座を高めた二つの経験
ーー貴社へ入社された当時のことをお聞かせください。
小林幹央:
1977年、私が新卒で弊社に入社した決め手の一つは、「作業着で仕事をするのが気楽でいいな」と感じたことでした。しかし、入社後に待っていたのは決して楽ではない、厳しい現場の日々です。お客様から「こんなお菓子をつくりたい」という要望があれば、徹夜をしてでも2~3日で形にする。そのような毎日を送っていました。
特に印象深いのは海外でその土地の環境に合わせて機械を最適化していく仕事です。30年以上も前のことですが、サウジアラビアやスペインで、納めた機械で製品がうまく出来ないと連絡を受け、一人で現地に1ヶ月以上滞在して問題を解決したこともあります。当時は非常に大変でしたが、グローバルな仕事の進め方を肌で学び、間違いなく自分の力になったと確信しています。
ーーキャリアにおけるターニングポイントはいつだったとお考えですか。
小林幹央:
技術者として経験を積む中で、大きな転機となったのは30歳手前の頃です。アメリカのパン学校へ半年留学した経験が、私を大きく成長させてくれました。それまでは先輩に言われるがままにパンを作っていましたが、そこで初めてパンの材料科学などを体系的に学びました。この経験を通じて、仕事への向き合い方が大きく変わったのです。教科書だけでは得られない知識を得て、そこで築いた人脈も、今では私にとって大きな財産です。
また、米国子会社であるオレンジベーカリー社の代表取締役社長就任も、大きな転機です。当時、弊社の経営体制が変わり、それに伴ってオレンジベーカリーの改革も急務となりました。改革を力強く推し進めるための新たな社長を探したものの、なかなか適任者が見つからないという状況でした。そこで「それならば自分で」と、当初は想定もしていなかった経営職を引き受ける決断をしました。
この社長就任は、技術者としての私の視野を根底から覆すものでした。それまでは自分の部署の成果を追求していればよかったのですが、初めて会社全体の舵取りを担う「全社の利益」という視点の獲得。同時に、機械の「作り手」からパンを製造・販売する「使い手」になったことで、これまでとは違う次元でお客様の想いを肌で感じられるようになったのです。この時に得た複眼的な視点こそが、現在の経営の礎となっています。
ーー貴社の社長就任後に最初に取り組まれたことは何ですか。
小林幹央:
「レオン自動機は機械の開発メーカーである」という原点に立ち返ることです。弊社グループの行動指針に「無駄をなくし、本来のやるべき仕事に集中して取り組む」という項目があります。これは「開発に徹底集中し、それ以外のことはやらない」という方針であり、改めて社内に徹底しようと考えました。
会社の外部からの評価としては営業利益率も大切ですが、私たちにとってそれ以上に重要なのは、世界の競合他社には決して真似のできない、圧倒的な技術力に裏打ちされた機械を開発する力です。単に新製品を作るのではなく、この独創的な開発力がなければ、数年後には機械は売れなくなり、グローバルな競争の中で会社の成長は止まってしまいます。
模倣品との競争を勝ち抜く 開発力という創業時からのDNA
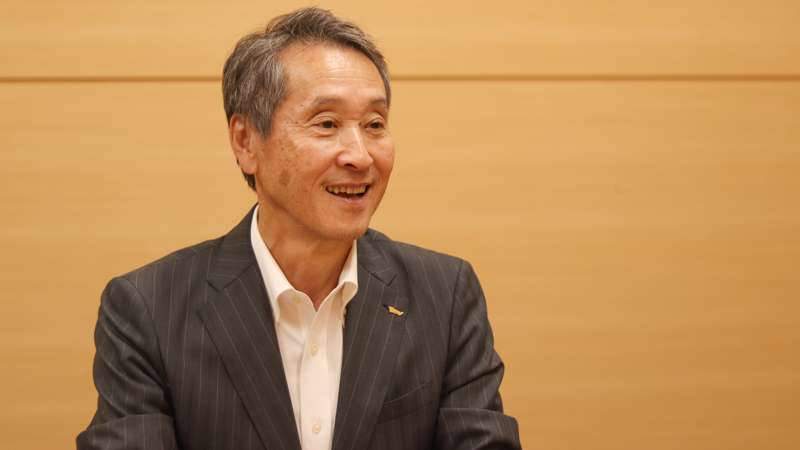
ーー貴社事業の強みについて、お聞かせいただけますか。
小林幹央:
弊社事業の根幹には、二つのコアな技術があります。一つは、世界で初めて開発した食品の餡などを生地で「包む」技術、つまり自動包あん機です。そしてもう一つが、パン生地を薄いシート状にしてから成形する独自の製パン技術です。生地へのダメージを最小限に抑えられるこの技術も、弊社の大きな強みといえます。この二つの基本技術を軸に、さまざまな食品へと応用展開しています。
しかし、今や自動包あん機のメーカーは世界中に何十社も存在し、弊社も選択肢の一つにすぎません。「一番歴史が長いから」という理由は、もはやお客様の選択を保証するものではなく、常に厳しい競争の中にいるという現実を直視しなければなりません。

自動包あん機 CN700

バラエティー製パンライン VM300
ーー今後の製品開発について、どうお考えですか。
小林幹央:
常に新しい技術や付加価値を追求しなければ生き残れません。その危機感が開発力の源になっています。これからは、お客様の要望に応えるだけの「御用聞き」になるのではなく、弊社オリジナルの標準機を増やし、世界を驚かせるような製品を展開していきたいと考えています。そのために、会社の資源を「開発」に集中させているのです。
創造性を阻む壁「大企業病」との決別と未来への展望
ーー現在、最も注力されている課題は何ですか。
小林幹央:
会社の成長を阻害する最大の敵は、社内に潜んでいます。それは「大企業病」です。組織が大きくなるにつれて手続きが複雑化し、仕事のスピードが落ちてしまう。そして社員から当事者意識が失われていきます。企業が成長し官僚的になると、挑戦より安全性が優先され、「創造性」が失われかねません。「新しい挑戦はリスクがあるから、前例踏襲で安全に進めよう」という空気が蔓延すれば、開発メーカーとしての生命線が絶たれてしまいます。
その原因は社員個人ではありません。「風通しが悪く、上にものが言えない」といった組織風土の劣化にあると考えています。この課題を解決するため、まずは社員の意識改革を進めています。私は常々「部署間で率直に意見をぶつけ合え」と伝えています。相互不干渉は組織の停滞を招くだけです。前例に倣うのではなく、管理職とメンバーが密に連携し、社員全員が意見を戦わせる「挑戦する組織」を取り戻したいと考えています。
ーー5年後、10年後を見据えたビジョンについてお聞かせください。
小林幹央:
これからも食品機械メーカーとして、常に業界の先頭を走り続けるトップランナーでありたいと願っています。その地位を確固たるものにするため、今後さらに開発体制を強化していきます。会社の成長は海外市場にかかっており、特に人口が増え続けるインドは、今後最も成長が見込める市場だと捉えています。
ーー今後、どのような人材を求めていますか。
小林幹央:
開発力を強化する上で、型にはまらない人を求めています。会議の場でしっかりと反論できるような、自分の意見を言える人に来ていただきたいと考えています。新卒・キャリア採用問わず、多様な考えを持った人材を積極的に採用しています。新卒採用では、採用数の3分の1を開発職に充てるなど、特に力を入れています。もちろん基礎的な知識や論理的に考える力は必要ですが、学んできた分野などのバックグラウンドは問いません。
ーー最後に、これからを担う若き技術者たちへメッセージをお願いします。
小林幹央:
私はいつも、開発や設計の担当者に「生涯で一台でもいい。自分の名を残す機械を作れ」と言っています。この言葉には、技術者としての誇りを持ち、世の中に真の価値をもたらす仕事を成し遂げてほしいという、私の心からの願いを込めています。私たちの挑戦は、これからも続きます。
編集後記
「作業服が楽でいいな」という動機からキャリアをスタートさせた小林社長。現場の技術者から子会社の経営、そして再び本社のトップへと至るその道のりは、顧客視点と「開発力」への強い信念を育んだ。今、「大企業病」という壁に「創造性」を武器に挑む姿は、変化を恐れず挑戦し続けることの大切さを教えてくれる。同社の未来から目が離せない。

小林幹央/1955年埼玉県生まれ、1977年明治大学法学部卒業後、レオン自動機株式会社に入社。2002年技術サービス部部長、2007年執行役員技術サービス部長に就任。2011年米国の子会社であるオレンジベーカリー社の代表取締役社長、2014年ホシノ天然酵母パン種代表取締役社長などを歴任し、2015年6月にレオン自動機株式会社の取締役兼執行役員に就任。2019年取締役常務執行役員、2020年取締役専務執行役員に就任を経て、2021年に代表取締役社長に就任。














