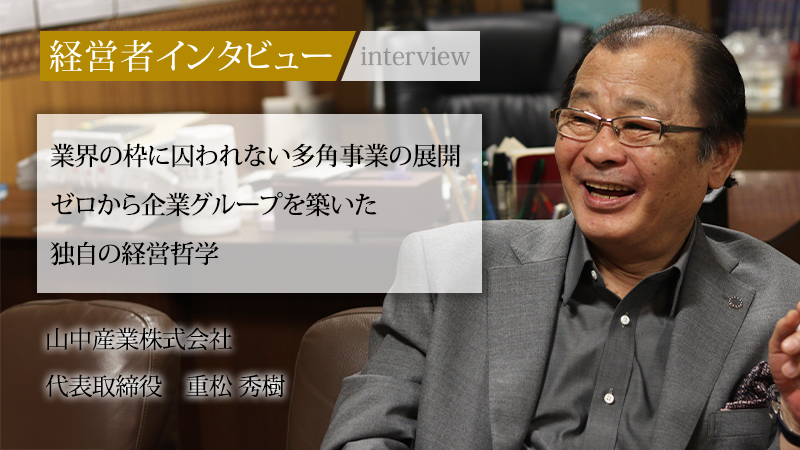
畳の材料などを扱う総合商社として、業界内で確固たる地位を築く山中産業株式会社。しかし、その姿は伝統的な商社の枠組みには収まらない。主力の住宅資材事業に加え、LNG(液化天然ガス)タンカーの防熱工事や、非住宅施設に対する改修工事も手がける。さらには銀座での高級日本料理店を経営するなど、その事業領域は多岐にわたる。この大胆な多角化を牽引するのが、代表取締役の重松秀樹氏だ。家庭環境に翻弄され、野球選手の夢を諦めた少年は、反骨心を胸に同社へ入社。型破りな行動力で数々の伝説を残し、会社のトップへと上り詰めた。歯に衣着せぬ言葉の裏には、鋭い洞察と経営哲学が隠されている。常識を破り、道を切り拓いてきた同氏に、その壮絶な軌跡と未来像を尋ねた。
裕福な生活からの転落 挫折が生んだ反骨という原動力
ーーまずは、ご自身のルーツである幼少期についてお聞かせください。
重松秀樹:
父は、タオルの名産地として知られる「今治タオル」を取り扱う事業を一代で興しました。今でこそ全国的なブランドですが、当時はまだ、自前の織機を持つ小さな機屋の集まりでした。その中で事業を始めた父のおかげで、幼少期は豊かな生活を送っていました。
しかし、私が小学6年生のとき、事態が急変します。父の会社が事業で失敗し、倒産。裕福な生活は一変し、突如お金に困る生活へと転落してしまいました。お金がなければ何もできないという現実をこのときに痛感しました。
ーーその後の学生時代は、どのように過ごされたのでしょうか。
重松秀樹:
野球をやるために、甲子園の常連校だった松山商業に進学しました。しかし、父の会社が倒産した影響で、野球を続けるためのお金がありませんでした。当時の名門校は実力の世界であると同時に、お金がないとやっていけない世界でもありました。遠征費や用具代などの負担が大きかったのです。親に負担はかけられないと、結局野球を続けることを諦めざるを得ませんでした。そこから私は目標を失ってしまい、何をやっても面白いと感じなくなりました。卒業が迫る頃には警察の厄介になるほどの「不良」となっていました。
ーー山中産業へ入社された経緯を教えてください。
重松秀樹:
卒業が近づき、働かなければならないという現実が迫ってきました。そんな折、昔、父の会社に出入りしていた山中産業(当時の山中商店)の専務が私の噂を聞きつけ、「一度会って
みたい」と声をかけてくれました。専務にお会いした際、私は深夜徘徊で警察に捕まって丸刈りにされた直後でした。専務に「どうしたんやその頭は」と聞かれ、正直に事情を話したら、腹を抱えて笑われました。
最終的に「面白い子やな。うちに来い」と言われ、就職することに。当時は「迷惑をかけたら、そこへ行って奉公してこい」というのが当たり前の時代でした。父の会社の倒産時、仕入れ先だった山中産業にも迷惑をかけたという思いがありました。行くあてもなく、働くためにはここに来るしかなかった、という背景もあります。
左遷から始まった東京での挑戦 雪中で死を覚悟した東北での転機

ーー入社後は、どのような業務からスタートされたのですか。
重松秀樹:
商業高校出身だったので、会社は私が簿記やそろばん、機械の操作もできると思っていたようです。しかし、当時の私はそういった類のことは全くできませんでした。そこで、「喋るのが好きだから、営業をやらせてほしい」としつこく頼み込みました。その結果、半ば呆れられながらも「一回やらせてみよう」となったのです。これが面白いように売れました。
ーーその後、東京へ異動になった経緯を教えてください。
重松秀樹:
とにかく貧乏でしたから、弟を大学に行かせるためにも稼ぐ必要がありました。そこで、会社の仕事が終わった後、炉端焼き屋や雀荘で朝までアルバイトをしていたのです。給料とは別に収入があり、賄いも出るので食うには困りませんでした。会社の社宅まで彼女に又貸ししていたくらいです。後にそれらが全て会社に発覚し、当然「あいつはクビにしなければならない」という話になりました。その結果、入社して1年9ヶ月後、事実上の左遷として東京へ異動させられたのです。
しかし、東京といっても立派な事務所があったわけではありません。目黒にあった旅館の一室を借りて、たった2人でのスタートでした。上手くいくように思われた取引でも、他社へ注文が流れてしまうことが多くありました。思い通りに取引が成立しない状況が続いたのです。このままではダメだと一念発起し、未踏のエリアである東北方面の開拓を始めたのです。
ーー東北では、どのようなご経験をされたのですか。
重松秀樹:
当時、会社に内緒で営業活動を始めました。仙台を中心に、まだ誰も足を踏み入れていない地域を一人で回り始めたのです。冬の東北ですから、道は雪で覆われています。あるとき、吹雪で視界が完全に奪われ、運転中に車ごと道路脇の溝に落ちてしまいました。どこを見ても雪、光一つない。携帯電話もない時代です。自然と涙があふれてきて、「俺はここで死ぬんだ」と本気で覚悟しました。あれほど強烈な孤独と恐怖を感じたことはありません。幸い、数時間後に通りかかったトラックに助けられ九死に一生を得ました。あの経験が私を強くし、大きな転機となったのです。
この経験で得た精神的な強さが、その後の仕事に大きく影響しました。半年も経たないうちに、東北での営業成績が大阪の本社に認められ、正式に活動できるようになったのです。東京の拠点も人が増え、世田谷の奥沢に一軒家を借りて、皆で寝泊まりしながら仕事に明け暮れました。
さらに、私が取締役になって最初の大きな仕事が、現在の社屋を建てることでした。建設会社も知らなければ、登記の方法もわからない状態からのスタートです。それでも、不動産屋との交渉から何から、全て一人でやり遂げました。あの東北での経験があったからこそ、どんな困難にも立ち向かえる自信がついていたのだと思います。
交渉の決め手となった「いりません」の一言 異例の社長就任劇の舞台裏
ーーどのような経緯で代表取締役に就任されたのでしょうか。
重松秀樹:
ある企業が建材事業を売却するという話が持ち上がったことが、全ての始まりでした。当時、私はまだ取締役でしたが、社長から「この買収をどう思うか」と個人的に意見を求められました。他の役員たちは皆「新しい血を入れるべきではない」と全面反対。私も「お金を払ってまで買う必要はない。しかし、従業員だけでも無償で引き取れるなら価値があるかもしれない」という考えでした。
その考えを聞いた社長から密命を受け、私は水面下で調査を進め、詳細な資料を作成しました。そして交渉の最終日、売却元の役員たちがずらりと並ぶ会議室で、社長は私に説明を命じました。私は資料を机に置き、相手方の目を見て、はっきりとこう言ったのです。「この話は、いりません」と。
向こうはうちが断れば行き場がなくなるため、完全に足元を見られていました。だからこそ、こちらから話を打ち切る必要があったのです。私が「いりません」と言い放った瞬間、相手の役員の一人がボールペンを机に叩きつけ、「ふざけるな」と激昂しました。しかし、私は冷静に「価値が合わないと判断したのは私です。それをうちの社長に進言しただけですよ」と返しました。
最終的に、彼らは土下座までして「なんとか引き取ってくれ」と頼み込んできました。この一件が全て終わった後、当時の社長から「お前は天才的に話がうまい。明日から俺と社長を代わってくれ」と言われ、私が代表取締役に就任することが決まりました。
畳からLNGタンカーまで 業界の常識を覆す大胆な事業展開

ーー貴社の事業概要について、お聞かせください。
重松秀樹:
弊社の事業の根幹は、畳などの住宅資材を扱う総合商社であることに変わりはありません。しかし、正直なところ業界は斜陽産業です。ですから、事業が立ち行かなくなった同業他社を買収しています。そうすることで、売る努力をしなくても仕事が入ってくる仕組みを構築しているのです。守りの戦略です。
ーー事業を多角化されている背景についておうかがいできますか。
重松秀樹:
守るだけでなく攻めの戦略も同時に進めなければ、会社の未来はありません。社長に就任してから12年の間に、11の会社を新たにつくりました。例えば、大企業から経験豊富な人材を迎え入れ、「経営は俺がやるから、面白い仕事を探してこい」と指示しました。そうして始まったのが、LNG(液化天然ガス)タンカーの防熱工事です。最初は配送業務など、誰もやりたがらない仕事から引き受け、信頼を勝ち取りました。最終的に船体のウレタン加工という専門的な工事を受注するに至ったのです。畳屋がタンカーをやるとは、誰も思わなかったでしょう。また、銀座で「志良田」という日本料理店を経営するなど、飲食事業も手がけています。これらも全て多角化の一環です。
私は「山中産業」という一つの会社を大きくすることには、あまり興味がありません。むしろ、内容の良い小さな会社をたくさんつくり、それぞれが自立して稼ぐグループ経営を目指しています。その方がグループ全体での経営効率化や節税といったメリットも生まれます。事業ごとのリスクも分散できます。何より、各社のトップに裁量を与えることで、グループ全体の活力が生まれると考えています。
「好きか嫌いか」の裏にある徹底した実力主義
ーー貴社では、どのような人材が活躍されていますか。
重松秀樹:
私の人事考課の基本は、はっきり言って「好きか嫌いか」です。もちろん、これは単なる感情論ではありません。どんなに好ましくないタイプの人間でも、圧倒的な結果を出せば評価します。逆に、どんなに人柄が良くても、結果を出せない人間は評価できません。特に弊社のような中小企業では、大企業のように簡単には人の入れ替えができません。だからこそ、今いる社員をいかに育て、結果を出させるかに全力を注ぐのです。
ーー結果を正当に評価するための、具体的な制度はありますか。
重松秀樹:
今年から新しい人事制度を試験的に導入します。それは、メンバーが上司を評価するというものです。毎日一緒にいるメンバーが、上司のことを一番よく見ているからです。また、ボーナス制を廃止し、完全年俸制に切り替える予定です。全社員に給与順の番号をつけ、誰が見ても評価が明確に分かるようにします。成果を出した人間が報われる。それが当たり前の会社にしたいのです。
ーー今後、どのような組織を構築していきたいですか。
重松秀樹:
後を継ぐ可能性のある息子には常々「社長という役職にこだわるな」と言っています。「お前は会社のオーナーなのだから、自分よりも優れた人間がいるなら、その人に社長を任せなさい」と。私自身がそうであったように、トップにはその器量が求められます。今後は、各グループ会社をそれぞれの役員に任せたいです。その中で最も結果を出した人間を次のトップにすればいいと考えています。私は、社員一人ひとりが自分の持ち場で主役になれるような、強く、しなやかな企業グループを築き上げていきたいと考えています。
編集後記
重松社長の口から何度も発せられたのは、既成概念や権威に対する痛烈な批判だった。その言葉は、強烈な自負に裏打ちされている。それは、貧困という逆境から這い上がり、学歴や社歴ではなく、自らの才覚と行動力だけで道を切り拓いてきた者の自負だ。雪の中で死を覚悟したという壮絶な経験は、彼の経営哲学に「生」への執着とでも言うべき力強い輝きを与えていた。「破天荒」という言葉だけでは表現しきれない、緻密な戦略と人間味あふれるリーダーシップ。山中産業グループの飽くなき挑戦は、この異端の経営者がいる限り、これからも続いていくだろう。

重松秀樹/1956年、愛媛県出身。愛媛県立松山商業高等学校を卒業後、山中産業株式会社へ入社。40歳の時に取締役店長に就任。その後、常務取締役を経て、2006年、代表取締役に就任。事業領域を拡大し、建築・大工・左官など17品目にわたる建設業の国交大臣許可(特定)の取得や、東京の事業拠点を一級建築士事務所として登録するなど、事業拡大に邁進している。














