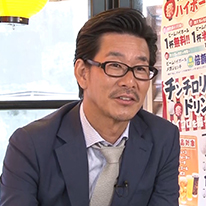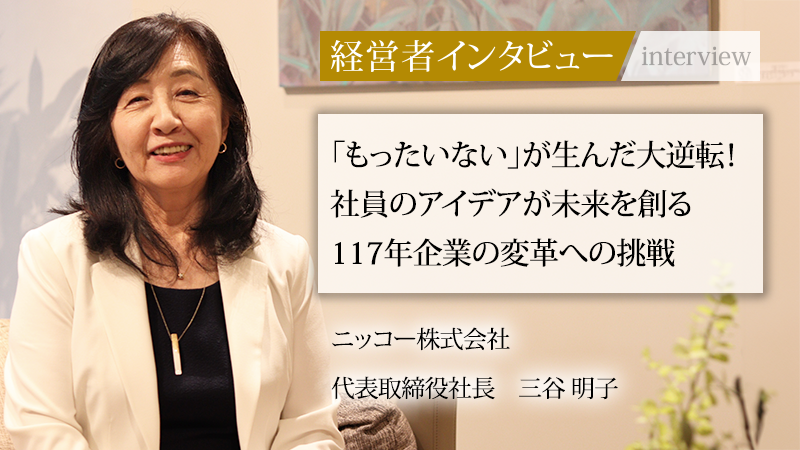
1908年の創業以来、117年の長きにわたり日本のものづくりを支えてきたニッコー株式会社。高品質な洋食器の製造で世界的に知られる一方、住宅環境機器や機能性セラミック商品など、時代のニーズに合わせて事業領域を拡大してきた。近年では「未来を素敵にする」というミッションを掲げ、廃棄物を肥料や新たな製品に生まれ変わらせるなど、サステナビリティへの取り組みも加速させている。同社の変革を牽引する代表取締役社長 三谷明子氏。今回は、異色の経歴から社長就任に至った経緯、社員のアイデアを起点とする独自の組織づくり、そして同社が見据える未来について話を聞いた。
育英会への思いが導いた経営への道
ーー三谷社長が経営にかかわるようになった経緯を教えてください。
三谷明子:
義父が設立した公益財団法人「三谷育英会」の代表になったことが大きな転機です。この育英会は、ニッコー株式会社(以下、ニッコー)を含む上場企業の株式配当金を原資に学生へ奨学金を給付しているため、会社の成長が不可欠でした。理事長として「ニッコーにもっと頑張ってもらわなくては」という思いが強くなり、株主として積極的に意見を述べるようになったのです。
その熱意が伝わったのか、やがて社外役員のお話をいただき、常勤役員を経て、最終的には赤字が続く厳しい状況下で、周囲からの強い後押しもあって大役を拝命いたしました。全く想定外の展開でした。
すべての変革は「知る」ことから事業部を超えた組織づくり
ーー社長に就任された際、まず何から取り組もうとお考えになりましたか。
三谷明子:
まず取り組むべきだと考えたのは、社内の風通しを良くすることでした。当時は、同じ会社でありながら事業部間の交流がほとんどなく、社員がお互いのことや自社の歴史をあまり知らない状況でした。特に、困難な時代の立て直しに尽力した社長である義父・三谷進三について知られていないのは違うと感じたのです。また、「良いものをつくっていれば売れるはずだ」という考えも根強く、品質の高さを社外に伝える努力が足りていない点も、もったいないと感じていました。
ーーそうした課題に対して、まず何から始められたのでしょうか。
三谷明子:
まずは、社内外へのブランディングを強化するため、専門部署(現在のブランド戦略本部)を立ち上げました。社内に対しては、イントラネットの全社的な活用を推進し、情報共有を徹底しました。というのも、当時は社員間の心理的な距離が非常に大きいという課題があったからです。たとえば、フロアを統合した際には、同じビルにいた社員同士が「初めまして」と挨拶を交わすほどでした。このままではいけないと強く感じ、懇親会などを企画して、物理的な距離だけでなく心理的な壁も取り払うことを目指したのです。
ーー社員が一体となるきっかけになった取り組みがあれば教えてください。
三谷明子:
創業111周年の際に実施した「111プロジェクト」は大きなきっかけになりました。各事業部から若手社員を集め、彼らの意見を中心に周年企画を進めたのです。このプロジェクトを通じて事業部を超えた交流が生まれ、社員の中から生まれた「1人の1歩は未来への大きな1歩」という合言葉は今も大切にされています。
現在は、部署を超えて同じ思いを持つ仲間が集い、改善活動や新規プロジェクトを発表する「ニッコームーブメント」という取り組みを毎年開催しており、社員の成長と組織の一体感につながっています。
品質の誇りと未来への挑戦 ニッコーの現在地

ーー創業117年の歴史で培われたニッコーの強みはどこにあるとお考えですか。
三谷明子:
創業以来、真摯に取り組んできた「品質」です。お客様のために良いものをお届けしたいという職人気質の社員が多く、その真面目な思いが当社の基盤を支えています。品質を追求し続けることが、社員のプライドであり、モチベーションにもなっています。また、心優しく素直な社員が多いことも、会社の大きな財産だと感じています。
ーー今後の事業について、どのようなビジョンをお持ちでしょうか。
三谷明子:
海外展開と、新商品・新技術の開発です。海外展開については、既に製品の輸出は行っていますが、よりスピーディーに対応するため、ベトナムのハノイに駐在員事務所を開設しました。これを足がかりに、浄化槽をはじめとする当社の製品をアジア、そして世界へと広げていきたいと考えています。コロナ禍で一度は落ち込みましたが、その間に社員の意識が大きく変わり、より付加価値の高いものづくりへと舵を切ったことも、今後の成長の糧になると確信しています。
社員の一言が生んだ革新 廃棄食器を「恵み」に変える逆転の発想
ーー貴社が大切にされている理念やミッションがあれば教えてください。
三谷明子:
私たちは200年企業を目指すにあたり、「未来を素敵にする」というミッションを定めました。これは、社会に存在し続けるために何が大切かを全社員で考え抜いた私たちの指針です。自分たちの仕事が未来につながっているという意識を共有することで、日々の仕事に誇りを持てるようになります。実際に、この言葉に共感して入社を決めてくれる若い方も増えています。
ーー「未来を素敵にする」ために、具体的にどのような活動をされているのでしょうか。
三谷明子:
たとえば、地球環境を守るための絵本『水の王さま』の制作もその一つです。また、食器メーカーならではの取り組みとして、廃棄する食器をリサイクルした「BONEARTH(ボナース)」という肥料も開発しました。
ーー食器から肥料とはユニークな取り組みですね。詳しくお聞かせいただけますか。
三谷明子:
もともとは、研究開発担当の「牛の骨の成分が入った食器は、肥料になるのでは」という一言がきっかけでした。社内で試すと効果が確認できたため、石川県立大学との共同研究でデータを集め、農林水産省から正式に認可を受けました。今ではこの肥料を使い、石川県内にお借りしている農場で、お米や野菜を育てています。割れた食器を捨てるのではなく、新たな恵みを生み出す。このサーキュラーエコノミーの実現も「未来を素敵にする」ための大切な取り組みです。
「やってみよう」が会社の力になる 誰もが主役の組織づくり
ーーこれからのニッコーを、どのような思いを持つ方々と一緒に創り上げていきたいですか。
三谷明子:
新卒、キャリアを問わず、多様な方に来ていただきたいです。住設環境機器の事業では必要な図面が読める方や、設計・施工に関心のある方、常にイノベーションを目指す製造業としては新商品や新技術開発においても地道な研究開発に取り組んでくださる理系の方などを求めています。もちろん、全く違う分野から新しいことに挑戦したいという方も大歓迎です。社員の紹介で入社される方も多く、会社のことを理解した上で来てくださるのは安心感があります。
ーー社員が誇りを持ち働ける会社として、ニッコーを今後どのように成長させていきたいですか。
三谷明子:
社員の生活を第一に考え、利益を上げてしっかりと還元できる会社にしていきたいです。誰もが安心して長く働ける環境を整え、毎日を楽しく過ごしてほしいと心から願っています。そのためにも、若い人たちが臆することなく「こんなことをやってみたい!」と自由にアイデアを出せる風土が不可欠です。「言っても無駄だ」ではなく、「やってみよう」という声が自然に生まれる。みんなのアイデアが会社の発展の土台となる。そんな、全員参加で未来を築いていける会社を目指していきます。
編集後記
経営への道は、野心ではなく「使命感」から始まった。元社長である義父への敬意、そしてニッコーの未来を担う社員への深い信頼。三谷社長が推し進める変革の原動力は、この2つに集約される。特に印象深いのは、社員一人ひとりの声に耳を傾け、そのアイデアを会社の力に変える、その真摯な姿勢だ。廃棄食器を肥料に変えた「BONEARTH」の物語は、社員の小さな気づきこそが会社の未来を創るという、同社の哲学を見事に映し出している。「未来を素敵にする」。その壮大なミッションは、社長が信じ、育む「やってみよう」という無数の声によって、着実に形作られていくのだろう。

三谷明子/1959年富山県生まれ。1982年東京外国語大学卒業。1984年有限会社北都代行社(現 株式会社アテナ)代表取締役社長に就任。2010年より三谷育英会等の代表理事長を務める。2011年にニッコー株式会社取締役、2014年同社常務取締役兼NIKKO CERAMICS, INC. 取締役会長に就任。2016年よりニッコー株式会社代表取締役社長に就任。