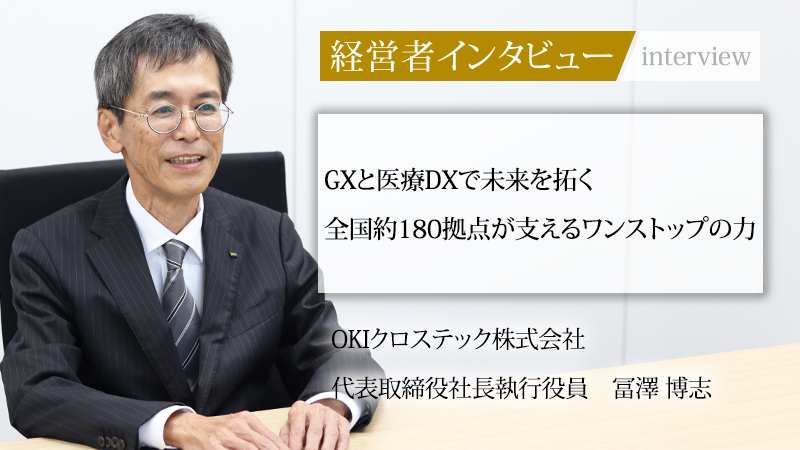
沖電気工業(OKI)グループの一員として、社会インフラを支えるOKIクロステック株式会社。同社は全国に約180の拠点を持ち、メカトロ機器(※1)の設置・保守からICTソリューション(※2)の提供までをワンストップで手掛ける。その強みを最大限に生かすのが、2024年に代表取締役社長執行役員に就任した冨澤博志氏だ。常に「なぜ」を問い続けるその姿勢は、いかにして育まれたのか。現場の声に耳を傾け、人手不足という課題に立ち向かう。新たな領域へ挑む同社の現在地と未来像について、話を伺った。
(※1)メカトロ機器:機械工学の「メカニクス」と電子工学の「エレクトロニクス」、さらに情報工学を組み合わせた総合技術を用いて設計・製造された機器。
(※2)ICTソリューション:情報通信技術(ICT)を活用して、企業や組織が抱える課題を解決するための方法や製品、サービス。
多様な経験が育んだ「疑問を持つ」姿勢
ーー社会人としてのキャリアはどのようにスタートされたのでしょうか。
冨澤博志:
大学でネットワークや通信プロトコルを学んでいたことから、沖電気工業株式会社(OKI)に入社しました。そして、通信部門で商品の開発に携わりました。当時、LAN(ローカルエリアネットワーク)の標準化が世界的に議論され始めた段階でした。私たちはすでに標準に近い製品をつくっていました。
しかし、「これからは標準ができてから製品をつくるのではなく、自ら標準をつくっていくべきだ」という思いが非常に強くなりました。そして、「私をアメリカに行かせてほしい」と会社に直談判しました。入社5年目にアメリカの大学へ留学し、研究生として通信の標準化を学びました。帰国後は、当時スタートアップだったシスコシステムズ社と日本向けの共同開発に6年ほど携わっています。
その後も情報システム事業部でCTI(※3)分野の企画・マーケティングを経験しました。さらに、本社の経営企画、ATM事業の企画、ブラジルでのM&Aと駐在など、さまざまな部署を経験しています。最終的には常務執行役員も務めました。
同じOKIグループ内でも、異なるチームへ異動すると言葉やプロセスが違います。それがとても新鮮でした。「なぜこうなっているのだろう」と常に疑問を持つ習慣が身につきました。それが一番の収穫だと考えています。
(※3)CTI(コンピューターテレフォニーインテグレーション):コンピューターと電話・FAXを統合し、連携させるシステム。
現場の声と向き合い会社の強みを未来へつなぐ
ーー貴社代表に就任した経緯をおうかがいできますか。
冨澤博志:
エンタープライズソリューション事業部長として中期計画に取り組んでいた折、社長就任の打診を受けました。計画を完遂したい思いもありましたが、「他にいない」という言葉が決め手となり、お引き受けしました。
就任後の3カ月間は事業内容の理解に注力し、社員の声に真摯に耳を傾けました。そうした活動の過程で、この会社の持つ圧倒的な強みを改めて認識した次第です。全国約180の拠点網と3,000人以上の社員がいます。その力で、電気工事から保守運用までワンストップで対応できる。まさに現場で社会を支えている会社だと実感しました。
ーー現場の課題と、それに対する具体的な取り組みをお聞かせください。
冨澤博志:
現場から出てきた困りごとや要望には、必ず何かしらのアクションを起こすことを大事にしています。「話を聞くだけで何も変わらない」と思われては意味がないからです。
ヒアリングの結果、どの部門からも共通して挙がったのが人手不足の問題です。これには「業務効率化」と「採用強化」の両面から対策を進めています。業務効率化については、各部門から集まった約130の要望に応えるべく、AIやRPA(※4)を専門に扱う「AI・RPA推進部」を新設しました。採用強化の面では、ご家族の意向なども踏まえた「限定勤務地採用」を導入。結果として応募者が大幅に増加し、その半数がこの制度の利用を希望しています。
(※4)RPA(ロボティックプロセスオートメーション):ソフトウェアロボット(ボット)が、人間が行っていたパソコン上の定型作業を自動化する技術。
ワンストップサービスを軸に社会課題の解決に挑む

ーー貴社の事業内容と強みについて教えてください。
冨澤博志:
事業の柱は二つあります。一つはメカトロ機器の設置・保守を行う「サポートサービス事業」。もう一つは、ビルの電気工事やICTソリューションを提供する「SI事業」です。最大の強みは、すべて自社で完結できる点です。ネットワーク設計からサーバー保守まで、通常は複数社に依頼する業務をワンストップで提供しています。このワンストップサービスが、他社との明確な差別化ポイントになっています。
ーーOKIグループの中で、貴社はどのような役割を担っていますか。
冨澤博志:
OKIグループでは、「中期経営計画2025」を策定しました。そこでは、「社会の大丈夫をつくっていく。」というキーメッセージを掲げています。私たちは、その「大丈夫」を品質とスピードで担保します。そして継続させていく重要な役割を担っていると考えています。
それと同時に、社員一人ひとりが自信と会社への誇りを持って働ける会社にしていきたい。その思いを込めて、新しいビジョンを策定しているところです。10年後を見据え、次世代を担う課長クラスの社員たちと共に進めています。
ーー今後の成長戦略として、特に注力している分野はありますか。
冨澤博志:
GX(※5)と医療DXの二つを成長領域と定めています。GXでは、軽量なソーラーパネルやEV充電器の設置・保守などを提供します。弊社の強みである電気工事の技術と組み合わせ、ワンストップで実現しています。医療DXでは、全国47都道府県で取得した医療機器の修理資格を活かします。病院内の多様な機器の保守を一括で請け負い、病院全体のDXを支援していきたいと考えています。
(※5)GX(グリーントランスフォーメーション):温室効果ガスの排出削減と経済成長の両立を目指すため、化石燃料中心の社会・経済・産業構造を、再生可能エネルギー中心の持続可能な構造へ抜本的に転換する取り組み。
社員の成長が会社の未来をつくる
ーー社員の成長を後押しするために、どのような取り組みをされていますか。
冨澤博志:
社員のスキルを可視化する「スキルアセスメント」(※6)を導入しました。これにより、個々が次に何を学ぶべきかが明確になります。スキルが向上すれば処遇も上がるとわかるように、制度も見直しています。また、新たなシステムの開発にも着手しました。過去の膨大な障害対応データをAIに学習させ、最適な対処法をサポートするものです。これにより、経験の浅い社員でも効率的に学び、成長できる環境を整えています。
(※6)スキルアセスメント:個人が持つスキルや知識を、採用、配置、人材育成などの目的に合わせて客観的に評価・可視化する手法。
ーー最後に、この記事の読者に向けてメッセージをお願いします。
冨澤博志:
私たちは、ワンストップで手掛ける技術力と全国ネットワークを活かします。そして、GXや医療DXといった社会課題の解決に貢献しています。自分たちの持つ力を通じて、サステナブルな社会の「大丈夫」を提供していく。この思いに共感し、共に挑戦してくださる方をお待ちしています。
編集後記
開発者としてキャリアをスタートし、企画、海外事業、そして経営のトップへ。冨澤氏の多彩な経歴の根底には、常に「なぜ」と問い続ける真摯な姿勢がある。その探究心は今、新たなフィールドで現場の課題を深く掘り下げ、具体的な解決策へと結実している。全国に広がる社員の声に耳を傾ける。そしてAIの活用や採用制度の改革といった大胆な施策で応えている。その姿は社会インフラを支えるだけではない。社員の働きがいをも創造しようとする、強い意志の表れである。同社の挑戦は、まだ始まったばかりだ。

冨澤博志/1963年群馬県生まれ。1985年東京大学工学部を卒業後、沖電気工業株式会社に入社。執行役員、上席執行役員を経て、2023年には常務執行役員およびエンタープライズソリューション事業部長を務める。2024年4月、OKIクロステック株式会社の代表取締役社長執行役員に就任。














