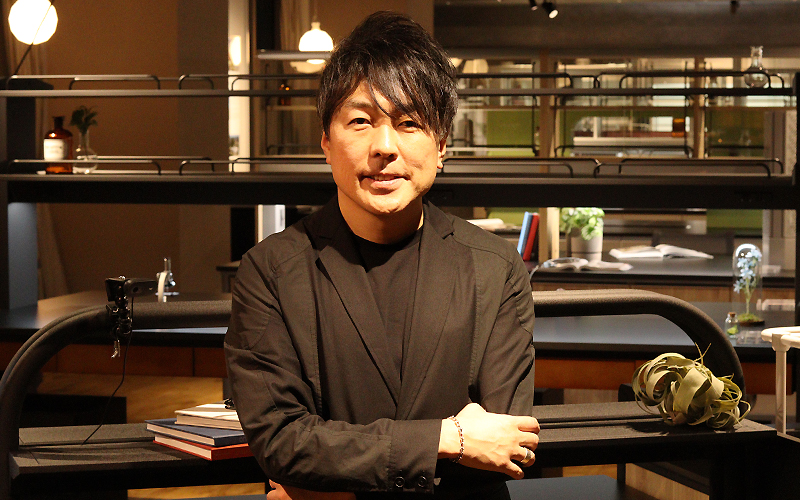トヨタ自動車をはじめとする自動車の鋳物部品を手がけるアイシン高丘グループ。その一員であるアイシン新和株式会社は、モデルの古い車種に必要となる補給部品など、少量多品種の生産を得意とし、グループ内で唯一無二の役割を担う。同社を率いるのは、豊富な海外経験を持つ代表取締役社長の安藤英明氏だ。エンジニアとしてキャリアを始め、海外でマネジメントの壁にぶつかった経験から「現場の技能員が能力を発揮できる環境をつくること」を自らの仕事と語る。安藤氏に、これまでの歩みと独自の会社づくりについてうかがった。
海外で培った現場主義 原点はトヨタ生産方式の面白さ
ーーどのような経緯で、ものづくりの道へ進まれたのでしょうか。
安藤英明:
大学では機械工学を専攻していましたが、当時は「この知識を生かして会社で何をしたいか」という明確な動機はありませんでした。入社後に生産管理の仕事へ就き、トヨタ生産方式を学ぶ中で、トヨタグループのものづくりの面白さに気づいたのです。若手の頃は、機械設備の保守や生産技術、トヨタ生産方式の推進という3つの部署を行き来する形で経験を積みました。この頃から現場に軸足を置き、技能員と一緒になって働くことに楽しさを感じていました。
ーー社長のキャリアにおける転換点についてお聞かせください。
安藤英明:
35歳でアメリカの子会社へ出向し、機械加工工場の工場長を務めた経験が大きな転換点です。それまではマネジメントの経験が全くなく、赴任後1年間はサラリーマン人生で最も厳しい時期でした。日本では当たり前の「叱って伸ばす」文化や「言わなくても分かる」という感覚が全く通用しません。
たとえば、現地の従業員に指示をしても「I understand(あなたの言ったことは分かった)」と言うだけで、誰も動いてくれないのです。試行錯誤の末、「I will do it(私がやります)」という言葉を引き出して、初めて人は動いてくれるのだと気づきました。そこで学んだのは、まず相手を褒めること、そして自分の意思を明確に伝えることの大切さでした。この経験が私のマネジメントスタイルの基礎となりました。
ーー海外でのご経験で、特に印象に残っていることはありますか。
安藤英明:
現地法人の社長時代に経験したリーマン・ショックです。仕事が激減し、週に2日分しか稼働できない状況に陥りました。しかし、私は「絶対に解雇はしない」と全社員に約束し、あらゆる手段を講じて彼らの生活を守り抜きました。その結果、事態が収束した際に社員から感謝の言葉をもらい、人を大切にする経営の重要性を改めて心に刻みました。
ものづくりの主役は、現場で働く技能員です。彼らが持つ能力を最大限に発揮できる状態をつくることが、私の最も重要な仕事だと考えています。
唯一無二の存在へ 少量多品種生産を強みに変える挑戦

ーー貴社の事業の強みや、グループ内での役割を教えてください。
安藤英明:
弊社の最大の特徴は、少量多品種の生産に対応できる点です。たとえば、自動車のモデルが古くなった際に必要となる補給部品などを手がけています。かつては、多い時で6000品目もの部品を生産しており、この多品種生産が経営の足かせとなっていた時期もありました。しかし今では、これほど多くの品目に対応できる会社は他にないと捉え、唯一無二の強みとして磨きをかけています。
現在主流の量産品でしっかりと利益を確保しつつ、少量品や補給品の生産レベルをさらに引き上げ、お客様から「アイシン新和があってよかった」と言われる存在を目指しています。
ーー社長に就任された当時、会社はどのような状況でしたか。
安藤英明:
私が就任した当初、会社には少し閉鎖的で、時代に合わないと感じる文化が残っていました。そこでまず着手したのが、社内や親会社、グループ会社とのコミュニケーションの活性化です。社員が「外の世界を見たい」と言えば、積極的に機会を創出しました。外の進んだ事例や異なる考え方に触れることで、社員の意識は変わります。良いものは真似し、さらに自分たちのものとして昇華させていく。そうした経験を通じて、新たな取り組みが生まれることを期待しています。
ーー今後の事業展望について、どのようにお考えですか。
安藤英明:
自動車業界は電動化の流れにあります。一方で、トヨタ自動車が開発を進める水素エンジンのように、既存の内燃機関の技術が生きる可能性も残されています。将来がどうなるか分からないからこそ、まずは足元を固めることが重要です。量産品では圧倒的な競争力を維持し、補給部品の分野ではさらに強みを発揮していきます。将来的には、産業用ロボットの部品など、自動車以外の分野への展開も視野に入れながら、どんな変化にも対応できる強い会社をつくっていきたいと考えています。
技能継承という重要課題 未来を担う人材育成への注力
ーー人材育成において、特に注力されていることは何ですか。
安藤英明:
団塊の世代が退職し、これまで培われてきた技能の継承が大きな課題です。そのため、社員教育にはこれまで以上に時間とお金をかけています。教育カリキュラムを全面的に見直し、社外の講習や資格取得への金銭的サポートも強化しました。
また、親会社やグループ会社との人材交流も活発に行っています。さらに、地域のつながりを活かし、異業種の優れた取り組みを学ぶ機会も設けるなど、社内外の知見を積極的に取り入れています。
ーー採用活動において、どのような人物を求めていらっしゃいますか。
安藤英明:
何事にも興味を持って、前向きに挑戦できる方を求めています。最初から高いスキルは必要ありません。大切なのは、知らないことを素直に学び、自分なりに考えて行動しようとする姿勢です。私たちは、一人ひとりが自分を磨き、上を目指したいと思えるような集団をつくりたい。会社がその成長をサポートすることで、会社も自然と強くなっていくと信じています。
ーー社員の自主性を引き出すために、何か工夫されていることはありますか。
安藤英明:
現場の従業員一人ひとりの行動に光を当てる「あっぱれ活動」という取り組みを行っています。落ちているゴミを拾う、緩んだネジを締め直すといった日々の小さな善行や改善提案を全社でたたえる活動です。もう一つは、社員の意見を直接聞く「生声(なまごえ)活動」です。当初は不平不満が多かったのですが、今では感謝の言葉も届くようになりました。これらを通じて、指示待ちの意識ではなく、自分たちの職場を自分たちで良くしようという雰囲気が生まれ、現場は大きく変わりました。
ーー最後に、読者へのメッセージをお願いします。
安藤英明:
ものづくりの会社は、全て「人」で成り立っています。人を大切にできなければ、会社は生き残れません。そして、私たちの先輩たちが築き上げてきた良い仕事や文化を、次の世代へとつないでいくことが重要な役割だと強く感じています。「温故知新」という言葉がありますが、私は学生時代、この言葉の意味を深く理解していませんでした。しかし、年齢を重ねた今、その重みを実感しています。まさに古きを学び、そこから新しい価値を生み出していく。そうした姿勢で、これからも会社を経営していきたいです。
編集後記
アメリカでの工場長時代、文化の違いを乗り越え「人を動かすための秘訣」を体得した安藤氏。その経験は「ものづくりの主役は現場の技能員」という揺るぎない信念へと昇華されている。同氏が推進する「あっぱれ活動」は、社員一人ひとりの主体性を引き出し、組織に活気をもたらす施策だ。人を育て、その力を最大限に引き出すことが会社の成長につながるというものづくりの原点と未来への確かなビジョンが示されている。

安藤英明/1964年4月愛知県瀬戸市出身。名城大学理工学部卒業。1988年アイシン高丘株式会社に入社、2012年常務役員、2017年専務役員、米国現地法人CEOを兼務(合計16年間の米国駐在歴)。2020年アイシン新和株式会社の監査役、顧問を経て、2021年6月から代表取締役社長。現地・現物・現任をモットーにものづくりの現場に軸足を置いた経営を心掛けている。