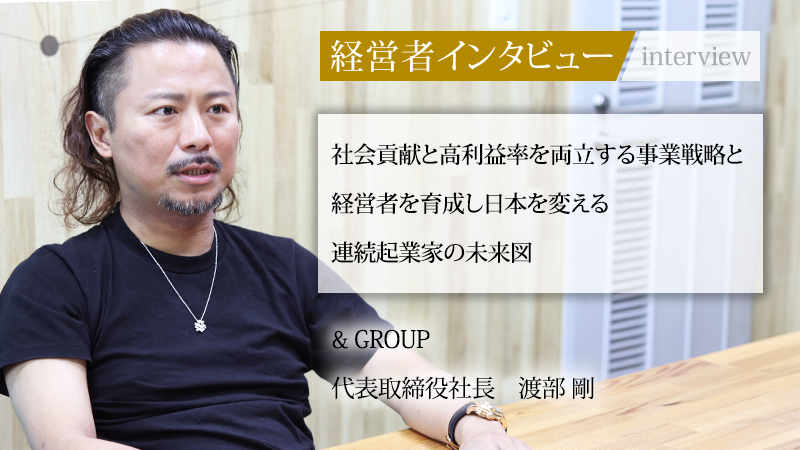
連続起業家として多彩な事業を展開する& GROUP。同社は、事業モデルを掛け合わせ、新たな価値創出を追求している企業だ。その根底には、代表取締役社長、渡部剛氏の独自の理念が存在する。同氏は、幼少期を海外で過ごし、大手メーカーでの勤務経験を持つ。そして、人口上位2%のIQを持つMENSAの会員であり、ゲームで日本1位にまでなったという異色の経歴を持つ人物だ。社会課題の解決をも見据え、常に時代の潮流を読み解きながら事業を創造し続ける渡部氏に、その思考の源泉と、次世代の経営者育成にかける思いを聞いた。
大企業ソニーで経験した事業家としての基礎
ーーキャリアの原点についてお聞かせください。
渡部剛:
父が商社に勤めていたため、幼少期はブラジルやインドで過ごしました。特にインドでの経験は大きく、貧困が原因で優秀な人々が命を落とす現実を目の当たりにしました。この経験が私の人生観を形成しました。中学校から日本に戻り、学生時代には珍しい時計や靴の転売ビジネスを始めます。これは、お小遣いが少なかったため、自ら稼ぐ道を模索したのがきっかけです。
ーー将来、ご自身で事業を立ち上げたいというお考えは、当初からあったのでしょうか
渡部剛:
中学生の頃からビジネスを手がけていたこともあり、起業するつもりでした。そのため、ファーストキャリアでは、ベンチャー気質が残る大企業で経験を積もうと考えました。ソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)に入社したのはそのためです。周りには卒業後すぐに起業する仲間もいました。しかし、彼らが下請けの仕事に終始する姿を見て、まずは安定した基盤の上で人脈を築く方が、より合理的だと判断したのです。
ーーソニーでの経験は、現在の事業にどう活きていますか。
渡部剛:
ソニーには6年間在籍しました。営業や「VAIO」のマーケティング、エリアマネージャーなどを経験した後、最後に新規事業開発部門に配属されました。そこではリソースが限られていました。そのため、法務や会計の基礎知識からシステム開発、広告宣伝まで、事業立ち上げにかかわる一連の業務をすべて経験できました。この時の経験が、グループ全体の事業を自ら細部まで把握できる、現在の経営スタイルにつながっています。
パターン認識とゲーム理論に基づく戦略的思考
ーー「& GROUP」という社名にはどのような思いが込められていますか。
渡部剛:
「AかBか」ではなく「AもBも」という発想で、さまざまな事業モデルを掛け合わせて、シナジーを生み出したいという思いを込めています。私は事業モデルそのものへの興味が強いです。たとえば、「Web3とAIを掛け合わせたら何かできないか」といったように考えています。時代の潮流や、まだ誰も手をつけていない領域に対し、最適なモデルを当てはめる形で事業を創造しています。
ーー事業の着想はどこから得ているのですか。
渡部剛:
元来、パターン認識やフレームワークで思考を組み立てるゲームが好きで、それが得意分野でもあります。どうすれば勝てるかという勝利のパターンを見つけ、それを他の分野に応用できないかと常に考えています。他の経営者からビジネスモデルについて伺うのも好きです。その話からモデルの作り方を学び、実行に移すプロセスを楽しんでいます。
新規事業を始める際の判断基準があります。それは、人を傷つけるような事業は絶対に手がけない点です。そのうえで、「時代の潮流に合っているか」「拡張性」「継続性」「競合との差別化が可能か」という4つの点を必ず考慮します。特に利益率を重視しています。これらの要素のいずれか、または複数で圧倒的な強みを発揮し、差別化が可能だと判断した場合に参入します。
高収益と社会貢献を両立する4つの事業領域

ーー現在、貴社が展開する事業について教えてください。
渡部剛:
大きく4つの事業ドメインに分かれています。
1つ目は、経営者向けのAIサービスを開発する「AIテクノロジー事業」です。この事業では、弊社の経営ノウハウを学習させたAIが、中小企業のCFOやCOOの役割を70点レベルで代行することを目指します。特に高コストで優秀な幹部メンバーを雇えない社長向けに、利益率70%の高収益なビジネスモデルを構築中です。
2つ目は「ライジング事業」です。熱意ある若者たちが、配送や解体業などの現場でしっかりと稼ぎ、将来的に地元で独立できるような循環型の仕組みづくりを目指しています。仕組みを徹底することで、特別なスキルがない若者でも月収100万円以上を稼げる構造を作っています。
3つ目は「D2C(※1)事業」です。特に強みを持つ不妊治療関連の領域や、ストーリー性のある伝統工芸品、農産物などを自分たちの力で直接お客様に届ける仕組みを構築しています。これは、流通コストを削減し、生産者の取り分を増やしつつ、高い利益率を確保する戦略です。
4つ目が「社会課題解決を目的とする事業」です。たとえば、ペットフード事業の利益で犬猫の避妊手術を行い、殺処分ゼロを目指す構想があります。また、WHOが推奨するナマズの完全養殖技術を開発し、この設備を貧困地域の学校に提供するプロジェクトも進めています。このプロジェクトは、学校がナマズを販売することで教育資金を自給自足できる仕組みの構築を目的としています。
(※1)D2C:「Direct to Consumer」の略で、企業が企画・製造した商品を、卸売業者や小売店を介さずに、自社が運営するECサイトなどで消費者に直接販売するビジネスモデル
ーー事業を展開するにあたり、大切にされている思いはありますか。
渡部剛:
20代30代は人生を楽しみ、さまざまな人に可能性を与えることが自分の中のテーマでした。私も40代になり、これまでに得た能力や資産を社会に還元・循環させたいという思いが強くなりました。社会課題の解決と、自分たちで収益を上げる仕組みを両立させ、それを回し続けることで、少しでも世界が面白くなればと考えています。
起業家志望を絶対条件とする独自の採用基準
ーー採用基準に「起業したい人」を挙げているのはなぜですか。
渡部剛:
起業家を目指す人材は言語化能力が高く、事業への理解が早く、本質的な議論ができるからです。弊社では新卒採用を始めて7期目になりますが、「起業家志望であること」を絶対条件としています。実際に、新卒1年目の夏から4億円規模の会社の社長を任せている社員もいます。
その他にも、素直で、周囲から信頼され、そして尖っていることを重視しています。素直さは成長に不可欠です。組織で問題を起こさないためにも、信頼される人物であることは重要です。そして「尖っている」というのは、地頭の良さに加え、行動力や突破力がある人材を指します。
ーー新卒社員にはどのような育成環境を提供していますか。
渡部剛:
日本でもトップクラスの起業家育成環境だと自負しています。ソニー時代の同期で、GAFAM(※2)などで部長職を務める優秀なビジネスパーソンたちに研修を依頼し、実践的なスキルを直接学べる機会を設けています。ビジネススキルは、その道のプロから学ぶのが一番ですから。
(※2)GAFAM:アメリカの巨大IT企業であるGoogle、Apple、Facebook(現Meta Platforms)、Amazon、Microsoftの頭文字をとったもの。
後継者育成を最重要視する経営者の信念
ーー経営者として最も大切にされていることは何ですか。
渡部剛:
後継者の育成です。お世話になった先輩経営者から「社長の一番大事な仕事は、自分の首を切るタイミングを見極めることだ」と言われた言葉が心に残っています。どんなに優秀な経営者でも、いつかは組織の成長を妨げる存在になりかねません。だからこそ、会社を創った日から、自分が組織の害になる前に引退できる準備を常に考えています。
ーー3年から5年後の会社の理想像を教えてください。
渡部剛:
現在進めている事業が軌道に乗れば、売上100億円、利益率30〜40%は達成できると考えています。
また、若手経営者コミュニティの仲間との連携も進めています。弊社の事業が伸びた後、彼らの会社をグループに迎え入れる構想があります。彼らが得意な分野でCOOやCFOを担ってくれれば、純粋な資金を提供し、さらに面白いことを一緒に実行できます。その仕組みをつくり終えたら、私は引退するつもりです。仲間が掲げる「日本を変える」という大きな目標があります。その目標に対し、資金面や組織力で貢献できる状態が私の理想です。
ーー最後に、この記事の読者である若者へメッセージをお願いします。
渡部剛:
起業を志す学生の皆さんにこそ、私たちの門を叩いてほしいです。誰かが創ったビジョンに共感して会社に入る、という考え方は持たないでください。そうではなく、自分の人生を生きることを最優先にしてほしいのです。弊社は個人の頑張りが、結果的に組織のためになるよう設計しています。社長という経験を若いうちから積める、面白い環境です。この環境を私だけが独占するのはもったいないと考えています。興味がある方は、ぜひ挑戦しに来てください。
編集後記
渡部氏は、まさに「経営をゲームのように攻略する」異色の起業家だ。連続起業家としての強さは、その異色のキャリアパスに裏打ちされている。そして同氏の挑戦は、単なるビジネスではない。それは、「自分の人生を生き抜きたい」と願う次世代の挑戦者に、社長という最短ルートを示す羅針盤だ。同社は、自分で人生を動かしたいという強い意志を持つ者にとって、最高の試練の場となるだろう。

渡部剛/1980年ブラジル サルバドール生まれ。1992年より青山学院中等部、高等部、大学 機械工学、大学院機械工学専攻。2005年よりソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)入社、2011年に複数社起業の後、2025年に再編し、&グループ化。X(旧Twitter)はこちら














