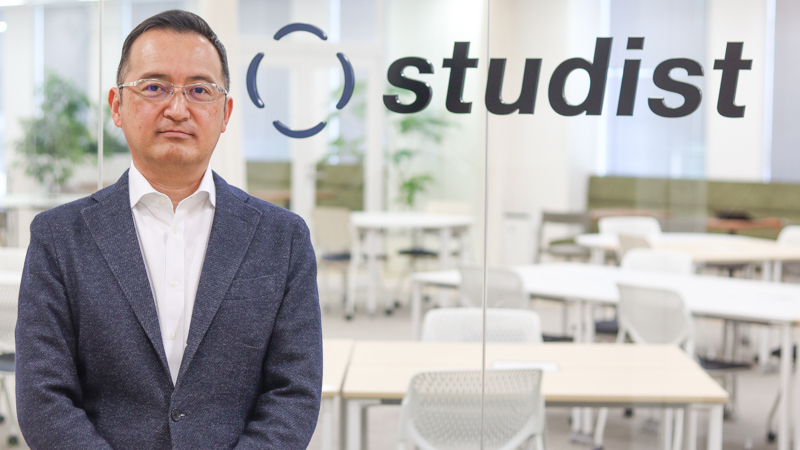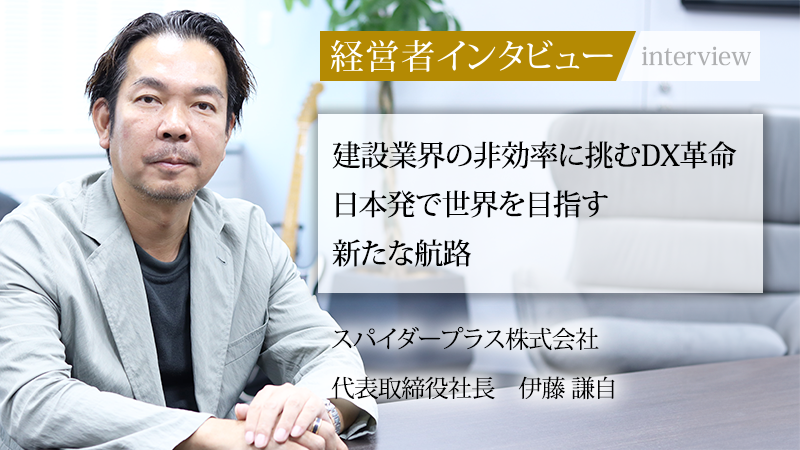
建設現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)を力強く牽引するスパイダープラス株式会社。同社が開発した図面管理・情報共有システムは、業界の非効率を解消する革新的なツールとして、多くのゼネコン(総合建設業者)や専門工事業者に導入されている。同社を率いるのは代表の伊藤謙自氏だ。今回は、逆境を乗り越えた秘話、そして世界を目指す未来像まで、その情熱と経営論に迫る。
ものづくりへの情熱と探求心 後の経営者像を形成した原体験
ーー社長のこれまでのご経歴と、現在の経営との繋がりについてお聞かせください。
伊藤謙自:
小学生の頃は漫画を描いたり、本物に近いクオリティにこだわってプラモデルを作ったりと、クリエイティブなことが好きでした。
こうした創作活動は、一見すると経営と無関係に思えるかもしれません。しかし、後に私が身を置くIT業界では、UI(画面のデザイン)やUX(使いやすさ)といった感覚が非常に重要です。見た瞬間に「これは使いづらそうだ」と直感的にわかる力は、この頃に養われたと感じています。
中学の後半からはギターに夢中になり、高校の3年間はバンド活動に明け暮れました。リーダー気質だったのでメンバー集めからライブの企画、チケット制作まで自分で行いました。役割分担して一つの目標に向かうバンド活動は、会社経営に通じる貴重な経験でした。この頃から自然と経営者視点が身につき、「誰よりも早く良いものを作って仕掛ければ、先行者利益が取れる」という感覚も養われたように思います。
社長の夢を追い東京へ 未経験から拓いた建設業界での挑戦
ーー社会人としてのキャリアはどのようにスタートされたのでしょうか。
伊藤謙自:
高校時代はバンド活動に夢中で、大学進学という選択肢はありませんでした。先生に「将来どうするのか」と聞かれたときも、「東京へ行って社長になるので、大学へ行く4年間がもったいないです」と答えたくらいです。「何の社長になるんだ」と聞かれても、「行ってみてから考えます」と。とにかく東京へ行きたい気持ちが強かったです。
最終的に福利厚生の条件を重視して就職先を決め、建設資材を扱う会社に入社しました。今思えば、社長になる道は、この時から決まっていたのかもしれません。
ーーそこから独立に至るまでの道のりについてお聞かせください。
伊藤謙自:
最初の会社で断熱材の販売を2年半経験した後、取引先の工事会社の社長から「うちに来ないか?」と誘っていただき、転職しました。そこは、サブコン(専門工事業者)から仕事を受ける保温断熱工事の会社で、見積もりの作成、職人の手配、現場の工程管理といった実務を1年ほどで一通り覚えました。その後、「独立するには現場の職人仕事もできなければならない」と考え、腕利きの親方の下で1年間、職人として修業を積みました。
タブレット誕生が示した未来 建設DX事業へと導いた運命の転機

ーーなぜ現在の事業を立ち上げようと思われたのですか。
伊藤謙自:
職人として働いた保温断熱工事は、まるでプラモデル作りのようで本当に楽しく、朝早くから夜遅くまで、時間を忘れて働けるほどでした。「好きこそものの上手なれ」の言葉通り、仕事は「楽しい」と感じなければ100%の力は発揮できない、というのが私の持論です。
その保温断熱工事も、管理者になると次第に仕事が単調に感じられるようになりました。海外の新しい断熱材の施工を手掛けることで一時的に情熱を取り戻したものの、長くは続きませんでした。
ちょうどその頃、同級生のエンジニアと「何かIT関連の事業をやりたい」と話していた時に、初代iPadが登場したのです。「これで世の中が変わる」と直感しました。特に、紙の図面が膨大にある建設業界は、ペーパーレス化するだけで大幅な効率化が見込めると考えました。経営者の家系で育った私にとって、独立はごく自然な選択でした。
ーー貴社サービスはどのようにして生まれたのでしょうか。
伊藤謙自:
最初は、自分たちの会社で使うために、保温断熱工事の積算(※1)を効率化するシステムを、インターネット経由で利用できるクラウドベースで開発しました。これを外部にも販売しようと考えましたが、保温断熱業界だけでは市場が小さすぎると判断し、断念しました。
そんな折、ある大手サブコンの幹部会でプレゼンする機会を得て、そこで社長直下のIT推進室の方から声をかけられました。「そのシステムをベースに、サブコン業界で使えるものにブラッシュアップできないか」と。この提案がきっかけとなり、現在の「SPIDERPLUS(スパイダープラス)」へと進化しました。
(※1)積算:工事に必要な材料や人件費などを事前に計算し、工事全体の費用を算出すること。
クラウドへの不信と資金難 逆風を乗り越えた信頼の力
ーー事業の立ち上げ期において、特に大きな壁は何でしたか。
伊藤謙自:
大きな壁は2つありました。1つはクラウドへの不信感です。「おもちゃのようなものに、顧客から預かった大切な図面データを預けられるか」と、情報漏洩を懸念する声がほとんどでした。風向きが変わったのは、事業開始から5年ほど経ち、スーパーゼネコン各社がクラウド活用を公表し始めてからです。これを機に「大手が良いなら」という流れができ、顧客が爆発的に増えました。
もう1つの壁が資金調達です。副社長とベンチャーキャピタル(VC、※2)を駆けずり回りましたが、全く相手にされませんでした。八方塞がりの中、建設業時代にお世話になった社長に「企業価値30億円で5000万円出資してほしい」とお願いしたところ、その場で「いいよ」と即決してくださったのです。
後日理由を尋ねると、「お前は言ったことを必ずやり遂げる男だと分かっていたからだ」と。過去の仕事で築いた信頼関係が、未来への投資に繋がったのだと感じています。この最初の出資がきっかけとなり、状況は一変。あれだけ相手にしてくれなかったVCが次々に集まり、事業を軌道に乗せることができました。
(※2)ベンチャーキャピタル(VC):未上場の新興企業に出資する投資会社や投資ファンドのこと。
100年企業を目指す次の一手 社員の創造性が育む未来の事業
ーー今後の事業展開についてお聞かせください。
伊藤謙自:
国内では、既存顧客との関係を深めることと、パートナー企業との連携による地方の中小企業の開拓を進めていきます。そして今、最も力を注いでいるのが海外展開です。日本発のBtoB SaaS(法人向けクラウドサービス)で海外で成功した企業は、まだほとんどありません。
真のグローバル企業になるには、日系企業だけでなく、現地のローカル企業に導入していただくことが絶対条件です。幸い、現在複数の国でトライアルが始まっており、反応は非常に良好で、海外でも十分に受け入れられる手応えを感じています。
ーー事業の持続的な成長のために、どのような取り組みが必要だと考えていますか。
伊藤謙自:
単一の製品だけで100年続く企業はないと考えています。そこで最近、週に1時間、就業時間内にクリエイティブな活動をしてもらう社内プログラムを始めました。エンジニアがシステムを試作したり、デザイナーがキャラクターを考えたりと、職種を問わずアイデアを出し合います。
社員300人がそれぞれの「好き」や「得意」からアイデアを出し合えば、きっと面白いものが生まれ、次の事業の柱に育っていくはずです。こうした活動が会社に新たな活気を生み、未来を創造していくと信じています。
編集後記
幼少期のプラモデル作りから高校時代のバンド活動、そして建設業界での職人経験まで、伊藤氏のキャリアは「楽しむ」という一貫した軸に貫かれている。その純粋な探求心と情熱が、業界の常識を覆すサービスを生み出す原動力となったのだ。「週に1度のクリエイティブタイム」という新たな試みも、社員一人ひとりが仕事を楽しむことを起点に、次の100年を創ろうという思いの表れに他ならない。同社の挑戦は、これからも多くの人々を巻き込みながら続いていくだろう。

伊藤謙自/1973年生まれ。北海道紋別市で育つ。高校卒業後に上京し建設資材商社営業、熱絶縁工事の施工管理を経て、1997年に伊藤工業を創業。建設業界のIT化の遅れを自ら体感し、タブレット登場とともに建設業をターゲットにしたIT事業を開始。ものづくりの原点は子ども時代のガンプラ作り。建設現場の目線を常に忘れず、プロダクト開発のモットーは「俺でも分かるように作れ」。