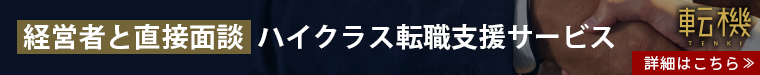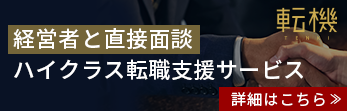予防領域に特化したヘルステックベンチャーとして2012年に誕生した株式会社FiNC。同社で事業立ち上げや業務提携を主導するのが、同社代表取締役室副室長の加藤真平氏だ。入社4年目にして『社長の右腕』と評された加藤氏の持つ、事業家としての強みに迫る。
研究に没頭した高専・大学時代

―ご幼少の頃からモノづくりに興味がおありだったのでしょうか?
加藤 真平:
はい。父は、群馬で木工家具を量産する機械の設計・製造や量産ラインの構築を行う企業を経営していました。 実家の会社で油のついた作業着を着て頑固一徹で働く父が、朝から晩まで働き機械を創り上げる姿が強く印象に残っており、私の中学卒業後の進路選択に影響を大きく与えたのだと思います。
―中学卒業後はどういった進路を選択されたのでしょうか?
加藤 真平:
高等専門学校・機械工学科に入学をしました。 高専では一般教養よりも技術の専門教科を早期に学び研究を開始しますが、私は自動車エンジンの燃費向上についての研究を行いました。人間の体のように複雑な構造のエンジンに関心を持ち、大学では宇宙・航空系の研究室で、ロケットエンジンの研究に携わりました。
研究自体の楽しさや厳しさも新鮮でしたが、それ以上に研究室の教授が何より私自身に影響を与えてくれました。私の研究室の教授は分からないことがあれば「そこはわからないから一緒に勉強しようか」と恥じることなく専門性の壁を臆せず飛び越え、学生と対等に議論をする方で、そんな教授の「向上心」や「なんでもやったる感」が、今の私の骨格を作り上げたのだと思います。
その後、企業で研究することを選び新卒でミシュランに入社をしました。私の上司はフランス人でしたが、大変に自由にやらせていただき働きやすく、研究やコンピュータシミュレーションで小さな成果が出始めました。一方で、当時私が身を置いていた製造業は中国企業や韓国企業の猛追を受け、日本の製造業の凋落がメディアで騒がれていた時期で、気持ち的には釈然とせず、なんとなく自分たちのような製造業の技術者がそれまで一生懸命やってきたことが否定されたような気がしていました。
そんな頃に、米国ではテスラが凄まじい勢いで成長をしていることを知りました。自動車・二輪と言えば日本でしょ、電動化もその気になれば日本の方が強いでしょ、と安直な考えが沸々と湧き始め「電気自動車を自分で作りたい」と思い始めたのが入社2年目のことでした。
六畳一間のグローバルカンパニー
―その後、電動バイクの開発を手掛けるベンチャー企業、テラモーターズに転職をされたと伺っておりますが、どういった経緯があったのでしょうか?
加藤 真平:
最初は電気自動車産業の中に入ろうと思ったんです。ただ、自動車は複雑で資金も必要だということで、それなら電動バイクの事業に挑戦しようかと思い立ちました。何より私自身がバイク好きでしたから。それで、様々な情報を収集する中で見つけたのが、当時創業間もないテラモーターズでした。とりあえず情報収集させてもらおうと考え、すぐに電話でアポを取り会いに行きました。直接詳細を聞くと、代表の考え方が自分と非常にシンクロしていて、これならオールジャパンで一緒にやったほうがいいだろうと思い至りました。
―具体的にはどういったところに共感されたのですか?
加藤 真平:
六畳一間のオフィスに10名弱ほどの社員が缶詰になっていました。驚きましたが、ただその一方で、なりふり構わず狭い雑居ビルで5年後・10年後の世界を語る経営者の狂気に真実味と高揚感を感じ、参画することを決意しました。
“混沌の2乗”という未知の領域を渡り歩けた理由

―テラモーターズではどういったお仕事をされていたのでしょうか?
加藤 真平:
創業から間もないスタートアップで約10名ですので、あらゆる分野の業務遂行が求められましたが、私は研究出身なので、技術のこと以外は一切わかりませんでした。欠けている能力や、必要なことを一からすべて教わりながら、商品である電動バイクを営業するという生活が続きました。あらゆる手段を駆使して全国津々浦々で営業を行い、またその一方で広報活動を行いながら会社の看板を売り、売上・利益をつくり、またその一方で製品開発・改善に邁進していきました。
そんな中で日本のほかにベトナム、インド、フィリピン、バングラデシュなど、5ヶ国ほど展開を進めることになり、そこで私はフィリピン現地法人トップとして立ち上げと事業展開に従事することになります。フィリピンはまだ工業化が遅れており、政府も企業も人も日本企業の技術を学び産業を定着させることに躍起になっていました。
社会としてもまだまだ成熟しているとは言いがたく、街並みや情報が混沌の2乗のような中、とにかく最善を尽くすしかないと思って事業に取り組んでいました。肉体的・精神的にはきついことも多々ありましたが、自分が身を置いていた製造業やその他の日本の基盤産業もこういった段階を経て形作られていったのかもしれないという勝手な歴史観と過去にタイムトラベルをしたような感覚が入り混じり、それが当時の楽しさ・高揚感につながっていた1つの理由でもありました。
―その後、FiNCにはどのようなきっかけでご入社されたのですか?
加藤 真平:
私がフィリピンに着任する前に、偶然にもテラモーターズとFiNCでフットサルをすることになったことが弊社代表の溝口との出会いです。身体が大きいのに動きが機敏な男がいると、非常に印象に残りました。そしてフィリピンから帰国した時期に、最終的にFiNCへの入社を決めることになります。
私の両親は既に70歳を超えていますが、体を壊し子供に迷惑をかけることがあってはならないと、食生活に最新の注意を払い運動を欠かさず、健康維持に努めています。そんな両親を率直に尊敬している一方で、私が同じ年齢のときに同じ努力が果たしてできるか、もっと方法はないのかという探究心が最終的に健康産業に身を投じることに決めた根幹でした。
曲者メンバーと門外漢な私
―2014年にFiNCにご入社され、具体的にはどのような業務に携わられたのでしょうか?
加藤 真平:
『FiNC Online Works』という、栄養士さんやトレーナーさんといった食や運動に関わる専門家に特化したクラウドソーシングサービスの責任者をやらせていただきました。
当時はまだ本当に予算がなく、またチームは、事業開発家・管理栄養士・インターン等々、様々なバックグラウンドを持つ個性的なメンバーとマネジメントに不慣れで門外漢な私、という寄せ集めのような集団で、日夜専門家集めや顧客とのマッチングのシステム構築等に奔走しましたが、当時は専門家獲得に苦戦し会社の足を引っ張り続けました(笑)が、今にして思えばこれが極めて楽しく最高の経験をさせてもらったと思っています。
―社長の右腕と称されるまでになったご自身のキャリアについて、どういったところが評価された要因だとお考えでしょうか?
加藤 真平:
正直、よくわかっていませんが、自信があるのは、FiNCの社員がハマりがちな落とし穴にハマってきたことでしょうか。失敗も多く、そのたびに反省すべきところは反省し、腑に落ちないところは反省をしないことにしていました。ですから、落とし穴に落ちた経験自体は多くの方に披露をしていきたいと思っています。
それとあとは手段を選ばない点でしょうか。これはやろうと決めたことは、嫌われても徹底してやります。本当は嫌われたくないので嫌われなくても済む方法も探しますが、嫌われるしかないときは一旦嫌われてあとで詫びをいれようと思っています。
―最後に、今後の目標についてお聞かせください。
加藤 真平:
この3年で事業や組織が急拡大をしました。当たり前ですが、大事にしなければいけないことだけでなく、変えなければいけないことも多々あります。組織的にも個人的にもです。より個人としても組織としても成長していけるよう、いつまでも生え変わりをつづけていくことができるよう、そういった姿勢を崩さないようにしたいと思います。

編集後記
単身で発展途上国に行き、数々の苦労を経験しFiNCに入社した加藤氏。ゼロからモノをつくりあげる大変さを通して得た、小さなチャンスを逃さない臨機応変さと、事業を成功に導く情熱は、まさにベンチャー企業にとって必要不可欠なマインドである。加藤氏の持つ逆境に対する強さは、今後FiNCをさらに成長させる推進力となるに違いない。

加藤 真平(かとう・しんぺい)/1985年生まれ。
国立群馬工業高等専門学校卒業後、筑波大学第3学群工学システム学類に進学。ロケットエンジンなどの研究を行う。2010年、同大大学院を卒業後、ミシュランリサーチアジア株式会社(現・日本ミシュランタイヤ株式会社)に研究職として入社。2012年、テラモーターズに参画し日本国内の統括や、同社フィリピン現地法人の立ち上げに従事。2014年、株式会社FiNCに入社し、『FiNC オンラインワークス』事業の立ち上げに携わる。2016年、同社代表取締役室シニアマネージャーに就任後、NECとの資本業務提携やPanasonicとの業務提携等を推進。2017年に代表取締役室副室長に就任。座右の銘は『人生は積み重ねよりも、積み減らすもの』。