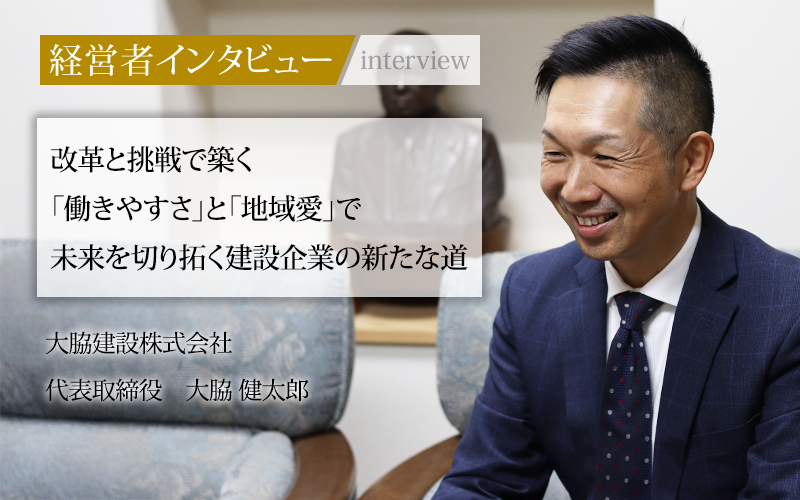
建設業界といえば、2024年4月からの時間外労働時間の上限規制の対象化や熟練労働者の高齢化によって、深刻な人手不足に直面している。
そんな中、100年以上にわたり岐阜県で地域の道路を守り続けてきた大脇建設式会社。「社員の前向きな姿勢が会社のブランドを支える」と語る代表取締役の大脇健太郎氏に、働きやすい環境づくりや、これからの展望について話をうかがった。
偶然の出会いから始まった建設業界への道
ーーまず、建設業界に進んだきっかけについて教えてください。
大脇健太郎:
もともとは大学卒業後、外交的な性格を活かそうと考え、自動車ディーラーに入社し、営業を担当していました。岐阜県では車が生活必需品であったことから、身近に感じたのが選んだ理由です。
しかし、当時付き合っていた彼女(現在の妻)との結婚を考え始めた際に、妻が3人姉妹の末っ子であり、上の2人の姉が結婚していたため、私が妻の父親の会社を継ぐ必要があるという話になったのです。その後、建設の専門学校に通い、卒業後は岐阜県関市の建設会社で3年間修行した後、弊社に入社しました。
ーー国会議員の秘書もされていたとお聞きしました。その経験も活きていますか。
大脇健太郎:
秘書になったのは、修行を終えて入社した頃、三代目社長である父からの依頼で、国会議員に立候補した県議会議員の選挙を手伝ったことがきっかけです。その議員から当選後も手伝ってほしいと頼まれ、最終的に3年間、秘書を務めました。
秘書時代に学んだことのひとつに、相手の状況を考慮して適切な言葉を選ぶことの重要性があります。年齢や立場に関わらず、相手の心情や立場に配慮した言葉を選ぶことで、信頼を得ることの大切さを痛感しました。その後、会社に戻り現場監督として働き、副社長を経て、5年前に事業を承継し、社長に就任しました。
創業は大正時代。社員の前向きさが支える地域の信頼

ーー貴社の事業と強みについて教えてください。
大脇健太郎:
弊社は、大正2年に材木商として創業し、長年にわたり地域に根ざした建設業を営んできました。「常に誠実に 努力は惜しまず 必ず実行せよ」をモットーに、地域の安心、安全、発展に貢献することを使命と考えています。たとえば、岐阜県美濃地方の国道41号線の維持管理業務では、国からの依頼を受け、半世紀以上にわたりその安全を守ってきました。
弊社の強みは、社員さん一人ひとりがこの国道管理業務に誇りを持ち、日々仕事に取り組んでいる点です。たとえば、大雨の際にはこの国道を通行止めにする業務が発生しますが、社員さんたちは嫌な顔一つせず、頼もしい姿勢で課題に挑みます。こうした前向きな社員さんの姿勢が、会社のブランドを支える大きな力になっています。
ーー社員が前向きに働ける組織づくりの秘訣は何ですか?
大脇健太郎:
社員さんのモチベーションにつながるような働きやすい環境を整えることを心がけています。
まず、勤務時間を柔軟に運用しています。通常の就業時間は午前8時から午後5時半ですが、午後5時以降は退勤を促し、気兼ねなく帰れる雰囲気を大切にしています。有給休暇についても柔軟に対応しています。有休が少ない新入社員には「会社が有給扱いにするから休んでいい」と伝え、オンとオフの切り替えを促しています。
この仕組みが「会社のために頑張りたい」という風土を育んでいるのだと思います。
ーーほかに取り組まれていることはありますか?
大脇健太郎:
最近では、小学生向けの軟式野球大会を開催しました。チーム数が少ない地域で、子どもたちに試合の機会を提供することが目的です。野球連盟から「国道工事の看板で貴社の名前は地域の人もなじみがあります。ぜひ大会を企画してみませんか」とお声がけいただき、大脇建設杯を2022年から3年続けて開催することになりました。
野球大会を通じて、子どもたちや地域の皆さんに少しでも喜んでもらえることが、私たちにとっても大きな励みになっています。
社員の個性を活かし、巻き込みながら互いに成長できる環境を

ーー社長就任後、改革したことはありますか。
大脇健太郎:
作業服のデザインを変えました。社員さんにどの色がいいか意見を聞いたのですが、まとまらなかったため、各自が好きな色を自由に選べるようにしました。ズボンと服で6色ずつ用意し、組み合わせは36通りです。自由に選んだ作業服の色は、社員さんの個性を表現しており、「作業服の色の自由さ」が弊社公式SNSアカウントのショート動画でも紹介され、社内外から好評です。
ーー逆に、失敗したことや、そこから学んだことはありますか?
大脇健太郎:
「自分なりの特色を出したい」と思うあまり、失敗したことがあります。副社長だった頃は「自分ならこうするのに、なぜ社長はしないのだろう」と、三代目社長の悪い部分ばかりに目が向いていました。しかし、自分が社長になり、経営者の覚悟と責任の重さを理解する中で、簡単に結論を出せない難しさを学びました。
もう1つの失敗は、社員さんがどのような仕事をしているか、表面的にしか把握していなかったことです。ある社員さんが定年退職した際に、「この人はここまでやってくれていたのか」と気付き、会社がうまく回っていたのはその社員さんの努力のおかげだったと反省をするとともに感謝しました。
その経験を踏まえ、今では幹部や社員さんを巻き込み、情報共有を徹底しています。頻繁に意見交換を行うことで、最近では「社長、それは私がやりましょうか?」とか「今日は社長は行かなくても大丈夫です」とお互いがフォローし合えるような体制になってきました。
ーー今後の展望をお聞かせください。
大脇健太郎:
時代のニーズに合わせ、社員さんの仕事量を減らすことが最優先と考えます。弊社はまだまだ紙ベースの業務が多いため、デジタル化を進めることで作業の効率化を図り仕事量の削減を行っていきたいと考えます。また常に時代の変化を敏感に感じ取り、この社会になくてはならない会社づくりを目指し、そこに柔軟に対応できる体制と会社の風土を築き上げたいと考えています。また私自身としては、インドのマハトマ・ガンジーの言葉を引用させて頂くならば「明日死ぬと思い生きよ。永遠に生きると思い学べ」の気持ちで日々を過ごしその姿を通じて社員さんが共に学び成長してくれることを期待しています。
編集後記
周囲の意見を取り入れ、コミュニケーションを大切にしながら、会社を発展させたいという強い意志が大脇社長の語り口から伝わってきた。何か依頼をするときも、慎重に言葉を選び、社員一人ひとりの意見や状況を尊重することで信頼が生まれる。信頼は自信を育み、その自信が仕事への責任感へとつながる。そして、生まれた責任は「自分たちがまちの道路を守っている」というプライドへと昇華する。
地域を愛し、地域に愛され続ける大脇建設がある限り、岐阜県のインフラの安心・安全は守られ続けるだろう。

大脇健太郎/1975年、岐阜県生まれ。1998年、名古屋学院大学商学部を卒業後、自動車ディーラーで営業職を勤める。結婚を機に東海工業専門学校土木工学科へ入学。卒業後、青協建設株式会社で修行。その後、大脇建設株式会社へ入社し、現場監督を務める。2010年、選挙の手伝いを機に国会議員秘書を3年間務める。2014年、再び大脇建設株式会社へ入社し、2019年同社の代表取締役に就任。














