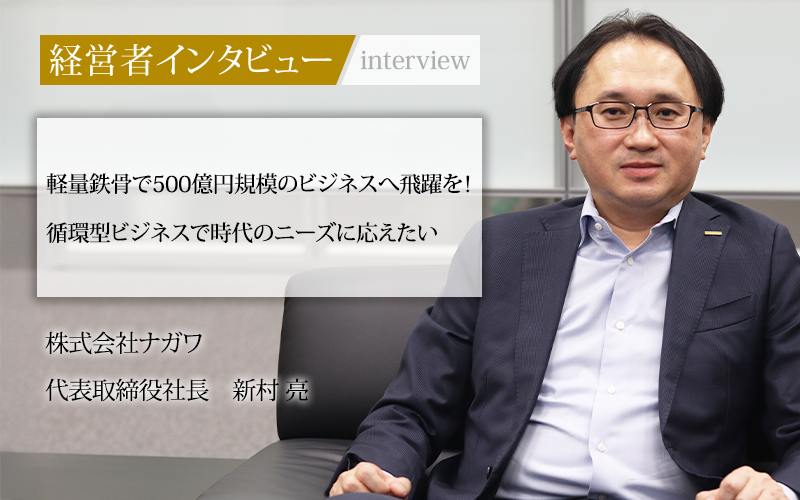
株式会社ナガワは、ヨーロッパのキャンピングカーから着想を得た、軽量鉄骨かつ全溶接構造の「スーパーハウス」を生み出した企業である。
システム建築やモジュール建築(プレハブ)、そしてユニットハウスなどを主な商品として展開する同社の代表取締役である新村亮氏は、大学卒業後から同社でキャリアをスタートさせた叩き上げだ。住まいや建築のあり方が見つめ直されている今、新村氏に同社が描く未来のビジョンについてうかがった。
人々の行動パターンを考察したモノづくりで事業の幅を広げる
ーーまずは株式会社ナガワにご入社された背景をお聞かせください。
新村亮:
私が弊社を知ったのは、1995年に発生した阪神淡路大震災の時のことです。当時、復興のために建てられた仮設住宅を見て、「こんなに早くタイミングで建物を届けられる会社があるのか」と驚いたことを覚えています。そこで、仮設住宅に携わっている会社を調べたところ、辿り着いたのが弊社でした。
ーー社長に就任した経緯はなんだったのでしょうか?
新村亮:
当時社長を務めていた弊社の高橋会長は、「とにかく経営は若い人間がやったほうがいい」という哲学を持っている方でした。高橋会長が61歳になるタイミングで、後任として指名されたのです。
ーー株式会社ナガワの歴史についてもお聞かせください。
新村亮:
弊社は約60年前に創業し、ガソリンスタンド事業から始まりました。事業はモータリゼーションに後押しされた一方で、当時はガソリンスタンドの月末請求書払いが一般的だった資金回収の仕組みが要因となり、売掛金の回収ができないケースが生じてしまいました。
そのため、売掛金の弁済としてブルドーザーなどの建設機械を受け取り、軒先に置いていたところ、地元農家の方から「貸して欲しい」というお声をいただきました。「これはビジネスになるのでは」と考え、これをきっかけに、建設機械のレンタル業にシフトしました。
建設機械のレンタルを始めると、必然的に建築現場に足を運ぶようになります。そこで私が目にしたのは、現場の職人さんたちが車の中や外で昼食をとっている姿でした。そこで「もっと職人さんたちが快適に過ごせる休憩スペースがつくれないものか」という発想から生まれたのが、弊社のユニットハウスです。
ーーそこからどのようにして「スーパーハウス」は生まれたのですか?
新村亮:
ユニットハウスを扱い始めた当初は、組み立て式だったため、コスパは決して良いものではありませんでした。この課題を解決したのが、1974年のヨーロッパ視察です。ヨーロッパでは幌馬車(ほろばしゃ)が引いて移動できる箱型のキャンピングカーが、事務所や宿泊施設として使われていました。
このアイデアを応用し、トラックで牽引して現地で降ろすだけで設置が完了するユニットハウスの着想を得て、「スーパーハウス」が誕生したのです。
短納期とオーダーメイドの対応で他社と差別化

ーー現在ではスーパーハウス以外の製品も取り扱っていますが、どのような経緯で製品の幅が広がったのでしょうか?
新村亮:
スーパーハウスの誕生後、建設業界が不況に陥りました。ユニットハウスを建築業界向けだけに提供したことで、売上が頭打ちになってしまったのです。建築業界だけでなく、より幅広い層に使っていただけるよう、軽くて地盤整備の手間がほとんどかからない軽量鉄骨建造物に着手しました。
ーー貴社の強みについてお聞かせください。
新村亮:
弊社は工場を保有しているため、ユニット式の建造物をお客さまが希望される場所に運び、すぐに設置できます。納期が短く、かつコストも下げられる仕組みを確立していることが、大きな強みです。
また、建設現場にユニットハウスのレンタルも行っています。購入ではなくレンタルという形で弊社の製品を活用いただけるのも、お客さまから選ばれている理由の一つです。さらに、弊社の製品は多種多様なデザインやオーダーメイドでのご提案が可能で、一般のお客さまにもご好評をいただいています。これも弊社の大きな強みといえるでしょう。
軽量鉄骨だから実現できるコスト削減で活路を拓く
ーー次世代に続くビジネスとして取り組んでいることはありますか?
新村亮:
今後の成長の鍵はモジュール、システム建築の強化です。特に大きな建物の建設において、軽量鉄骨を用いることでコストを削減し、職人不足にも対応しています。これにより、競合他社との差別化を図りつつ、需要のある建築市場でしっかりとポジションを確立していきます。
現在、建設市場は厳しい状況です。以前は90兆円規模だった建設投資が、今は50兆円ほどにまで縮小しています。将来的に再び90兆円規模に戻ることは難しいと思いますが、弊社では今後も毎年5%程度の成長を見込んでいきたいです。
原材料の価格上昇や職人不足の問題がありますが、弊社では軽量鉄骨を使うことでコストを抑え、規格品であれば少ない職人で作業が可能です。こうした強みを活かして、モジュール、システム建築事業は非常に成長しています。
現在、売上は320億円程度ですが、これを500億円規模に拡大することを目指している最中です。この分野はまさに、社会的なニーズに応える事業だと思います(※2024年11月時点)。
製品の生産においてはロボットの導入も始まっています。茨城県の工場では、従来よりも効率的に生産を行い、一日あたりの生産数も増加しています。
ーー今後はどのような製品に注力をしていきますか?
新村亮:
プレハブは現地で壁を設置し屋根をかけるのに対し、ユニットハウスは完成品を現場に設置するだけです。この設置の違いが市場にも大きな影響を与えています。30年前、プレハブが市場の80%を占めていたのに対し、現在はユニットハウスが市場の90%を占めています。こうした変化は、リサイクルやリユースの流れとともに進んできました。
また、多くの方が軽量鉄骨の利点に気づいていない状況ですが、私たちはCMなどを通じて軽量鉄骨の可能性を伝えています。20年、30年後には、軽量鉄骨が主流になっていると思うので、今後も積極的に情報発信をし続けたいですね。
編集後記
建築資材高騰や人手不足など、さまざまな変化と困難を迎えている建築現場で、株式会社ナガワの提供する製品は、まさに時代のニーズにあった価値を提供している。古い製品にこだわり続けることなく、挑戦を続ける新村社長が切り拓く未来に大きな光を感じた。

新村亮/1975年生まれ、埼玉県出身。1998年城西大学経済学部卒業。新卒で株式会社ナガワに入社。企画室長兼海外事業推進室長や、インドネシアとタイの現地法人の海外赴任、専務取締役管理本部長兼企画室長などでキャリアを重ね2023年4月、代表取締役社長に就任。














