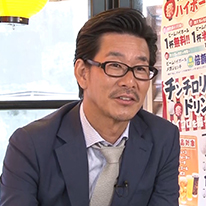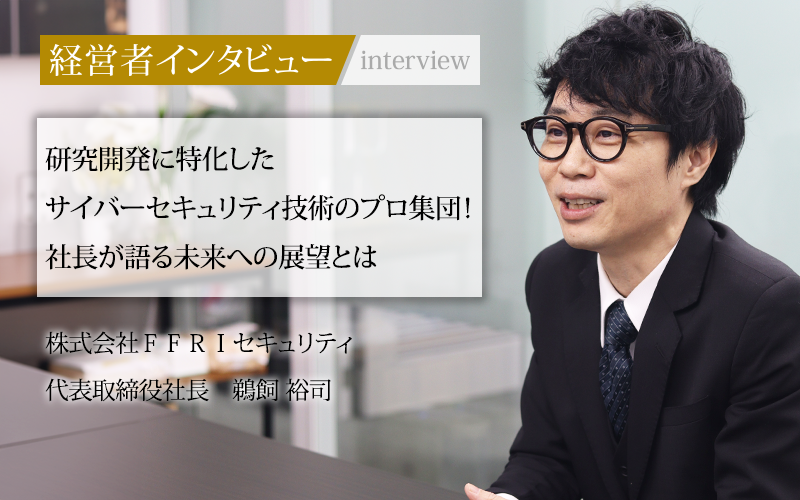
インターネットの普及により便利さが増す一方で、サイバー攻撃の脅威も拡大している。総務省の報告によれば、2022年には各IPアドレスに対し17秒に1回の頻度でサイバー攻撃関連の通信が観測されているという。このような状況に立ち向かうべく日々研究開発に取り組んでいる企業がある。株式会社FFRIセキュリティだ。代表取締役社長の鵜飼裕司氏に、創業当時の思いや同社の事業内容について話をうかがった。
初心を貫き通してサイバーセキュリティを追求する行動力
ーー創業までの経緯を教えてください。
鵜飼裕司:
学生時代からサイバーセキュリティに興味があり、独学で学んでいました。就職活動の際には、国内でサイバーセキュリティ対策を手がける企業を調べましたが、どの企業も自社で技術開発を行わず、海外から技術を導入して展開しているだけでした。この現状に失望し、一度はサイバーセキュリティの業界から離れる道を選びましたが、他業界に就職後もサイバーセキュリティへの関心は薄れることなく、個人的な研究活動を続けていました。そんな中で、2003年にアメリカの企業から声をかけられたのをきっかけに、渡米を決意したのです。
カリフォルニア州にあるeEye Digital Security社で4年半、サイバーセキュリティの研究開発に従事しました。同社がスタートアップから成熟企業へと成長する過程を経験し、改めて日本の状況を見直すと、依然として国内にはサイバーセキュリティを本格的に研究する企業が存在しませんでした。
一方で、アメリカではサイバーセキュリティが安全保障における重要なテーマとして認識されており、この差に強い危機感を覚えて帰国を決意したのです。私はもともと経営者になることを強く志望していたわけではありませんでしたが、「日本にサイバーセキュリティ技術の研究開発を行う民間企業をつくりたい」という思いから、会社を設立することを決意しました。
ーー上場を決めたのは何故ですか。
鵜飼裕司:
サイバーセキュリティ業界においては、技術が重要であることはもちろんですが、同時に信頼も極めて重要です。なぜなら、平時には何も起こらないため、お客様が導入を決める際には、その企業や製品への信頼が必要不可欠だからです。また、社員が安心して働ける環境を整えるためにも、上場は有効だと考えました。
私が仕事をする上で大切にしている思いは2つあります。1つ目は、サイバーセキュリティ技術の研究開発を通じて、経済および安全保障の観点から日本国内に確固たる基盤を築くことです。
そして2つ目は、信頼を積み重ねることで会社を成長させることです。この2つを実現するためにも、上場は大きな一歩だったと考えています。
技術集団が生み出す純国産の最先端のセキュリティ

ーー改めて貴社の事業内容を教えてください。
鵜飼裕司:
弊社はサイバーセキュリティ専業のベンダーとして2007年に創業しました。日本にもサイバーセキュリティを手がける企業はいくつか存在しますが、弊社はその中でも特異な存在で、研究開発に特化している点が特徴です。多くの企業が海外から技術を輸入して展開している中、弊社はその技術の源をつくり出すことに重きを置いています。その結果、弊社の競合は主に北米の企業だといえます。日本国内では競合する企業はほとんどなく、むしろ協業関係にあるケースが多いですね。
弊社は世の中にまだ存在しない技術の研究・開発に取り組むため、リスクがある中でも、高い価値を創出し、競合他社との差別化を図ることができています。こうして生み出された技術から、製品化可能なものを商品として提案・提供し、事業収益を上げているのです。
ーー具体的にはどのような事業を行っているのですか?
鵜飼裕司:
弊社の事業は大きく2つに分かれています。
1つ目はプロダクト事業です。弊社では「FFRI yarai」という次世代型ウイルス対策ソフトウェアを研究開発し、販売しています。従来型のウイルス対策ソフトは、パターンマッチングという技術を用いて、既知のウイルスを収集し、それらと照合して白か黒かを判定するものでしたが、2006年頃にはこの技術では限界があることが明らかになってきました。1日あたり数万件だったウイルスの生成数が、何十万、何百万と膨れ上がり、対応が追いつかなくなったのです。
その課題に対応するために、yaraiのような次世代型ウイルス対策ソフトが必要になりました。この次世代型では、ウイルスが行う「振る舞い」や「行動情報」に基づいてウイルスらしさを判定します。弊社は2007年の創業と同時にこの開発に着手し、2009年にyaraiを発売しましたが、この製品は、次世代型ウイルス対策ソフトとして世界最速で市場投入されたものでした。2011年頃、日本国内でコンピューターウイルス被害が拡大し、社会問題化した際、国内で次世代型ウイルス対策ソフトを提供できたのは弊社だけだったため、yaraiが広く普及する結果となりました。現在では民間企業から官公庁まで、多くの組織で利用されています。
2つ目はサービス事業です。この分野では、調査・分析やプロトタイプ開発といったセキュリティ案件をスポットで請け負い、お客様に提供しています。一般的なセキュリティ会社が行う診断業務などは扱わず、複雑で専門性の高い案件を中心に対応しているのが大きな特徴です。特に最近は「サイバー安全保障」に関する需要が増えており、国や防衛関連企業へのサービス提供の機会が増加しています。
日本国内でのキャパシティを増やすために欠かせない人材確保
ーー5年後、10年後に向けた目標を聞かせてください。
鵜飼裕司:
研究開発を基盤にサイバーセキュリティ分野で社会に貢献していくことは、10年後も変わらないと思います。特にサイバー安全保障は、日本にとって今後さらに重要なテーマとなるでしょう。5年後、10年後にはサイバー安全保障の状況が変化していると予想されますが、どのような環境においても日本を支えられる企業でありたいと考えています。そのため、人材の採用を積極的に強化しています。
弊社の採用は新卒を中心としており、これまで毎年約10名を採用してきましたが、来年以降はその倍、さらに将来的には2倍、3倍と採用を拡大する予定です。具体的な取り組みとして、就職エージェントの活用拡大、広告媒体への掲載、勉強会の開催、学会への参加、大学との共同研究、人材育成セミナーへの講師派遣など、さまざまな形で優秀な学生との接点を広げています。
求める人物像としては、何よりもコンピューターサイエンスが好きな方を重視しています。将来的に技術開発の仕事に携わりたいという情熱を持った方にぜひ来ていただきたいですね。サイバーセキュリティの分野は、人海戦術になりがちですが、技術で解決できたときの達成感は技術者冥利に尽きるものがあります。
編集後記
サイバー攻撃がますます巧妙化する現代において、守りを担う技術の存在は極めて重要である。その中で、純国産の技術開発にこだわり、日本の安全保障にも寄与する株式会社FFRIセキュリティの取り組みは特筆に値し、技術への情熱と、社会の未来を見据えた理念には心を打たれるものがある。同社の技術は、インターネット社会の安全を支える柱となり、私たちの日常を守り続けるだろう。その道のりを追い続けられることに期待したい。

鵜飼裕司/1973年、徳島県生まれ。工学博士。2003年に渡米し、eEye Digital Security社にてサイバーセキュリティ技術の研究開発に従事。2007年に帰国し、株式会社FFRIセキュリティを設立。多数の政府関連プロジェクトの委員、オブザーバーを歴任。世界最大級のセキュリティカンファレンス「Black Hat」では審査員を務めるなど、セキュリティ業界のトップランナーとして活躍している。