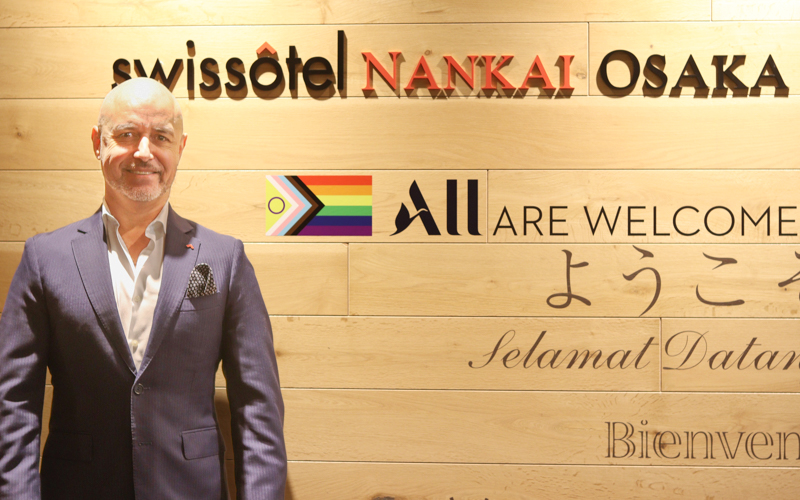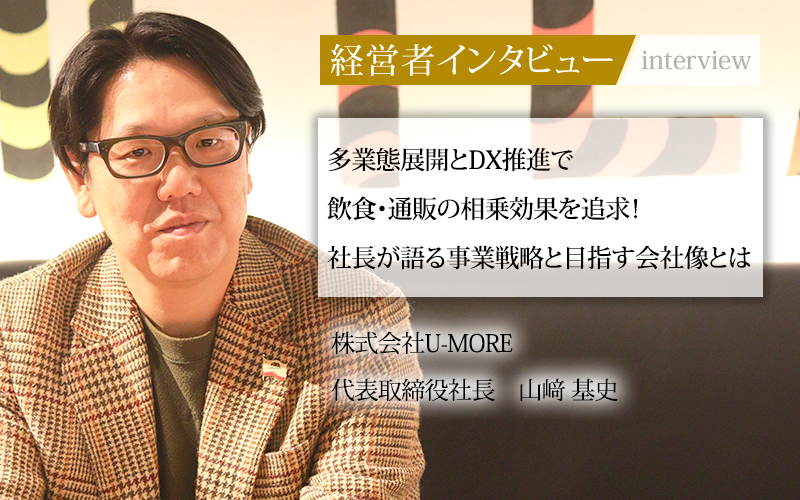
ビジネスの成長には、自社の強みを生かし、合理的な戦略を構築することが欠かせない。しかし、定石通りの方針が常に成功をもたらすわけではなく、ときには、経営者自身の不得意な手法に挑戦することで、リスクを招くこともある。
飲食店経営や食品販売を手がける株式会社U-MOREは、独自の強みを巧みに生かしながら、従来のセオリーにとらわれない、柔軟な経営方針を掲げている。今回は、代表取締役社長の山﨑氏に、同社の事業の強みと、それを支える経営戦略についてお話をうかがった。
放送への夢から飲食店経営への転身
ーー株式会社U-MOREを創業された経緯についてお聞かせください。
山﨑基史:
大学で放送研究部の部長を務めていたこともあり、放送関連の企業を志望し、株式会社USENの前身である、有線ブロードネットワークス社に入社しました。同社には店舗事業部があり、私自身が店舗経営に興味を持っていたこともあって、入社すれば新たな挑戦の機会が広がると期待したのです。
当時の同社は主力事業である音楽関連に加え、新たな領域にも積極的に取り組んでおり、営業部門に配属された私は、営業を通じて多くの飲食店経営者と関わる機会を得ました。営業先の個人オーナーの方々と直接お話しする中で、私も次第に飲食店経営に興味を持つようになったのです。
その思いを形にするため、店舗事業部への異動を希望し、転属後は徐々に責任のある役職を任されました。その後もいくつかの会社で経験を重ねたことで、多くの知見を得ることができたと思います。どの会社でも、「会社をより良くしたい」という思いは変わらず、組織の調整役としてさまざまな業務を担ってきました。
そうした中、発生したのがリーマン・ショックです。このとき、有線ブロードネットワークス社(当時USEN)が経営合理化を進め、一部の事業を切り離す計画が浮上しました。当時、エンタメ事業と飲食事業を統合した取り組みも行われていましたが、大きな成果には至らなかったのです。そのような状況下で、店舗事業の分社化という提案をいただき、これを機に株式会社U-MOREの設立に至ったのです。
人材育成と多業態展開を軸に、独自の経営戦略で市場開拓

ーー仕事をするにあたって大切にしている考え方は何でしょうか?
山﨑基史:
私は「謙虚であること」を特に大切にしています。この業界では、立場が上がるにつれて、お客様や取引先に対して威圧的な態度をとる人も少なくありませんが、それは決して正しい姿勢とはいえないでしょう。
確かに、何かのゴールを達成すれば、その瞬間には自信を持つこともあるかもしれません。しかし、私はビジネスに明確なゴールはなく、常に進化し続けるものだという認識のもと、どんな時でも謙虚さを忘れないよう心がけています。
たとえば、お客様から提案をいただいた際、それが実現困難な案件であっても、頭ごなしに否定するのではなく、一旦持ち帰って慎重に検討することを基本としています。お客様の予算や事情を十分考慮した上で、可能な限り対応することが、私たちの務めです。
ーー株式会社U-MOREの事業内容について教えてください。
山﨑基史:
弊社の事業は、焼き肉やもつ鍋など幅広いグルメを提供する直営の飲食店事業と自社サイトの「KOGANEYA SHOPPING」などで自社ブランド製品の製造販売事業を行う通販事業、イベントの企画・運営を手掛ける催事イベント事業の3本柱で展開しています。
飲食店経営は座席数の制約があるため、利益を確保するのが難しい面もあります。コロナショックの際には、多くの企業がデリバリーやテイクアウトへの転換を余儀なくされましたが、弊社ではそれ以前から、こうした施策を戦略的に検討していました。
また、弊社が多業態で事業をスタートさせたことは大きな強みです。弊社では和食も洋食も取り扱っているため、幅広いジャンルの人材が集まるだけでなく、社内で異なるジャンルへの挑戦が可能な環境を整えています。このような柔軟なキャリアパスの提供が、多くの就職希望者から注目されています。
さらに、飲食店経営と通販事業の相乗効果も弊社の特徴の1つです。有名店の料理を通販で提供することでその知名度が上がり、逆に通販で人気が出た商品が店舗の集客を促進するという好循環が生まれています。
飲食店で食事を楽しむことと、通販での商品購入は異なるニーズに応えるものであり、むしろ両者が互いを補完する関係にあります。目指すのは、多業態展開によるドミナント戦略を通じて、お客様が無意識のうちに弊社の複数のサービスを利用するという構図です。
顧客の記憶に刻まれる企業を目指して
ーー今後の展望についてお聞かせください。
山﨑基史:
通販事業では、全国をターゲットに多業種での商品展開を軌道に乗せることを目指しています。既存のブランド力に依存するのではなく、「この商品、あのお店のものなんだ。買ってみたい」とお客様の心に響く商品開発に注力する方針です。
また、私たちが持つリソースを最大限に活用し、現場オペレーションの効率化を目指してDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入を推進しています。効率化と同時に、人員を投入して質の高いサービスを提供することは重要です。しかし、人に依存しすぎると将来的な限界も見えてきます。そこで、属人化を避け、誰もが同じ水準の仕事を行える仕組み構築に取り組む所存です。
さらに、豊富な経験を持つ年齢層の方々も活躍できるような環境づくりを重視しています。新業態を始める際には、経験豊富な人材を中途採用するケースが多いため、比較的年齢の高い層からの応募が増える傾向があります。DXの推進と働きやすい環境整備を通じて、こうした層の採用をさらに強化し、長期的に働いていただける仕組みを構築したいです。
特に中途採用では、飲食業への純粋な情熱を持つ方々との出会いを期待しています。たとえば、独立経験のある方は、独自のアイデアや店舗運営への熱意を持っていることが多いです。新たなチャレンジを提案できる熱意のある方であれば、年齢は一切問いません。
もちろん、出店数や売上目標の設定も重要ですが、弊社が目指しているのは、お客様の記憶やストーリーの中に自然に溶け込んでいく存在になることです。業界内の順位にこだわるのではなく、「目立つ存在であるか」を重視し、現有リソースを最大限に活用しながら新たなステージへ進化していきたいと考えています。
編集後記
山﨑氏の経営哲学は、一般的な経営指標とは一線を画す。「顧客の記憶に入り込むこと」を重視する姿勢から、数値至上主義では見落としがちな経営の本質が浮かび上がってくる。その一方で、DXの推進や業務効率化といった現実的な課題に果敢に取り組む姿勢からは、合理性と未来への展望がうかがえる。
「新たなステージ」という言葉に込められた構想が、今後どのように具現化されていくのか。U-MOREの成長と革新の過程から今後も目が離せない。

山﨑基史/京都市生まれ、学習院大学卒。大学では「放送研究部」の部長を務め、部員100名を超える学内文化系最大の部(当時)となる。大学卒業後は、USENの前身である有線ブロードネットワークス社に入社。営業職を経験後、店舗事業部へ転部し、その後複数社にわたる事業継承におけるプロセスで要職を歴任。2017年「株式会社U-MORE」を設立し、代表取締役社長に就任、現在に至る。