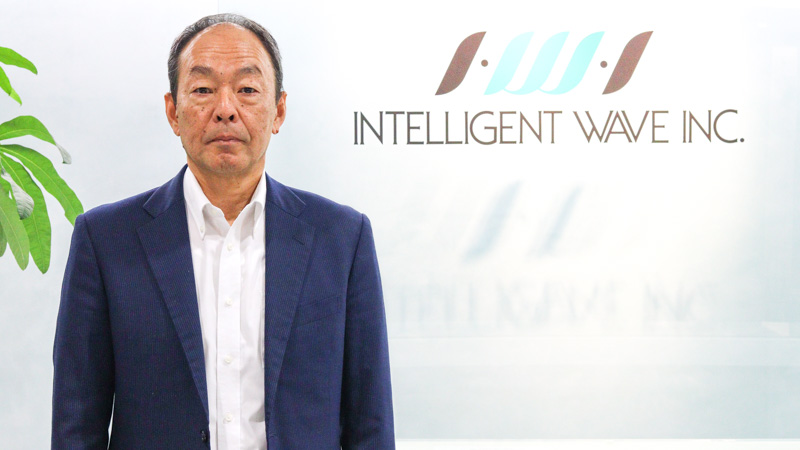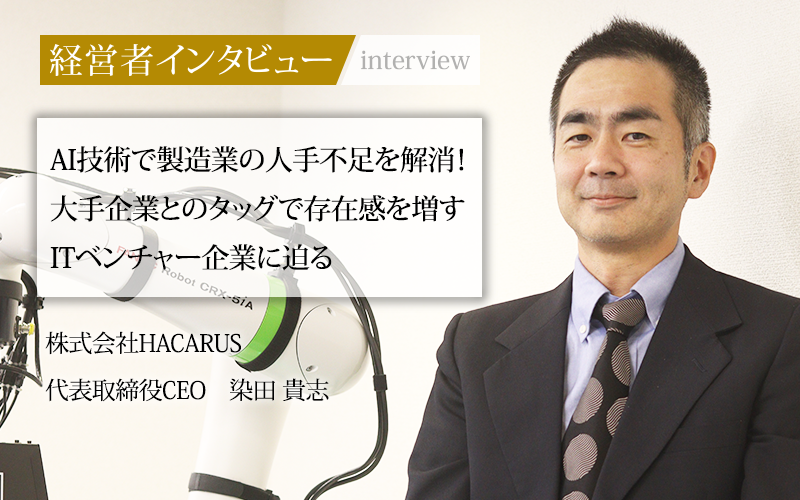
AIによる複雑な部品の検査を可能にしたソフトウェア製品を提供し、製造現場の省人化に貢献する株式会社HACARUS。その他にも、建設現場での危険予知活動をサポートするアプリの開発や、製造工場での労災防止システムの共同開発なども行っている。会社経営の難しさを痛感したエピソードや、自社の商品のアピールポイント、今後の展望などについて、代表取締役CEOの染田貴志氏にうかがった。
会社員、フリーランスを経て創業者へ。事業を立ち上げて痛感した経営の難しさ
ーーまず、染田社長のご経歴を教えてください。
染田貴志:
高校生の頃にWindows 95が普及し、それをきっかけにパソコンでゲームをするようになり、ITに興味を持ち始めました。情報学科がある大学へ進学することを決め、プログラミングやウェブシステム開発について学び、卒業後に外資系のIT企業へ就職したのです。
その会社では多くの学びを得ましたが、製品開発を米国の本社が行っていたことから、お客様のサポート業務がメインでした。そのため、当時は「エンジニアとしてシステム開発に携わりたい」という思いを抱いていましたね。
あるとき目にしたのが、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運営する「未踏ソフトウェア創造事業(現:未踏IT人材発掘・育成事業)」です。この事業は優れたIT人材の育成を目的としたプロジェクトで、個人でも参加できるものでした。そこで大学時代の友人を誘って参加してみたところ、プロジェクトに採択。その後、約1年間はフリーランスとしてソフトウェア開発に取り組みました。
ーーそこから起業するまでの経緯を教えていただけますか。
染田貴志:
フリーランスのときに京都のベンチャー企業から声がかかり、エンジニアとして入社することになりました。その会社で上場する過程を間近で見たのを機に、自分で一から事業を立ち上げてみたいと思うようになったのです。同じ会社で働いていた2人を誘って起業し、私は創業者兼CTO(技術責任者)として参画しました。
しかし、現実はそう甘くありません。会社を興したにもかかわらず2年で廃業することになり、「事業を継続するには技術力だけでなく、ビジネスとして成立させることが重要だ」と痛感したのです。
再び幹部のポジションに就き、組織運営を指揮
ーーHACARUSへの入社を決めた理由は何だったのですか。
染田貴志:
私の希望条件にすべて合致していたことが理由です。起業した会社をたたんだ後、私は再びベンチャー企業へ転職しました。ある程度成果を出したところで、やはり経営に携わる仕事がしたいと思うようになったのです。そこで「経営に関与できるポジションであること」「創業者自身が技術者であること」「グローバルな視点を持っていること」の3つを転職の希望条件にしました。
そんなとき、HACARUSの創業者から、「CTOとして来てもらえないか」と声をかけていただいたのです。同社はちょうど私が希望する3つの条件すべてに当てはまっていました。また、事業に対する代表の思いに共感したため、参画することにしたのです。
私の他に社員が2人いましたが、技術者ではなかったため、システム開発に関しては私が指揮を執らなければなりません。そこで、一から開発チームを立ち上げるべく、技術者の採用から始めることになったのです。
その後、消費者向けから法人向けへ事業転換することになり、システムの大幅な改修に加えて、自分とは畑が違う営業組織の立ち上げも担当するなど、私にとって大きなチャレンジの連続でした。大変な場面もありましたが、希望通りの環境に身を置いて、充実した日々を送ることができたと思います。
他社に先駆け検査工程の自動化を実現。大手企業との業務提携で急成長

ーー改めて貴社の事業内容について教えてください。
染田貴志:
弊社は製造業向けの外観検査AIシステムを提供しています。検査工程を自動化することで、製造現場の省人化に貢献することを目指しています。製造業は国内GDPの約20%を占める、日本にとって重要な産業です。しかし、2002年から2019年の間に製造業の労働人口は約200万人減少し、2030年には40万人近くもの人手が不足すると予測されています。
現在、部品の検査は従業員が一つひとつ目視で行っているところがほとんどです。特に自動車に使われる部品は形状が複雑なため、自動化が難しいと言われてきました。しかし、弊社では高度なAI技術を駆使し、検査の自動化を可能にしています。
ーー貴社は現在多くの大手企業と取引をされていますが、この要因は何なのでしょうか。
染田貴志:
他社が参入できなかった領域で事業化し、サービスの提供ができていることではないでしょうか。この点は、弊社ならではの強みですね。また、近年、オープンイノベーション(※)の動きが高まり、大企業もスタートアップとの協業に積極的になってきています。弊社もこの追い風を受け、複数の大手企業様と業務提携をしており、順調に市場を拡大しています。
(※)オープンイノベーション:自社以外の組織や機関などが持つ知識や技術を取り込んで市場を拡大すること。
ミッションに込めた思いとさらなる成長を見据えた今後の展望
ーー貴社が求める人物像について教えていただけますか。
染田貴志:
経験のないことにも果敢に挑戦するマインドがある方を求めています。たとえば、ある女性社員は、自分の専門外ながら人事採用にチャレンジしてくれました。不安もあったと思いますが、候補者の方々に会社の魅力をアピールしてくれたおかげで、優秀な人材の採用につながったのです。
このように、最初からできないと決めつけず、とりあえず挑戦してみる姿勢を大切にしてほしいと考えています。なお、弊社はベンチャー企業で業務範囲が広く、それ故の楽しさもあるため、チャレンジングな環境で働きたい方にぜひ来ていただきたいです。
ーー最後に今後の展望についてお聞かせください。
染田貴志:
まずは開発、営業、管理業務など、幅広い分野の人材を確保して組織を拡大したいと考えています。そして今後5年を目途に、パートナー企業の協力を得ながら国内外の市場開拓を進めていきたいです。
また、提携している多くの企業様がグローバル展開しているため、最近は協業パートナーである弊社も海外企業との接点が増えつつあります。今後も多様な協業先と連携しながら弊社のソフトウェア製品を提案し、海外展開を進めていきたいと考えています。
さらに、検査だけでなく製造現場の安全管理などの支援もしていきたいですね。すでに共同開発プロジェクトは進行中ですが、将来的には自社の製品として提供していく予定です。これからもAI技術を使って現場が抱える課題の解消に貢献し、日本と世界のものづくりを支えていきます。
編集後記
「最新技術を使って世の中に新たな価値を届けたい」という思いから、マネジメントにも注力するようになったという染田社長。検査の自動化で製造現場の課題解決に貢献する同社は、まさにその思いを実現した事業だと感じた。株式会社HACARUSはこれからもAIで人手不足の製造現場を支え、安全に働ける作業環境を支援していく。

染田貴志/京都大学大学院情報学研究科で統計学と情報学を専攻。卒業後、サン・マイクロシステムズに入社。システムエンジニアとして経験を積んだ後、共同創業者として起業を経験。2016年に株式会社HACARUSに参画し、取締役CTO、COOを経て2024年1月に代表取締役CEOに就任。