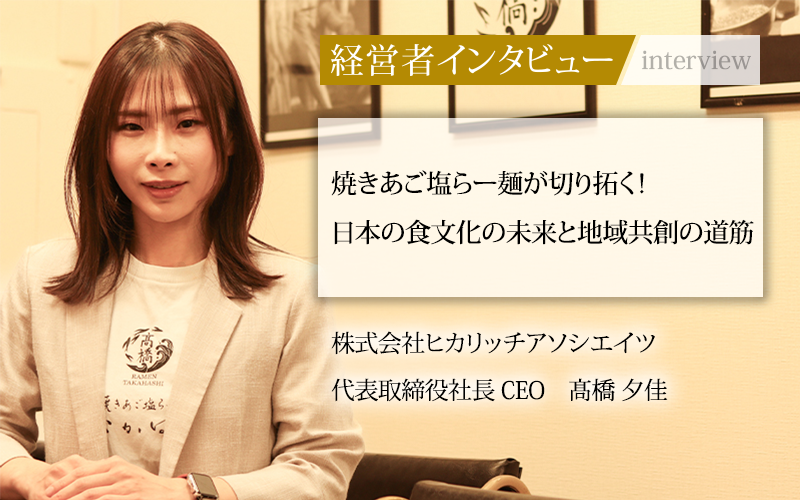
日本の食文化は長い歴史の中で変化してきたが、現代においては、水産資源の保全や食の技術と文化の継承など、さまざまな課題に直面している。その中で、地元新潟で慣れ親しんだ「焼きあご」を活かし、独自のラーメン文化を広めることに挑戦する企業がある。
株式会社ヒカリッチアソシエイツは、「焼きあご塩らー麺たかはし」を通じて、水産資源を活用し、上質な食体験を提供して、日常を豊かにするという「価値の連鎖」を循環させるビジネスモデルに取り組んでいる。代表取締役である髙橋夕佳氏に、これまでの歩みと未来への展望について話をうかがった。
「焼きあご」を使ったラーメン!日本の伝統的食材を広める情熱
ーー最初に、貴社を設立した背景についてお聞かせください。
髙橋夕佳:
2011年に株式会社ヒカリッチアソシエイツを設立し、翌2012年に「焼きあご塩らー麺たかはし」を開業しました。その背景には、新潟の焼きあご文化を全国に広め、多くの人を幸せにしたいという強い思いがありました。
私の出身地である新潟はトビウオ漁がさかんでした。子どもの頃から特に焼きあごに親しみ、日本の初夏にトビウオを焼いてつくる焼きあごは、当時の私にとって身近でありながら特別な存在でもありました。
焼きあごは優れた風味と旨味を持つ高級な食材ですが、その価値はいまだ十分に認知されていません。その魅力を多くの人に知ってもらいたいという思いから、ラーメンという親しみやすい形で焼きあごを提供することを決意しました。焼きあごは日本料理の要ともいえる「だし」に用いる伝統的な食材です。私自身、その旨味がラーメンに与える深い味わいに感銘を受けたことが、設立の大きなきっかけとなりましたね。
旨味を最大限に引き出す独自製法への取り組み

ーー「焼きあご塩らー麺たかはし」には、どのような特徴があるのでしょうか?
髙橋夕佳:
焼きあごを使ったラーメンは、他にはない独特の風味が特徴です。私たちが開発した焼きあご塩らー麺は、焼きあごの使用量に対する旨味と香りを最大化させる独自製法が特徴です。これにより、高級食材である焼きあごをラーメンという手頃な価格の商品として提供し、多くの方々にその魅力をお届けしています。焼きあごのスープは、今や幅広い層のリピーターを生む存在になりました。
さらに私たちは、新商品の開発にも積極的に取り組んでいます。焼きあごと旬の食材を組み合わせた季節限定商品や、手軽に使える家庭向け商品なども展開し、焼きあごの多様で汎用的な価値を提案しています。
ーーだしに関連する技術革新の取り組みについて、さらに詳しく教えてください。
髙橋夕佳:
だし食材の潜在能力を引き出すために、技術革新にも取り組んでいます。たとえば、東京大学との共同研究で、だし食材の製造工程において酵素の働きを活かし、魚が潜在的に持つ美味しさを引き出す製造技術を開発しました。この技術は特許を取得(※1)し、グループ会社である株式会社ヒカリッチフードサイエンスの製造現場で既に実装されています。
これにより、従来は不向きとされた脂の乗った魚体の大きな原料でも有効に利用できるようになり、漁獲負荷を分散しながら、他の生産者と競合しない新たな供給源を生み出すことが可能になりました。
他にも、だし業界の課題である多脂肪原料の脱脂にも挑戦し、こちらは実用化が遠いものの、同様に東京大学との研究成果として特許を共同出願(※2)しています。
(※1 特許第7632834号 PCT/JP2024/008122 ※2 特願2023-150485)
この新事業をきっかけに、弊社はラーメン屋からだしの総合企業に軸足をシフトしました。上流に位置する水産業を起点にした価値の連鎖を構築する新たな発想で、水産資源の持続的利用や、一次産業の収益力強化を図ります。
今後も、日本のだし文化を未来の世代にも変わらずに継承していくことを使命として、果敢に挑戦していきます。
持続的成長が可能なビジネスモデルで100年続くブランドを
ーー今後のビジョンや課題についてお聞かせください。
髙橋夕佳:
3〜5年後を見据え、食料危機や原材料不足に対応しながらも、持続的成長が可能なビジネスモデルの構築が急務と考えています。たとえば、だしの総合企業としての技術開発や、原料調達力の強化がその一例です。この地盤固めができた上で、「焼きあご塩らー麺たかはし」を体験型メディアとして、だし文化の発展や、世界での市場創出にアクセルを踏んでいきます。
私たちの目標は、流行り廃りの激しい食の業界で、100年続くブランドを築くことです。そのために、上流となる水産の研究・製造から、「焼きあご塩らー麺たかはし」の運営まで、グループ連携して事業価値の最大化を追求してまいります。
ーー最後に、今後挑戦したいことや展望をお聞かせください。
髙橋夕佳:
一次産業従事者の高齢化、水産資源の減少など、このまま放っておけば、私たちは美味しい魚が日常的に食べられなくなることは容易に想像できます。さきほど、水産業を起点に価値の連鎖を構築する発想の必要性をお話しましたが、具体的には未利用魚の高付加価値化を飲食事業で推し進める構想を練っています。このように、水産現場の未利用資源が、太く安定的な出口を持つことは、グループ連携した事業価値の最大化へもつながると考えています。
もともと「焼きあごでたくさんの人を幸せにする」ことが私の起業の動機であり、今後も変わることのない弊社の存在目的です。この目的をブレずに持ち続け、長く成長し続ける会社経営を目指します。
編集後記
髙橋夕佳社長が語る焼きあごへの情熱は、「文化を守り、未来へ紡ぐ」という強い信念に裏打ちされ、単なる事業を超えた崇高な理念を感じさせる。その熱意が結実した焼きあご塩らー麺は、食の多様性を広げるだけでなく、地域資源の持続可能な活用への大きな可能性を示唆している。ヒカリッチアソシエイツの挑戦は、これからの日本の食文化に新たな道を切り拓いていくに違いない。

髙橋夕佳/新潟大学教育人間科学部卒業。2011年、株式会社ヒカリッチアソシエイツを設立し、「焼きあご塩らー麺たかはし」を展開。2022年から2年間、東京大学大学院農学生命科学研究科受託研究員として、酵素の働きを活かした水産加工技術の研究に従事。共同研究の成果となる特許技術の社会実装を目的に、2023年、株式会社ヒカリッチフードサイエンスを設立。グループで、日本を代表するだしの総合企業を目指す。














