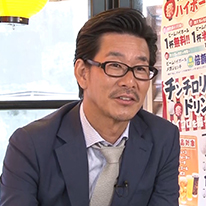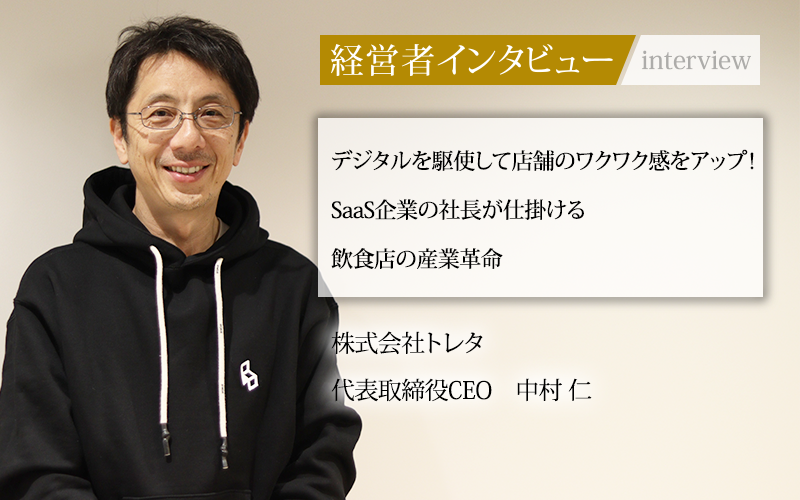
近年、賃金や労働時間、労働人口の減少などにまつわる就業環境の厳しさや労働生産性の低迷など、飲食業はさまざまな課題に直面している。飲食業界のこうした現状にメスを入れ、デジタル化を推進しているのが、株式会社トレタの代表取締役CEOである中村仁氏だ。デジタルを駆使しながら飲食業界に変革をもたらした中村社長に事業戦略をうかがった。
市場規模35兆円の飲食業のビジネス構造を改善する
ーー飲食店のデジタル化に取り組んだ理由を教えてください。
中村仁:
飲食店の生産性を向上させるためです。飲食店の現場をみると、働いている人たちの多くは低賃金と長時間労働に悩まされ、経営者は低い利益率を改善できていないのが現状です。この状況が続けば、産業としての持続性が低下します。
私たちの楽しみと憩いの場であるはずの飲食店が元気を失っているのを「救いたい」という思いが、飲食店のデジタル化のきっかけでした。飲食店はアナログな作業も多く、デジタル化にはこれまで決して積極的ではありませんでしたが、深刻化する人口減少や物価高騰を考えれば、このままのやり方を続けていては立ち行かないことはもはや自明です。そこで、私はデジタルテクノロジーと知恵を駆使して飲食店に山積する課題を解決しようと考えたのです。
ーー飲食店の課題解決に専念するという事業方針だと思うのですが、外食産業の市場規模はどのくらいあるのですか?
中村仁:
弊社が飲食店のデジタル化に取り組んだ頃の市場規模は年間35兆円超でした。コロナ禍で一時的な落ち込みはありましたが、2023年には32兆8419億円にまで回復しています。民間の調査会社の推計によると、2024年の市場規模は、インバウンド需要などを背景に、約34兆3916億円と予想されており、35兆円は目前です(※2024年7月時点)。
飲食店は400万人以上の人が働く場所であり、私たちの日々の暮らしにとって重要な社会インフラです。やはり、働く人もお客さまもハッピーでいられるお店づくりをサポートできるというのは、魅力的ですね。
飲食店のアナログな「聖域」をデジタル化してワクワクした店舗空間を築く

ーー飲食店の業務では、どのあたりからデジタル化に着手したのですか?
中村仁:
飲食店のお客様にとっての外食体験の入口から出口まで、つまり店舗として考えれば業務の最初から最後までの一連の流れをデジタル化しようと考え、まずは、入口にあたる、お客さまとお店の最初の接点である予約システムのデジタル化に着手しました。
現在、弊社が予約システムをリリースしてから10年が経ちます。この間、ユーザーのデジタルリテラシーが高くなり、デジタルツールに対するハードルが低くなったことで、予想よりも早いペースで普及することができました。今では飲食店をオンラインで予約するのは当たり前になり、消費者の利便性も、そして飲食店の業務効率もかなり改善したと思います。
ただ、途中でコロナ禍という想定外の状況に遭遇しました。コロナ禍では多くの飲食店が廃業の危機に直面したのですが、その状況を見て、改めて「予約」をデジタル化しただけでは飲食店の危機においては全く無力であることを痛感しました。飲食店が真に持続可能な産業になるには、もっと根本的なところからお店のあり方を変えねばならない。そういう危機感から、予約に続く次のサービスの立ち上げを前倒しで実施しました。
ーー予約システムの次に取り組んだこととは何でしょうか。
中村仁:
紙のメニューをデジタル化し、注文も会計もオンライン化する、いわゆるモバイルオーダーへの取り組みを始めました。
多くの飲食店にとって、現場は「聖域」です。そして、お客さまとの接点は全てアナログでなければならないと考える飲食店は少なくありません。しかし、私はこの聖域にあえて切り込んで、デジタル化しようと考えたのです。なぜなら、飲食店の付加価値の源泉は「現場」にあるけれど、その現場がアナログ一辺倒で非生産的、非効率だからこそ、飲食店の利益率が上がらなかったり、そこで働く人たちが報われる十分な報酬を支払えない事実があるからです。飲食店の生産性を向上させるには、外食という産業の核心部分である「現場」をデジタル化するのが不可欠だと思いました。
そのプロセスで改めて気づいたのが、お店のメニューブックというのは実は「メディア」である、ということです。お店の提供する商品の魅力や価値を伝えることがメニューブックの大切な役割です。いわば、キッチン、ホールに続く、第三のスタッフと言ってもいいでしょう。そこで、それぞれの料理のこだわりやお得な情報など、お客さまがワクワクしながら注文したくなるデジタルメニューをつくろうと、皆で知恵を絞りました。
そのうえで、注文も会計もオンライン化すれば、注文の取りこぼしも会計待ちのストレスも解消されます。結果的にお店の負担は大きく軽減することにもつながります。
飲食店に対する愛情こそがハイクオリティなシステム構築につながる
ーー飲食店のデジタル化事業を進めるにあたり、人材面で考慮していることはありますか?
中村仁:
飲食店の経営や現場をよく知っている人材を雇用することはとても大切だと思っています。飲食店で働いた経験を持ち、飲食店のオペレーションをよく理解している方なら、常に店舗さまの側に立った機能開発や活用方法をご提案できます。また、私たちは消費者の外食体験もアップデートしようとしていますので、飲食店での勤務経験がなくても、外食が好きで、飲食店への愛がある方にも活躍の場はたくさんあると思います。「私があなたのお店のお客さまなら、こういう体験ができたら嬉しいと思います」という提案ができることもとても大切です。
お店とお客さまをつなぐシステムを提供するためには、双方が持つニーズを深く理解しないと、クオリティの高いシステムはできません。そのため人材には、スキルも大切ですが、それ以上に人柄を求めます。飲食店のために頑張るという熱意があり、チームワークを大切にする人を歓迎しています。
もう一つ重視しているのは、お客さま目線でものを考える姿勢です。飲食店はそれぞれが個性を活かしながら、お客さまにワクワク感を提供しています。その個性を守りつつ、システム化を推進することが重要です。
ーー飲食店への愛が飲食店の未来を切り拓いていくわけですね。
中村仁:
飲食店はさまざまな厳しい課題を抱えていますが、それを解決するには生産性、効率性を高めることが必要です。あらゆる課題を解決できたとき、おそらくこれまでとは全く違うスタイルの飲食店が登場するはずです。
テクノロジーには、お店を利用するお客さまも、そこで働くスタッフの皆さんも、そしてそのお店を運営する経営者も、そのすべてを同時にハッピーにできる可能性があります。より素晴らしい外食体験を実現しながら、より良い待遇でやりがいのある仕事をできるようになり、そして利益もしっかり確保できて安定して経営を続けられるようになる。そうした「幸せな場づくり」に取り組むなかで、弊社で働くメンバーたちにとっても、各々のキャリアアップが叶えられるような好循環を目指しています。
編集後記
インタビュー前は、飲食店のデジタル化が加速すると顧客の心情としては寂しく感じるのではないかと考えていた。しかし、中村社長のお話を聞くうちに、ロボットの配膳サービスなど、デジタル化した店舗が生み出す新しいワクワク感に気づき、今までにはない外食の楽しさが生まれていることを実感した。ホールスタッフにゆとりが生まれることで、お客さまも落ち着いて過ごせるようになる。インタラクティブなデジタルシステムによって、飲食店が従来とは異なる場所に変貌を遂げた未来が待ち遠しくなった。

中村仁/1969年、東京都生まれ。家電メーカー、外資系広告代理店を経て、2000年より飲食店を経営。「西麻布 壌」(現在は閉店)は立ち飲みブームをつくり、「とんかつ 西麻布 豚組」(2005年)、「豚組 しゃぶ庵」(2007年)ではTwitter(現:X)集客が評価され、外食産業記者会(報道集団)にて「外食アワード2010」を受賞。2013年に飲食店向け予約システムの開発を手掛ける株式会社トレタを設立。主な著書『外食逆襲論』(幻冬舎/2019年出版)。