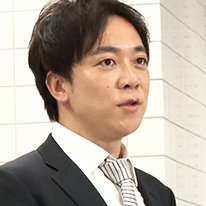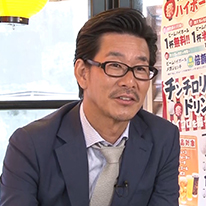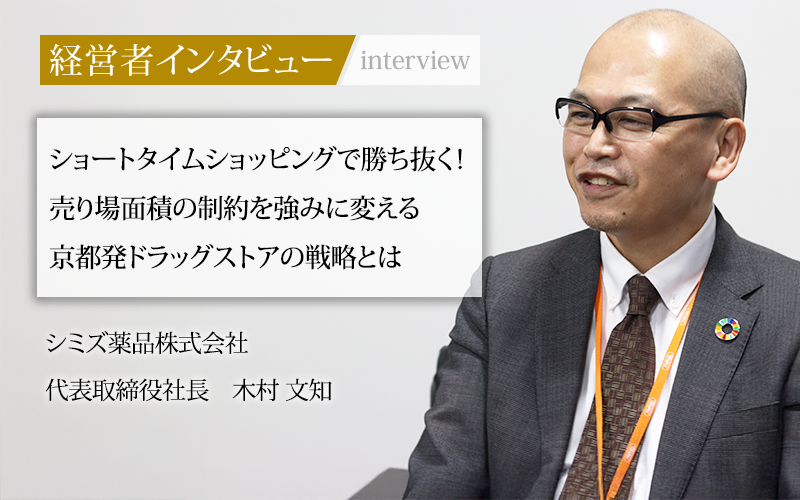
京都に根差し、地域住民の健康づくりを支えるシミズ薬品株式会社。京都府内にドラッグストア「ダックス」を展開する同社は、平均150坪という小回りの利く店舗規模を強みに、顧客が短時間で効率良く買い物できる独自の店舗設計を確立している。調剤薬局併設型ドラッグストアチェーンを運営するウエルシアグループの一員として、さらなる成長を目指す同社の代表取締役社長、木村文知氏に話を聞いた。
業界の垣根を越えて辿り着いた経営者への道
ーー貴社に入社された経緯を教えてください。
木村文知:
私はもともと生き物や自然が好きで、就職活動を行っていた際も生き物に関わる仕事を探していました。そうした中で最初に入社したのが、ホームセンターを展開する地元の家電量販店です。しかし、その企業のホームセンター事業は採算がとれない状態で、徐々に縮小されていったため、新たな道に進もうと退職を決断しました。
その後、専門学校で環境アセスメント(※)を学び、ビオトープ関連の資格も取得しましたが、残念ながらその分野での就職は叶いませんでした。他の業界への転職も考える中で、あるとき近所のドラッグストアが目に留まりました。そこで見た食品や薬、日用品など、生活に必要な全てを兼ね備えた業態に将来性を感じたのです。最終的にホームセンターかドラッグストアかという選択肢に絞った中で、寺島薬局株式会社に採用されたのがドラッグストア業界参入のきっかけですね。その後、ウエルシアグループでのキャリアを経て、現在に至っています。
(※)環境アセスメント:大規模な開発が周辺の環境に与える影響を、事前に予測し評価する制度のこと。
ーー社長就任後、特に印象に残っているエピソードを教えてください。
木村文知:
就任後、すぐに起きた出来事が私の方針を決定づけました。ある日、店舗を巡回していた際に、小さな女の子が「トイレに行きたい」と母親に訴えているのを見かけたのです。母親は「我慢しなさい」と言い、買い物を終えて店から出ていこうとしました。私が声をかけようとしたとき、娘さんが「トイレここにあるよ」と言いましたが、母親は「汚いからだめ」と拒否したのです。
これは私にとって衝撃でした。トイレが汚いということは、お客様にとっても社員にとっても良い環境ではありません。そこで、業績向上も大切ですが、まずはお客様と社員が快適に過ごせる環境の整備を優先すべきだと考えました。
新しい店舗ではトイレを綺麗にするだけでなく、社員の休憩室も改善しています。また、カウンターテーブルを設置して壁にも色を加え、カフェのようなおしゃれでリラックスできる空間を整えました。
導線とレイアウトの工夫で実現する、競争力のある店舗設計

ーー貴社の事業内容を教えてください。
木村文知:
弊社は京都に根差したドラッグストアチェーンとして、1938年の創業以来、地域の皆様の健康づくりをサポートしてきました。現在はウエルシアグループの一員として、調剤併設店舗の拡大や深夜営業など、利便性を追求した取り組みを進めているところです。
事業内容として、医薬品や健康食品の販売、処方箋調剤のほか、日用品や食品まで幅広く取り扱っています。店舗は主に京都の郊外に位置し、平均して150坪ほどの売り場面積です。他社と比較するとコンパクトな店舗ですが、効率的な売り場づくりで必要な商品をしっかりそろえています。地域密着型の経営を心がけ、店舗ごとに地域の特性やお客様のニーズに合わせたサービスを提供していることが弊社の特徴です。
ーー貴社の強みはどのようなところにありますか?
木村文知:
弊社の大きな強みは、社員の京都愛と会社への思いが強いことです。企業規模が大きくなるほどそういった意識の共有は難しくなりがちですが、弊社ではしっかりと共有できています。そのため社員同士の関係も良く、職場が温かな環境になっていると感じています。

また、店舗規模の特性を活かした戦略も強みといえるでしょう。他社に比べると店舗面積が狭いため、商品数では太刀打ちできません。そこで「ショートタイムショッピング」をテーマとして、短時間で売り場全体を見渡せるように、導線やレイアウトを工夫しました。デッドゾーン(顧客が入りにくい場所)を極力なくし、スムーズにお買い物していただける店舗設計を心がけています。
変化の激しい業界で、自律的に考え行動できる組織へ

ーー今後の展望をお聞かせください。
木村文知:
現在注力しているのは、社員が明確なキャリアビジョンを描ける体制づくりです。現行の体制では、店長からエリアマネージャーへ昇進する際、業務内容に大きなギャップがあります。そこで、これを埋めるために両者の中間のような役職となる「エリア店長」を新設し、社員がキャリアアップを身近に感じられるようにしていくつもりです。
また、自律型の組織を目指しているため、自分で考えて行動できる人材を育てることが重要だと考えています。トップダウンではなく、社員が自ら興味を持ち、「こういうお店をつくりたい」「こういう場所に出店したい」という声が自然と出てくる環境をつくりたいですね。そのためには、社員の意見を聞くだけでなく、実際に形として反映させることが大切です。それにより社員のモチベーションが上がり、企業の成長にもつながるでしょう。変化の激しい業界で生き残るために、常にチャレンジと検証を繰り返して、新たな価値の創造に挑戦し続けたいと思います。
編集後記
「経験から答えを導き出す」という木村社長の言葉が印象的だった。自身を「要領が悪い」と評しながらも、失敗を恐れず実践を繰り返すことで成長してきた軌跡には説得力がある。派手な成果より着実な成長、表面的な数字より顧客と社員の満足を優先する姿勢は、短期的な成果が求められがちな現代社会に対する警鐘にも思えた。

木村文知/兵庫県生まれ。新卒で地元の家電量販店に入社し、2005年茨城県の寺島薬局へ転職。2008年にウエルシア薬局株式会社の子会社となった後、2011年に長野・福島エリアの営業部長へ就任。2013年、ウエルシアホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社イレブンへ出向し、統合業務に従事。その後もウエルシアホールディングス株式会社へ参画した企業の統合に携わり、2021年に株式会社よどやの代表取締役副社長に就任。2024年、シミズ薬品株式会社の代表取締役社長に就任。