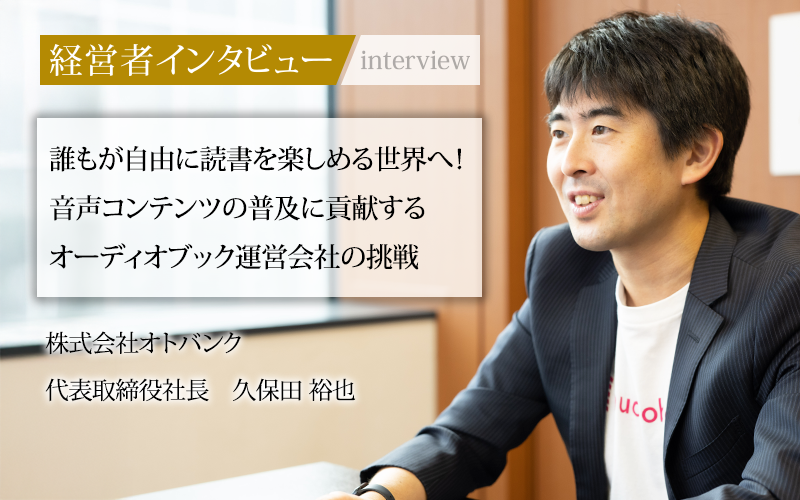
YouTubeなどのSNSや動画配信サービスの普及により、娯楽がありふれている現代。仕事や家事、睡眠以外の時間=可処分時間のうちこれらのサービスを閲覧する時間が大半を占めるようになったことで、人々の読書離れが進んでいる。こうした中、書籍を音声化し、耳で読書体験ができるオーディオブックサービスを展開しているのが、株式会社オトバンクだ。
新しい事業に挑戦するベンチャーに飛び込むことにした経緯や、いまやユーザー数300万人の人気プラットフォームになった同サービスの成長秘話などについて、代表取締役社長の久保田裕也氏にうかがった。
安定性を捨て、ベンチャーに参画。読書のあり方を変えたコンテンツが生まれたきっかけ
ーーまずは事業に参画されたきっかけについてお聞かせください。
久保田裕也:
大学のゼミの打ち上げで、創業者の上田から声をかけられたのが始まりです。すでに事業を立ち上げていた上田は、就職活動をするなど普通の学生生活を送っていた私にとって、異色の存在という印象でした。
それまで特に会話をしたこともなかったのですが、ある日突然「次の会議に参加してほしい」と言われたのです。その場は軽く流しましたが、当日他の予定がキャンセルになりました。時間を持て余した私は、「暇だから顔を出してみるか」と思い、事務所に行ってみたのです。
そこから仕事を手伝う流れになり、ボランティアスタッフとして関わり始めました。ただ、私はすでに外資系のコンサルティング会社への就職が決まっていたので、当初はただ助っ人として参加していました。
入社を考えるようになったのは、「どんな環境で、どんな人たちと、どんな想いで働くか」を大切にしたいと思ったからです。インターンで十数社の仕事を経験する中で、働くことに対して前向きになれないというお話をされる方も多く、そんな話を耳にするうちに、自分は納得できる形で仕事に向き合いたいと強く感じるようになりました。
そこで、何の経験も実績もない数人で始めた組織を大きくできたら、自分の力で生きていくスキルを身に付けられるのではないかと考えて、事業への参画を決めたのです。
ーーオーディオブック事業を始めた経緯を教えていただけますか。
久保田裕也:
上田は彼の祖父が緑内障で失明したのをきっかけに、目の不自由な方にも日常生活を楽しんでもらいたいという思いで事業を立ち上げました。そこでまずは、視覚障害を持つ方に対面朗読をするNPOを立ち上げることにしたのです。これが今のオーディオブック事業につながっていきます。
しかし、今のように起業家へ投資する仕組みは少なく、何のコネクションもなく、関係者の協力が大前提の事業であったため当初は売上も全く立たずで、運営資金は常に枯渇していました。それでも、「自分たちの思いに共感してくれる人を集めれば何とかなる」と、最初のうちは前向きに捉えていましたね。
しかし、「このまま収益を求めずに活動を続けても、世の中にサービスが定着しないのではないか」と次第に考えるようになりました。そこで、まずは多くのユーザを獲得して市場をつくるべく、事業化を決めたのです。
その後はそもそもオーディオブックの需要があるか調べるため、日比谷公園で1人ずつ声をかけ、試作版を聴いていただきました。私は当初、「誰にも興味を持ってもらえないのではないか」と内心びくびくしていたのですが、実際は「お金を払ってでも聴きたい」と言ってくださる方が多く、これはビジネスになると確信したのです。
そのタイミングでMP3プレーヤーが普及し、だんだんと手軽にどこでも音声コンテンツが聞けるようになりました。
地道な努力が実り、大手企業に先んじて新たな市場を開拓

ーーそこからどのように事業を確立していったのですか。
久保田裕也:
書籍を音声化するにあたり、著作権の関係で作家さんや出版社に承諾を得る必要がありました。当時は音声化の前例がほぼなく、慎重な姿勢をとられる出版社が多い中で、お話を聞いていただくのも難しい状況でした。
それでも、私たちは「音声化によって本の魅力を新しい形で届けたい」という思いを伝えるべく、粘り強く交渉を続けました。音声化に関して出版業界の方々が懸念する事項を丁寧に聞き出し、一つずつ解消することに努めていきました。
また、サンプルをお渡しすることをきっかけに、お話できる機会も増えていき、段々と信頼関係を構築されていきました。すると、書籍のプロモーションに使う音声CMの作成や、絶版予定の書籍の音声化など、少しずつ依頼をいただけるようになったのです。
こうして許諾をいただいたものからコンテンツ化していったところ、今度は紙の本を買った読者から「この本を音声化してほしい」といった声が書店さん等を通じて出版社へ届くようになり、1社また1社と協力先が増えていきました。このようにコツコツと地道に開拓していき、今ではほぼすべてのジャンルの出版物を取り扱えるようになりました。
ーー出版社の皆様からの賛同を得た秘訣を教えていただけますか。
久保田裕也:
私たちは、著作権の処理から音声コンテンツの制作・配信まで一貫して自社で完結できるのが大きいと思いますね。はじめは手探りでしたが、「そこまでやってくれるんですね」と驚かれることもありました。また、作家さんや出版社のご意向を丁寧にお聞きしながら、高品質なコンテンツを制作することで、少しずつ信頼していただけるようになったのかなと思っています。
企業や公共施設へのサービス拡充でオーディオブックの普及を推進
ーー改めて貴社の事業内容についてお聞かせください。
久保田裕也:
弊社の主軸は、書籍を音声化するオーディオブック「audiobook.jp」の運営です。現在会員数は300万人を突破し、多くの方にご利用いただけるサービスとなりました。
さまざまなコンテンツがある中で私が特におすすめしたいのが、毎朝6時に配信している日経新聞のダイジェスト版です。通勤中に経済の動向をチェックできるため、忙しくてニュースを見る時間がないという方におすすめです。
また、最近では個人向け以外のサービス展開にも注力しています。社員教育やリスキリング(学び直し)、社内報などに活用いただいている法人版のオーディオブックは、すでに150社以上の導入実績があります。業界や幹部、管理職、一般社員などのレイヤー別にカスタマイズできるため、必要な情報をピンポイントで収集できるのも利点です。
さらに、場所や時間を選ばず学習できるため、一般的な学習・研修サービスの利用率が1ケタ台なのに対し、弊社のサービスは継続率が87%と圧倒的に高いのが特徴です。加えて、図書館や医療機関など、公共施設でオーディオブックの導入を進めるプロジェクトも行っています。
経営者になってわかった意思決定の重要性。読書の新たな楽しみ方を生み出した企業が求める人材とは
ーー経営者として意識していることを教えてください。
久保田裕也:
とにかく意思決定のスピードを速めることを優先していますね。2012年に社長に就任した際、肩書は変わったものの、社内の環境はほとんど変わりませんでした。しかし最終的な決断を求められる立場となり、事業責任者とは比較にならない、「経営者にかかる重圧」をはじめて肌で感じました。
実は、私はそれまで100%正確な決断をすべきと考えていたため、判断が遅くなる傾向があったのです。しかし、私が決断を躊躇してしまった結果、それまでずっと右肩上がりに伸びていた業績がストップしてしまいました。そこから結果的に自分の判断が間違っていたとしても、気付いた時点で引き返せばいいのだと考え方を変え、決定のスピードを優先するようになりましたね。
ーー最後に求職者の方々に向けてメッセージをお願いします。
久保田裕也:
弊社では自分が成し遂げたい目標を持ち、達成に向けてとことん突き詰められる方を求めています。また、著者の方が伝えたいメッセージは何なのか、ユーザーに伝わりやすくするためにはどうすればいいかなど、著作物の本質に深く関わる仕事のため、コンテンツ制作に興味がある方が向いていると思いますね。
また、関係各所から制作方針を尋ねられることも多いため、自分の意見をしっかり伝えられるようにしておくことも重要です。創業当初から掲げている「当たり前に耳で読書を楽しめる世の中にしたい」という思いに賛同いただける方をお待ちしています。
編集後記
誰もがうらやむ有名企業の内定を勝ち取ったものの、大学の同級生から誘われたのを機に、先の見えない小さな組織の運営に関わることになった久保田社長。誰にも相手にされなくても諦めない彼の強いバイタリティがあったからこそ、今の成功があると感じた。新たな読書体験を提供する株式会社オトバンクは、これからも人々の生活に寄り添っていく。

久保田裕也/1983年神奈川県出身。東京大学経済学部経済学科卒業。オトバンクに立ち上げ当初から参画し、2006年に新卒で入社。オーディオブック配信サービスの立ち上げや制作インフラの開発、事業責任者を経験し、2011年代表取締役副社長を経て2012年に代表取締役社長に就任。














